
ハワイアンの残留孤児、ウクレレのこと
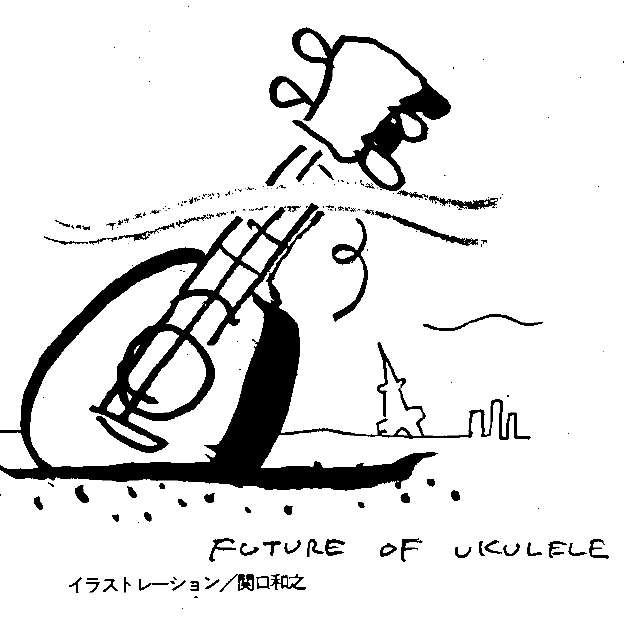
僕がまだほんとうに小さかった頃に、どうやらハワイアン(つまりハワイの音楽)のブームはあったらしい。
残念ながら、記憶の中にその心あたりはない。まして、1990年の今日や、街を歩きながらハワイアンを口ずさんでいる人に出くわすこともないだろう。
しかし、ブームの痕跡は意外な所に残っているものだ。それは大学の軽音楽部においてである。僕が大学に入った頃には、まだ「〇〇大学ハワイアン研究会」とか「〇〇大学ハワイアンズ」といった具合に、実質はロックやポップスのサークルにもかかわらず、名前だけが継承され続けているクラブがあったのだ。(今はどうかしらないけれど)
音楽と観光は実に密接な関係がある、と思う。その時代の日本人観光客の足が届く場所、そこの音楽が時代の流行となる。つまり、昔はせいぜいハワイ、今や世界各地にいたるところ、つまりワールドミュージックの時代となっているわけだ。
しかし、そんなことはたった今考えたことだからどうでもいいことである。僕が書きたいのは、そのハワイアン・ミュージックの残留孤児ともいうべき楽器、ウクレレのことなのだ。
僕がウクレレを購入したのは4年ほど前のことだ。「カイロの紫のバラ」というウディ・アレンの映画の中で、主人公(ヒロイン)のミア・ファーロウが可憐なしぐさでウクレレを奏でるシーンがある。ワーナーの試写会でその映画を観た数日後、僕はすでに渋谷のヤマハでウクレレを探していた。
「昔はもっと種類があったんですけどねえ、今はもう……。ですからねえ」
と言いながら、ヤマハの人は店の奥から3本程ウクレレをひっぱり出してきた。僕は胴のくびれがないパイナップル型のウクレレを選び、一種類しかない教則本を一緒に買い求めた。
その教則本の表紙には、みやげ物店でも見つからないだろうと思われる絵ハガキのごとく着色されたワイキキ・ビーチの写真がついていた。
同じ民族楽器の中でもインドのシタールやアフリカのコラ、あるいはギリシャのブズーキといった楽器に比べたら、ウクレレは見ためにもはったりがきかない。弦だって4本しかないし、音域も狭い。音量も小さい。
しかし、いや、だからこそ、ウクレレは愛らしい楽器なのだと思う。特に、気が滅入った時にこの楽器を手にすると100%効きめがある。ウキウキしちゃうのである。これは確かだ。
コラムニストのE氏が、僕とまったく同じきっかけ、つまり「カイロの紫のバラ」を観たことによって、しかも僕と同じ型のウクレレを同じ教則本付きで買った、と聞いた時にはいたく感激した。しかもE氏は、編集者やラジオ・ディレクターの友人とともに池袋のウクレレ教室(おそらく都心ではひとつしかないだろう)にまで通っているというではないか。かつてのC・サンタナとJ・マクラグリンみたいに「魂の兄弟」と僕らはお互いを呼びあい、ウクレレ復興を誓い合ったものだった。
まもなくE氏はウクレレ・デュオグループを結成。イギリスでは「ウクレレ・バリュエーション」などという傑作アルバムが発表されたりもした。
そしてはや2年。
バンドブームで、ギターやベースのソフトケースをしょっている若者は俄然増えたが、ウクレレをかついで歩いている人を見かけることはない。まして「勝ち抜きウクレレ合戦」という番組が企画されているという噂もない。E氏の作ったウクレレ・デュオグループは友人の結婚パーティなどの場ではほとんど失態に近い演奏をくりひろげ続けていると聞く。
しかし、たったひとりでも、ウクレレで音楽を奏でる楽しさを知ったり、手にっと手ひと掻きしてニコリとしてくれる人がいたなら、こいつも本望なのじゃないかしら。と、部屋にあるウクレレをながめながらそんなふうに思ってしまう。つまり、それほど可愛らしい楽器なのだ。
【1990年「美容と経営」に掲載のコラムを、原文のまま掲載しています】
関口コメント:
1990年というのは、僕がウクレレ普及活動を始める以前で、「ウクレレ快楽主義」という最初のウクレレ本を出版する2年前。まだまだ「ウクレレ冬の時代」。90年代の後半になってようやく、ウクレレはフラとともに衆人の認知度を高めることになる。今や日本のフラ人口は本家本元のハワイよりも多いと聞く。ウクレレは楽器店での売り場を広げ、大きな楽器ショーでの注目度はギターを凌いでいる。まさに隔世の感である。
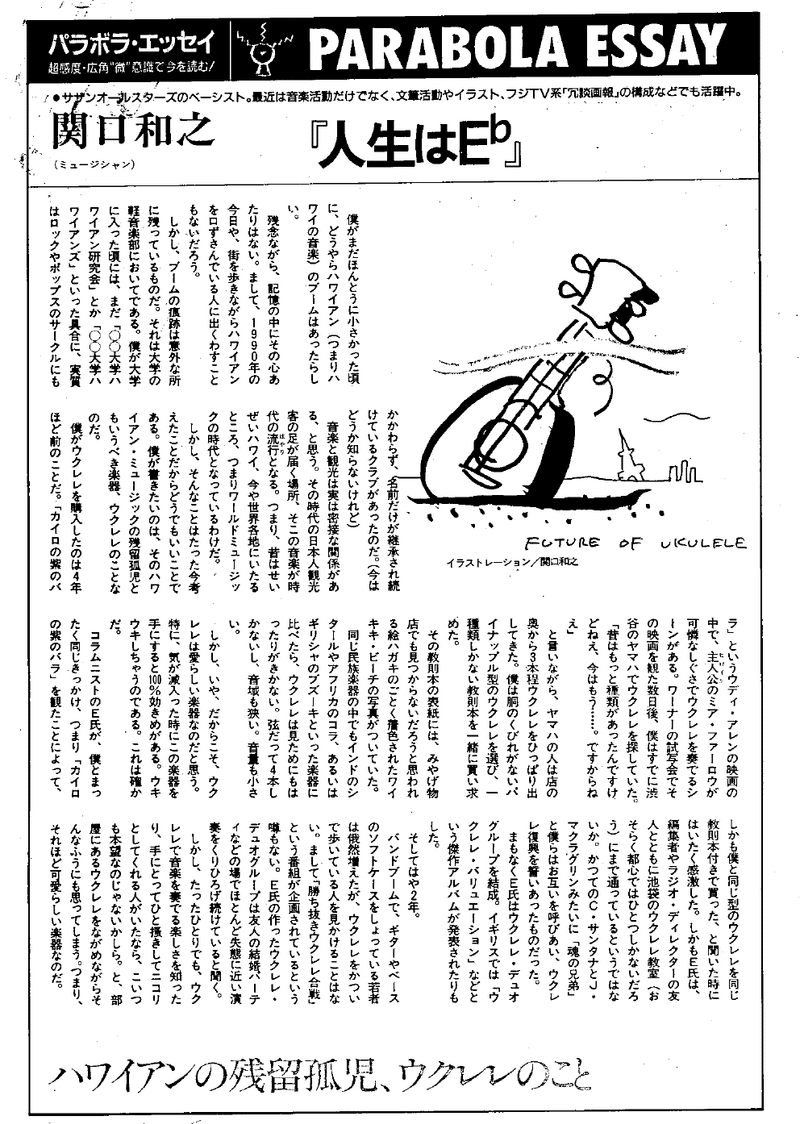
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
