
遊んで暮らす
【1989年に「ヴァンテーヌ」で連載されたフォトエッセイを原文のまま掲載】
昔の自分が突然話しかけてくるときがある。
「私、関口君からもらった年賀状のこと、よく覚えているわ」
先日、高校の同級生だった女の子にいわれた。それは、僕が高校時代その女の子(同い年だから、すでに一人前の女性ですが……)に書いた年賀ハガキのことだった。
「今でも忘れられないんだけどね」彼女はそう前置きしながら、どんなハガキだったかを話しだした。
「赤いスカートをはいた女の子が傘をさして立っているの。そういうイラストが描いてあって、その下に言葉が書いてあったのよ。「ボクは、どう頑張ってみたって、ペンキ屋か童話作家ぐらいにしかなれません」って……」
僕は赤面した。僕の頭の中では、すっかり記憶の底に埋もれてしまっていたことだ。いきなり登場した他人の思い出の中の僕は、一瞬見ず知らずの人みたいに思えた。
「えっ、そんな恥ずかしいハガキ書いたの? 忘れてたな、すっかり」
確かにハガキを書いたこと自体は忘れていたのだが、ペンキ屋、という言葉を聞いた瞬間から、あのころの気分や空気を閉じ込めていた記憶の氷塊は溶け始めていた。
当時、僕は親や友人に向かって公言していたのだ。「ボクは将来、ペンキ屋になるんだ!」と。ペンキ屋というのは、駅の広告や映画の看板などを描く人のことだ。そのペンキ屋になりたい、などとは変な奴だ、とおおかたの友人は思ったに違いない。まして両親にしてみれば「息子は何を考えているんだろう」とうろたえたことだったろう。
もともと小さい頃から何かしら書いたりすることが好きだった。同じ年齢の子どもの中で誰よりも先に字を覚えたし、当時2枚で1円だった、わら半紙というのをたくさん買ってきては、それに絵を描いていた。
といっても、それは「遊び」のひとつだった。ひたすら自転車を乗りまわすことや、墓地で探検隊ごっこをすることなどと同じ次元のものだった。
文字は暗号であり、何かを築きあげる積み木のようなマテリアルでもあった。ましてわら半紙のキャンバスは、砂場よりもあらゆる形を創造できる驚異の世界だった。飛行機、忍者、ロボット、未来都市、いろんなものを友達と一緒に描いてはみせっこしていたものだった。
そうやって考えると、子どものころというのは遊びの材料に事欠かなかった。どんなものからでも、どんな場所でも新しい遊びを考案した。それに飽きたとしても、さらに次の遊びを見つけだすことができたのだ。
ペンキ屋を見かけたのは、高校時代のある日のことだった。街角で広告の看板を描いていた。ペンキで汚れた作業ズボンの足を脚立にかけ、一心不乱に字を書き込む、その青年の動作に僕は見入った。
丸木橋を渡るときのように、気を抜くことなく、注意深く、そしてひと息に、まっすぐな線を引く。砂で作った要さいを端から徐々に崩していくように、色を塗りつぶす。我軍の船団が波間にかっこよく進んでるかどうかを確認するときのように、少し遠目から字のバランスを見る。
わあ、これは楽しそうだ、と僕は思った。しかも、誰が見ても彼は仕事しているのだ。
その日から、僕はペンキ屋になることに決めた。とにかくそう宣言することにしたのだ。
「何になりたい?」
「大人になったなら、何になるんだい?」
「何学部に入って、将来は?」
子どものころから、嫌になるほど質問され続けることがある。しかもその質問自体の幅はどんどん狭まってゆく。
僕はそれまでオトナの質問に対して、いつもそれなりに納得されるに違いない答えを返してきた。学校の成績がよかったので、いわゆる優等生として扱われ、親や周囲の期待を感じ続けていたのだ。漠然とではあるが、立派な何かにならなければいけない。いつのまにかそう思うようになっていた。人から尊敬される人物、さもなくば世に名を残す偉大な人。新しい数理方程式を考え出したり、世界中の人が待ちこがれているものを発明したり、貧しい人たちを救ったり、とにかくそんな立派な何かにならなければいけない、と。
道の反対側ですれ違うみたいに、「遊び」と「将来」は交差することなく、入れ替わってしまっていたのだ。いつの間にか。
高校生になって、すでに標準以下の少年になった僕だが、まだ「将来」についての呪文が心の裏側に貼りついているみたいだった。進路のことを聞かれるのが嫌でたまらなかった時期だ。苦しくもがいているときに僕はペンキ屋に遭遇した。
そのころ、きっと何かひらめくものがあったのだろう。僕の心はずいぶん軽くなったのだ。
「お願いだから、大学だけは出ておくれ。その後でペンキ屋になるのはかまわないから」その当時僕の体たらくをはらはらしながら見ていた母親は僕にそういった。呪文はすでに消えていた。その代わりに僕が見つけたもの(隠れていただけなのだ)はあっけらかんとするくらい正直な心の声だった。
「遊んで暮らしたい!」これだったのだ。
そして大学に入り、ペンキ屋や童話作家になる代わりに、僕は音楽を選んだ。僕の中ではペンキ屋でも音楽家でも同じだったのだ。
ふと周りを見渡してみて、それらの職業以外でも遊んで暮らしている人間がたくさんいることに気づいたのは最近だった。むしろ職業ではなく、やり方なのだ。彼らは皆遊びに貪欲だ。仕事でさえも遊びながらやる。つまり遊びの感覚で工夫するのだ。
僕はそんな人たちに比べると、まだまだ「遊び」足りていない。時々「好きなことをやってるんだから我慢しなくちゃ」などと思ったりする。冗談じゃない。弱気になりそうなときは叫ぶことにしようと思う。
「遊んで暮らしたい。死ぬまで遊んで暮らすぞ!」
そんなことを、後ろめたく思っちゃ前には進めない。最近つくづくそう思う。

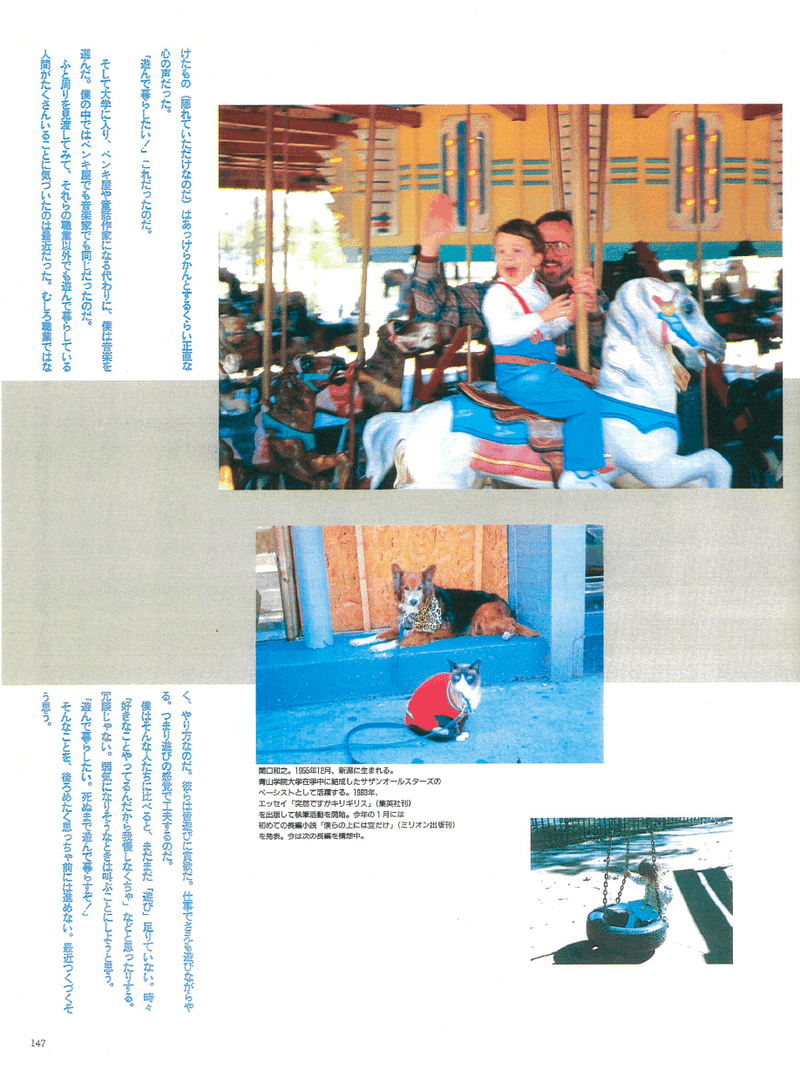
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
