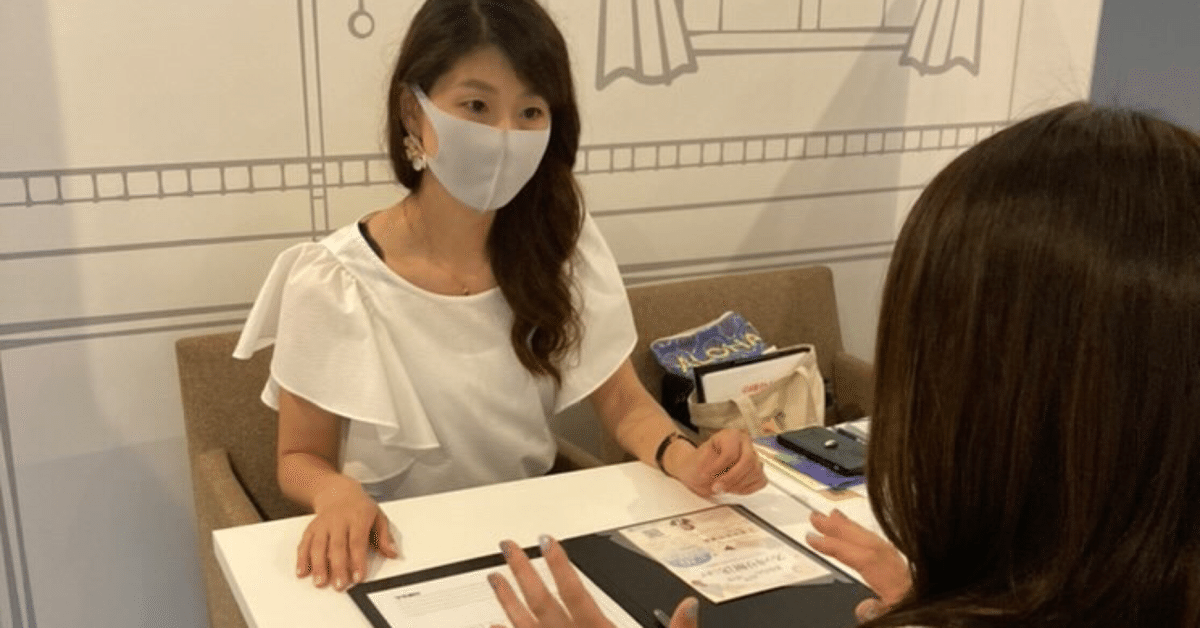
「気になる文字②」
のぼかんの仕事を通じて出会う方とお話しする内容で一番多いのが「親子関係」についてです。ご自身とその親御さんとの関係あるいは、ご自身とお子さんとの関係は身近であるからこそ悩ましいものですね。
そのようなお話の共通したテーマは、どうやら「自立」と言えそうです。
辞書で調べますと「自立」とは、自分以外のものの助けなしで、または支配を受けずに自分の力で物事をやっていくこと。とあります。
今月は、この「自立」という文字を分析していきたいと思います。
「自立」
のぼかん六つの形分けでは、直情の形と言い終始一貫した主張があり、外にも内にも何時でも何処でも自分のスタイルを通す姿勢があるとします。
次に字の理論で観ていきます。一画目の「′」でその場の環境の中の情報より必要と思うものを瞬時に選び取ります。続く「|」で選び取ったものをまずはの意思とします。「′」と「|」が重なる部分から「¬」とし、意思としたものを新たな情報も合わせて整理し、必要なものだけを三方向を線で囲まれたこの空間の中に入れ、自分が取り組む事への範囲を定めます。
続けて、この空間を縦に三等分するように横線二本を書き、最後は「一」で閉めます。
こうして「目」の内に入れた意思を周りの状況に左右されることなく上中下と自身の経験則を基に時間をかけて掘り下げていくと考えます。またここは四方を線で囲まれていますから、外からは中の世界が見えにくく、他方、中の世界は守られているとも言えますが、出せない、出さない状態とも言えそうです。接地面が直角性を持ちぴったりとついていると感じられるところから、自分で選び時間をかけて掘り下げた意思については、その時々でゆるがない自信を持っているとみます。
その意思を「‘」で受け「一」へ展開して「亠」とし、ここで受けた全ての意思や情報を「亠」の両端から少し内に入った部分にそれぞれ「|」を書き三方向を線で囲む空間となり、自分の取り組む範囲を余力を残した位置、つまり無理せずに確実に出来る範囲を定めるとみます。
その下に「亠」と平行に長い「一」を書き空間を閉じます。
取りこぼしがないかを確認する粘り強さやタフさ、堂々とした安心感、安定感はありますが、その仕切りを持たない内側は確固たるものが見えない、出さない、出せないという様子もうかがえます。
ですから、ここに具体的な確固たる意図は見えなくても、まずはそうと構える意思を有する事が大事であることを表しています。
まとめますと「自立」とは、自分で必死に考え決めた事を周りの状況や意見に左右されることなく取り組む姿勢と言えそうですね。
そこにその具体性は見えなくても、まずはそうと立つ心の大事さを教えてもらいました。
親の教えを子は守り、成長しながら自身の経験則と照らし合わせながら親の教えとの違いに首を捻り、迷いながらも自らも親となれば子に自分の意思を伝えていく。これが時代が変わっても変わらない親と子の関係であるとしたら、親も子も「自立」の意味をしっかり理解することで見えてくること、感じること、思うことがありそうですね。
若い頃は「自立」と聞くと親の干渉から自由になりたいと思っても、心もとなさも感じていました。自分では「自立」できたと思っても親から見たら危なっかしいものだったことでしょう。わかってもらえない、かと言って伝えることもできないもどかしさを子であった自分も親もお互いが感じていたのかもしれませんね。しかし、いつの間にか時は流れ、自分で決めたことを自分が出来る範囲でやるという「自立」の姿勢に心地よさを覚えるようになりました。
今度は、下に続く者に対し自身のあり方、生き様を通して「自立」をより具体的に伝え促しサポートできるように努めていくことが役割なのかなと感じました。
ふだん使っている言葉でも、こうして分析することで自分の気持ちが確認できたり目標が明確化されるのですね。背筋が伸び清々しい気持ちになりました。
ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
