
気になる文字
ブログへのご訪問ありがとうございます。
上流観名法「のぼかん」講師の磯村美樹です。
今日は毎月1日に更新される「のぼかん」ホームページに掲載された
私の原稿を投稿します。
「文字の再発見」というページで毎月、各講師が自分のテーマとした文字を分析しています。
「のぼかん」に触れたことのない方でも、文字を書きながら読んでみてください。
新たな発見があるかもしれませんよ〜(^^

「のぼかん」を学んでいると、文字の形を見ただけで印象や大まかな意味がわかるようになってきます。見て感じることと一般的な意味、解釈が重なることを確認しながら、見た目と意味が重なるように成り立っている文字がすごいのか、見た目から意味が読み解ける「のぼかん」がすごいのかと答えのない問いを抱きつつ日々を過ごしています。
ところが、私が感じる見た目の印象と一般的な意味、解釈が異なる文字があります。
それは「絆」という文字です。「絆」というと「大切な繋がり」とか「結ぶ」という解釈が一般的だと思うのですが、私はこの文字を見ると「切る」とか「分ける」という印象を受けるのす。そして、「切る」とか「分ける」という印象のせいでしょうか。「絆」という言葉に対して少し怖いような印象があります。
辞書で「絆」の意味を調べますと①人と人との断つことのできないつながり、離れがたい結びつき ②馬などの動物を繋いでおく綱。とあります。
また、訓読みは「きずな」「つな-ぐ」「ほだ-す」と読むそうです。「きずな」は辞書の意味の①と、「つな-ぐ」は②の意味と繋がりますね。
「ほだ-す」を辞書で調べると①つなぎとめる ②自由を束縛するとあります。
「きずな」「つな-ぐ」と「ほだ-す」とではニュアンスが違いますね。
また、私が受けた印象とは逆の意味を示しています。なぜでしょうか。
今日は、この「絆」という文字を分析して私が受け取った印象と辞書の意味の違いを検証したいと思います。
「絆」
「のぼかん」六つの形分けでは「受け入れの形」となり、常にテーマを持ち情報や圧力を受け入れては流すことを繰り返し、この繰り返しが検証となり吟味する力となっていくとします。
次に字の理論で観ていきますと、保守の部の一画目の小さい「く」で必要なものを取り、不要な情報や圧力は流します。最初の「く」の下に平行に一画目よりも大きな「く」を書きます。先に取った情報を基に新しい情報と合わせ、本当に必要なものだけを取り入れ不要なものは流します。「く」の最後を「ヽ」で閉じ「ム」とします。
間口が右上方向に向いて開いた空間が二つ構築されることから、先の事に開けた姿勢や向上心があること、同じような形が二つ繰り返されるところから、情報の取り方、選び方に慎重さがあると観ます。「ム」の真ん中辺りから「亅」を書き、取り入れた情報を基にまずはの意思を持ちます。「亅」の中心部分を挟むように左側に「ノ」右側に「丶」を書き、情報を左右バランスよく仕分け意思を集約しては明快にします。
保守の部に構築された「糸」で意思としたことを、革新の部の「′」で受け止め展開しては、余分なものは流しながら「糸」を見つめます。その右側に「ヽ」を書き「ハ」とし、「糸」を見つめながら新たな情報も限定的に受け止め受け入れては、情報を徐々に広げ展開していく姿勢を観ます。
「ハ」の」下の一呼吸おいた位置に「一」を二本書き「=」とし、これまでの流れを受け止めては整理し、二度にわたって検証する慎重さや粘り強さがあると観ます。
「ハ」の真ん中から長い「|」を書き、これまで宙に浮いていた「ハ」が分けられ「=」が固定されます。「|」が「=」をクロスし「=」が左右均等に分けられるところに、物事の両面を平等に捉えながら明快に表現、行動する姿勢を観ます。
大まかに「絆」をまとめますと、先の事を視野に入れながら慎重に情報を取り、集約した意思をさらに精査し、粘り強く、明快さ、公平さを持って表現、行動していくとまとめられます。
ならば、先の事を視野に入れた考え、同じ方向性を持つものの間に生じるものが「絆」であるとすれば、その絆を絶やさないように、あるいは強固なものにするには「個々」の迷いのない明快さ、粘り強さの先の間違いのない理解が必要ということでしょうか。
ゆえに、自由だったものを繋ぎとめる様から「つなぐ」「ほだす」との解釈が生まれるのでしょう。「つなぐ」「ほだす」というと、自由を奪われてしまうというニュアンスを感じますが、文字の形からは遠からず先の事を見越した末に繋ぎとめるという様子がうかがえます。
私が見た目の印象で「切る」「わける」と感じたのは、「絆」の革新の部の「ハ」や「=」を「|」で切断しているように見えるからだと思いますが、切ろうとして分けようとしてその「個」の世界の一つ一つを理解してこその繋がり、連帯して得るものが「絆」なのかなとも感じました。
「絆」が先の事を見越した末に繋ぎとめるものだとしたら、繋ぐ目的が私利私欲からくるものであったり、人の自由を奪うものでないことを強く願いたいと思いました。
「絆」という文字を分析することで、「絆」という文字に触れる度に感じていた違和感や怖さの正体がわかったような気がします。
文字というのは、静かではあっても深い部分に影響を与えるものかもしれませんね。
ますます文字の世界の奥深さを感じ探求心が湧いてきました。
ありがとうございました。
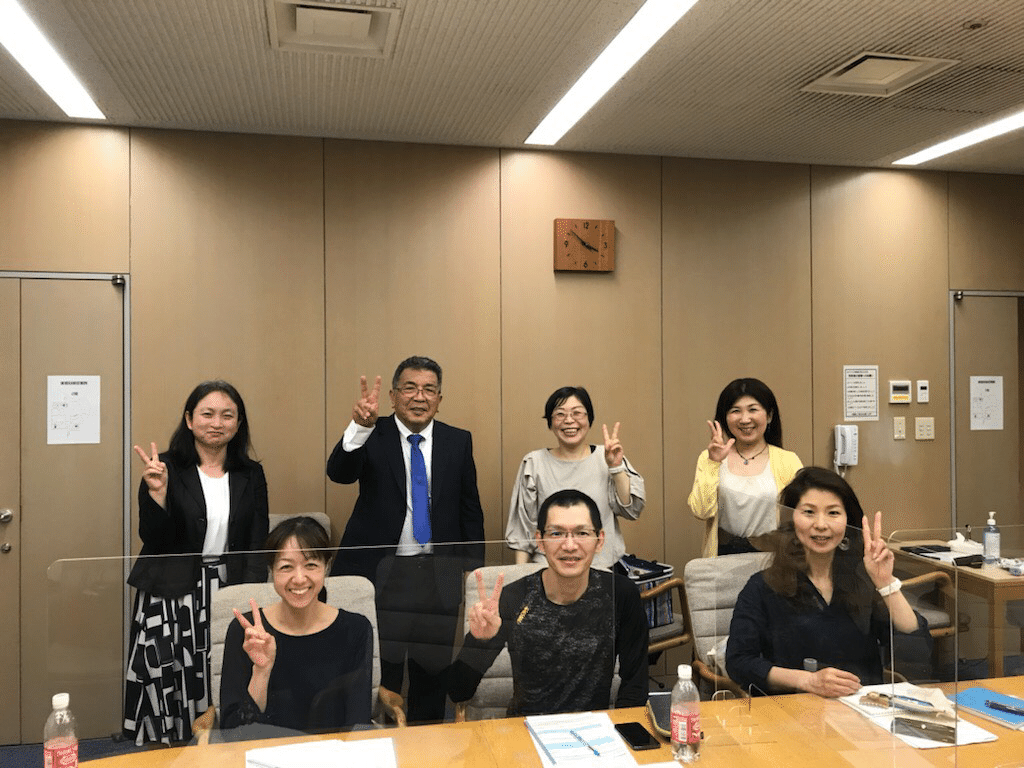
↑創始者のぼり先生勉強会にて
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
