
Day1:SFプロトタイプってなに?そもそもSFってなに?
この記事は何?
こちらの記事は、北海道上川町役場とデザイン会社グッドパッチが行う、「2050年の暮らし」を手触り感のある形で上川町で暮らす方々と描き、そこから現在を思考する「No Limitsプロジェクト」の公式アカウント記事です。
今回の投稿では、5月15日に実施した1回目のワークショップ内容について共有します!
プロジェクトについて詳しくは、こちらのNoteをご覧ください。
1. Day1の内容と目的🔔
Day1は、
自己紹介
プロジェクト概要の共有
みんなで感想・質問・提案・雑談をする
という内容で実施しました。

目的は、みんなでプロジェクトをスタートできる状態になることです。
誰かが置いてけぼりになったり、理解できないまま進んでしまったりしないように、プロジェクトをみんなで楽しみながら、発見や気づきを得られるような場にしながら進めていければと思っています。
自己紹介では、
「最近、一番楽しいことは😀?」
「あなたにとってSFときいて思い出すものは🤔??」
「得意なこと♪ / 苦手なこと💦は?」
という3つの項目を用意しました。
お互いのテンションが上がることを理解することや、何が得意で何が苦手なのかを理解して、プロジェクトを一緒に進めていく上での下準備を整えました。
2. SFってなに?
自己紹介の項目の一つ、「あなたにとってSFときいて思い出すものは🤔??」については、実はメンバーそれぞれバラバラの回答になりました!
回答の一部を抜粋すると…
小学生の頃大好きだった星新一さん
タイムスリップ映画好きです。アバウトタイム、サマータイムマシンブルースなどなど
たくさんありますが、やはりSTAR WARSです。小学生の時に映画館で観た興奮が忘れられません!もちろん今も大好きで新作は欠かさず観ているSF作品です。
華氏451。思想統制のため読書が禁止された世界の物語。本を持っていると「ファイアマン」によって焚書(ふんしょ)が実行される。
ドラゴンボール(カメハメ波打てるかもしれない)
といった様々な作者・作品の名前が上がっていました。
また、
SFってあんまり関わりがないと思っていたけど、そうか、好きだったあの本とか映画もSFって呼ばれるんだなぁって思ったら身近だった
といった声や、
どんなシチュエーションでも人間は人間と関係をもっているということに気がついた。それがなければ物語にならない
といった、改めてSFというものを考えてみた時の気づきもありました。
Day1では、さらにSFとは何なのかについて理解を深めました。
SF=「Science Fiction」?

SFと聞いて、一番思い出されやすいのが、Science(科学)とFiction(空想)を組み合わせた「Science Fiction」ではないでしょうか。
「Science Fiction」について日本では「空想科学小説」と呼ぶ人もいたそうです。
Science Fictionの起源といわれているのが、イギリスの作家メアリー・シェリーにより1818年に発表された『フランケンシュタイン』です。
科学的実験の結果として生まれた人造人間と博士であるヴィクター・フランケンシュタインの関係を中心に描く物語。フランケンシュタインというと「頭か首にボルトが刺さったスキンヘッドの人造人間」を思い浮かべますが、実は博士がフランケンシュタインという名前なんですね。
わずか18歳で『フランケンシュタイン』を書いたメアリーの半生を描いた映画もあります。
その後、電気技師のヒューゴー・ガーンズバック(Hugo Gernsback)が「Science Fiction」という言葉を作り出しました。彼は、1926年に世界初のSF雑誌となる『アメージング・ストーリーズ(Amazing Stories)』を創刊しました。この雑誌によってScience Fictionは大衆文化の一部として広がりました。
その後、特に1960年代には、技術や科学の発展を題材にした作品が多く生み出されました。文学に留まらず映画やTVにも大きな影響を与え、1966年に『スタートレック』がTV放映され、1968年にはスタンリー・キューブリック氏が製作・監督を行った映画『2001年宇宙の旅』が公開されました。1970年代には『スターウォーズ』が人気を博し、Science Fictionがさらに広まっていきました🎉
SF=「Sukoshi Fushigi」?
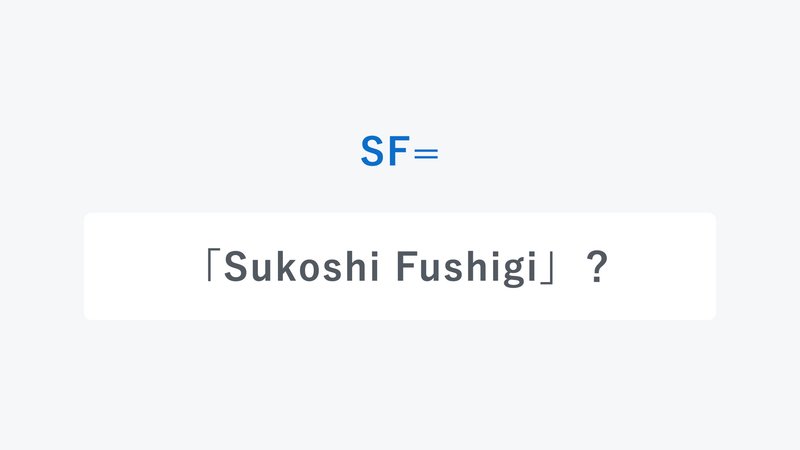
代表作に『ドラえもん』を持つ藤子・F・不二雄氏は、SFを「Sukoshi Fushigi」と意味付けました。
従来のScience Fictionとは異なり日常生活の中に少しだけ不思議な要素を取り入れた物語を指します。
僕にとっての「SF」は、サイエンス・フィクションではなくて、 「少し不思議な物語」のSとFなのです。(1989年 藤子不二雄ランド『少年SF短篇』2巻(中央公論社))
藤子・F・不二雄氏は幼少期から海外SF小説の熱心な愛読者だったそうで、影響を受けている作品は多くありますが、「少し不思議」な物語は、「どっちかといえばF(フィクション)の部分に重点が置かれ、S(サイエンス)についてはかなり弱い。」とご本人が語っています。科学的な要素を少し含みつつも、現実世界との接点を持つストーリーが特徴です。
SF=「Speculative Fiction」?

もう一つ、「Speculative Fiction」という捉え方についてご紹介させてください。Speculativeとは、「思弁的」。つまり経験によらず思考だけで物事を認識しようとすることを意味します。
「Speculative Fiction」という言葉自体は、1940年代に生み出されましたが、Science Fictionが科学的要素を強く持っていたことに対し、科学的要素だけでなく文化・社会・哲学的な要素も取り入れたSFの新しい捉え方としてその言葉をつかったのは1960年からの作家や編集者による「ニューウェーブ運動」でした。
つまりはSFって?
結局、定義づけはとても難しくそれぞれの解釈によるのが一番良いように思います。
ただ、SFが、想像力を活かした空想によって今現在の当たり前や前提と捉えられていることを覆し、新しい視点や刺激を与え、新しい問いをもたらしてくれることは、いずれの定義に従っても言えることなのではないかと思います。
また、アイザック・アシモフ氏の作品である『われはロボット』内で示された「ロボット工学三原則」は、現実のロボット工学研究においても倫理的基準として使用されています🤖。
SFは現実世界から影響を受けますが、現実世界もまたSFからの影響を受けているとも言えます🔄。
3. SFプロトタイピングってなに?
SF的思考で未来を描くことで、今はまだ無い価値や事業を思い描き、
その未来に辿り着く為に、現在すべきことを考え、行動するメソッドです。
インテル(アメリカ)が初めて導入した発想法とされます。
日本においても、ブライアン・デイビッド・ジョンソン氏の著書『インテルの製品開発を支えるSFプロトタイピング (PROFESSIONAL & INNOVATION)』が2013年に翻訳・出版され、広まっていきました。
SFプロトタイピングのプロジェクトでは、この著書の中で紹介されているプロセスが現在も踏襲されることが多いように感じます。
このプロセスを紹介している記事から引用させていただくと、下記のようなプロセスです。
Step1 科学を選び、世界観を作る (科学技術の選択)
Step2 科学の変化点 (科学技術の変化予測)
Step3 科学が人々に及ぼす影響 (2による影響)
Step4 人間の変化点 (人間の変化予測)
Step5 何が学べるのか (4による影響)
▼プロセス引用元記事
明るい未来を思い描くのは難しい
2023年にソニー生命が中高生を対象に行った調査に、「中高生が思い描く将来についての意識調査2023」があります。
こちらのプレスリリースから引用すると
10年後の日本や世界について、明るい見通しをもっているか、不安を抱いているか聞きました。
中学生についてみると、『不安(計)』は、【10年後の日本】では71.0%、【10年後の世界】では69.0%となりました。また、高校生についてみると、『不安(計)』は、【10年後の日本】では67.9%、【10年後の世界】では69.0%となりました。10年後の日本や10年後の世界に対し、悲観的なイメージを抱いている中学生が約7割となりました。
ということで、中学生・高校生共に約70%の人が日本や世界の未来に不安を抱いているそうです。
SFプロトタイピングを行うと、ディストピア的な、悲観的な未来を描く方もいます。もちろん、それが有効な場合もありますが、今回我々が行うNoLimitsプロジェクトにおいては、「明るい未来を描く」ことにこだわりたいと思っています。
1つ目の投稿で詳しく記載したのですが、その背景には町の方の中で、未来の暮らしに希望を持てなくなっている方がいらっしゃることがあります。
現在のこの状態から、「上川町の未来ってワクワクするかも」とか「自分の暮らしの未来にワクワクするかも」と思う人が増えていけばと思っています✨
また、スタートは数名のコアメンバーですが、ゆくゆくは上川町のもっと多様な方々にも参加していただきたいと考えています。

また、1つの未来像を描くのではなく、それぞれの視点で複数の未来(FutureS)を描くこと、1つの決まった結末を描くのではなく、複数の結末を前提とするOpen Endの思考でいることにこだわりたいと思います。
4. プロジェクト当初の予定プロセス
きっと、町の人と関わりながら、一緒にプロジェクトを進めながらプロセスは変わっていく、むしろ変わっていく方がよいなぁと思っていますが、プロジェクト当初の予定プロセスとして立てたプロセスをご紹介します。
「NoLimits」では、『インテルの製品開発を支えるSFプロトタイピング (PROFESSIONAL & INNOVATION)』で紹介されたプロセスの考え方を踏襲しつつ、Science Fictionに限らずSFを捉えているため下記のようなプロセスを進めていく見込みです。
STEP1 上川町の明るい未来を想像するというテーマ設定で、世界観をWillベースで考える
STEP2 科学に限らず社会全体の変化でリサーチし、変化仮説をつくる
STEP3 2と同様、価値観の変化などを含め、対話で深掘りしたり広げたりしながら影響を考える
STEP4 人間を含め世界への変化仮説をつくる
STEP5 バックキャストで学びとして現在から未来への道すじを可視化する
月毎の詳細プロセスに落とし込むと下記になります。

5月・6月:未来の社会像仮説を作成していきます。
7月・8月:その上で、ストーリーのプロトタイピング(小説作成)を7月までに行い、未来像のブラッシュアップや冊子作成を行っていきます。
9月:SF作家の方を招いて小説化を実施します
10月:SF作家の方の作品も土台とした未来社会像の作成とプロトタイプの方法を検討します

11月以降:手で触れるプロトタイプを製作すると同時に、アクションプランへの落とし込みを行っていきます。
方法は進めながら一番良い形を模索していきたいと思っており、変わる可能性が大きいのですが、まずはこのプランをベースに進んでいきたいと思います。
📣最後にご案内
一つ目の投稿がこちらです!
プロジェクトで目指すものや、「No Limits」というプロジェクト名に込めた思い、メンバー紹介をしています。
また終盤で、上川町とGoodpatchの紹介もしていますので、よかったら読んでみてください📕
また、少しでも興味を持っていただければ、気軽にご連絡いただければと思っています✨!
「全部は関われなくても、ちょっとだけ関わりたいな」、「どういうことかいまいちわからないけど、興味がある気がするな」という方はぜひ、お気軽にX(Twitter)のDMよりご連絡ください✉️!!
北海道上川町役場とデザイン会社グッドパッチは、手触り感のある形で「2050年の暮らし」を描き、そこから現在を思考する「No Limitsプロジェクト」を開始します。 #kamikawa #Goodpatch #未来 #SFプロトタイプ
— No Limits by kmkw x Goodpatch (@kmkwNo_Limits) May 16, 2024
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
