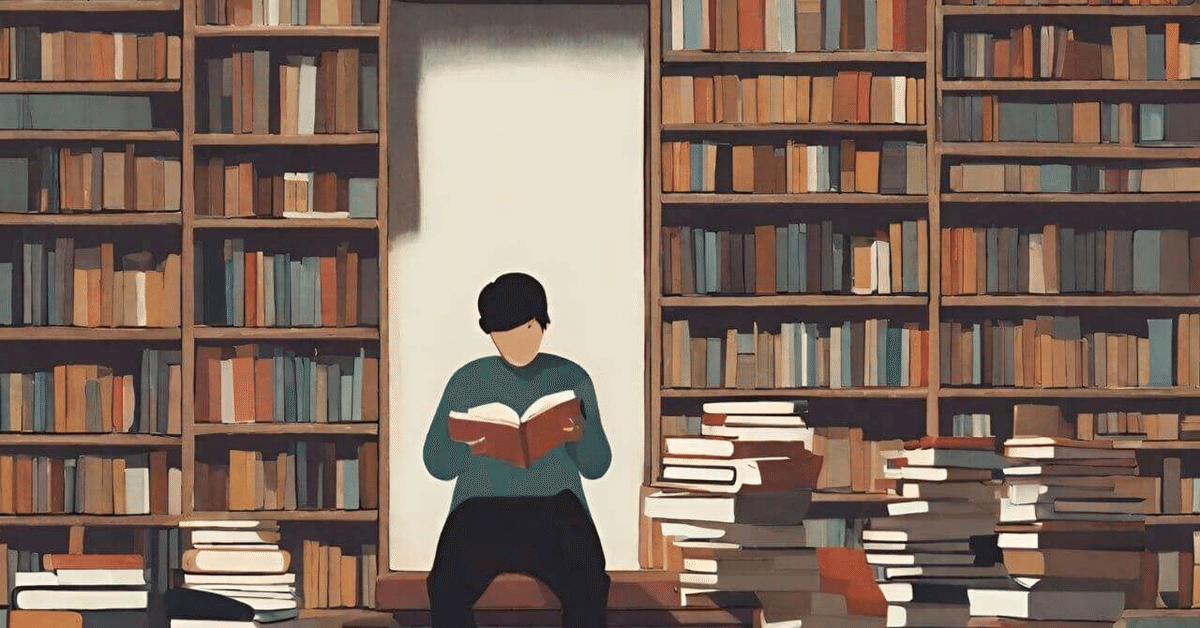
【体験談】50歳からの新規就農~事前に調べる
おはようございます。
私は、昨年の春に脱サラし、今年4月に認定新規就農者となりました。
因みに、現在51歳です。
認定新規就農者制度は原則45歳未満が対象です。また、就農準備資金・経営開始資金は49歳以下が対象です。
こうした国の制度を鑑みると、私のように50歳以上で新規就農を目指すのは、あまり賢い選択ではなさそうです。
そんな賢くない選択をした私の就農までの道のりを、何回かに分けて書いていきたいと思います。
今回は、私が「農業をやろう」と思い立ってから実際に行動に移す(大学校受験)までに行ったことを書いていきます。
『成功する農業』に出会う
「農業をやろう」と思い立った当時、私はまだサラリーマンとして海外駐在中でした。
農業について知るために、農業に関する本を10冊以上読もうと決めました。
最初に読んだのは、畔柳茂樹氏の『最強の農起業』でした。本多静六氏の「人生の最大の幸福は職業の道楽化」という言葉が紹介されていたのが非常に印象的でした。
面白そうと思った農業に関する本を手当たり次第に読んでいきました。
このように色々な本を読み漁ったお蔭で、私の農業の方向性を決定づける本に出会うことができました。
それが、岩佐大輝氏の『成功する農業』です。
この本には就農前の準備が「農業をはじめるための6つのステップ」として具体的且つ分かり易く書かれています。
私は、その中のステップ3の「作物・作型を考える」とステップ4の「10年間の経営のビジネスプランを数字に落とし込む」を熟読し、実践しました。
私が実際に実践したことを、その手順通りに以下に紹介します;
1) 「産地でないところにその作物を作るノウハウがない」
産地でないところに行っても、その地域にその作物を作るノウハウがありません。<略>作りたいものがあるなら、その産地に行くことが大事です。
私の場合は、就農地を自宅のあるさいたま市と決めていました。
なので、さいたま市の主要農産物を調べ、ニッチ作物などを除外したうえで下記の5品目をリストアップしました。
甘藷
さといも
ほうれんそう
小松菜
いちご
2) 「すでにダウントレンドになっている品目は基本的に避ける」
作物・作型選びをする際、絶対に外していけないのは「将来的にマーケットがなくなりそうなところにつっこむのは危険」<略>
新規就農者が、すでにダウントレンドになっている品目を選ぶのは基本的には避けたほうがいい
次に、上記1)でリストアップした5品目について、直近10年の出荷量及び市場価格の推移を調べました。因みに、出荷量推移は野菜ナビと果物ナビから、市場価格推移は青果物卸売市場調査からデータを入手できます。
この調査の結果、ほうれんそうが出荷量及び市場価格ともにダウントレンドっぽいけど、そこまで顕著な差とも言い難いと評価しました。
甘藷:出荷量は横這いx市場価格は上昇
さといも:出荷量は横這いx市場価格は上昇
ほうれんそう:出荷量は減少x市場価格は横這い→ダウントレンド??
小松菜:出荷量は増加x市場価格は下落
いちご:出荷量は減少x市場価格は上昇
3) 「10年間のビジネスプランを数字に落とし込む」
次はいよいよ10年間のビジネスプランを数字に落とし込んでいきます。
なぜ10年かと言うと、農業は設備投資した資金の投資回収までに10年前後かかるからです。
いよいよビジネスプランの作成です。
具体的には、10a当りの10年間収支試算表を作成します。
作物・作型ごとの経営モデル(農業経営指標)はネット検索できます。
私の場合、埼玉県やさいたま市の経営モデルはありませんでしたが、他県が公表している経営モデルを参考にしました。
なお、出荷量(収量)については、公表されている経営モデルの値に「素人係数」を掛けました。私は「素人係数」を1~3年目は60%、4~5年目は80%、としました。
上記1)でリストアップした5品目について10年間収支試算を作成し、各作物の収益性指数(PI)を算出しました。
因みに、収益性指数(PI)とは投資の初期コストに対する投資の現在価値の比率です。即ち、収益性指数が1より大きければその投資は採択されるべき、1未満であれば棄却されるべき、と判断できます。
なので、私は、収益性指数(PI)≧1と算出された、さといも、ほうれんそう、いちご、の3品目に絞り込むことにしました。
4) 「どの作物・作型がいいのか、数字を見比べて決める」
どの作物・作型がいいのかを検討するには、いくつか比較して試算するのが普通だと思います。決め打ちで「この作物と作型でいく」とするのではなく、数字を見比べてきめるほうがいいでしょう。
さいたま市では確保できる農地面積が境界条件となります。
さいたま市が公表している「貸付意向申出農地一覧」を実際に調べましたが、全247箇所の平均は約750m2、最大でも約6,000m2でした。
つまり、土地生産性の高い作物を選択する必要がある訳です。
そこで、上記3)のビジネスプランをもとに、年収1千万円を稼ぐのに必要な面積を計算しました。
計算結果は、さといもは300a、ほうれんそうは100a、いちごは50a、でした。
こうして、私はいちごを選ぶことにしたのです。
5) 「何を入り口にしたらいいか?」
いちごを選んだ私は、その栽培技術を学ぶための研修先候補をネットで調べ、以下の2つに絞り見学に行きました;
埼玉県農業大学校短期農業学科
GRA新規就農支援事業
因みに上記2つは費用が大きく異なります。
埼玉県農業大学校は年間12万円程度、GRAはその10倍以上…
なので、私の第一候補は埼玉県農業大学校。
どうやって埼玉県農業大学校に入学したかは、次回に書きたいと思います。
この記事が誰かの助けになれば嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
