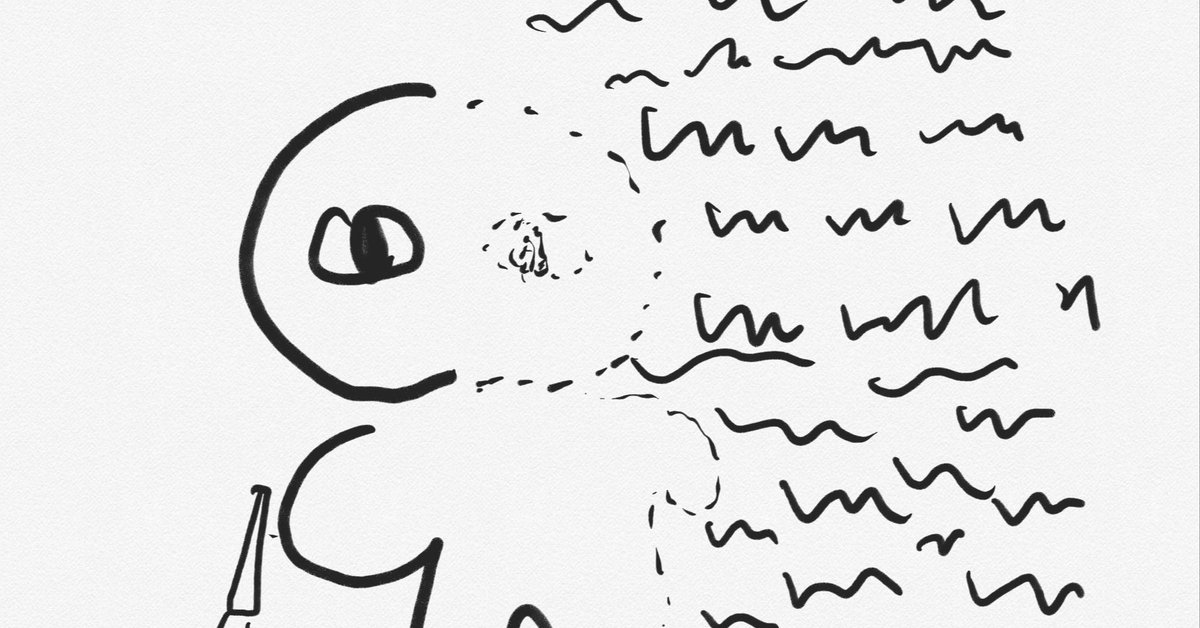
呼吸
息をするように書けたらいいのに。
そう思っている時点で、まだわたしの中で書くという行為は、不自然なものだと気がつく。
書くということが、何かを別の形で文章の中に生み出すということなら、その書かれるものに対しての質感や違和感、感じたものを素通りすることはできない。
もし、わたしが活字世界の一次元的存在だったら、と思う。わたしにとって書くことは息をすることであり、生きることであり、存在そのものである。そして、日常のように意義のない行為である。ただ徒然と文字列を生成する。排泄するように、感情を吐露するように。
果たしてそれは書くことか。
書かれる前と後の世界の間に立つわたしはそのどちらにも慣れることができない。慣れてしまえば、書けなくなるか、それとも書くことの意味を失ってしまうか、そのどちらかだ。
そうだろう。あえて書くということは、本来なら書かなくてもよいということと背中合わせだ。わざと言葉をつかもうとして、あるいは自分で言葉を投影して本来の姿から少なからず目を背けることだ。
逆にあえて書くということから逃れてしまえば、何も迷いがなくなる。多分、書いて嬉しいことも、悔しいこともなくなる。
別に、「書くこと」でなくてもいい。がわたしは特に「書くこと」と「そうでないこと」の狭間にいると感じる。
その場所では、何を書いているかは関係なくなる。何を書いていようが、いつも頭をよぎる。「なぜ書くのか」という問いを振り切るためにひたすら書く。だから、書く内容は関係ない。ただ書いているときにわたしは書くことの最大の幸福を受け止めている。内容が関係なくなったときに、書くという行為の純粋な運動だけが取り出される。それすらも書いてみたい。そういう純粋なものだけを書いていたい。
そのときに、「書くとは何か」という問は、一般に言われている「書く」という言葉から逸脱してしまっている。自分の存在を懸けたり、揺るがしたりする行為に近い。「息をすること」、「食べること」みたいに根源的なのに、基本的で慣れきった動作に近い。
食べなくては生きていけない。だから、食べることに対して疑問を持つことは、生きることに対する疑問につながる。かと言って常にその疑問を抱いているわけではない。
意識の外で、問うている。
なぜ息をするのか、息してもいいのか。体が言葉もなく問うている。だからわたしの意識は問うことを忘れてしまっている。そして、息が止まったときに「ああ息をしてはいけなかったのか」と初めて気がつく。それでも、「まだ息をしたい」と体は問い続けるだろう。「息してもいいですか?」息をするために、力の限りもがくことを求めるだろう。
できる限り、わたしは「書くこと」をそのようなレベルで問いたいと思う。本能とまではいかないけれども、問うことを忘れて問いたいと思う。
一つ一つの言葉が、問う。「書いていてもいいですか?」
ずいぶん甘い。書きたければ勝手に書けばいい。他人に聞くことじゃない。
だから、多分書いていてもいいか、書くのをやめるべきか、それを最終的に決めるのは自分なのだと思う。書くことは、自分への問いだったのだ。
わたしは自分には甘いから、最後の最後まで「書き続けてもよい」と認めるだろう。むしろ、醜くても、拙くても書くことを自分に求め続けるだろう。力尽きるまで、書くことを求めるだろう。そうじゃないと納得できないのだ。
だとすると、書いてもいいですか、と問うことはナンセンスになる。書くことだけが答えを知っている。
それが、命の危険におよぶ「山に登ること」とか「探検すること」じゃないから、当分の間は、言葉が止むことはないだろう。書くことは、ゆるやかに自分を擦り減らしていく。ゆっくりゆっくりとしたスリルがある。多分、この目で見ることはできない。振り返ったときに、初めてわかる。
書くことがわたしを変えてしまった、と。
最後までお読みくださりありがとうございます。書くことについて書くこと、とても楽しいので毎日続けていきたいと思います!
