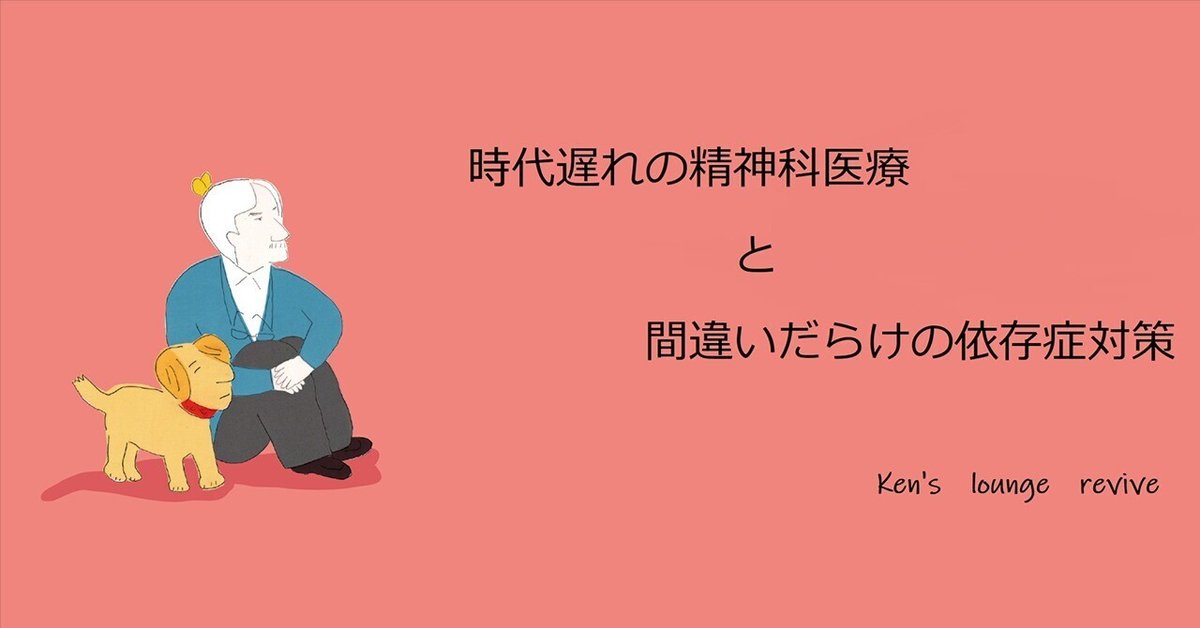
「レガシー」とやらについて③
◎レガシー(legacy)「遺産」、「伝統」、そして「次の時代に受け継がれていくもの」を指す。
▼断酒会との出会い
★長崎市保健所にて
1970年代、久里浜研修に出かける前だったような・・・。あの日のことは、しっかりと覚えている。
「あっ、西脇先生ですね。お忙しい中、私どもの例会に出席いただきありがとうございます」とネクタイをきっちりと締めた、スーツ姿の恰幅のいい中年男性が、笑みをたたえて私を迎え入れてくれた。そして、名刺を差し出して「私は長崎断酒友の会の福川と申します。よろしくお願いいたします。実は、私どもの例会に精神科の先生が出席されるのは初めてなんです。これからもよろしくお願いいたします」。
そのときの私は、ヨレヨレのポロシャツにジーパン姿で、もちろん名刺など用意していない。「いやその、副院長に・・・その・・・保健所の断酒会に参加するようにと指示されたもんですから・・・これからもとおっしゃられても、次は来られるかどうかわかりませんが?」「そうですか、そうですか。まあまあ、とにかくこちらの席にお座りください。今から今日の例会を始めますので」。
それが私と断酒会との出合いだった。
席に座って、改めて名刺の肩書きを見ると、「長崎断酒友の会(現・長崎県断酒連合会)会長 福川辰夫」と書かれてあった。
“福川さんって、断酒会の会長なんだ!ということはアルコール依存症者だよね”
しかし彼は、私がそれまで診察してきた、なんとなく荒んだ感じのする、自暴自棄なアルコール依存症者とはまったく違っていた。あんな紳士然とした人がアルコール依存症のわけがない。嘘でしょう!と思ったのである。ところが、その例会で語る福川氏の体験談は、まさしくアルコール依存症そのものだったのだ。驚いた。
福川氏は、長崎県北部の佐世保市在の国鉄職員だった。10年ほど前までは、それこそ精神医学書どおりのアルコール依存症の病状を繰り返していたようだ。その結果、北九州市の精神科病院に入院し、そこで北九州市の断酒会を紹介されて、退院した後にその断酒会に入会したのだそうだ。しばらくは北九州断酒友の会に通っていたが、私が初めて例会に参加した数年前に、彼は長崎県に断酒会を発足した。
そして、私はというと、1回だけの例会出席のつもりが、それから四十数年間、アルコール依存症に留まらず、さまざまな依存症疾患の治療を生業にさせていただいている。
▼ダルクとの出会い
★めがね橋、そして“ちゃんぽん”
20年近く前に、1本の電話がかかってきた。「ダルクの中川といいます。一度、会っていただけませんか。」
ダルクは、薬物依存症者の回復施設である。当時はまだ、長崎にはその施設はなかった。その頃私は、アルコール依存症の治療に携わって二十数年経っていたのにもかかわらず、同じ依存の問題を抱える薬物依存症についてはかなりの抵抗を感じていた。それらの依存症者を、非合法薬物を摂取する者、犯罪者といった捉え方をしていたのである。しかし、その電話に出たとき、きっと私は機嫌が良かったのだろう。「今度の月曜日、お昼に当院のサテライトクリニック前の眼鏡橋で待ち合わせましょうか」と快諾したのである。
そして当日、眼鏡橋の上に数名の若者が待っていた。その一人が電話をくれた中川氏だった。お昼時である。眼鏡橋のもう一つ下手の石橋(袋橋)のたもとに中華料理屋があり、そこの「ちゃんぽん」は鶏ガラ出汁でおいしく、私のお気に入りであった(最近は旅行雑誌にも紹介されて、観光シーズンには行列ができている)。そこで私は彼らに「ちゃんぽん」をご馳走した。そして、その際、長崎にダルクを開設するに当たっての協力を要請され、引き受けてしまった。私は彼らにご馳走したのである。私が彼らからご馳走してもらって協力(支援)を引き受けたのではないのだ。後年、ここがダルクのしたたかなところだと知ることになるのだが、そのとき私は、そんなことは知る由もなかった。今考えると、多少共依存的になっていたのかもしれない。
★長崎に根付いて・・・
彼らはその後、実によくやってくれた。まず、準備室を開設し、長崎ダルク相談室を作り、さらに通所型の長崎ダルクヘと発展させ、長崎ダルクのグループホームを開設したかと思えば、2016年には、ギャンブル依存症のグループホームも立ち上げた。
そんな彼らの取り組みを眺めているうちに、いつの間にか私の薬物依存症者に対する抵抗は薄れていた。もっとも、私の理解がそんなに深まったのなら、ダルクが資金難に悩まされ続けていた時期に、好きな飲食、それに伴う遊興を少し控えて、そこで要したお金をダルクの献金にすればいいものを、これがなかなかできなかった。今考えると、いささか情けない。しかし、グルメ志向で夜遊び好きのヤブ医者に協力を求めたのは彼らである。
きっと、「大変な奴に頼んでしまった」と後悔しただろうと思うが、頼りにならない精神科医を選んだのがよかったのかもしれない。協力をお願いした精神科医があてにならないなら、自分たちがしっかりしないといけないからだ。つまりこれが、依存から自立である。
『依存するということ』 西脇健三郎著 幻冬舎 2019年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
