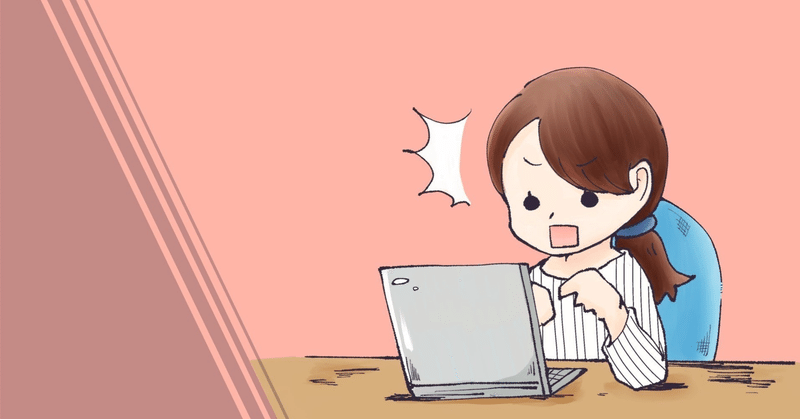
【授業報告】継承語クラス「メールの書き方」
先週に引き続き、メールの書き方。
なぜなら予定が消化できなかったから!
しかも、今週もなぜか予定が終わらなかった。なぜだろう?!
昨日は「問い合わせのメール」の書き方。
午前クラスは先週終わらなかった「感謝の表現」に加え、何でもいいから、日本の団体などに問い合わせるメール。
午後クラスは取り上げなかった日本語タイピングに加え、何でもいいから、は結構みんなそれに時間を食われていたので、日本の高校の体験入学の可否を尋ねるというテーマ指定での問い合わせメールの書き方。
ランダムに分けた2~3人グループで、件名と本文の書き方を相談しあって、考えていくとした。
メールの書き方自体(宛名や挨拶などの順番)は先週取り上げたので、休んだ人のために簡単におさらいして開始。
敬語の練習にもなるし、話し合いもできるし、話し合ったこと発表するのは、引っ込み思案な子でもやりやすいし、結構いい内容になると思った。
例えば「返事」は「お返事」なのか「ご返事」なのか、迷っているグループがあったので、タイトルの付け方(~のご連絡、~のご案内、~のお知らせ、~について問い合わせ等)にかこつけて、なぜ「お」と「ご」に分かれるのか再確認。
基本は漢語が「ご」で、和語が「お」、外来語にはつけない、なんだけど、「お教室」「おビール」「おタバコ」などの例外もあるという話から、「お返事」は漢語だけど「お」が多い気がするという話をした。
「ご返事」もありなので、ルールで覚えたいなら「ご」がいいね。
午前午後全6グループの中で1グループだけが、「ご検討いただけるとうれしいです」というような書き方で、残りは全て「お返事お待ちしております」「ご返信よろしくお願いします」と言った書き方。
先方に返信義務のない問い合わせ(こちらが顧客じゃない)で、返事しろという書き方は、どんな丁寧な書き方でも上から過ぎという話をした。
ドイツ的なんだと思う。
「お返事くださると、ありがたいです」など、下手に出るようにという指導で終了。
もう1つ用意してたテーマがあったけど、またいつかにしようと思う。
でも、メールという文化はいつまで残るのか。
この子たち(高校生年代)が社会人になるときには、企業もチャットしか使わないとかになるんだろうか。
若い子の読解力低下(PISAの結果)は読書量の低下とチャット文化にあると新聞で読んだことがあるけど、そういう世代が主流になっていけば、おじさんおばさんの書いた文って長くて読みにくいって思うようになるのかもしれない。
(私が明治生まれの祖父の日本語は変だ!と思ったみたいにね。 「とほくへいきませう」みたいなw)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
