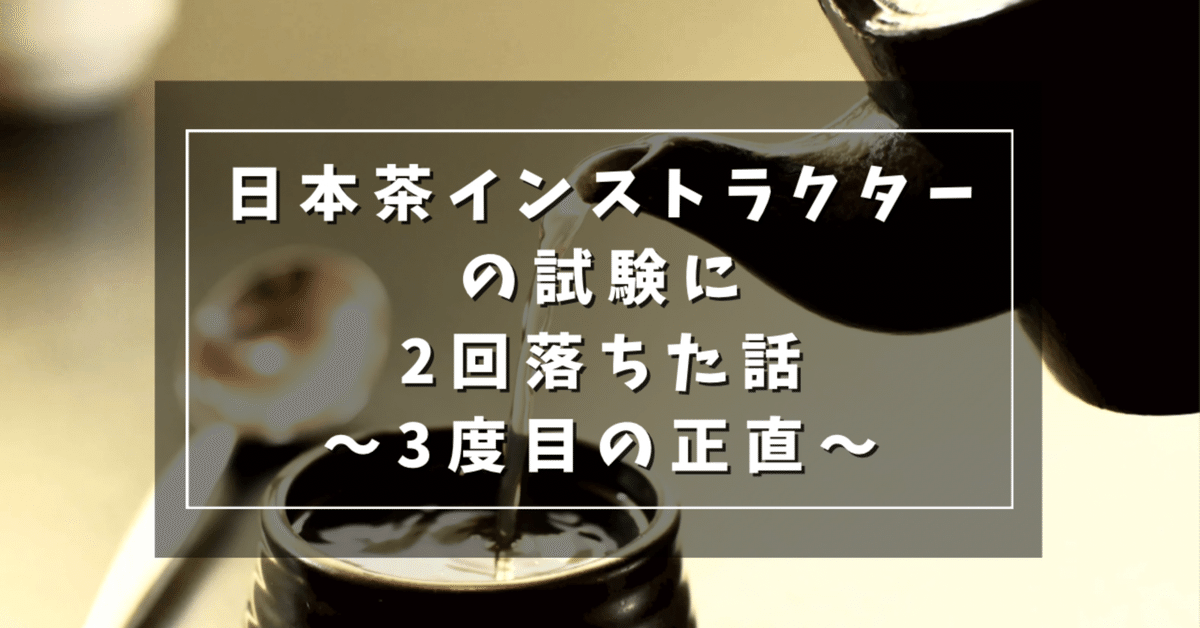
日本茶インストラクター試験に2回落ち、3度目の正直で合格した話
3回目の受験でようやく日本茶インストラクター試験に合格
3度目の日本茶インストラクター試験に2022年度、ようやく合格することができました。
しかし、ここまでの道のりは長く、「もう次受からなければこの資格は取るな」ということなんだなと諦めようと考えていました。
私の試験合格までの道のりについて、少々お付き合いください。
日本茶インストラクター1次試験になかなか受からない・・・・・・
私の日本茶インストラクター試験の勉強の始まりは2019年。
2019年度の日本茶インストラクター通信講座を受講し、テキストを見て内容の難しさに驚き年度内の受験は諦め、課題の提出物のみ出してまずは日本茶アドバイザーになろうと考えました。(※日本茶アドバイザーは日本茶インストラクター通信講座の添削課題を期間内に全て提出し終われば、課程終了とともに自動的に付与される資格です)
しかし、ここで私の甘さが発動(−_−;)
通信講座の最後の添削問題の提出が間に合わず、提出すれば日本茶アドバイザーにはなれたはずであるのに、その機会を逃してしまいました。
自分に甘く、勉強時間も確保できていなかったため、とても中途半端な勉強をしていました……。
「もっと真剣にやらないと受からないよ!」と当時の自分に言いたいです。
そして心改め2020年度、日本茶アドバイザー試験と日本茶インストラクター試験を同時受験。(同日午前中にアドバイザー、午後にインストラクターの試験を実施)
日本茶アドバイザー試験は二者択一問題で難易度としては易しかったため、何とか合格できました。
しかし、日本茶インストラクター試験の方は、茶の健康化学、茶の利用、茶業概要の項目が半分以下の正答率だったようで不合格となってしまいました。
勉強をし直し心機一転、2021年度も再々受験。しかしまたも不合格。
この時は茶の健康化学の項目が合格のラインである正答率5割を切り、不合格となったようでした。
2021年度は、その受験年の4月から勉強をはじめ、テキストを1ページ目から全て音読をしていく勉強をしました。もちろん、それ以外にも模擬試験をひたすら解いたり、間違えたところを何度も見返しノートにまとめたりなど、高校生や大学生の時のように真剣に勉強をしました。
音読をしたおかげで、テキストは流し読みではなく、どこにどの説明があったのか掴めるようにはなりましたが、これだけでは勉強は足りなかったようです••••••。
3度目の受験の勉強
3度目の受験勉強の際には、これまで落ち続けた結果、練習問題が2019年版、2020年版、2021年版、2022年版と4つ揃っていました(・∀・)
練習問題を一問ずつ解き、テキストの該当箇所を読んでアンダーライン、また一問解いて、読んでアンダーラインを繰り返し行い、地道に一つずつテキスト内容と細かい数字まで覚えていきました。
4年分の練習問題を解くと、アンダーラインが重なる部分と、引かれないところとがあり、何度も年度を超えて頻出する問題は重要な問題なのだなと推測。
また、例年の試験でいつも正答率が5割を切る、茶の健康化学の項目は何度も何度も音読をして理解できるように務めました。
前回の試験勉強の反省点で、4月から7ヶ月かけてじっくり勉強すれば大丈夫とタカを括り、長期に勉強したけれども結局最初の方に勉強したことは忘れてしまったりして、実質的にはあまり頭に入っていなかったということがありました。
テキスト覚えることも大事ですが、どんな問題が出るかを先に確認した上で、勉強をした方が
ただ目的なく流し読みするより、よっぽど効果的だったなと感じます。
2次試験当日のハプニング
私の詰めの甘さが露呈した出来事をお話したいと思います。
ようやく1次試験を突破し、2次試験対策も受講。
しっかりインストラクションと鑑定の試験準備をし2次試験を迎えましたが、なんとここでも私はやらかします。
2次試験当日に試験会場を間違えるという凡ミス(T_T)
試験以前の問題で確認不足。私の不徳のいたすところ。
2次試験対策講座を受けた会場と、当日の試験会場は全く異なる場所でしたが、抜け抜けの私は2次試験対策講座の会場に時間に余裕を持って着き、のんびり受付時間になるのを待っていたのでした……。
試験受付時間が近くになっても人が誰もいないことに気づき、ようやく全く違う場所に来ていたことを認識。
慌ててタクシーを拾い試験会場に向かい、電話をして何とか受験をさせていただくことはできました。
対応いただいたスタッフの方々に感謝しかありません🥲
一次試験突破のために取り組んだこと
世界のお茶の栽培面積ランキングや生産量ランキング、緑茶の生産量ランキングや栽培面積ランキング、紅茶の生産量ランキングと栽培面積ランキング、などなど、兎に角世界のお茶のランキングの順位は正確に暗記する必要があると数回受験するうちに確信!
ランキングメモをポッケに忍ばせ、通勤時間や歩きながらでも、そのメモを確認しながらひたすら暗記しました。
もう一つポッケに忍ばせアイテムにしたのが害虫の名前と何を害する虫なのかという一覧。
これも試験1ヶ月前から毎日確認して脳に刷り込みをしました。
そして、案外範囲が少なくても侮ってはいけないと感じたのが茶の利用。
茶の利用の方法や、お菓子作りなどで何を(花粉?粉末?)どのくらいの量まで混ぜると良いか悪いかという正確な数字も覚えました。
品種の特性も頻出した気がします。
茶の樹の樹勢や味の特徴など……。
やはり結果的にテキストはかなり読み込みました。
合格に近道はないと感じますが、苦労して勉強した甲斐があったなと思います。
こんなに苦労してとったのだから、必ず活かしたいと思います!!
最後までお読みいただきありがとうございました😊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
