
体の中に耀る月 第6話「胸中」
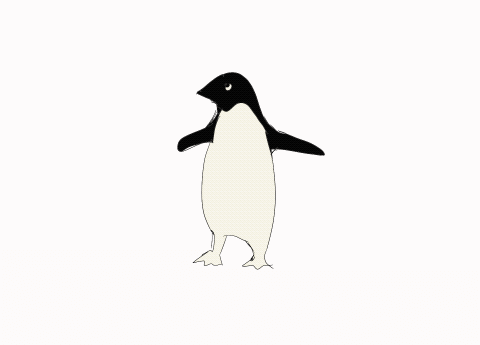

今より昔、当時、なんとなく書いていた部分が、今では意味が変わっていることもあります。
そういうとき、単純な拙さとは別の読みづらさがありますが、やっぱり小説を書くことを、まだやめたくないですね。
第6話「胸中」
睦は電車を飛び出してから、途方にくれて佇んでいたが、まず敦子に返事をすることにした。
「大丈夫?」
と。それに対する返答はなかった。何コール待っても、電話への応答もない。5分・10分と、時間だけがゆっくり過ぎた。液晶のホーム画面には、アナクロの時計が映しだされている。長針が夜8時の丘から少し先に進んだ。意を決して敦子の家に行くことにした。自分が行って、何ができるか皆目検討が付かなかったが。行ってから考えよう‥‥行ってから。
睦は、敦子の家を囲うブロック塀の陰で、中の様子を伺おうとした。無論、玄関の戸は閉まっているのだから、中が見えるはずはない。睦の動きはただ挙動不審なだけで、なんの意味もないものだ。カーテンが閉じられているのか、家から漏れる灯りはない。塀からはみ出したモチノキの葉が訝しげに睦を覗きこんでいた。迷った末、睦は勇気を鼓してインターホンを鳴らした。そして、再び身を翻し、塀の陰に隠れた。
もし、敦子の母親が玄関に現れたら、逃げる。しばらく待って、誰もいないようなら諦めて帰る。敦子が現れたら、そのときは‥‥そのときは、なるようになる。
特殊器官を使えば、家に人がいるかいないか分かるかもしれないが、今日はジュンシや典子の事で疲れていた。ジュンシとの約束もある。睦は塀の陰で息を潜めていた。ブッという音がして、呼鈴から人の声が聞こえた。
「‥‥どなた?」
か細い声で、それが敦子か敦子の母親か睦には分からない。応えて良いものか考えあぐねていると、雑音は消えて再び辺りは森閑とした。
睦はため息を吐き、諦めて帰ろうとした。そのとき、背中で物音を振り返ると、数センチほど扉を開いて、睦の顔を仰視している敦子がいた。
「‥‥睦くん?」
暗がりで、大きな黒い瞳の対が妖しく光っていた。敦子に招かれ、恐る恐る家の敷居を跨いだ睦は、あっという間に異様さに呑み込まれた。以前にも増して汚い。明かりがないため、睦が感じたその汚さは雰囲気だった。夏の盛りに2日も窓を開けていないかのような暑苦しさ、埃と何かが腐ったような臭い。敦子自身にも生気がなく、萎びた野菜のようだった。敦子のメッセージを思い出して、睦は「大丈夫?」と彼女に声をかけた。
「うん‥‥」と項垂れる彼女は、とても大丈夫に見えない。実を言うと、これも睦は項垂れる敦子を見たのではなく、敦子の影を見ただけである。敦子が先程ドアを開けた玄関も、その先のリビングも、二階へ続く階段にも、どこにも電気が点いていない。
「ちょっと、ごめん」
睦が手探りで明かりのスイッチを探すと、「ダメ」と敦子が睦のその手を制した。酸い臭いが鼻を突いた。皮脂と汗が混じった不快臭。敦子は何日も風呂に入っていないのでは、という疑いが睦の頭に過った。
「どうして?」
電気を点けない訳を尋ねると、「夜九時以降は消灯、絶対に部屋から出ないこと」それが母親との約束らしい。
睦は驚いて、
「夜中トイレに行きたくなったらどうするの?」と聞くと、朝まで我慢する、と言う。
「西のお母さんは、家にいないの?」
と聞くと、小さく頷いた。それなら、こっそり電気を点けても分からない、と言ったが、敦子は首を振った。
「嘘を吐いても、お母さんは電気料金の明細を見たら、気付く」
睦は言葉を失った。これはいったいどういうことか、答えをくれる人に尋ねたかったが、周りには睦と敦子以外誰もいない。彼女との間に、敦子の母も、保健室のパーティションも、友人もいない。睦は、敦子との間になんの隔たり無いことに気付き、そしてその隔たりを切望していることに気付き、動揺した。この場を取り囲む臭気が不快で、睦は家へ帰りたくて堪らない。だが、心細そうに佇んでいる敦子を一人置いていく訳にもいかず、睦と敦子はしばらく黙してその場に佇んでいた。沈黙を破ったのは睦だった。
「あの」
「なあに」
「この家、汚くない?」
「汚くないよ」
「そうかな」
「うん」
もう話すことが無くなってしまった。睦は冷や汗を流しながら、続けた。
「お風呂に‥‥お風呂に入った方が良いよ」
睦なりに直接的な言い方にならぬよう、気を配したつもりだった。その優しさが、かえって少女の心を傷付けるかも知れないと、そこまでは考えなかった。睦はある一定の深度で鈍感であり、敦子も比喩を解さない性格なことが幸いした。睦の提案の突拍子のなさに、敦子は眼を丸くして、しかし気を悪くした様子はない。
「でもお母さんが」
母親がいないときは、風呂に入ってはいけないらしい。母親の言いつけに逆らうよう、敦子を説き伏せるのは容易ではなかった。入った方が良い・いや、入らない、という問答を繰り返した後、睦が責任を持って敦子の母親に謝ると言うので、敦子はやっと了解してくれた。
敦子を風呂場まで見送るついで、睦はそっと浴室を伺った。そこも完璧に衛生的であるとは言い難く、床や壁に張られたタイルのあちこちにカビが生えていたが、きっと体を洗うのに支障はないはずと、睦は眼を閉じ自分に言い聞かせた。
睦が傍に立っているのにも関わらず、敦子がすぐに服を脱ぎ始めたので、睦は慌ててカーテンを閉めた。
睦は居間に戻った。女の子の家、暗がりで二人きり。睦は視線を落として股間を見たが、特に反応はない。この家は異常だ。空間そのものが視線の塊のようで、窒息しそうだ。睦は籠る熱気と臭気に気持ち悪さを覚えて、ソファの横にある窓をそっと開けた。呑気な鈴虫がそこかしこですだいている。睦は額の汗を拭う微風を感じたが、臭気は消えなかった。窓の傍から離れて、異臭の元を辿った。カウンター型の台所に忍び込み、シンクを見ると、排水溝に元の姿分からない何かがこびりついていて、それが胃液と干物、それから洗剤を混ぜたような臭いを放っていた。睦は胃がムカムカして、口元を抑えて換気扇のスイッチを押した。深呼吸するに足る空気が少しずつ居間に満ちて、そこで睦はようやく冷静に、そして大胆になった。それでも足音を潜めながら、荷物を置き、ソファに身を沈めた。眼を閉じると、無意識下で聴覚が研ぎ澄まされ、睦は風呂場で敦子がシャワーを使う音を聞いていた。部屋の中はやはり汚かった。そこかしこに紙ごみや空き缶が散乱していて、ゴミ袋こそ部屋の隅にまとめられてはいたものの、睦を外に追い立てるような脅迫観念を与えていた。
睦は、急に悲しくなった。母親は、子どもの心配をするものだ。母親は、子どもに衛生観念を強要するものだ。母親は、家の掃除をするものだ。母親は、家で子どもの帰りを待ち、遅くなると叱るものだ。疎ましいと思うことがある。良いか悪いかは分からない。けれどそれが当たり前だった。
敦子の母親は、今敦子を置いてどこにいるんだろう。ここは違うとハッキリ悟った睦は良いようのない不安と悲しさに襲われた。目の前のテーブルの上で、突然バイブ音がなり、睦はビクッと肩を竦めた。天板の上の、茶渋がこびりついたマグカップや女性誌を、親指と人差し指だけで除けると、染みだらけの螺シャのクロスにスマホが現れた。ピンクの枠に嵌まった液晶の中には、「生玉先生」と書かれていた。睦は思わず手を伸ばした。
「もしもし?」
「先生」
応えた少年の声が、典子の予想と違ったのは当然である。
「ちょっと、アナタ誰?」
と詰問された声が、慌てていたので、睦は鉄面皮の典子が動揺している様を想像して、思わず笑った。
「‥‥アツシ、そこで何してるの?」
睦は、典子に聞かれて考えた。そうだ、俺は敦子の家に来て何をするつもりだったんだろう。敦子が心配で家を訪れたはずだ。しかし、家の異様な雰囲気に呑まれて、敦子の心配どころか敦子がシャワーを浴びている間に、そっと家を出たいと考えていた。自分の関わるべき問題ではない。敦子が、睦に向けた笑顔、細くとも微かにあったはずの情を、敦子の母親が知らぬ間に切ってしまったかのようだった。答えに窮していると、
「敦子はどこにいるの?」
と、典子から次の質問が。返答が、即座に意識の閾に上がり、何も考えずに応えた。
「今、風呂」
「お風呂?!アンタ、敦子に何かしたの?!」
その慌てぶりに驚き、喫驚の理由を察した睦は、慌てて否定した。
「べ、別に何もしてないよ。ただ‥‥あんまり」
汚かったのだ、と睦は罪悪感で語尾を濁しながら答えた。敦子を、典子に「臭かった」などと言うのは、彼女をことばで辱しめている気がした。典子は敦子の状態を聞いても動揺せず、次に
「よく家に入れてもらえたわね。敦子の母親はどうしたの?」
と聞いた。
「‥‥いない、みたい」
「どこへ行ったの?」
「‥‥分からない」
睦は、敦子の母親の不在がまるで自分の咎であるかのように、小さく呟いた。
「そう」
そして、典子は沈黙した。睦も他に何を言って良いか分からず、しばらく黙していたが、話の継ぎ穂、穂というより葦にすがるように言った。
「先生、俺どうしたら良いかな」
きっと、先生は「そんな事知るか」と言うのだと思っていた。叱責でも良い。叱責なら、ここを飛び出す口実ができると睦は無意識に望んでいた。
しかし、典子は黙っていた。溜め息も聞こえない。単なる沈黙ではなく、何かを考えているようだった。それは睦の思い過ごしかも知れない。睦は沈黙に耐えきれず喋り出す。それで墓穴を掘ってきたことを忘れて。
「敦子の、母親は、変、だ」
途切れ途切れになったのは、話すうちに、しっくりしたことばが見付かるのじゃないかと期待していたからだ。しかし、結局有り体なことばになってしまった。変、変わっている。頭がおかしい。語彙の無い者が使う拒絶のことば。自己嫌悪が睦を襲った。
敦子も変だ。答えは簡単だ。こんな家に居るから、敦子は「死にたく」なるのだ。あんな母親の言うことを信じるから、敦子はおかしくなるのだ。
けど、敦子は母親とこの家が、自分のことを守ると信じている。敦子は変で、敦子の母親も変で、ただ二人の関係に問題がないだけだ。それで終わってしまう。睦にできることは何もない。
可愛い敦子が好きだと思っていた。でも、今はその気持ちに自信がない。母親に反抗できず、傷だらけなのに、その傷に無自覚なのが痛々しい。可哀想だと思う。けれど、睦には何もできない。誰か助けてあげて。けどそれは卑怯な事じゃないか。
睦は途切れ途切れに話した。典子は、そう、と相槌を打つだけで、黙って話を聞いていた。そして、睦は気付いた。
ひょっとして典子にも、どうしようもなかったのではないか。問題のないところには解答もない。教師という枠を気にしながら、あの母親と話し続けることぐらいしか、できなかったのではないか。大人はもっと何でもできると思っていた。教師は、もっと偉いと思っていた。何を根拠にそう信じていたのだろう。
「あの、ごめんなさい」
「何よ、突然」
「生意気言って」
「殊勝なことね。けどアンタが生意気なのは今日に限らないわよ。どこまでに対する謝罪かしら」
典子は高慢に答えた。
「‥‥」
「アンタこそ私に怒ったり、怖いとか思わないわけ。今日は暴力的な反応になって悪かったと思ってるのよ」
「俺は」
確かに典子が怖い。たとえ睦が、致命的な間違いを犯しても、軽蔑の目で見つめるだけで何も言わないような、その冷ややかさが。
「ただ、教えてほしいんだ」
正解を知っているなら教えてほしい。敦子が明るく登校できるような未来のために、どうすれば良いのか。
「何をよ」
それとも、睦にできる事など、ないのか。それならそう教えてほしい。罪悪感に対する免罪符として。
「俺、ここに来ない方が良かったかな。帰った方が良いかな」
けれど、典子の答えはやはりすげなかった。
「知らないわ」
「‥‥」
電話越しに典子の深い溜め息が聞こえた。睦は意気消沈した。呆れられている。
「アツシ、敦子がお風呂から出てきたら、私の家に連れてきなさい。駅まで迎えに行くわ」
睦は目を丸くした。
「良いの?」
「さあ。良いか悪いかこの目で見ていないから何とも言えないけど、アンタの言うとおりなら家の衛生状態が良いとは言えないみたいだから。一応の言い訳として使えそうね」
しかし、睦は先行きに不安を感じてまた口をつぐんだ。典子の言うことを聞いたとして、敦子は母親に無許可で家を出ることを承諾するだろうか。
典子は睦の悩みを感じ取ったかのように続けた。
「まあ、敦子を連れ出すのは一筋縄ではいかないでしょうし、後々のトラブルもある程度覚悟しておかないといけないわ。別に、敦子を放って帰ってもアンタの責任ではないわよ。保身を考えるなら、今日の事は忘れて帰りなさい」
「そんな‥‥」
「誰もアンタを責めないわ」
「でも先生は」
「私も、アンタが悪いとは思わないわ」
典子の声音は不思議に優しく感じられた。しかし、何故だろうか。先まで望んでいた免罪符は、期待していたほど睦の心を軽くしたりはしなかった。
「俺を無責任だと思わない?」
「何度も言わせないでね。思わないわ。アンタが自分を責めるのは、自分の気持ちに責任が持てなかったからよ。でもそれは、誰にでもあることだわ」
そうか、誰にでもあること。睦はようやく安心した。
「ホッとしたわね」
気持ちを見透かされて、睦は動揺した。
「え」
「敦子の事が好きじゃなくなっても良いやと思ったのね。でもね、アンタ、覚えておきなさいよ。もしアンタの恋愛の相手が私なら、私はアンタを責めるわよ」
睦は、典子と相思相愛になる想像こそできなかったものの、典子が凶器を持って睦を追いかけ回したり、暗闇で睦を呪う想像はあまりにも容易く、ゾッとした。
「一度相手に情を感じたら、その気持ちがなんなのか分かるまで悩み続けることは、人間の義務だと思うわ。だから、脳がアンタに罪悪感を与えるのよ」
「一度でも?そんなに人を好きになるのって重いことなの?いつまで悩めば良いのさ」
「一生よ」
典子はさも当然のように答えた。
「一生?!無理だよ、そんなの。先生はどうなの?他の大人はどうなの?人を好きになるのって‥‥そんな‥‥」
もっといい加減なものだと思っていた。いい加減なもののはずだ。そうでなければ、大人がみんな真実の愛を見付けていたら…そんなの、どうなるか想像も付かないけど。
典子は窓辺に寄って遮光カーテンを開けた。凸凹のビルにかぎられた夏の夜空の空気は澄んでいた。窓に映る透明な琥珀の瞳の中に、月が煌々と輝いていた。いつも典子は教えるべきことより言ってはいけない事を考え、悩む。信仰、戦争、教育、愛。言葉ではぐらかせばいくらでも表現できるもの。しかし、真実ではない。中学生は大人とも子どもとも判じきれない年齢だ。少なくとも、大人が常に正しいとは限らないと感じてもらう事が、教師の使命であるような気がする。それは、いつも生徒に感情移入しすぎる典子には、時に辛く感じられた。
「恋愛感情なんていい加減なものよ‥‥悩み続けたところで、誰も褒めてはくれないし、誰かに聞いても煙たがられるだけでしょう。答えを知っていると語る人はきっとみんなインチキだわ」
「じゃあ、悩む意味なんてないじゃないか」
睦は反駁する。素直な良い子だ。この素直さが、典子に不安を若起する。もう少し話したら出掛ける準備をしよう。日はとっくに沈んでいる。典子はカーテンを開けたままにして、窓辺を離れた。
「答えのない疑問に悩む意味がないなんて、ただの欺瞞よ。自分の気持ちそのものに向き合うのを止めて、恋愛はみんな錯覚だと解脱のフリをしたり、セックスだけを悦しんだり、自己陶酔のために恋愛する大人は、確かに多い。たとえ生活が保証されていても、疑心暗鬼に満ちた世の中で悩み続けろ、だなんて、アンタには理不尽な大人の言い分に聞こえるでしょうね。けど、アンタや私。一人を咎めたり責任を課す人は誰もいない。でも、誰に咎められなくとも、周りに流されたまま悩むのを止めると、目先の利益の為にしか人に優しくすることができなくなるわ」
典子は深呼吸した。自分を諫めた。私はこの子に期待してしまっている。睦が、敦子を好きな気持ちが揺らいだにも関わらず、心配だと言うから。心身ともに成長の過渡期と言える年齢で、自分を誤魔化さず、人の気持ちと向き合い苦しむ勇気と健全さが、尊いと思った。
睦は黙って聞いていた。納得しているか、ただ典子の多言に圧倒されているだけかは分からない。典子が洗面所へ行き、片手で顔を拭ったところで、睦が返事をした。
「えっと、つまり‥‥」
典子は思わず苦笑した。
「敦子に優しくしてあげて」
「うん」
了解を示す短い返事の後、電話は切れた。典子は、睦への説教を反芻して顔をしかめた。何を言っても、言葉は言葉でしかない。愛情に実体を伴わせる事はできない。言葉にだって実体はないのだから仕方のない事だが、世間はいつも、愛情の真実は虚なのに、言葉により実体があるかのように見せかけてきた。しかし、恋人の愛をセックスの有無で、夫婦の愛を法律や戸籍で、子どもへの愛を教育のレベルで、隣人への愛を歳暮など時候の挨拶で、果たして証明できるだろうか。ドラマや映画の感動やときめきを、そっくり一人の異性に投影することは可能だろうか。典子などは幾分ひねくれてしまっているから、それを馬鹿馬鹿しいとも思う。けれど、その反面、安寧を求めるのに必死で、愛情を可視化しようとした人の努力を否定するべきではない、と感じる。感情の煌めきを表現しようと、ことばや絵、音楽として引き出してみると、なんだか流行りのCMや歌、映像に影響を受けた事が如実に分かる、陳腐で、それでいて自分の気持ちそのものではないような、なんだか恥ずかしいもののようになったことは、典子にも経験がある。しかし他人の感情をその表現の巧拙で評価し、さらに否定できてしまうは、自身に情の源泉が無いと豪語しているようなものだ。
典子は、窓に映った半透明の自分の姿を思い出した。酸化ケイ素を通過しきらず屈折して、瞳に映った虚像。虚と実は対をなすが、虚は無を表さない。たとえ未来永劫愛情が視認できず、玄学的な人を納得させ得るような体系化された学問にならなくとも、典子には愛情を実感する僅かな時間の為に、霧の中で手探りに歩み続ける生き方を、とても豊かで尊いと思う。そんな事、とても生徒には言えないけど。
睦は電話を切ってから、肩を首の後ろにやり、両手で天を突いた。そのまま肘を左右にぐるぐる動かすと、大分気持ちがスッキリした。ふと、自分のスマホが気になり、ソファ脇のリュックを探った。嫌な予感は的中した。母親から何件もの不在着信がある。今日は友だちと遠出をすると言って家を出た。特別な日の門限である夜9時を30分も回っていた。
「ごめんなさい。やることがあるのでもう少し遅くなります。大事なミッションです」
そのメッセージで母親が納得するとは到底思えなかったが、睦はスマホをオフにして再びリュックにしまいこんだ。しかし肝心の敦子はなかなか風呂から出てこない。パシャパシャという水の弾く音が間断なく続いていたから、まさかのぼせて倒れている訳でもない。覗きに行くのも気が引けて、後少し後少しと待つうちに、今度は別の不安が浮かんだ。もし、敦子を連れ出す前に、彼女の母親が帰ってきたらどうしよう。以前、敦子が睦を連れて公園に行っていたというだけで、激昂し掴みかかろうとした母親である。深夜、親の不在中、娘が異性の友だちを家に引き入れていたら、並みの親でも娘の貞操を心配するだろう。普通ではない、睦にとって変な敦子の母親は、どうするだろうか。ひょっとして、殺されるかも知れない‥‥睦はゾッとした。ソワソワと立ち上がって、風呂場の近くへ行き敦子の気配を確かめたり、いざというときの逃走経路を探したり、ローテーブルの下に隠れたりした。低くなった視線の先、フローリングの床にゴキブリが這っているのを見付けて、睦はきゃっと悲鳴をあげて飛び上がった。慌ててローテーブルの下から出ようとし、天板に頭をぶつけた。
「アツシ君、何してるの?」
いつの間にか風呂から上がった敦子を、睦は仰ぎ見た。小綺麗になった敦子はまるで天使のようだった。胸元にフリルの付いた白いAラインのワンピースを着ていてた。デコルテから上には何のアクセサリーもなく、ただ敦子の首が乗っているだけである。しかし、耳元や首筋にかかる豊かな黒い髪、瞼の下にところ狭しと蔓延る睫毛、そして窓から差し込む月光が、彼女の全体に深い陰影を与えていてた。先ほどの憂鬱は何処へやら、敦子はコロコロと笑った。
「おでこに、たんこぶ」
睦も照れ笑いを返した。睦が何気なく敦子の顔から視線をずらすと、彼女は手に何かを握っている。それはオークでLL版の写真立て。中の写真の一対の男女は若々しく華やかな笑顔をこちらに向けているが、女の腕の中にいる幼児は眩しそうにレンズから目を逸らしている。
「アツシ君に見てもらおうと思って、これ」
季節は今と同じ頃だろうか。太陽はフレームの外にあるが、家族3人の後ろに映る灌木は、どれも青々と繁り、撒かれた水がレンズに反射して輝いていた。
「この写真は」
「家族写真。これが私、それからお父さん、お母さん」
「けっこう昔のだね。最近のはないの?」
睦は何気なく聞いたが、敦子の顔は曇った。
「最近のはダメ。お父さんがダメだから、お母さんが見えるところに飾るのはダメなの。でもこれは、お母さんのお気に入りでもあるから、良いの」
睦は聞いたことを後悔した。しかし同時に、敦子の母親とこの家の汚さを繋ぐ糸の存在を感じた。写真には、敦子の母親の執心があった。彼女は、自身の内に存在する活力、 優しさ、娘にかける愛情だけでなく、隣に佇む美男への愛を永遠の物として、この写真のように留めて置こうとしたのだ。人は移ろいやすい。身体の栄枯盛衰だけではない。娘への愛情ですら、それは水のようなものだ。睦は、甕に注いで放置したまま腐りかけている彼女の愛情を、呑まされつづけた敦子をすら、今までにない薄気味悪さを感じた。そしてにわかに睦の「使命」を思い出した。
「あのさ、良ければだけど、ちょっと外に出ない?ここ蒸し暑いし」
睦自身、上手い誘い方ではない事を重々自認していた。しかしこの短時間では、上手い口実など作りだせる訳がない。敦子の顔が蒼褪めた。
「どうして?嫌。アツシ君言ったよね。ここに一緒に居て、お母さんに謝ってくれるんでしょ?言ったよね」
「そうだけど…そうだ」
そう言って睦は話題を変えようとした。まさか嫌がる敦子を引きずって外に連れ出す事はできない。たとえ敦子の喉が細くとも夜のしじまには響くだろう。睦はリュックのポケットをまさぐって、くしゃくしゃになった紙袋からパワーストーンのようなものを取り出した。
「今日、宇宙センターに行ったんだ。西にあげる。小さいけど、本当の月の石だって」
「何これ?わー、きれい」
敦子が喜ぶのを見て、睦はホッとした。けど、どうしよう。はぐらかしているだけじゃダメだ。
「に、西とも一緒に行きたいな。俺」
「どこにあるの?それ」
「電車で一時間ちょっとのところ」
「ふうん。どんなところ?」
「そうだな、ビローンとしただだっ広いところの右側に、でっかいロケットがドーンと置いてあって、そこで写真撮ったよ。それから、えっと、展示スペースには学校にあるのより何倍も大きい地球儀があるんだ。上から地球を眺められるよ」
何がおかしいのか、敦子はクスクスと笑っている。
「…今から行ってみる?」
無論、今はとっくに営業時間外である。しかし意外な事に、先よりも強い拒絶反応を見せなかった。
「でも、お母さんに怒られる」
「メールしておいたら」
敦子は俯いて黙っている。
「そんなに敦子のお母さんって怖いの」
「うん。悪い子だって物を投げたり、閉じ込められたり、追い出される事もあるの」
「もう悪い子でよくない?」
睦は何気なく言った。敦子は目を丸くした。
「もう良いじゃん。悪い子で。家出しちゃえば、プチ家出」
敦子は凝然としている。睦が言ったことに、即、首を振ろうとしたようだが、迷いが小首を傾げたままの首に表れていた。
「ぷち‥‥家出?」
「一緒にさ、ロケットの近くまで行ってみて、考えよう。どうしても家に帰りたくなったら、帰ろうよ。俺も一緒に行って謝るよ、約束通り。でも母親が怖くて帰りたくなかったら、そのまま家出しちゃえよ」
「家出」
敦子は何を考えているのだろう。家出、家出、とそのことばだけを反芻していた。敦子は、ふと顔をあげて睦に尋ねた。
「アツシ君も家出してくれる?」
「えっ」
睦は驚いた。家出、家出。今度は睦がそのことばを胸の内で反芻することになった。これは敦子の提示した条件と考えていい。睦が首肯すれば、敦子を連れ出せるかも知れない。ただ、睦は母親に反発する事こそ頻繁だが、本気で家出したいと思ったことはない。しかし、ここで、
「それは無理だよ」と言えば、敦子は再び渋るか、悪ければ睦を拒絶するだろう。睦は言った。
「うん、俺は西の側にいるよ。俺は西が悪いなんて思わないし、ずっと西の味方 だ」
敦子の顔に恍惚とした笑みが広がった。頬に朱みが戻った敦子の顔は天上のものと錯覚するぐらい愛らしい。しかし、敦子の笑顔に蕩けそうになる睦を、ぐいと現実に引き戻そうとする危機感が突如生まれた。少女は夢を見ていた。少年は夢から醒めかけていた。少女の目を覆う手を、彼女の母親の手から、少年のそれに代わるだけである。悩み続けろという典子のことばが、睦の中で既に呪詛として変わりつつあった。
「じゃあ、行こう」
悦ぶ敦子の脇をすり抜けて、睦はそそくさとリュックを背負った。ともかく生玉先生のところに連れていくんだ。
「待って」
睦の後ろ暗さを見抜いているかのように、敦子が睦を留めた。
「な、なに?」
「準備、持っていきたいもの。あのね、アツシ君に手伝ってほしいの」
睦は壁にかかった時計を見た。10時‥‥。敦子の母親はまだ帰らないんだろうか。後どれくらい余裕があるんだろう。
「良いよ、何を手伝えば良い?」
リュックを降ろさずに、睦は敦子に歩み寄った。
「あのね、着替え持ってくる。あとね、アツシ君に探してほしいの」
「何を?」
「私の宝物。丸くてこれくらいの花柄の缶」
「無くしたの?何が入ってるの?」
「お母さんがどこかに隠しちゃった。汚いって。でも、綺麗なのよ。原石とか貝殻が入ってる。お父さんからのお土産も入れてたから、お母さんが怒ったのかも知れない。」
また、あの母親か。と、睦は内心で毒づいた。戸惑っている睦に、敦子は畳み掛けるように言った。
「これをね、入れたいの」
月の石を示した。
睦は断ることもできずにただ首肯した。敦子に誘われるままに二階に向かう。玄関という出口が遠ざかる事に不安を感じた。二階は比較的整然としていた。一階ほどの埃っぽさはなく、昼間の熱を放出して冷えた床が、足の裏を押し上げてくる。睦は敦子の部屋に入ろうとしたが、彼女は部屋に入る直前に振り返り、睦の背後にある壁を指差した。
「たぶん、そこ」
「え?」
睦が振り返ると、そこには壁と保護色の取っ手があり、折り戸のラックになっていた。
「物置き。お母さんは何でもそこにしまうから、たぶん、私の宝物もそこにある」
「へえ」
「私、お着替え取ってくる」
睦の承諾を待つこともないまま、敦子はそう言って部屋に入った。
「あ‥‥ちょっと」
いくら敦子に頼まれたとは言え、一人、他人の家探しをするのは気が引けた。ただ今は時間にどのくらい余裕があるか分からない。睦は闇に繋がる階下への階段を一瞥してから、生唾を呑み込み戸を開けた。壁に沿ってそっくり収納になっているので、高さは二メートル以上ある。ラックの左半分に床と平行の間仕切りはなく、ただの空間で、掃除機の先やモップなど、縦に嵩高いものがしまわれていた。厄介なのは右半分で、上は睦が背伸びしてやっと届くくらいの高さから足元まで等間隔に仕切られており、段のひとつひとつにプラスチックケースや布状のもの、スプレー缶など様々なものが収まっている。物のない僅かな隙間から目で奥行きを測ると、大体30cmほど。おまけに睦が強引に勧めた風呂以外、敦子は相変わらずどこにも電気を付けようとしなかったので、廊下は真っ暗である。
睦は焦っていた。右側に当たりをつけて、特殊器官を使い、敦子が言う「丸い缶」を全て引き出して見ることに決めた。花柄という特徴が当てにできなかったのは、無地かよほどシンプルなデザインでない限り、目を凝らして見なければそれが花柄なのか英字なのか、風景なのかキャラクターなのか判別できなかったからだ。
特殊器官を使えば訳もなく見付かると思っていた。睦は、すぐにそれが慢心であることを思い知らされた。なにしろ中には細々した物が大量にある。すぐ、下段にひとつ上面が楕円形の缶を二つ見付けたが、空振りに終わった。最上段の奥にそれらしい物があると分かっても、脚立が無いと取れない。敦子が部屋から出てきたら、椅子を借りると決めて、それを後回しにする。下段から最上段まで順に特殊器官を使っていって、これかと思ったものが全て空振りに終わると、また、最下段に戻った。一度め、脳に伝わる感覚から、引っ張り出す前に「これは違う」と除外したものを結局引き出してみる事になる。
初めは、睦がそこを漁ったことが分からぬよう、引き出したものを全て元の位置に戻していたが、次第にそれが疎ましくなった。焦りが意識の閾に一段と際立ち、上段は最後に折戸さえ閉めれれば良いと適当に詰め込んだ。
実物を見たことがない事が、これでもか、と不利に働いた。缶の中に大小様々な物が入っていて、これかと思っても中身はなんだかよく分からない釘だったり、リボンやビーズだったり、電池、画鋲、クリップ‥‥。虚しい孤軍奮闘を続けるうちに、数十分が経った。部屋に閉じ籠ったままうんともすんとも言わない敦子に声をかけると、「もう少し」とだけ返事があった。
ちまちま中身を確認せず、目ぼしい缶を全部引き出しておいて、後で敦子に確認してもらえば良かったんじゃないか。いや、それよりも結局影のような外観かから絞れる缶の数が少なくないことを考えると、スマホのライト機能を使えばもっと効率よく探せたんじゃないか‥‥。
そもそもなんで、敦子はたかだか着替えの一枚二枚を用意するのに、こんなに時間が要るんだ。不満、焦り、疑念、疲労、後悔。不毛な雑念が頭を循環して、睦はため息を吐き、その場にへたり込んだ。
額を拭うと冷たい汗の雫が手の甲を伝って廊下に落ちた。睦は、頭から一気に冷えて気を失う寸前のその感覚で、俊之の部屋を漁ったことを思い出した。睦は、漸く特殊器官を濫用すると、気分が悪くなることを知った。背後からドアを開く音と
「アツシ君、あった?」
と、いう敦子の声。鈴虫のようなコロコロした声に呑気さがあって、睦の勘に障った。
「ない‥‥」
睦は呟いた。
「本当にここ?」
「たぶん」
睦はイライラして言った。
「捨てられたんじゃないの?もう良いから、行こう」
敦子は返事をしなかった。くたびれた睦の勘がのろのろと嫌な予感を伝えた。しかし、振り向いて敦子の顔を見たときには、もう手遅れだった。
「そんなはずない」
敦子は怒っていた。
「そんなはずない、お母さんが捨てるはずない。そんな酷いことするはずない。アツシ君の嘘つき。信用していたのに。お願い聞いてくれるって言ったのに」
睦が宥めようとするのを一切聞かず、敦子は「嘘つき」と睦を罵り続けた。
にわかに階下の廊下がパッと点灯し、ギィギィと床をきしませて誰かが2階へ上がってくる。見なくとも千鳥足と分かるその足音で、敦子の母親が酔っているのが分かった。しかし、疲労で反応が鈍っている睦は、いざ敦子の母親の顔を見ても、しばらく驚かなかった。
「あ、こんばんは」
口を突いて出たそのことばを、もう一人の睦が他人事のように聞いていた。睦の意識は一人廊下の天上に逃れて、あーあ、もう終わりだよ。あーあ。と、睦を煽った。
「なにしれるの」
「え?」
「なに、しれるの」
何をしているか気付いた睦は
「ええと、敦子さんに頼まれて、探し物を手伝っていました」と答えた。
「はあ?バカじゃないのアンタあ。アツコはなんで寝てないの?」
敦子の母親は、階段の手摺に寄りかかり腰を屈めている。
「あの」
睦が思わず、落ちますよ、と手を引こうとすると、敦子の母親はそれを振り払った。途端に母親の上体が階段の方へ大きく傾いたが、母親はぐっと手摺にかかる手の力を強くしたらしく、その場に留まった。睦は内心ホッとしたが、敦子の母親の目は虚空をさ迷っていた。
ブツブツと何かを言っている。睦に対する讒言ではあるが、とても返事を期待したものとは思えない。怖いんだよ、キモいんだよお前、何時だと思ってんだ、非常識、クズ‥‥などなど。
睦が硬直していると、泥酔女は突然
「それで!なんでお前起きてんの?!」
と叫んだ。
睦の傍らに、やはりただ固まっていただけの敦子は、絞り出すように言った。
「お母さん‥‥私の‥‥」
敦子の母親は、彼女の声を遮り叫んだ。
「うるさいんだよ、お前は。いちいち口答えするな、寝ろ、寝ろ」
恐らく「寝ろ」とか「死ね」とかいろんなことばが混じった奇声を発して、敦子の母親は敦子に飛びかかった。敦子の悲鳴が響いた。睦が敦子を庇おうと彼女に覆い被さると、なぜか敦子は、狂気の母親だけでなく睦にも恐怖を感じたらしい。睦耳元でつんざくような悲鳴をあげて、睦から逃れるべく身を捩って階段の方へ逃げた。睦は混乱したが、逃げた敦子を尚も追いかける敦子の母親を止めようと、腰に取りすがり全身の体重で彼女を留めた。
どうするんだよ、あーあ。
必死の睦を、睦の意識の一部が安全圏にどっかり居座ったまま煽りつづけた。
「敦子!」
睦はそれを無視して叫んだ。
「さっきは悪かった。俺が悪かった」
敦子は今や紙のように上から舌まで真っ白だった。瞳だけが、洞窟の入り口のようにひたすら黒い。
「お母さんには俺が謝るよ。敦子の母親が許してくれたら、ちゃんと敦子の宝物も探して持っていく。だから先に外に行って!」
敦子の母親の腰は柔かかったが、睦を振りほどくためか、たまに渾身の力を体幹に籠めて身を捩る。睦は気が抜けなかった。
「約束」
敦子は呟いて、ゆっくりと、しかし着実に階下へ進んだ。ドアが開いたことを示す、空気が唸る音を聞いて、睦は力を弛めた。それがいけなかった。睦の母親は怒りに任せ、階下に向かって睦を突き飛ばした。なぜ人は落ちるときに、時間が止まったように感じるのか。呼吸を忘れるように、ひょっとすると心臓も鼓動を忘れているのかも知れない。段差の一つ一つ。木目が見えるほど鮮明に、睦の網膜に焼き付いていた。睦は、階段の二三段、緩やかな弧を描いて落ち、寸暇の後、咄嗟に手首で体重を支えようとしたのだ。脳に刺すような痛みが走った。一度手を突いてしまった以上、他の部分を宙に浮かせたまま、手首だけの力を緩めることはできなかった。勢いのまま一回転し、尚も止まらず、睦は一階へ滑り落ちた。最下段で睦は腰を強か打ち付けて、睦はいもむしのように悶絶した。
たとえ体の末端や命に別状ない外傷でも、上半身と下半身一ヶ所ずつ痛いと、もう全身が滅茶滅茶になっているように感じられた。呼吸は浅く途切れ途切れにしかできなかったが、睦は痛みに悶えながら、自分のどこが痛んでいるのか正確に把握しようとした。左手首と右側の尾骶骨が、ズキズキする。
痛みの信号が同時に脳に向かって発信されて、ビリヤードのように弾かれ全身を巡っている。睦は手首を庇いながら、肩を壁に預けながらなんとか立ち上がった。リュックは二階に置いたままだが、取りに行く気などあるはずがない。落ちたとは言え、二メートル弱歩けば出口があるのは、蜘蛛の糸よりはるかに丈夫な救いの糸が、地獄に下ろされているようなものだった。
睦は痛みで、筋肉の収縮も思うままにできず、大量の汗をかきながらも、必死に玄関へ歩を進めた。何かが耳を掠め、次の瞬間に今度は肩に激痛が走っていた。睦はぎゃーとかなんとか叫んだ気がするが、このときはもう自分が何を言ったかなんて、どうでもいい。気が触れたように辺りを見回すと、スパナが白々しく廊下に転がっていた。私は何にもしてませんよ、という具合に。
金属の無機物を涙目で睨み付けたあと、後ろを仰ぐと、そちらもまた足元の覚束ない中年女が、壁に頼りながら、一階へ来ようとしていた。睦が胴若すると、女は攻撃成功の甲高い笑い声を上げた。
女の胸元まで伸びる長髪は、まるで一本一本が生き物のように、四方へ好き勝手に広がっていた。ヨロヨロしながらキシキシの髪を振り乱してケタケタ嗤うその女は、間違う事なき鬼婆だった。
睦は半狂乱で、ともかく体を右へ左へ捩って前へ進もうとした。叫んで敦子に助けを求めようとしたが、口は金魚のように僅かながらの空気を食べるだけで、有意な音はちっとも出てこない。
最初のスパナ以外、睦に当たらなかったものの、その後も雑多なものが次々と後ろから飛んできた。鬼婆が棚から引っ張り出してその場に放置した物を手当たり次第に投げてきているのだと、睦はようやく気付いたが、現状を把握するだけで突破口をようとして見付け得ないポンコツの頭こそ叩きのめしてやりたくなった。
俺は本当に背後の鬼婆に殺されるかも知れない。
そうだ、ロバートだ。不意にあの陰気な映画、「誰が為に鐘が鳴る」を思い出した。ああ、ロバート。俺はあいつが羨ましい。ゲリラ兵が決死の作戦を決行したとして、二階級特進など望めない。それでも、少なくともマリアと相思相愛だったなら、自分の中にある愛が本物だと確信していたなら、進んで選んだ道ではなく、たとえそれが抗えない運命だったとしても、死を受け入れる事もできただろう。
ただ俺は、ここまで来て、ここまで来ておいて・・・不満を抱いている。後悔している。
好きでもない女のために、俺はなぜ満身創痍になっているんだ。心を病んでいるのを可哀想だと思ったがために? 違う。俺は期待していた。可愛い彼女を得て、周囲に羨ましがられる夢想。敦子との心暖まる恋愛。睦にだけ注がれる天使のような笑顔。幻影。夢想。イメージ。
好きだよ。私も。みたいな。
風を受け入れてそよぐ木の葉のように美しく、甘酸っぱい恋の思い出。
しかし、敦子を母親の呪いから解放するために、腐臭のする執着ともども注がれた親の愛情の栓を抜けば、敦子に何か残るだろうか。そこに果たして敦子の本質みたいなものが。
何もないのを透明で綺麗だと思い込んだ。そこには果てない希望が広がっていた。
しかし、元々睦が望んだことは、敦子で無くても代替が効のだ。
それがいけなかったんだろうか。生き物を白いキャンバスに見立てて好きに夢想した事が、それほど業の深い事なんだろうか‥‥。先生。そうなんですか?
睦はとりあえず無傷の右手を使ってドアノブを下げ、全身を使って開けた。普段ならどうということもない気圧が睦の力に抵抗するのが恨めしかったが、何とかドアは開き、庭に敷き詰められた砂利に倒れ込んだ。
敦子。
睦は彼女がどこにいるか、床に臥したまま顔だけ上げて、確かめようとした。睦の意思に反して体は仰向けに転がされ、鬼婆が睦に馬乗りになった。鬼婆が胸を上下させ荒く息を繰り返す度、アルコールと胃液の混じった臭いが、睦の鼻に流れ込んできた。なぜこの鬼婆は、執拗に俺を攻撃するのだろう。
勘弁してくれ。
睦をそう叫びたかったが、腰に荷重が加わり、その痛みに歯を食い縛るしかない。鬼婆は、不明瞭な事をなんだかんだと呟いたあと、突然睦の顔に何かを振りかざした。眼前に迫る白刃の煌めき。まさかと思って右手で鬼婆の手を止めると、そのまさかである。小さくて細くて、ぎらぎらと連なった嫌らしい刃物、鬼婆はカッターで睦を刺そうとする。
中年女と若さの盛りである睦の力は、本来なら比べ物にならないが、あいにく睦は弱りきっていて、左手も使えない。震える右手で鬼婆の動きを止めながら、歯の切っ先から顔を反らそうとするが、腰は相変わらず断続的に痛みを訴えており、その痛みに反応すると瞬間的に手の力が弛む。鬼婆を蹴り飛ばして逃げようとも試みたが、下半身はどのような姿勢でも最早、痛い。痛みと鬼婆のどちらかに「タンマ」を訴えたが、全く聞き入れてもらえない。もしかしたら怪我するだけで死なないかも知れない、という期待にすがり、目を閉じようとしたが、やはり意識のある状態ではどうしても刃物が顔を裂くことを受け入れられなかった。
ふと体が軽くなって、辺りを見回すと、典子がいた。鬼婆に馬乗りになって、躊躇なく彼女を殴打している。睦はこれ幸いと立ち上がり、その場から逃げた。敦子は、玄関先のモチノキの根本にうずくまり泣いていたが、睦はそれを無視して閑静な住宅街を一気に走り抜け、駅へ向かった。韋駄天が憑いているかと思うほど、体は羽のように軽い。
しかし気を抜くと鬼婆が後ろに迫ってくるようで、睦は息も付かず一気に住宅街を走り抜け、駅の改札をくぐり抜けた。睦はようやく一息ついた。風の音だろうか、誰かがすすり泣く声が聞こえたような気がしたが、駅構内には誰もいない。
それだけでなく、風があるのはどうやら睦の遥かに上、建物に進路を阻まれた風が唸っているような音が微かに聞こえるだけで、睦の周りは凪いでいる。人気はおろか、あらゆる生物も風も光もない。そして、待てどもくれども電車は来ない。
睦は恐ろしくて居ても経っても居られなくなり、線路に沿って走り始めた。典子をどうやって振りきったのか、悪い予感は的中して、鬼婆はいつの間にか睦のすぐ後ろに迫っていた。
がむしゃらに走った。
脇を通り過ぎる景色は様々に変化していたが、睦のたどり着きたい場所は見付からない。その内、こんなスピードで走っていては足がもつれるのでは、と不安になった時はもう転んでいた。
鬼婆は睦の隙を逃さず掴みかかってきて、睦の顔に再び凶器を振りかざした。刃物はカッターではなく、禍々しい鎌のようなものに変わっていた。睦はギュッと目を閉じ痛みを覚悟した。おそるおそる睦が目を開けると、痛みが襲って来なかったのも然り。睦の体を典子が全身で覆っていた。彼女の胸には鎌の刃先が貫通して見えていて、睦は驚いて目を白黒させるばかり。
「大丈夫よ、アツシ」
不適な笑みを浮かべながら典子は言った。鎌の刃先は典子の胸を息苦しそうに右往左往した後、退いていった。鬼婆が穿った典子の坑からは、なぜか一滴の血も溢れず、均衡を失った周りだけが砂壁のようにボロボロと崩れた。睦は不思議な光景に目を奪われていた。胸の坑から差し込む一条の光。雲のない夜空にあかる月が、どこに向かおうかといざよっている。鬼婆は、睦の油断を許さずに、穴から睦を覗きこんだ。睦は洞穴のような黒々とした瞳に身を竦めた。
鬼婆は意地悪く嗤うと、鎌での攻撃を再開した。
しかし典子の体を張った「盾は」強力だった。鬼婆の攻撃に怯むどころか、鬼婆が穿つ先から、傷、というより崩れ去った黄肌色のコンクリートのような物は、瑕疵も残さず修復されていった。典子の体は膨張し、やがては体節の全てが失われ、半円形のドームになって睦を覆っていた。
先生は、人間じゃない。もはや、人の形を留めていない。
その事にようやく気付いた睦は、おそるおそる尋ねた。
「先生、大丈夫?」
「大丈夫よ、アツシ」
人の体を失っても、仏像のような虚心坦懐の顔だけは、睦の目の前にあった。
ドームの外では、鬼婆の嗤い声が微かに聞こえた。
いや、嗤っているのではなくて、泣いているのかも。
ひょっとすると鬼婆ではなくて、誰か別の。睦はドームに耳を押し当てて外の様子を探ろうとしたが、何も分からない。
南戸の声のようなモゴモゴした声が聞こえたかと思えば、それは春。彼女の歳のわりにハスキーな大人びた声。それとも、敦子の呑気なハミングにも、聞こえる。
鬼婆は、とっくに何処かに行ってしまって、外はもう平和なのを、俺が知らないだけだろうか。
睦は必死になって、典子の元腰辺りの壁に耳を押し当てたが、外に響く音は、徐々に遠退くばかりだった。やはり鬼婆が猛威を奮って、外を行く人に奇襲を仕掛けているかも知れない。しかし、睦は矢も盾もたまらなくなり、
「先生、どいてよ」と叫んだ。
「大丈夫よ、アツシ」
睦が掌で叩いても、典子の壁は乾いた音を立てるだけでびくともしない。典子は同じことばを繰り返すだけで、頑として動こうとしない。
「先生!どいてよ。もういいから、どいてよ!」
睦は、怒って典子を叩いたり蹴ったりした。
「先生、どいて、どいてよ。頼むから、どいてったら」
遮二無二叫んでいると、睦に覆い被さっていた柔らかい何かがむくりと頭をもたげた。それは春だった。やっとどいてくれた。睦はホッとした。
パーティションに区切られ、たった一本点滴のバーが聳える殺風景な部屋。靄のかかった視界が徐々に物と物との境界をハッキリさせた。睦はそこに鬼婆がいない事を認めると、朦朧とした意識のまま春に呟いた。
「ごめん、ハル。あのとき俺、無神経だった。悪かったよ‥」
「え?」
と目を丸くした春は、よく見ると春ではなく典子だった。睦も驚いて目を見開いた。ああ、また典子に言ってしまった。先生を怒らせて、敦子を傷付けて、鬼婆を怒らせて、おまけに春にまで余計な事を言っていたのだ、と。自爆型の、どうしようもない餓鬼だと、軽蔑されるだろう。癪。癪だが、助けてくれた。先生、ありがとう。
「先生、あの、どうしよう‥俺、ハルを怒らせた‥」
そう独白すると、典子はいつになく優しい声音で言った。
「大丈夫よ、アツシ。あんたよくやったわ。春はとても気が強いの。忘れたフリをしてあげて。今は休みなさい」
休みなさい、という呪文にかかり、睦は再び目を閉じた。薄暗い部屋の中。再び意識を夢中に手放すとき、睦は、廊下の灯りに反射する典子の頬を見たような気がした。
それを典子の第六感だと言うのは、あまりにも大袈裟だ。敦子の家から最も近い駅でいくら待っても、睦と敦子はやって来ない。睦が敦子の説得に手間取っているとか(それは事実である)、敦子が支度にぐずぐずしているとか(それも事実である)、いろいろな事情が想像できたが、それにしても連絡のないまま、あまりに長い時間が経っている。
典子は、まさか敦子の母親が帰って来て、睦と敦子に危害を加えていないか心配になった。
それもやはり事実だったわけだが、それは典子の勘と言うより、十人並みの想像力に過ぎない。典子は行き違いを心配しながらも、改札を離れた。
典子の恰好は部屋着に近い。白のタンクトップに麻のカーディガン、アースカラーで七分のパンツという出で立ち。何しろ深夜とは言え残暑が厳しい。温湿度計の機能が付いた腕時計を見ると、ただその場で待っているだけで汗が噴き出たその訳がよく分かる。
皮肉な事に、敦子の家へ向かって緩やかな坂を上り始めてからの方が、心地良い風が頬に触れて、わずかながらの涼気を感じた。駅に沿う大通り周辺にはレストランや商業施設があるが、通りを一つ違えると、そこはもう閑静な住宅街である。
駅周辺の店も大方が閉店していて人通りは疎らだったが、住宅街の方は水を打ったように静まりかえっている。典子はすれ違う人の顔を確認しながら歩を進めた。顔と言っても、数十メートルごとの電燈と月あかりだけでは光源に乏しい。しかし、駅から住宅街へと、典子と同方向へ行く人はあっても、今時分から駅へ向かう人は無に等しい。シルエットだけでも、年若い男女のそれなら多少横見していても見落とすはずがなかった。
典子は一度、生垣から伸びる棕櫚竹の細長い葉が、月に影を作っているのに気を取られた。
意外ね。アツシは真剣に敦子の事を悩んでいた。
もっと軽薄な子だと思っていた。
敦子の家に行った事を評価するわけでも、睦の相談に真剣に乗らなかった事を後悔するわけでもなかった。ただ、意外だった。
典子は軽く頭を振って、また歩を進めた。今考えるのは止そう。まず、典子の目に入ったのは、敦子の家の玄関先で蹲っている敦子その人である。典子は呑気に一時間弱もの時間を駅で待っていたことを、後悔した。溜息を吐きながら敦子の肩に手をかけた。
「大丈夫?アツシは―?」
そう言いながら、典子はやっと異様な玄関そのものを見た。ことばを失った。灯りの無い玄関先では、敦子の母親も睦も区別が付かなかった。ただ「誰か」が「誰か」に馬乗りになって襲っているシルエットだけが、典子の目に飛び込んできた。
それからの典子の行動はほとんど反射である。こちらに無意識である「上」の方の「誰か」に走り寄って、その勢いで蹴った。手ではなく足を使ったのは、蹲ったかれらを引き離すのに、殴るよりは蹴った方が早いだろうと考えただけの事である。もし「上」が男なら、典子はそこで警察を呼ぶつもりで、スマホを握っていた。「誰か」は玄関の上がり框に易々と転がっていった。
表を返したその「誰か」が、敦子の母親にあることを認めると、典子はスマホをしまって、その粉を吹いた顔を激しく打擲した。赤く腫れるはずの顔が、サッと青白くなったので、典子は女から身を離した。女は噴水のように嘔吐して、そのまま気を失った。典子は吐き戻しで窒息しないよう、女を回復体位にすると、身を翻して女の下になっていた方の様子を窺った。それが睦であることを認め、さらに息が止まっているのを知って、典子も一瞬呼吸をするのを忘れた。
震える手で、睦の上衣を剥いだ。肩は酷く腫れている。右手首も折れている。しかし、致命的と言えるような傷は見当たらない。典子は敦子に駆け寄り、
「救急車を呼びなさい。ストレッチャーは二台よ。良い?」とスマホを押しつけた。
典子の顔色が変わっている事に恐怖した敦子は、ただ頷いた。典子は再び睦の元に駆け寄り、まずは気道の確保。二度、睦の唇から典子の呼気を流し込んだ。睦の胸の上で手の甲を重ね、上半身の体重を規則正しいリズムで睦に預けた。直に救急車が来た。隊員は玄関先で倒れる二人を見た。典子は即座に
「こちらの方が重症です」
と、叫んだ。
睦の心臓が止まっている事を告げると、救急隊員はAEDを持ってきた。
「離れて下さい!」
殆ど「邪魔」と叫んでいるのと変わらないような語調で隊員は叫び、典子と睦の間に押し入った。AEDの一回目のショックでは、睦の心臓は止まったままだった。
呆然として座り込んだままの敦子が、思い出したように呟いた。
「もし、アツシ君が死んだら、私も死ぬ」
敦子の手は祈るように胸の前で組まれており、掌からキーホルダーが覗いてカタカタと音を立てていた。典子は猛然と腹が立って、敦子の頬を手の平で打った。怒りに身を任せたため、力の加減が効かず、敦子の青白い頬は見る間に晴れ上がり赤く染まった。敦子の瞳から滂沱の涙が零れ落ちた。救急隊員は、驚いて典子を制した。落ち着いて―
睦は気を失ったままだったが、AEDの二回目のショックで、睦の心臓は目を覚ました。
「ホラ、アツシは死なないわ。だから、アンタも生きるのよ」
「はい」
敦子は蚊の鳴くような声で返事をした。
いつの間にか救急車の中に乗っていた典子は、「患者がケガをした理由」を尋ねられていた。
「分かりません。私は直接見ていないですから」
では―と、退院が視線をずらしたその先に、敦子が身を屈めて座っていた。じゃあ、敦子の母親が乗っている方の救急車には?と典子は思った。どちらにせよ、敦子が状況を説明できるとは思えない。案の定、敦子はただ首を振って、救急隊員の前では一言も喋ろうとしなかった。
「あの、失礼ですけど、貴女はこの子の」
「教師です。今は夏休みですけど、急ぎ相談したい事があると言うので行ってみたら、こうなっていました」
「その子は…」
「彼の友人です。もう一人運ばれた女性の娘です」
典子の説明に、救急隊員は首を捻るばかりだった。もしかしたら、隊員の頭を悩ませなくとも、ただ知情のもつれの喧嘩だ、とでも言ってしまえば、隊員は納得したかも知れない。いや、典子が言わなくとも、一対の男女と女の親とだけ情報を与えれば、行き付く先は下世話な想像ぐらいしかかも知れない。けれど、彼らがどう想像しようとどうでも良いのだ。ただ典子は、睦が死にかける事になろうとは想像しておらず、自責の念に捉われていた。
典子は睦の事を、常に危なっかしい子だと思っていた。怪我しても知らないから、と斜に構えていた。けれど、いざ実際に傷付いているのを見ると、典子は本当に駄目になってしまう。
頭が電気を流したように痺れて、手足が震え、怒りでいっぱいになってしまう。だから言ったのに、だから言ったのに…。きっとその、脳の麻痺や手足の震えは「忠告を無視された」事が怒りの原因なのだと、典子は生徒に警告をしなくなった。それでも駄目だった。生徒が傷付くと、耐え難い苦しみが典子を襲う。しかし、尚も典子が打ちのめされていったのはその後だった。典子は生徒が感じる痛みに対して、段々鈍感になってきている。典子が教師になりたての時に、仕事を教えていた先輩教師は言っていた。
「生玉先生は真面目過ぎるのよ!同情し過ぎると、もたないヨ。もっと適当にしないと、ね」
学生時は、些細な変化も見逃さない観察眼が尊重され、そしてそれを磨いてきた。
典子には、生徒の何を見るべきで、何を「見ないのが良い」のか、区別が付かなかった。
春を支えるために就職したはずが、春を見る度に苦しく、次第にその心を深く穿つ気力が、萎えてしまった。
典子は頑なに、指導要綱書かれている事以外は生徒に伝えない事で、自分を守ることにした。生徒の心に触れない事で、生徒の心を守るようにした。
典子が打ちのめされるのは、曲りなりにもそういう教師としてのスタイルが定着した頃。
生徒らの心の潮汐を遠ざけ、凪いでいる自分に気付いた時である。典子は教師に向いていない訳ではない。我流でも、仕事を続けるやり方を見付けているのだから。しかし、ジュンシの言うように、優しいとか責任感があるとか、人格でもって教師であるわけでもない…自己嫌厭の根には、神経質な性分があるだけ。
教師として成り立っているのは、先輩教師の言うよう、適当にしたからだ。
典子は、昔嫌気していたはずの「教師」になっていた。
けれど、典子は、教師に「凪」を求めていただろうか。
典子の両親や、楓姉さん、春、長谷川先輩。典子の気持ちを揺らしていった人の力が、典子を形作り決定していった。
移ろいやすい人たちに傷付き、悩みもしたが、それでも彼ら自身に居なくなってほしいと本気で願った事があっただろうか。
楓姉さんは、そして春は、私に居なくなってほしいと願っていたのだろうか。そうではないのかも知れない。しかしそうかも知れない。分からない。ことばは嘘を吐き、心は変わるから・・・。これで良いのだろうか。
確信が持てないまま正解を決める事は、典子にとって、あまりにも横着で、瑕疵を自分で舐めているだけのような嫌悪感がある。ただ惰性のような懊悩を続けている。
典子は、結局、生徒に近づく動機も、勇気も持てずに、凪いでいる。生徒の、睦の熱情を羨ましいと思いながら。
睦は、外傷の手当てを受けてから入院棟へと移された。
消灯時間をとうに過ぎていたが、睦の両親が来る間、典子は睦の傍らにいることを許された。
生気を取り戻して眠る睦の顔から、どうやら命に関わる傷は無かったようだと安心はしたものの、その顔は苦しみに歪んでいた。
寝苦しいのか、それとも傷が痛むのだろうか。典子は自分の想いや企みを、もう一度思い起こした。敦子には、睦とはまた違う、センシティブな一面があった。
学校の成績は中の下、体育は欠席が多すぎて留年スレスレ、帰宅部、内気と、外見以外にことごとく目立つところのない彼女は、しかし何故か学校生活への関心が人一倍強く、月に半分来れば良い方という登校率の悪さなのに、クラスメートと全教職員の顔と名前を覚えていた。
映像記憶やサヴァン症候群という認知度の高い卓抜した能力(能力というべきか症例というべきか)を疑ったが、敦子のそれは精度の高いものではない。
もし本を読むだけで内容のほとんどを記憶してしまうような能力なら、歴史の教科書を虫食いにしただけのような試験問題で「平均点」という敦子の成績は、あまりに普通だった。
前担任から、敦子の話を少しだけ聞いていた。敦子は極度の人見知りで、しかも家庭環境に「やや」問題があると。
家庭環境の不和など珍しい事では無いから、傍から見た他人がそれを問題だとする事こそ問題になる世の中である。前担任はそれを承知していたからこそ、ややだの多少だの、含みのある言い方しかしなかったのだろう。
実際、典子が敦子の母親と話をしてみると、確かに彼女は「多少」勘が強く、敦子は「多少」そんな母親に抑圧され、周囲の人間とうまくコミュニケーションを取れずにいるように見えた。人と仲良くなるために、たとえば流行りの曲や動画の話、つまり自分と相手に直接関わらない事なら何でも良い、それを話題にするのが無難だし、敦子くらいの年齢なら、大半が深く考えずに難なくそれぐらいの処世術を身に付けている。
たとえ関心事が大方のそれとズレているような子どもも、話し相手の一人も見付けられないような事はあまりないし、もしそうでも、他人への関心より先に自分が受け入れられない事を察知して、自分の殻にさっさと閉じこもってしまうものである。
敦子の特殊なのは、他人への好奇心を抑えきれず、相手の最もデリケートなところが見えると、そこへ直接切り込んでしまう不器用なところにあった。教頭から「不登校児の心に寄り添う事が大事だから」と急き立てられるようにして、敦子に話しかけた。
「何か悩んでいる事があるの?」
「いいえ」
彼女は歌うような調子で言った。
「先生の方こそ、福吉さんと仲直りしなくて良いんですか」
春と典子の軋轢は、生徒はおろか教師陣の誰一人として知らない筈だった。典子が、教師として春と関わるとき、刹那に表れる両者の緊張だけで、誰が二人の確執に気付けると言うのだろう。典子は背筋が凍るような気がした。しかし思えば、敦子にも、程度こそ低いにせよ、世間と家での顔を使い分けるという意識くらいあったのだ。
人並み以上の他人への好奇心と、それを攻撃的な形で発露させる無神経さは、自身を守るための諸刃の刃だったのかも知れない。敦子は、学校の内外で決して彼女の母親に逆らわず、彼女への反感をおくびにも出さない代わり、母親の前では寡黙過ぎた。
典子は生徒に保護欲から近付く事を嫌厭していたが、敦子についてはアカデミックな好奇心から積極的に話しかけるようになった。典子にとって、敦子がクラスに馴染めるかどうかは二の次だった。
ただ、単に敦子と話すだけでも、敦子の母親は彼女の友人関係に対して執心の鬼で、敦子には常に母親の畏れが付きまとい、まともな会話ができない。
ならば敦子を少しでも母親から引き離そうと画策するうち、あっという間に周囲に違和感を禁じ得ないほどの肩入れしてしまった。
更に滑稽なのが、「生徒の心がどうだ」というご高説を典子に呉れたはず教頭が、まず「やり過ぎだ」とか「生徒の家庭に首を突っ込むな」と典子に説教を始めた事だ。教頭の説教など典子にとって大事ではなく、「そうですね」とか「大変申し訳なく思っております」とか心にもない返事だけで事なきを得ていたが、しかし教頭の言う事が「結果として」正しかった事に皮肉がある。
典子は、敦子や敦子の母親と話すうち、確かに幾つかの家庭事情を鮮明に理解する事はできたが、だからと言ってどうする事もできない。
敦子の母親には自分の考えを疑う芽が無い。典子のような敦子の母親にとってポッと出の存在が、それを植えたとしても腐り枯れ落ちるだけだろう。更に悪くすればその八つ当たりは敦子に行く。敦子も、敦子で母親に対抗しようと言う芽は無い。その事に気付いただけ、成果なのかも知れない。引き際を見極めるのもまた、観察なしでは出来ない事なのだ。
典子は、確かな結果を期待して、敦子とはまた違う勘の良さと不安定さのある睦を、彼女に引き合わせたわけではない。どちらかと言うと捨て鉢な思い。敦子が自身の才能に気付かずに、いつか母親によって致命的な打撃を加えられ腐り落ちるなら、せめて、典子自身がせいぜい場を引っ掻き回してからにしてやろうというデモニッシュな考えに基づく。
だから、敦子が、母親の憤りを前に睦を「友だちだ」と庇った事には、本当に吃驚した。睦が何を言って、敦子の心を絆したのか、問い質したくなった。
年相応に多感で移り気な睦は、社交性のない敦子に、じき厭きるだろうと思っていた。この予想も、睦は裏切った。睦は意外にも敦子を真剣に想い、意外にも真剣に、その気持ちが本物かどうかを悩み、さらに意外な事に、真剣に、その気持ちが嘘である可能性に怯え、苦しんだ。
だから睦はこんな事になっている。睦がここまで傷付いたのは、典子のせいだろうか。典子は再び自己嫌悪に陥りそうになる。いいや、誰も典子のせいだと思わない筈だ。睦だって、典子の責任だとは夢にも思わないだろう。誰も典子を責めはしない。
然るに典子は、睦の両親がこの病室に来た時のために、ただの紋切型の謝罪を睦の両親の胸に迫るものに昇華するべく、感傷的に訴えるシミュレーションをするべきだ。典子の心は凪いでいる。この時まで、凪いでいるつもりでいた。しかし、典子は不意に、睦に対する嫉妬に喘いだ。
楓姉さんが、典子に対してあんな陳腐な罵倒ではなく、もっと殴るなり殺そうとするなり典子を然るべき断罪に処していれば、彼女はこんな、見えない業にいつまでも苦しむ必要は無かったのではないか。信仰を持たない典子が、こんな時にだけ「業」だ「神のご意志」などと、天を恨む事が理不尽であるとわかっている。
しかし理不尽と言うのなら、結局、運や天の采配というのは、この上無く理不尽なもののだ。典子に業があるなら、楓より先に典子を縊り殺せば済む。典子の狡猾を責めるなら、睦をこんなにボロボロにしなくても、典子に矢でも降らせれば良いではないか。典子は声を押し殺して泣いた。
「先生、どいてよ…」
睦の呻き声に、典子はハッと顔を上げた。この子はいつから意識があったんだろう。いぶかし気に顔を覗きこむと、睦は寝ぼけているのか、典子を春と勘違いしているようで、モゴモゴと何か言っている。やがて自分の間違いに気付いたらしく、
「先生どうしよう。俺、春を傷付けた…」
なんの懺悔か典子にはピンと来なかったが、春が睦に好意を抱いているらしい事は知っていた。その事で睦が何か春の逆鱗に触れるような事を言ったのだろうと当たりを付けて、適当に宥めた。睦は再び目を閉じた。少年は何やらいろいろ考えていたらしいが、眉や頬には、まだ彼が乳児だった頃を思わせるあどけなさが残っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
