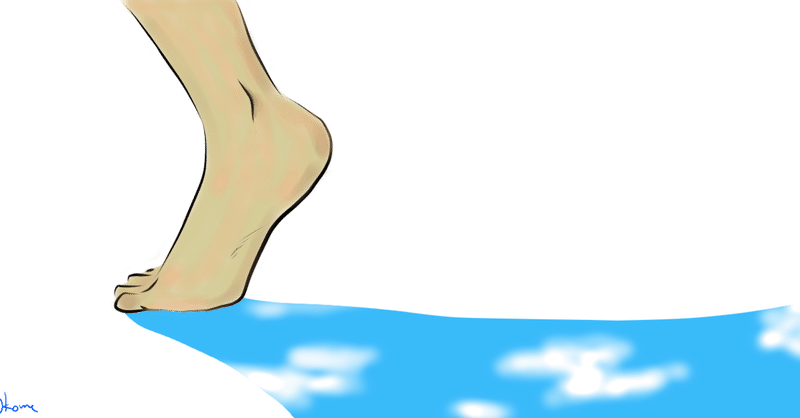
〇〇らしさ と TPO
息子の学校から、校則見直しの手紙が届いた。
きっかけは、靴下の長さを生徒が学校に確認したことらしい。
結果、長さ、色は校則で指定しないとなった。
手紙は続く。
TPOという言葉の意味と説明が書かれ、
学生らしささから逸脱しない・・・。という一文が載っていた。
自由な学校生活を送るには、自分たち側で自由を制限されないよう、意識することが大事ということも書かれていた。
以前の私は、この手紙に対し何も感じなかった。
学生らしさを考え、靴下を選択し、使用するのは生徒になるが、指導するのは先生。
生徒たちが「先生の考えを忖度して行動する」流れにならないだろうか。
そうするように、言われている気がする。
学生さしさを逸脱する靴下。学生らしくない靴下。
どんなのだろう。
生活指導や学校内で先生からの指摘?指導では、その時代の、その先生個人が持つ「学生らしい」に非常に影響されている。
靴下に学生らしい物ってあるんだろうか。学校生活にふさわしくない靴下って、色?値段?どんなものだろう。
例えば、高価な靴下をはいていたら、裕福だと思われて誘拐されたり、カツアゲされたりするとか?
自分の身を守るために、学校に「イケてる」や「いいね」を持ち込まないでという事だろうか。
学校生活で誰かを傷つけるような靴下?
思いつかない。
お手紙には 「自由」 の文字が書かれているけれど・・・・なんだろう・・・先生受けするものを選ぶよう言われているようで息苦しい。
そんな風に思う私って、「忖度する」人間なんじゃないだろうか。
「考えが浅い」とか、「へりくつ」と言われそうだけど、もやもやする。
都立北園高校の頭髪指導の事を思い出した。
やっと、都立北園高校生の言っている事、問題にしている事が分かってきた(・・・気がする)。
そして、「他者の靴を履く」という言葉が浮かぶ。
校則は「誰の」「何の」ためにあるのか。
大人側も理解を進めて、これからの子どもたちが、安心して校則を考えれる社会に・・・。
私は・・・のところで何ができるだろうか。
2021.11.5 加筆
少し前、私は、ピティナ広報部さんが発信されているショパンコンクールの記事を読み、未来に対し希望を感じられ、楽しい時間だった。どの記事も素晴らしく、色んな面ですごい時代にいることを気づかされる。
おそれおおくも・・・若いコンテスタントさんたちを「若さ」という共通項だけで、息子たちに重ねたり。
など、楽しい時間で元気をもらえた記事だった。
それらの一つ、「ショパンコン日記~エピローグ:音楽で世界を元気で平和にするために」で、ショパンコンクールが長年続いてきたことについて書かれていた。
「伝統ある○○」といったとき、私たちはつい、その○○が長年変わることなく、ずっと古き良き形で残されてきた、とイメージしがちです。
しかし、数十年、数百年という単位で存在し続けてきたものこそ、実は時の流れや変化に柔軟に対応しながら、生きながらえるための工夫をし、決して思考停止状態に陥らず、代謝と呼吸を続けてきたのだと思います。だから今があり、生き長らえている。
「・・・決して思考停止状態に陥らず、代謝と呼吸を続けてきたのだと思います。・・・」この一文がずっと心に残っている。
今、私の中で「校則」の隣にいる言葉だ。
校則、ルールは一度作ったら終わりでなく、時代、関わる人の変化にあわせていくもので、校則を見直すことって大事なのだと思う。
未来の校則。
「学校に関わる生徒と先生が、安心して話しあえる」そんな学校の校則だと思う。
私にできることは、言葉(文字)にして、議論に参加することだと考えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
