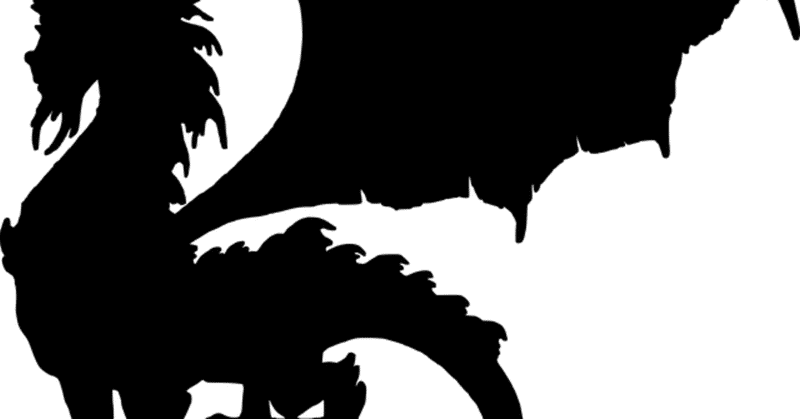
【おうた】最後の夢から、一万年。【サラマンドラ】
■たぶんおそらく、の話だけれど、
『サラマンドラ』は、私にとって、
生まれて初めて〈聴いた〉歌だ。
ぴかぴかの幼稚園生だったころに。
当時は、尾藤イサオが歌ってるって知らなかった。
というか、「みんなのうた」で流れるそれぞれの楽曲について、
歌っているのが誰か、ということを考えてみたことがなかった。
というか、今思うとへんな感じがするんだけれど、
自分が聞いているそれぞれの歌を、
〈歌っているひとがいる〉ということを意識したことがなかった。
歌は歌単独のかたちでそのへんをふよふよ流れていた。
歌に人間がくっついていなかった。
そういう〈感じ〉は思い出せるのだけれど、
今となってはもう、そんなふうに歌を歌だけで聞くことってできない。
だからこれは私が、
必要以上にこの世界と仲良くなりすぎる前の話なんだとおもう。
■そのころ、というのはええと、
3歳とか4歳とか5歳ころ、のどこからへん、
ものごころついたかどうだかね、というころの自分には、
うた、というのは、「歌うもの」だった。
アウトプット用のツールだった。
まあ、母親の鼻歌とか、幼稚園で習う手遊び歌とかね、
「みんなのうた」もそうだけれど、それら全般を、
てはじめにはまず、聞いていたことに違いはないのだろうけれど、
それはたぶん、
自分で歌えるようになるまで聞いていた、
のであってつまり、自分で歌うために聞いていた、
のであってつまり、誰かが歌うのを聴いていた、
というのとは、だいぶん意味のちがうことだったように思う。
いま、私は歌を歌わない。
や、鼻歌とかは歌う。
失せ物を探しながら即興の鼻歌とかは歌う。
たまに名曲が生まれる。いやそれはどうでもいい。
言いたかったのは、アウトプット用のツールとして、
というかなんだろうつまり、
自分以外の世界全般に対して、
聞いててね、という意味で歌うことはしない。
子供のころに歌ったようには、歌わない。
ちなみに、二次会等でカラオケに行ってもあんまり歌わない。
歌うのが嫌いなわけじゃないし、
たぶんものっすごいヘタっぴとかそういうわけでもないんだけど、
どちらかというと聞いてるほうがいい。
聞いているほうが好き。
もはや仲良くなり済み、の世界の中でいつのまにか、
うた、という種類の快楽は、
享受するもの
に変わっていた。
とりこむもの、とりいれるもの、
すいこむもの、すいこむために浮遊するもの。
■その変わり目の、
いちばんはじめのところに、
『サラマンドラ』がいて、
(当時は歌い手の存在すら認識していなかったにせよ)
尾藤イサオの声が、あった。
ということに、
こんなに大人になってから気づいて愕然としている。
というのも、ついこのあいだ、わたくし自身から、
①尾藤イサオがすごい。
②みんなのうたの『サラマンドラ』がすごい。
という情報を、別々のタイミングで
(加えて不必要なまでに熱く)
聞かされていた某人から、
「YouTubeで『サラマンドラ』聞いてみたよ」
および、
「思った以上に渋い曲でびっくりしたよ」
という主旨の感想に加えて、
「ずいぶん小さい頃から尾藤さんが好きだったんだね」
というメッセージを頂戴して、
「?」
となったからである。
「いや、え、何?」
となったからである。
「みんなのうた」の優良視聴者であったふよふよ期はともかく、
その後の数十年、こんなけっこうな大人になるまで、
どうして、どうやって、
「『サラマンドラ』を歌っているのは、
尾藤イサオである」
という事実に気づかずに生きのびてこられたのだろう。
びっくりである。びっくりでしかない。
■前置きが長い。うん、まだ前置き。
長いよなと思いながらこんなに長くなったのは、
こういったあれこれを説明してからでないと、
〈どんなふうに好きか〉
ってことが言語化できないからで、
というか、つまるところ、
ふよふよ期の自分が、言語の外で感じていたことを、
がんばって呼び起こして言語化しようとすると、
こういったテマヒマがかかるものなのだな、と、
ひとごとのように思いながら書いてる。
■そろそろ本題。
『サラマンドラ』は自分にとって、
アウトプット用でない在り方をした、
はじめての歌だったのだと思う。
なんでそう思うのかというとだ、
『サラマンドラ』以外の「みんなのうた」については、
〈見ながら一緒に歌ってた〉楽しい思い出があるからで、
おそらくたぶんの話だけれど、
『サラマンドラ』は、ふよふよ期の私が、
〈一緒に歌おうとしなかった〉、それとも〈できなかった〉
はじめての歌なのだった。
まあなにぶん、3歳か4歳か5歳の女児にとって、
大人の男のひとが(というか尾藤イサオが)歌っている歌って、
単純に、うたいにくい、ということはあったろうとおもう。
キーとか、テンポとか、その他もろもろ。うたいにくそう。
でもきっと、そういうことだけでもないのだともおもう。
だって、それ以外の「みんなのうた」とちがって、
『サラマンドラ』には、
なんかさびしかった、
なんかかなしかった、
という、ふよふよ期なりの「負」の感じがついてくる。
好きだったな、という気もするし、
いやどちらかというと軽いトラウマかも、
という気もする。
たぶん私は、はじめて、
(ふよふよ期なりに、はじめて)
この世には、
歌を歌えるひとがいるんだな、
ということに気がついたのかもしれない。
否、
なにぶん歌に人間がくっついてないふよふよ期のことであるから、
もっと当時の感覚に即したテイストで言うと、
この世には、
歌われている歌があるんだな、
と気づいた、という、感じだ。
変な日本語だ。
でもそんな感じ。
■歌える人にしか歌えないうた、
というものがあるんじゃないのかと、ちょっと思う。
いやそれも違うか、もうちょい感覚に寄せると、
歌える人が歌ったときにしか、
聞こえない部分がある歌、があるんじゃないのか、
と、たぶん私は思っている。
思っているというか、
思ってる、ってとこまで脳みそ使ってもないんだけど、
尾藤イサオが好き、
というときに感じているその〈好き〉は、
つまりそんな風なことなんである。
このひとの声でしか、
聞こえない部分があるんだよな、
ということ。
声、ってたぶん、音声のことだけじゃなくて、
そのひとが歌ったときに、
〈歌われているうた〉
の全体を指してそう感じるのだと思うのだけども。
■ たとえばだけど、かの有名な、『明日のジョー』の、
「サンドバッグに」
って、いう、ファーストフレーズが耳に届いたとき、
〈そのサンドバッグ、絶対新品じゃないよね〉、
というような情報が、
もはや伝達されてる気がする、その感じ。
〈だいぶん使い込まれてるよね〉が、
聞こえる気がする、その感じ。
「サンドバッグ」という歌詞を、
「サンドバッグ」としてお届けすることは、
おおむね万人にできるとおもう。
だけど、
「サンドバッグ」を、
「その・サンドバッグ」として歌うことが、
というか、歌わせる、ことが、
どうしてできるのか、
どうやったらできるのか、
私にはさっぱりわからない。
それは単に歌がうまいとか技術が高いということなのか、
それとももっと、なんだろう、
かみさま的な何かに与えられたギフト的な何かなのか、
そういうこともよくわからない。
わからないけど、すごいと思う。
■この『サラマンドラ』という歌も、
そういうふうに、なんていうか、
歌詞が物語る以上のことを、
歌い手の〈声〉が語る、から、
これは自分には歌えない、
という判断をくだしたのではないかと思う、
そうしてただ、〈聴いて〉いたのではないかと思う、
ふよふよ期の私も。
『サラマンドラ』は、
(たぶんウルトラ怪獣のことではなくて)
例のあの、炎属性の蜥蜴(竜)の歌なんだけれど、
それが実にまさしくね、「その・サラマンドラ」、なんですよ。
サラマンドラの内の任意の一匹、ではなく、「その」、
最後の、サラマンドラの、歌。
その、サラマンドラの、歌。
もちろん歌詞だけ見てもそれはわかるんだけれども、
だけれども、なんだけれども、
歌詞の創り出す世界観の中でさらに、
尾藤イサオの〈声〉が増幅させる
〈その〉感のすごさよ、と思う。思うのよ。
だってね、前後になんの説明もなく、
「最後の夢から一万年」
みたいな言葉が、
ポンと置かれちゃってる。
これはもう歌詞としてというか詩としてというか言葉としても、
だいだいだいだいだいすきなフレーズなんだけれど、
かといって
「それ、どういう意味ですかね?」
と誰かに聞かれたら、
あんまり上手に説明はできない。
最後の夢って何だったのか、
一万年前に何があったのか、
まったくぜんぜんわからない。
そのぜんぜんわからなさが、
ポンといきなり置かれてることがまず、
歌詞としてほんとうに美しいと思うのだけれど、
ふよふよ期の私もそうだったし、
現在の私もそうであることには、
あのね、
尾藤イサオが歌わせるその〈うた〉の中では、
もっと言うと
尾藤イサオが震わせるその〈空気〉の中では、
それが何か、わかる気がするんです。
「最後の夢から一万年」の意味が。
聞きとれる、気がするんです。
聞きとれる、といってもそれは、
1文字も言葉にできないことに変わりはないのだけれど、
それが聞こえるから、
このうたはさびしいし、切ないし、
なつかしいし、優しい。
あの子が一万年前に見た夢を、
私もたしかに見たことがある、
と、おもう。
そしてたぶんそれを見せてくれたのが、
尾藤イサオの〈声〉、なのだと、思っている。
■ううむ。
どんだけ好きか、みたいなことを語ろうと思ったのだけど、
もはやなんらかの信仰告白みたいになっている。
まあいい。近いものはあるんだ。
■ついでにもうひとつ告白するけれど、
というか誰も得をしない情報を付加するけれど、
『サラマンドラ』は、
ふよふよ期の私が、はじめて〈聴いて〉、
〈泣いた〉、
歌でもあるのだった。
どうして泣いたのかもまた、
ふよふよ時代の私には言語化して理解できてはなかったのだけど、
その〈感じ〉は、まだ覚えている。
というか、この歌を聴くと、オートマティカルによみがえる。
この世のどこかに、
ひとりぽっちの竜がいますよ、
なかまのさいごの生き残りですよ、
ということを、いろんな角度から述べた末に、
『サラマンドラ』は。
ラスト近くで、いきなり言うのだ。
「だれか来て」、「彼と話して」って。
歌には歌い手というものがいると知らなかったふよふよ期の私は、
ああ、行かなくちゃ、
と、思ったんだとおもう。
行ってあげなくちゃ、
話を聞いてあげなくちゃ、
だけど、
〈何処に?〉
何処に行けば?って、まだ思う。
何処に行けば?って、ずっと思ってる。
どこかに行かなきゃならないことはわかってて、
だけどそれがどこかは知らなくて、
どうしてか、
誰に聞いたってわからない、誰も知らない、
ということもわかっていた。
それまで全幅の信頼を寄せていた、
ふよふよ期の私の世界、
知らないことなんてないと思ってた大人たち、
父にも、母にも、せんせいたちにも、
教えてもらえないこと、というのが、
この世界にはある。
そういうことのぜんぶを、
いきなり、まるまる、投げかけられた体験、が、
私にとっての『サラマンドラ』で、
その世界を拡張して増幅していたのが、
尾藤イサオの〈声〉、だったので、
いやもうこれ刷り込みですよね、
って思ってひとまずいろいろ諦めることとする。
ひよこがはじめて見たものについて行くかんじで、
ぴよぴよとまったき確信をもって、
尾藤イサオが好きだ。
■みたいなことを含め、
『サラマンドラ』は、ようするに私にとっては、
生まれて初めての
〈かたおもいの記憶〉
なんだと思う。
届かないものを、歌えないうたを、ほしいとおもう気持ちのすべて。
行き着けない場所を、会ったことのない誰かを、
なつかしいとおもう気持ちのすべて。
ふよふよを終えたその後の人生でも
曲がり角ごとに出くわすであろうそうしたものたち、
〈持ってもないのに喪われるものたち〉の、
輝けるアイコン、みたいな、竜の歌だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
