
【齋藤孝】最強の人生指南書 佐藤一斎「言志四録」を読む
第四章 「やむを得ざる」の生き方――人生論
「やむを得ない」のが本物だ
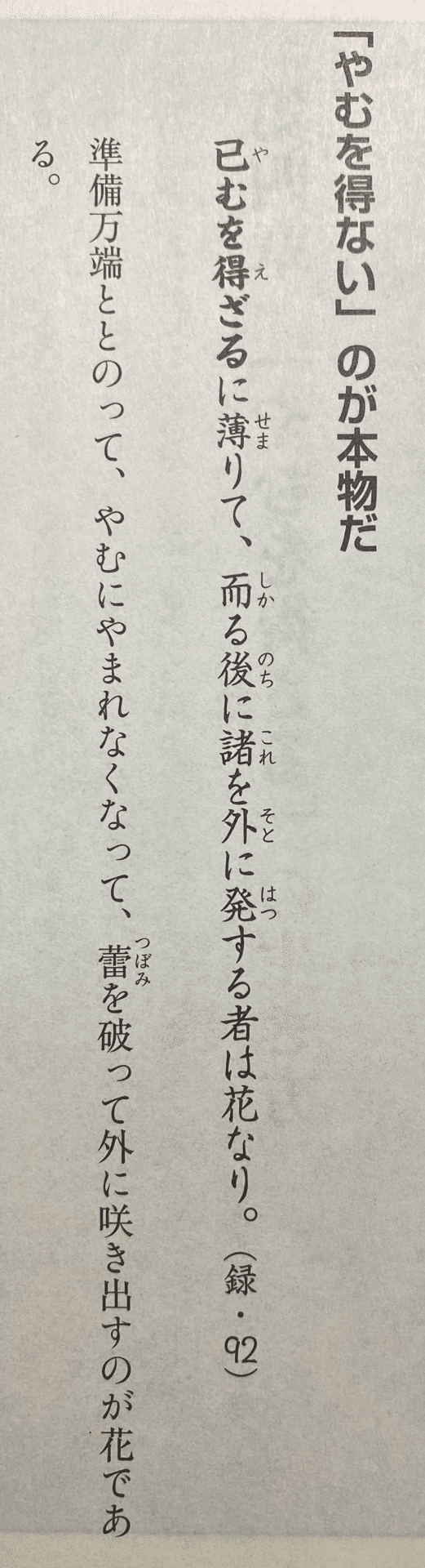
己むを得ざるに薄りて、耐る後に諸を外に発する者は花なり。
(言志録・92)
万端ととのって、やむにやまれなくなって、蕾を破って外に咲き出すのが花である。
能を大成した世阿弥の言葉に
「秘すれば花なり、秘せずば花なるべからず」
というものがありますが、
そこでいう「花」とは、その人が持っているよいもののことです。
佐藤一斎のいう「花」も意味しているものは同じです。
それも、やむを得なくなって外に発したものこそが
その「花」だと言うのですから、
「見て見て」とこれみよがしに見せるのは「花」ではない
ということになります。
日本人は花が好きで、よいものの比喩によく花を用いますが、
実際の花も誰かに褒められたくて咲いているわけではありません。
時期がきたときに自然と咲くのです。
そんな花と同じように、
人も無理に自分のよい部分を見せようとするのではなく、
やむを得なくなったときに、
つまり自然の時期がきたときに、
内側から満ちるようにして外に溢れ出るのが、
その人の持つ本当の美しさであるということです。
無理に自分の実力を人に見せつけようとすると、
どうしてもわざとらしくなります。
人に見せようとするのは、人の評価を気にしているからです。
ですから、野の花のように、人の評価を気にせず、
もっと自分の中から満ち溢れてくるものを大切にしたほうがいい。
この時代の人は、
自然のものと自分の心を重ね合わせて表現するということをよくします。
それはやはり、当時の人の根本に
自然原理を尊重する気持ちがあったからだと思います。
自然というのは、長い時間をかけて整えてきたバランスの世界です。
ですから、そうした自然のバランスを人間界に応用すれば、
人間も自ずとうまくいくはずだと考えたのでしょう。
いまの若い人は、すぐに評価をしてほしがる傾向があります。
四月に入社したらすぐにでも褒められたい。
でもそれはいくら何でも焦りすぎです。
まだ種か双葉のうちに咲こうとしても、
きれいな花を咲かせられるはずがありません。
ですから、「評価してほしい」という焦りの気持ちがある人は、
自分が本当にやむを得ない時期にきているのか、
それまでにちゃんと土の中で自分を育んできたのか、
この言葉を口にすることで自分に問いかけてみてください。
こうした「やむを得ない」ものを追っていると、
それは自然と正しいものになります。
一斎はこうも言っています。
「雲烟は已むを得ざるに聚あつまり、
風雨は已むを得ざるに洩れ、
雷霆らいていは已むを得ざるに震ふるう。
斯ここに以て至誠の作用を観るべし。 (言志録・124)」
(雲は自然の成り行きでやむを得ずして集まり生じ、
風や雨も同様に、やむを得ずに天上からもれて来るし、
雷も同様にやむを得ずに轟きわたる。
これらを見て、至誠の作用を考えるがよい)
私は、やむを得ないというと思い出す話があります。
それは、宮沢賢治の『学者アラムハラドの見た着物』という短編です。
アラムハラドは学者で、一一人の子どもたちを教えていました。
彼は火や水、小鳥など自然のものの性質を説明したうえで、
子どもたちに問いかけます。
「人が何としてもさうしないでゐられないことは一体どういふ事だらう。」
するとある生徒が、
「いいこと」をすることだと思いますと答えます。
アラムハラドは自分が期待していた答えが出て満足します。
でも、ふと見ると、
セララバアドという子が何か言いたそうにしていることに気づきます。
セララバアドは言います。
「人はほんたうのいゝことが何だかを考へないでゐられないと思ひます。」
この答えはアラムハラドの予想を超えるもので、
彼は軽いめまいすら感じたのでした。
このように「やむを得ないもの」という観点があると、
自分の行動の基準が見えてきます。
なぜなら、自分にとっての「やむを得ないもの」を知ることは、
自分の無意識を知ることでもあるからです。
自分の無意識を知り、無意識と仲良くなるのはとても大事なことです。
自分の無意識に気づかないまま欲求に蓋をしてしまうと、中で混乱が起き
自分でも訳がわからないまま苦しむことになってしまうからです。
無意識とうまくつきあうためには、
きちんと無意識と対話することが必要です。
そして、そのためには、自分はどんな思いに突き動かされているのか、
無意識から生じる「やむを得ないもの」
に意識を向けることが必要なのです。
実は私にも、最近、無意識と対話したことで
初めて知った衝撃の事実がありました。
それは、「自分は酒がそんなに好きじゃない」ということです。
二〇歳から飲みはじめて二五年間、
私はずっと自分は酒が好きだと思って飲んでいました。
ところが最近、自分は飲まなくてもまったく平気だ
ということがわかったのです。
飲まなくても、テンションは高いし、充分ご機嫌でいられる。
酔っていないから、
余計なことを言ってしまうような失敗もしなくて済みます。
つまり私は、やむを得ないから、
飲まずにいられないから飲んでいたわけではなかったのです。
単なる習慣で、あるいはその場の勢いで飲んでいただけだったのです。
では、私がやむを得ずにやってしまっていることはなんだったのか。
結論から言えば、それは本を書くことと授業をすることでした。
本を出すのは大変です。
辛いと思うときもたくさんあります。
これをやめれば楽になると思うこともあります。
でも、何かの拍子で一ヵ月くらい本を出さなかったことがあるのですが、
そうすると何かむずむずしてきてどうも落ち着かない。
何か物足りないというか、不完全燃焼感というか、
イライラして本を出したくなるのです。
授業も同じです。
大変な部分はあるのですが、
やはりやらないとイライラして体調まで悪くなってしまいます。
私の場合、本を出すのも授業をするのも仕事です。
自分は仕事をやむを得ざる勢いに突き動かされてやっている。
雲がわき上がるように、
やりたくてやっているんだと気づいたとき、
私はなんて幸せな人生を生きているのだろうと感じました。
このように、自分にとってやむを得ないものは何か
ということを見ていくと、
自分の行動の中の無駄なものがそぎ落とされていきます。
そして、本当にやりたいことだけが残るので、
生活がシンプルになるだけでなくストレスまでも軽減されるのです。
こちらの内容は、
『最強の指南書』
佐藤一斎「言志四録」を読む
発行所 祥伝社
著者 齋藤孝
2010年6月10日 初版第1刷発行
を引用させて頂いています。
よろしければ、サポートよろしくお願いします❤ ジュニアや保護者様のご負担が少ない ジュニアゴルファー育成を目指しています❕ 一緒に明るい未来を目指しましょう👍
