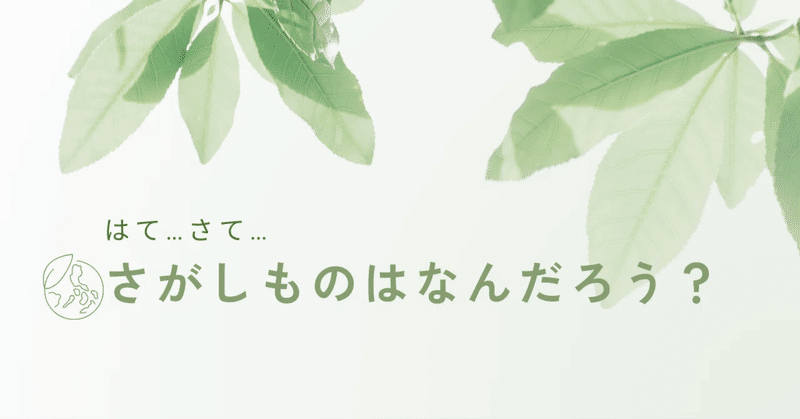
【中部銀次郎】ゴルファーたちの名言
2001年12月に逝去された中部銀次郎さん。
「プロより強いアマチュア」と呼ばれ、
球聖と呼ばれたボビー・ジョーンズのように
生涯アマチュアゴルファーを貫き
数々の輝かしい成績を残された中部さんの
珠玉のことば
『中部銀次郎 ゴルフの神髄』
新編 もっと深く、もっと楽しく
が古書店で110円で売られているのを見ると、
これらに触れない若い人が多くなるのかな……
と残念な思いがします。
私が携わるジュニアゴルファー、
ゴルフを始めた若い人が
同書を読むきっかけなればと思います。
ゴルフは人生に
よく似ているのである。
ゴルファーたちの名言
あまり読書をしないことは、褒められた習慣ではないが、
わたしはほとんど本を読まない。
以前にも触れたと思うが、
生来の弱視なのか、細かい活字を追っていると、
たちまち活字がかすんでしまうのである。
そういうわけで、雑誌の短い記事くらいは目を通すが、
単行本の類はよほどのことでないと、まず手にしない。
ゴルフに関する本でいえば、まだ十代のころに、
ボビー・ジョーンズの『ダウン・ザ・フェアウェイ』と
ベン・ホーガンの『モダン・ゴルフ』を読んだだけである。
そして――ひょっとしてわたしの錯覚かもしれないが
――ゴルフ関係書はそれで十分だと思ってきた。
以後、唯一の例外を除いて、ゴルフ書は読んでいないのである。
唯一の例外は、ゴルファーたちの名言集だ。
いずれも、ごく短い言葉のうちに
ゴルフの魅力、魔力、このゲームの機徴、教訓
などなどを直接・間接に表現していて、
笑ったり、素楽したり、共感したり、教えられたりする。
何より、この種の本のよさは、
最後まで読み通さなくてもいいところである。
面白そうな言葉だけを、拾い読みしてもいい。
途中で、ページを伏せてもいい。
自分の心に響いた、あるいは感覚にぴったり合った
科白(せりふ)を楽しめば、それでこと足りるのだ。
例えば、リー・トレビノの言葉にこういうのがある。
「いいゴルフとは、
決してスーパーショットをぶっ放すってことじゃない。
悪いショットを、
そう悪くないショットにする方法を見つけることさ。
もしオレがそれを覚えてなかったら、
いまでもみんな“トレビノ"はイタリア人だと思ってたろうよ」
じつに簡潔に、ゴルフの要諦を説いていると思う。
ゴルフに、ミスは避けられない。
どんな名手でも、思い通りのショットなどできないのだ。
まさしくトレビノのいうように、
悪いショットをどうしたら
"そう悪くないショット"にできるかが問題なのである。
それにしても、
こういう言い回しの巧みなことには、感心させられる。
前半ではゴルフの神髄を述べながら、
後半では、それが自分に如何なる結果をもたらしたかを、
下世話な表現ながら的確な比喩でしめくくる。
じつに見事なものだ。
同じような表現法は、
次のジョニー・ミラーの言葉にも、共通する。
彼は、こう言っている。
「平常心というのは、
大ミスショットですら、
まだまだうまく行ってるうちだと自覚することである」
ミスが起こると、恐慌をきたしてさらにミスを重ねる。
ゴルファーに通例の行動パターが、
平常心、つまりミスをするのがゴルファーというものだ
と達観していれば、
ショットごとに一喜一憂したりすることもないではないか。
このような科白を読むにつけ、西欧人の言い回し
――難しくいえば“修辞"だろうが
――の諧謔(かいぎやく)ぶりには、ただ脱帽するしかない。
たいていの日本人には、逆立ちしても真似ができない芸当である。
その証拠に、日本のゴルファーが残した言葉で、
内容が立派で深く共感できるものはあるにしても、
思わずニャッとしたり、吹き出したくなるような科白というと、
ほとんど皆無に近いのではないだろうか。
少なくとも、わたしは知らない。
結局、これは言語をあやつる思考そのものの違いだろうと思う。
ふだんから日本人は、
人に訴えるために独自の表現を工夫したりする習慣がない。
コミュニケーションには、紋切り型の言葉が最も有効なのだ。
それはゴルフや野球の選手のインタビューを聞いていても、
よくわかるであろう。
人の意表を突くような発言は、むしろ避ける。
個性の主張は歓迎されないのである。
その点、欧のスポーツ選手は、個性の塊でもあるかのようだ。
癇癪持ちで有名だったトミー・(サンダー)・ボルトは、
ミスをするとクラブを投げることで突出していた。むろん、
彼だってクラブを投げ出すことがマナーを問われることぐらい、
わかっている。
にもかかわらず、ミスを起こした自分が腹立たしくて、
思わず手にしたクラブを投げてしまう。
これによって自分の感情を噴出させ、
後に引きずらないようにするための、
彼なりの精神制御法なのだ。
クラブ投げについて問われ、トミー・ボルトはこう釈明した。
「クラブを放り出すんだったら、
前へ投げたまえ。
そうすれば、
後に戻ってクラブを拾いあげるなんて
エネルギーを浪費しないですむからだ⋯⋯」
クラブを投げるなど、論外である。
が、投げるのがいいか悪いかの問題は別にして、
それについて答えなければならない立場になれば、
いかにも"合理的風"の表現で笑いにまぎらわせてしまう。
その巧妙さが憎いではないか。
ついでにいうなら、彼の時代には、
自分で気に入らないショットをすると、
クラブを放り出すゴルファーは決して珍しくはなかったらしい。
あのボビー・ジョーンズも若いころには、
よくクラブを投げ出していたことを自伝にも書いているし、
あるマッチプレーでは相手と二人で、
ホールごとにクラブを投げていたそうだ。
当時といえども、
むろんクラブ投げは周りのひんしゅくを買ったし、
事実、ジョーンズは自分のマナーの悪さを新聞に叩かれ、
ショックを受けたといっている。
そして自分の感情を制御できないかぎり、
ボールをいくら自在に打ち分けられても、
いつまでも試合には勝てないことに気づき、
「ペイシャンスー――忍耐」
を覚えるようになったと悔いを込めて書いた。
そのボビー・ジョーンズは、
ゴルファーの情報過多やショットへの遅疑逡巡を戒めて、
こう言う。
「いったんスタンスをとったら、
もはや思い悩んでも遅過ぎる。
なすべきことは一つ、
ボールをひっぱたくだけである」
ゴルフ史上、スイングについてはいろいろ論じられてきたが、
アドレスに入ったら、
体のどこをどう動かせばいいのか考えても無意味である。
ただ、何が何でもボールを狙ったほうへ打ってやるという
気迫こそが大事なのだと、彼は言っているのだ。
その上で彼はなお言う。
「クラブを遅すぎるほどゆっくり振ったゴルファーは皆無である」
よし、狙ったほうへボールを打つぞと気迫を込めるのはいいが、
かといって、打ち急いではいけないと注意しているわけだ。
わたしにはよくわからないが、
この辺りは欧米語の発想法の独特なところかもしれない。
日本人なら、
「ほとんどのゴルファーは、速くスイングしすぎる」
と言うであろう。
どちらが聞く者にとって興味深く響くか。
人の感性によって反応はまちまちだろうが、
わたしにはひっくり返した表現のほうが
ずっと効果的に伝わるように思える。
ゴルフスイングについての言葉では、
ボブ・トスキの表現も面白い。
「われわれはコルフスイングをあまりにメカニカルにしていないか⋯⋯
ゴルフは決して純粋な科学を意味するわけではない。
芸術的なフォームなのだ。
アインシュタインは偉大な科学者であるが、
ゴルファーとしてはへボなのである」
ティーチングプロとして高名なトスキが言うだけに、
説得力のある言葉だ。
生身の人間が肉体を使って運動するかぎり、
理詰めでスイングがつくられようわけがない。
科学的に正しいフォームが、
そのゴルファーにとって最適である保証もない。
"芸術的"という彼の表現は、
フォームは個々のものだということを示している。
それはいいとして、その指摘を面白くするために、
最後にアインシュタインの名前を持ち出すところが
例示の妙なのである。
アインシュタインがゴルフを愛好したかどうか知らないが、
あの天才科学者を引き合いに出すところが、
レトリックというものだ。
アインシュタインの風貌を思い浮かべ、
ギクシャクしたスイングでボールを打ってる姿を想像すると、
思わず微笑ましくなるではないか。
意外なのは、
鉄のごとき意志の人で軽口などとはまったく無縁とも思える、
かのベン・ホーガンすらが、
次のような科白を吐いているらしいことだ。
「ゴルファーの中には、
スイング中にバランスを崩す人がいるのにわたしは気づいた。
頭が重いのである。
きっと髪の毛が多いのだろう」
バカバカしいだけの冗談に聞こえるかもしれないが、
それがホーガンの言葉であるからこそ、笑ってしまうのだ。
髪の毛が多かろうと少なかろうと、
スイング中に頭を動かしては絶対にいけないと、
鉄人はいっているのである。
真面目さにかけてはベン・ホーガンにも匹敵するトム・ワトソンは、
くそ真面目にゴルフの真理を説いている。
「ネバー・ギブ・アップ。
もしプレー中に諦めたりしたら、
人生でも諦めることになるだろう。
そして一度諦めたら、
二度目はもっと簡単に諦めるだろうし、
三度目、四度目は諦めるのがさらに易しくなるはずである」
もう勝てなくなってからずいぶん長くなるが、
ワトソンが
メジャー大会で優勝戦線にいながら脱落していくのを見ていると、
彼がそれでも諦めずに王座奪回を目指していることが、
こちらにもひしひしと伝わってくる。
先のことは誰にも予見できないが、
仮にワトソンが二度と勝つことがないにしても、
後半生を通じて彼は、
常に人生の勝者であり続けるだろうと思えるのだ。
ゴルフは人生によく似ているのである。
こちらの内容は、
『中部銀次郎 ゴルフの神髄』
新編 もっと深く、もっと楽しく

発行所 日本経済新聞社
著者 中部銀次郎
2003年10月1日 第1刷発行
を引用させて頂いています。
https://ameblo.jp/nfieldgolf/entry-12851219482.html
https://ameblo.jp/nfieldgolf/entry-12851122523.html
よろしければ、サポートよろしくお願いします❤ ジュニアや保護者様のご負担が少ない ジュニアゴルファー育成を目指しています❕ 一緒に明るい未来を目指しましょう👍
