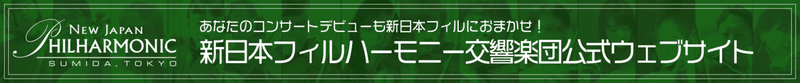「J.S.バッハとは何者か?」(下)
新日本フィルnoteではダントツの情報量「岡田友弘《オトの楽園》」。《たまに指揮者》の岡田友弘が新日本フィルの定期に絡めたり絡めなかったりしながら「広く浅い内容・読み応えだけを追求」をモットーにお送りしております。今回は定期に絡めてバッハの回。ケーテンに住んでいたころまでの親近感の湧くような普通の人っぷりを書いた前回はこちら!
前回の記事「J.S.バッハとは何者か?(拡大版・上)」では大バッハの前半から中半生までを俯瞰した。もう一度、バッハが活動した都市を時系列でみてみよう。
「アイゼナハ時代」
「オールドルフ時代」
「リューネブルク時代」
「第1次ワイマール時代」
「アルンシュタット時代」
「ミュールハウゼン時代」
「第2次ワイマール時代」
「ケーテン時代」
ここまでの話題を駆け足で触れてきたが、バッハが最晩年に活動した都市が「ライプチヒ」である。今回はこの「ライプチヒ時代」のバッハについて紐解いていこう。このライプチヒ時代がバッハにとっては最も長い時期を過ごした時代になる。その期間は1723年からバッハが没する1750年まで。実に4半世紀以上である。
ライプチヒはザクセン選帝侯の支配する地域にあったが、市民の権利が保証され、民衆の経済的、文化的な民度が非常に高かった。ザクセンの代表的な都市といえばこのライプチヒと古都として旧市街が世界文化遺産にもなっていたドレスデンだ。「世界文化遺産になっていた」と、過去形で記述したのには理由がある。世界遺産に登録されていたドレスデン旧市街を流れるエルベ川に新たな橋を建設することを、ドレスデンの市民は住民投票の末に決定した。それを理由に世界遺産として抹消されたため「世界遺産だった」という過去形なのである。伝統や歴史を大切にしながら、現在の暮らしや利便性などを現実的に考えるところが如何にもドイツ人的発想とも言える。なお、橋の建設についてドレスデン市議会は反対を、ドレスデン市長とザクセン州は住民投票の結果を尊重する姿勢を見せたことを付記しておきたい。
ライプチヒは産業も発達し、さまざまな「見本市」が開催される経済的中心都市であった。経済が豊かな街には多くの人々が訪れる。彼らは遠くイタリアやフランスの先進文化をライプチヒの市民にもたらし、また経済的に豊かな市民は教養を深め、文化が大きく花開いたのだ。ザクセンの産業で有名なのは「マイセン陶磁器」だ。世界三大陶磁器(マイセン・有田・景徳鎮)の一角をなし、またヨーロッパ三大陶磁器メーカ(マイセン・ロイヤルコペンハーゲン・ビレロイ&ボッホ)としても有名なマイセン陶磁器は、王立窯が生産を独占しザクセンの大きな経済的基盤となっていた。余談だが、イギリスの有名陶磁器メーカーであるウエッジウッドはイギリスの作曲家レイフ・ヴォーン=ウィリアムズの母方の実家で、牧師であった実父なき後はウエッジウッド家で育った人物である。
バッハはそのような文化的、経済的に豊かな大都市ライプチヒでの職を切望していた。ケーテン時代の黄昏時にバッハに願ってもないチャンスが舞い込んでくる。ライプチヒの聖トーマス教会という大教会の「カントル」(教会附属の学校での音楽監督)の空席ができたのである。
バッハは採用候補者の順位としては5番目くらいの候補だったらしく、当時の市議会の記録によれば「上位の候補者の辞退やらが色々あって、平凡な人物(バッハ)を採用した」という記述がある。上位の候補者には当時のドイツで活躍していた作曲家のテレマンなどがいたことは事実とはいえ、当時の採用担当者たちの「見る目のなさ」に呆れるばかりである。しかし、見方を変えたら当時のバッハの評価を窺い知ることができるエピソードともいえよう。
紆余曲折はあったにせよ、バッハはトーマス教会のカントルに就任した。のちにライプチヒの音楽監督にもなり名実ともにライプチヒでの音楽部門のトップになったのである。ライプチヒでのバッハの仕事は想像以上に多岐にわたっていた。トーマス教会合唱団の指揮と指導、寄宿学校の生徒である少年たちの音楽以外の教科の指導もした。バッハの住まいは寄宿舎と薄い壁一枚で隔てられた同じ敷地にあり、少年たちの喧騒と、大家族であったバッハ家の住空間の劣悪さの中で、毎週1曲の教会のためのカンタータなどの作曲、ライプチヒの市庁やザクセン選帝侯のための音楽作品の作曲、パイプオルガンの演奏などに大忙し。それ以外にも結婚式や葬式での演奏曲の作曲や演奏するという「内職仕事」も生活の足しにしていたそうだ。
ケーテン時代までの仕事と比べて、ライプチヒでバッハが受け取っていた報酬は決して安くはなかったのだが、ライプチヒはこれまでの都市に比べて物価が高かったため、バッハの暮らしむきの肌感覚はかなり厳しいものだったようである。折に触れて報酬の増額を求めたり、友人に自らの窮状を吐露する手紙を送ったりしていた。通貨の換算方法で諸説あるのだが、私が簡単に計算したところ内職仕事も含めても200万円前後の年収だったようである。この頃バッハが主人のザクセン選帝侯に自らの不遇を訴える請願書が残っている。
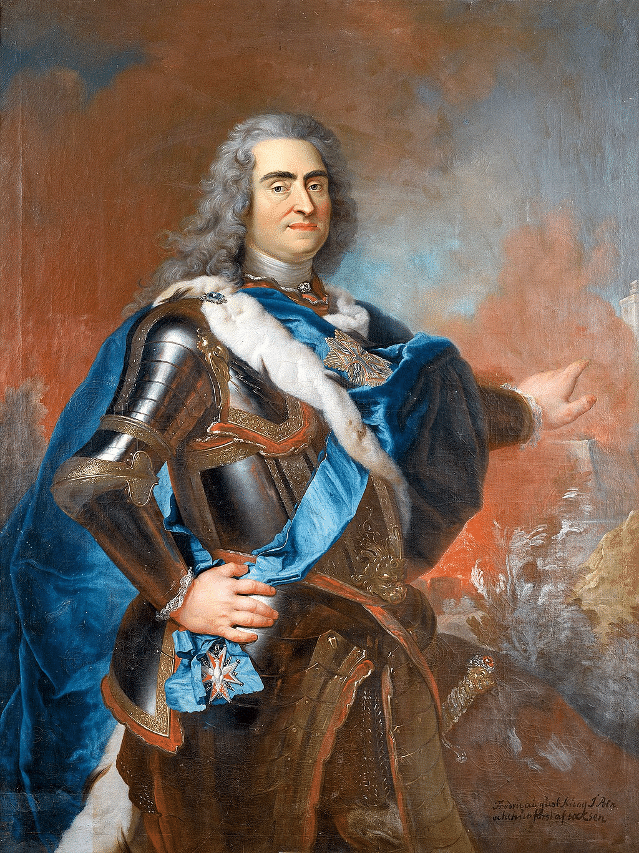
ルイ・シルヴェストル「アウグストII世(ザクセン選帝侯アウグストI世)」
「私は数年前より現在に至るまでライプチヒの両中央教会に音楽監督として奉職してまいりましたが、その間、言われなき侮辱を被りますことも2、3にとどまらず、また、ときにはこの職務に付随いたします臨時収入の減少にも悩まされてまいったのであります。しかし、もし陛下がご慈悲をもって私に陛下の宮廷楽団の然るべき称号を授与くださり、そのむねの訓令を伝えるよう陛下のご命令を当局に発せられますならば、右のような事態は完全に跡を断つものと思われます。」(角倉一朗編「バッハ資料集」(バッハ叢書第10巻、白水社、1983)より引用)
大仰な文章ではあるが、かいつまんで言えば「俺はこんなに頑張っているし、才能もあるのに、周りのやつらに邪魔されて、挙げ句の果てには収入も減ったから、俺にそれなりのポジションと称号を与えてくれないか?」といった感じだろうか。以前、精神分析学者がこのバッハの発言からバッハの精神的傾向を分析していたが、その学者は「妄想性パーソナリティ障害と完全に一致する」と分析していた。
参考までに「妄想性パーソナリティ障害」とは以下のようなものである。
「何ら明確な理由や根拠なく、あるいは何の関係もないほんの少しの出来事から勝手に曲解して、人から攻撃される、利用される、陥れられるといった不信感や疑念を病的に激しく疑い、広く対人関係に支障をきたす」(Wikipediaより)
キリスト教音楽を多く作曲し、教育者、指導者としても優れた活躍をしていたバッハも、現代社会に生きる我々と同じような「こころの病」を抱えていたのだろうか。私たちにとって、そのようなバッハの姿は意外でもあり、またどことなく身近に感じる部分でもあるかもしれない。誰しもが、大なり小なり性格的な悩みを抱えているものなのだろう。
この悩ましくも最重要な時期でもあるバッハの「ライプチヒ時代」は大きく3つの時期に分けられる。
初期は多くの教会カンタータや「ヨハネ」「マタイ」の両受難曲を作曲し、創作的にも充実していたにもかかわらず、教会サイドからの評価はイマイチだった時期、それに嫌気がさしたのか大学生の楽団とともにコーヒーハウスなどで作品を発表していた中期、古い教会音楽の研究や自作の編纂をしたり、息子が働いていたプロイセンのポツダム宮廷で即興演奏をしたりして「フーガの名手」として名を馳せるようになった最晩年である。最晩年には白内障を患い英国人の高名な医者(実態はヤブ医者)の手術を受けたが失敗、その療養中に脳卒中で死亡した。ちなみ同年生まれのヘンデルも同じ眼病でこのヤブ医者の手術を後年受け、それもまた失敗したそうである。バッハ死亡時の肩書は「ポーランド国王とザクセン選帝侯の宮廷作曲家、ライプチヒ音楽監督」というものであった。肩書を見ても、バッハが音楽家としてトップの地位を極めたことが窺い知ることができる。
現代において「音楽の父」として音楽史上に君臨し、後年の多くの作曲家、音楽家に多大な影響を与えたバッハだが、生涯で一度も国外に旅行したことがなく、現在のドイツ国内のごく限られた地域のみを移動していたことは注目すべきことであろう。当時の音楽の先進地はイタリアであった。そのイタリアに旅行し見聞を広めたり、イタリアに留学したりすることが「一流」へのパスポートであり、嗜みであった。しかしバッハはごく限られた狭い地域で、その技法やスタイルを習得しただけでなく、バッハ独自の音楽性を内包した楽曲を多く残した。当時のザクセンが商業の発展によって他国との交流が盛んだったこともプラスに働いたとは思うし、バッハも最先端の音楽のスタイルに触れることができていたとは思うが、最も遠い場所でベルリン郊外のポツダムに赴いただけの「超ローカルな音楽家のオッさん」が音楽史において「ルネサンス音楽」と「古典派クラシック音楽」を橋渡しする役割を果たした「歪んだ真珠」ともいわれるバロック音楽の最高峰に位置し、前時代の音楽と次代の音楽を見事に繋ぎ、現代の我々にも色褪せない魅力を放ち続けていることは驚嘆に値する。
それなりに生存中は地位も名誉も得たバッハであるが、長らく音楽史上で「忘れられた存在」となっていた。もちろんハイドンやモーツァルト、ベートーヴェンもバッハの音楽に驚嘆し認知していたのだが、「バッハ復興」の大きなきっかけとなったのは、同じライプチヒで活躍した作曲家でありライプチヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者もつとめたフェリックス・メンデルスゾーンだ。メンデルスゾーンが1829年に「マタイ受難曲」を復活上演し大成功を収めたことを分岐点としてバッハ再評価が進み現在に至るのである。それを発火点にしてバッハの作品が出版されるようになり、「旧バッハ全集版」「新バッハ全集版」へと研究は発展、深化してくのである。

James Warren Childe 「メンデルスゾーン」(1839)
メンデルスゾーンたちの時代よりも前にも、バッハの作品はいくつか出版されていた。そのきっかけを作ったのは大バッハの2番目の息子であるカール・プィリップ・エマニュエル・バッハ(C.P.E.バッハ)である。また、ライプチヒではバッハの時代に「写植楽譜」の出版をするものが登場した。その名はベルンハルト・クリストフ・ブライトコプフ。彼がライプチヒに1719年に書籍・美術・音楽出版社を設立したことも重要な出来事であろう。彼が設立した出版社は現在でも「ブライトコプフ・ウント・ヘルテル社」として世界を代表する楽譜出版社として音楽出版界のトップランナーであり続けている。
※
最近、日本酒などの醸造過程でクラシック音楽やジャズの音楽を「聴かせる」ことがある。それによって味がまろやかになるなど諸説あるが、詳しいことはよくわからない。私もかつてモーツァルトを聴かせて仕込んだ日本酒を飲んだことがあるが、実にまろやかで美味しい酒であった。もっとも、どんな酒を飲んでも同じ感想を述べるに違いない・・・。私はバッハを聴かせて仕込んだ酒を飲んだことはないが、バッハはコーヒーだけでなくビールやワインも愛飲していたそうで、あの威厳のある肖像画の姿とはまた違った「人生を楽しむ」一面が垣間見える。
またバッハの音楽にはリラクゼーション効果がある・・・と、まことしやかに語られることは多い。「バッハの音楽には1/fゆらぎがある」とか「バッハの音楽は他の作曲家の音楽よりα波が多い」などとする説が色々なメディアで語られるが、真偽の程は不明である。これらの説はバッハの弟子が不眠症の貴族のためにバッハの作品を演奏したというエピソードに枝葉がついて広がった話なのではと思う時がある。なお、そのバッハの作品が有名な「ゴルトベルク変奏曲」である。確かに、あの曲をチェンバロの演奏で聴いていると眠気に襲われる気がしないでもない。
それとは別にバッハの作品には知的好奇心をくすぐるエピソードがいくつかある。例えば、バッハは自分の名に異常ともいえる執着を持ち、バッハの名にちなんだ音を用いたり、作曲に反映させたりしている。例えば’Bach”という名をドイツ音名(B-A-C-H)に置き換えて音楽のテーマを作ったり、”BACH”という語をA=1,B=2,C=3…H=8として「14」という数字を「バッハの数」として多くの楽曲にそれを隠したりしている。数字や数学を音楽に結びつけ、その美しさを音楽にも投影する試みをしていたのである。バッハ最晩年の作品「フーガの技法」は途中で曲が終わっている。息子のC.P.E.バッハが語るところによればそれは「単にそこで作曲家が死んだから」と理由を述べている。この途中で曲が終わっているのが「コントラプンクトゥス14」なのだ。前述の通り「14」は「バッハの数字」である。またこの「コントラプンクトゥス14」には「B-A-C-H」の音列を用いているのである。このようなバッハの暗号が含まれた曲が、曲の途中でいきなり終わるのである。その理由はバッハ本人しか知る由はないが、夢とロマンを求める一人の男としては、バッハが「今の自分が作曲できる能力はこれが限界だ!私の後に続く作曲家たちよ、この続きを完成させてくれよ!」と語っているように感じるのである。
「フーガの技法」でバッハが課した問いに対して、今日までの作曲家たちはその「解」を出すことが果たしてできたのだろうか?私はそのようなこと考えながらバッハ後の多くの作曲家の作品に耳を傾け、楽譜に目を落とす日々を過ごしている。
(文・岡田友弘)
「オトの楽園」
岡田友弘(おかだともひろ)
1974年秋田県由利本荘市出身。秋田県立本荘高等学校卒業後、中央大学文学部文学科ドイツ文学専攻卒業。その後色々あって桐朋学園大学において指揮を学び、渡欧。キジアーナ音楽院(イタリア)を研鑽の拠点とし、ヨーロッパ各地で研鑚を積む。これまでに、セントラル愛知交響楽団などをはじめ、各地の主要オーケストラと共演するほか、小学生からシルバー団体まで幅広く、全国各地のアマテュア・オーケストラや吹奏楽団の指導にも尽力。また、児童のための音楽イヴェントにも積極的に関わった。指揮者としてのレパートリーは古典から現代音楽まで多岐にわたり、ドイツ・オーストリア系の作曲家の管弦楽作品を主軸とし、ロシア音楽、北欧音楽の演奏にも定評がある。また近年では、イギリス音楽やフランス音楽、エストニア音楽などにもフォーカスを当て、研究を深めている。また、各ジャンルのソリストとの共演においても、その温かくユーモア溢れる人柄と音楽性によって多くの信頼を集めている。演奏会での軽妙なトークは特に中高年のファン層に人気があり、それを目的で演奏会に足を運ぶファンもいるとのこと。最近はクラシック音楽や指揮に関する執筆も行っている。日本リヒャルト・シュトラウス協会会員。英国レイフ・ヴォーン=ウィリアムズ・ソサエティ会員。マルコム・アーノルドソサエティ会員。
◆ 行ってみたいコンサートがたくさん!チケットもスマホでサクッと購入!
思い立ったらバナーをクリック!
#音楽コラム
#オトの楽園
#新日本フィル
#岡田友弘
#たまに指揮者
#バッハ
#読み応えだけではない
最後までお読みいただきありがとうございます! 「スキ」または「シェア」で応援いただけるととても嬉しいです! ※でもnote班にコーヒーを奢ってくれる方も大歓迎です!