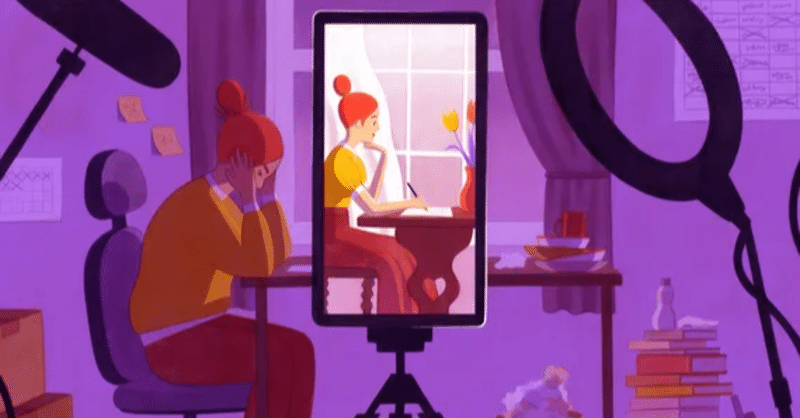
【翻訳記事】いまや誰もがセルアウト
レベッカ・ジェニングスによるVoxの記事より翻訳。
レイチェル・ケイ・アルバースが自作を売り込むと、ビッグ・ファイブ(訳注:アメリカの出版業大手の五社。ペンギン・ランダムハウス、ハーパーコリンズ、マクミラン、サイモン&シュスター、アシェット・リーブルのこと)に勤める編集者は彼女のアイデアを気に入ってくれた。だが問題はマーケ部門からやってきた。アルバースには十分なSNSフォロワーがいないという問題が。
あらゆる書籍、とくにノンフィクションで顕著なことであるが、これまでの作品をすでに読んでサポートしてくれているフォロワーという潜在的顧客を持つ作家を、出版社は保証として求めるものだ。そして大事なのは、そのフォロワーが推し作家のデビュー作に27ドル──新作ハードカバーの典型的な値段だ──支払ってくれるかどうかである。
アルバースが売ろうとした本が「自己ブランド」の時代が人間性に与える影響について書かれたものであることを考えると、これは皮肉な話だ。39歳のアルバースは、自身が「オンラインビジネス産業複合体」と呼ぶものの専門家だ。この複合体とは、ネットを使って金持ちになる方法がわかるコースを受講させたりコーチングしたりして人々のアテンションと金を奪い合う、宣伝屋たちのネットワークのことだ。
アルバースが(自著で)語っているのは、レンタカーのランボルギーニを見せびらかし、怪しげな「不労所得」手法を宣伝して荒稼ぎする教祖連中についてである。しかしその他にも、「会計士として働く65歳の老婦人が『自己ブランドの確立』のためLinkedinに投稿するよう自分の勤める会社から勧められる」といった奇妙な出来事についても語られている。
インターネットにより、誰であろうとどんな仕事であろうと──9時5時で働く中間管理職、宇宙飛行士、ハウスクリーナーに至るまで──自己ブランド化の専横からは逃れられなくなった。ある人にとって自己ブランド化とは、昇進のたびにLinkedinのつながりを更新することだ。またある人にとって自己ブランド化とは、Googleマップのレビューで5つ星をくれるよう客にお願いすることだ。さらにある人にとって自己ブランド化とは、愛嬌はあるけれど屈託のないキャラをInstagramで装うことだ。そして、ベストセラーや記録的ヒット作を出版したい人々にとって自己ブランド化とは、新しい作家と契約するコストを正当化するために企業のお偉方が作家のファンを利用できる「プラットフォームの構築」のことである。
純粋にクリエイティブで、市場に汚されないモチベーションを持った特異な天才が生み出した作品という考えは好まれるものだが、音楽、出版、映画業界とは、画一的な大量生産品が一番人気となるような利益追求企業である。近頃ではもはや隠しようもないことだ。
企業合併とストリーミングサービスは、アーティストが旧来持っていた収入源を断ち、文化産業を壊滅させた。Spotifyにようなビッグテックのサイトに文化を「民主化する」などといった売り文句が書かれるが、その代わりに、アーティストが旧来のやり方で稼げた額よりもごく小ない金のために二倍の仕事をするよう彼らに要求したりしている。
この仕事がなにかといえば、トレンドを追いかけたり、投稿戦略を常に変化させたり、自分が時間を費やして行っているのが実のところアートではなくマーケティングであるように感じ続けたりといった安っぽい行為を通じて、絶え間なく自己宣伝することだ。アルゴリズムに支配されたメディア供給の圧制下において、アーティストや作家──人間であることの意味が自分の作品そのものと結びつくあらゆる人々──はいまや、起業家にもならなければいけない。
「これらの素晴らしい本を書いているのに、作家たちは私に問いを投げかけます。『どうすればブランドを作れるのか?』という疑問が、彼らを寝かせてくれないのです」こう述べるのは、出版エージェントのカーリー・ワッターズだ。作家たちは自己ブランド化に自分の時間を使いたいわけではない。そうしなければならないと感じているだけだ。
「ミレニアル世代やX世代は、本当は自分のことを売り込み屋のように感じているのだと思います。彼らが想像していたキャリアはそんなものではありません。これらの世代の価値基準では、こうしたやり方は本質的に間違っているように感じられるのです」
なぜそう感じるかというと、自己宣伝はクソだからだ。そんなことのためにTikTokの動画を作ったりメルマガを使ったマーケティングを学んだりするのは本当にクソつまらないし面白くもない。「プラットフォームの構築」なんてほとんど誰も望んでいない。ただプラットフォームを持っていたいと思っているだけだ。
アメリカンドリームに乗り出す人々がなんのために版権契約を結んでいるかといえば、自分自身のために働き、自分がやりたいことで金を稼ぐためである。自己宣伝とかプラットフォーム構築とかオーディエンス作りとか、テック業界の覇者たちが作家に要請する行為にかかる手間は不快なものだ。こうした行為の効果は保証されることもなければ、とてつもなく幸運でないかぎり逃れることもできない。
ファスト・カンパニー誌の1997年8月/9月号の表紙記事は「あなたという名のブランド」だった。この見出しのデザインは、タイド(アメリカの洗剤ブランド)のロゴの上手いパロディである。
もし「自己ブランド」(この言葉はライターのトム・ピーターズによる造語だった)を作り上げられていないなら、あなたはすでに新しい経済に置いていかれている。そしてこの新しい経済では、キャリアの成功はただ会社の出世コースを昇ることではなく個人的な成長と自己宣伝によって定義される。以上が、この記事の要点だった。「あなたというブランドを生み出すにあたってひとつの正しい方法というものは存在しない」と、ピーターズはオチでこう書いている。「今日から始める、それ以外を除いては」
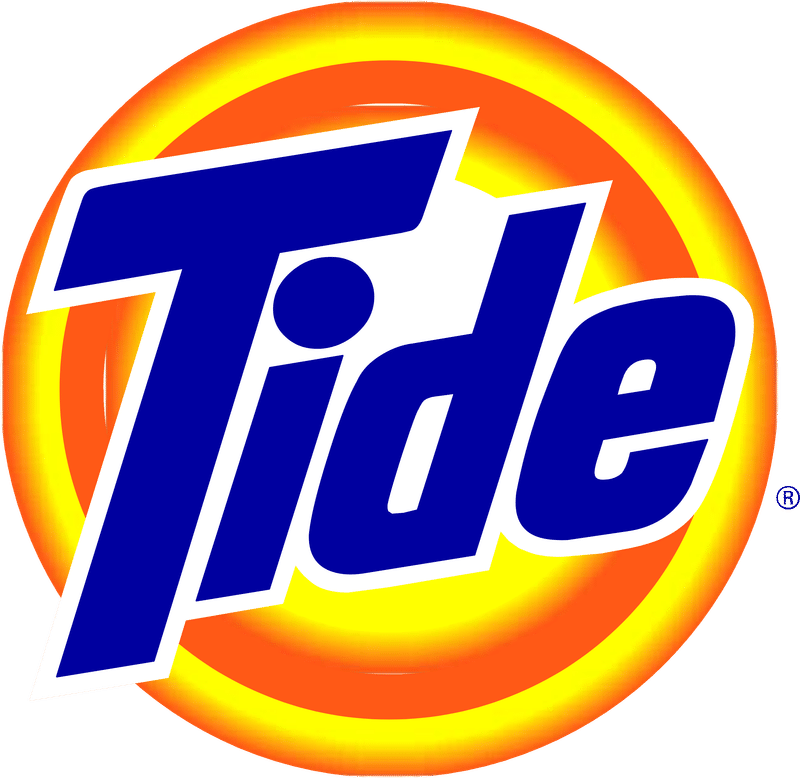
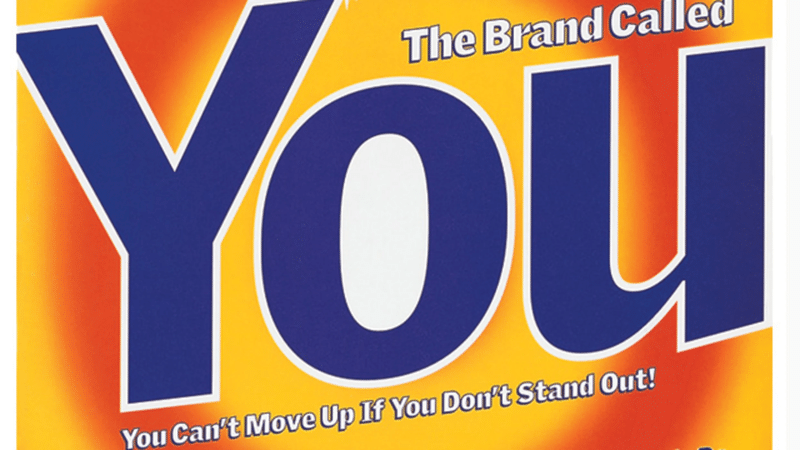
ファスト・カンパニー誌を読むホワイトカラー会社員にとっては自己ブランド化の感情は当時そこまでダサく感じるものではなかったが、彼らの世界へついに足を踏み入れる若い人々にとっては、間違いなくダサかった。アーティストの真正性や純粋さへの強迫観念で定義できる10年間が仮にあるとしたら、それは90年代である。気にしすぎたり頑張りすぎたりするのはなんであれ恥ずかしいことであり、セルアウトなどは究極の罪という時代だった。
エッセイ集「ザ・ナインティーズ」でチャック・クロステルマンは「セルアウト」という言葉を「裕福になるため何かを売る者」ではなく「裕福になるため自分の価値を売ることに妥協する者」と定義する。「妥協した人間が過去と同じような作品をいまなお作り続けていた場合、セルアウト行為はとくにまずいものとなる」とクロステルマンは書いている。「目の肥えていないファンも楽しめるよう、過去作をパッケージングし直している場合でもなければ」
しかし当時ですら、アーティストを「セルアウト」として批判する考えに反対する意見があった。セルアウト批判は、アーティストの野心やイノベーションを罰する、ナイーブで偽善的な考えであると。クロステルマンは以下のようにも書いている。「これは敗者しかいないゲームであって、誰もがそれを知っている。それでも、我々はこの敗者のゲームをプレイせざるを得ない」
問題は、アメリカは大なり小なりセルアウトの考えで動いていることだ。セルアウトが背負う汚名は──そんなものがこれまで意味を成すようなかたちで存在していたとしたら──グレート・リセッション(訳注:リーマンショックに代表される世界金融危機)以降、ほとんどの人がなんらかのソーシャルメディアに参加してからは存在しなくなった。
(ファスト・カンパニーの記事を書いた)ピーターズは、自身の予言が現実のものとなったのを見た。安定しているはずの企業での大規模なレイオフ、停滞する賃金、企業での仕事に対する全体的な幻滅といった過去10年にわたる出来事が、自分自身のボスでありたい若者たちにとって起業家精神をますます魅力的に見せているのだ。経済のより大きな変化により、起業家になりたいとは思っていなかった人ですら、起業家のごとく振る舞うよう強制されてしまっている。
たった5つの企業が約80%の書籍流通を支配する出版企業を例にとってみよう。出版社が少なくなるということは高額な頭金を巡る競争が激しくなるということである。Amazonと大規模小売店による合併統合のおかげで書籍販売業者が減るということは、作家は昔ほど印税で稼げないということである。現在の書籍の売上は比較的好調であるにも関わらず。本の売れ行きが問題なのではなく、作家に渡る金が少なくなっていることが問題なのだ。
同じことが音楽産業にもいえる。人々が音楽を聴く時間はこれまでになく増えているにも関わらず、アーティストはもはや印税で生計を立てていけないと訴えている。ニュースやラジオ放送の代わりに、ファンはTikTokのようなアルゴリズム制御されたプラットフォームを通じて本や音楽を見つけるようになっている。こうしたプラットフォームでは、たったひとつの動画やトレンドが作品を爆売れさせたりチャートのトップに立たせたりするのだ。
この仕組みはあるトレードオフの関係を持つ。あるものに関して主流となるような総意を形成するのはより困難になるが、理論上では誰でもバズることができ、クリエイターが成功を掴む上で従来は足枷となっていた部分をスッ飛ばせるようになったのだ。いまやアーティストは自分の曲がTikTokで使われた回数をもとに取引やレコード契約に値段をつけている。たとえば、27歳のアレックス・アスターは構想段階の本をTikTokに投稿し、それが出版されるよりも先に映画化の権利をヤングアダルト系出版社に売却した。ある男性はシーシャンティ(訳注:労働歌の一種)を歌った動画で束の間バズったことで、書籍とレコードの契約の両方を手に入れた。
予想されていた通り、こうした芸術作品のレビューを専門とする出版にも同じ運命が訪れてしまった。広告運営型のジャーナリズムはゆるやかに崩壊しつづけ、文化批評の職業は廃れていく──1月には、コンデナスト(ヴォーグやザ・ニューヨーカーなどを有するマスメディア企業)が音楽レビューサイトのピッチフォークをGQに吸収合併し、スタッフを解雇している──賢明で、編集が行き届き、ファクトチェックが成された批評(そして致命的なのは批評を書く人が生計を維持する力)を我々は失いつつある。
大規模レイオフの以前ですら、プロによる批評は一部のユーザーには届かなくなっていた。たとえば、ニューヨークタイムズによるポジティブなレビューは以前であれば一晩中は読まれていたが、いまやほとんど波風を立たせられないと、あるエージェントはそう語ってくれた。こうした批評に代わって登場したのは、イスラエル・ダラモラが自身の記事で書いているような存在である。すなわち、「特定のアーティストへの推しを通じてしか音楽に関わらないファンコミュニティや若者リスナーに質の低い情報を与えるYouTuberやインフルエンサーによる、緩やかな集まり。批評の価値を理解せず、自分が好きなものをこき下ろされるのを真っ向から忌み嫌うような音楽ファンを大量に生み出したのはすべて彼らのおかげだ」
文化産業におけるこの構図は、アーティストの人生が帯びるロマン派的な理想とは一致しない。18世紀後半から19世紀初頭以降、我々は「アーティスト」のことを、ロマン派運動以前のように職人や名匠として捉えるのではなく、自分たちより高次の精神的次元にある孤高の預言者であると考える傾向を持つようになった。そう説明するのは、「芸術家の死:億万長者とビッグテックの時代にクリエイターはどうあがくか」の著者であるウィリアム・デレシェーヴィチである。
第二次世界大戦のあと、博物館や大学院学位課程、芸術評議会、各種表彰といったかたちでアメリカは文化的な力を制度化し、より多くのアーティストが補助金や在留許可、組合加入や教職を通じて生計を立てられるようになった。この構図は「飢えたる芸術家(訳注:物質的な幸福を犠牲にして創作に打ち込む、芸術家の理想像を指す慣用句)」という建前からはたしかに乖離していたが、そのおかげでアーティストたちは市場の大部分から切り離されて創作に労力を費やすことができていた。
企業がこの構図に入り込んできてからも、たとえば出版社やレコード会社と仕事をするアーティストたちがビジネス的な事柄に関わることはほとんどなかった。デレシェーヴィチが言うには、「インターネットが普及する前は、芸術家が自分の所属する会社に金の心配をしてもらえたけれど、実際はそんな選択を取ることもなかった。会社は金の心配などさせなかったからだ」
だがこれも、ソーシャルメディアが現れて、誰もがアカウントを持って著者と出版者の両方をやるまでの話だった。「ビジネスマネージャー兼アーティスト」の構図のもとでは、その両方に長けた者が成功を掴み取れる。
「私の一日」動画の台頭には、その緊張感が張り詰めているのを見て取れる。作家やアーティストが自分が過ごす丸一日を撮影し、編集してTikTokやReels用のショート動画にするものだ。ほとんどの人にとって執筆という行為はひどく退屈に見えるものだが、作家兼コンテンツクリエイターはノートPCでタイピングするという視覚的に味気ない作業を見ごたえあるものに変えることで成功を掴みとっていく。
ウェス・アンダーソン映画のサントラをBGMに作家が暖炉のそばで紅茶を飲むとか、森の小屋で目覚めを迎えて川辺で読書するとか、文学の登場人物に扮して自作の執筆風景を撮るオックスフォード大の女子生徒とか、コテージコア風の動画は多く見られるはずだ。
@avenvetch this day felt chaotic #writer #author #nanowrimo #booktok #scrivener #drafting #writingvlog
♬ Mr. and Mrs. Fox - Alexandre Desplat
これらの動画は、「孤高の天才」による芸術性というロマン派的な理想をなぞるものだ。物書きが今よりも「純粋」あるいは趣深い職業であるとされた時代を思い起こさせてくれる。だがしかし、彼らがなによりうまく表現しているのは、買い手に消費してもらうためにアーティストが自身を巧みにパッケージングしなければならないという、アートの現状である。
動画作成など、ほとんどのアーティストにとってはまさしく不愉快な作業の類だ。なにしろ定義の上では、この世界で人間である意味について関心を寄せるのがアーティストであって、ブランドである意味に関心を寄せるわけではないからだ。(アーティストはSNSもうまくやるという)お決まりについてはかなりの反発が起こっており、最近ではミュージシャンがTikTokに対して反発を見せていた。
ここ数年では、インディーアーティストがナヨナヨとしたふりをしながら「夏曲作っちゃった!?」という動画を12月に投稿して問いかけるといった出来事がよく見られるようになった。あるアーティストは、Radioheadのトム・ヨークがこんな動画を投稿している様子を想像してみるようフォロワーに問いかけるTikTok動画を作ったりしている。
170万人のTikTokフォロワーを擁する30歳のミュージシャン、リッキー・モンゴメリーは、バズったことをきっかけにレコード契約を手に入れた人という観点から、思慮深く追及する動画を投稿した。
モンゴメリー曰く、うまくレコード契約を結んでいくつかのヒットソングを飛ばしても、絶え間ない自己宣伝というランニングマシンからは逃れられない。「次に起こることはご存じの通り。3年経ったころには、アートに捧げる時間はほとんどなくなる」彼は私にこう言った。「アートについてはヘタクソになる一方なのに、自分は優れたマーケターになっていく。ますます劣化していく製品のマーケターにだ」
@rickymontgomery #stitch with @Willow Kayne
♬ original sound - ricky montgomery
レコードレーベルや出版社にとって、このシステムは素晴らしいものだ。マーケティングの手間をアーティスト自身に委ねられるのだから。けれどそれが意味するのは、モンゴメリーが言うように「もし動画編集の知識が全くなかったらまるっきりおしまい」ということだ。
TikTok動画を作る作業には──最短の時間で最大の人に自分のことを知ってほしいなら、TikTokをやるしかないようなものだ──長い時間とスキルの両方が必要となる。進化し続けるアプリの編集機能に慣れ、プラットフォームの文化を理解し、自分の身なりを整え、しかしフェイク野郎と思われない程度には整えすぎない。何を話すか準備し練習し、しかしこれもやはり、やりすぎない。そういったことをしなければならないのだ。何度も、何度も。なぜなら、フォロワーを増やすのに大事なのは投稿し続けることだと、どのインフルエンサーも言っているからだ。
しかも、自らの時間を費やしてこの作業を行った上で、アルゴリズムが自分の投稿を拾い上げて自分の言いたいことを人々が気にかけてくれるようになるという千載一遇の機会に賭けなければならない。それが陳腐で媚びたものであり、高校や大学の友達に「インフルエンサーになろうとしてる」と笑われるかもしれないとしても、投稿しないわけにはいかない。話すべきことが全然ないと感じるときにも投稿しなければならない。とにかく投稿しろとアルゴリズムがせっついてくるからだ。
自己宣伝は本質的にネガティブだとみなすカルチャー出身であろうと、自慢することで今受けている以上の社会的汚名を背負いこんでしまう女性であろうと、自己宣伝からは逃れられない。なにかを強制されないことが自分にできる最高にクールな行為であったとしても、自己宣伝からは免れないのだ。
地獄じみて、供給過多で、ハラスメントだらけで、uber式の競争が繰り広げられるアテンションエコノミーに自分のコンテンツを提供するよりほかに仕方がない。そうしなければ、誰にも自分のことを知ってもらえないからだ。the Guardian誌に最近掲載されたインタビューで作家のナオミ・クラインは、大量消費主義と避けがたいブランディングに関して書かれた1999年の自著「ノー・ロゴ」以降に起こった世界最大の変化をこう語っている。
「新自由主義により、自分自身を商品にすることがあらゆる経済的安定につながる唯一の道筋ではないのかという不安が生み出されてしまいました。そのうえ、わたしたち自身を絶え間なくマーケティングするための道具を、ソーシャルメディアが提供してしまっているのです」
「自分をさらけ出す」ことで利益を享受する人々のほとんどがそれ以前に社会から利益を受ける側だったとしても、自己宣伝しなくてはならない。貧しい人々、有色人種、家父長制的な社会規範に抗う人々に対してアルゴリズムが負のバイアスをかけているとしても、自己宣伝しなくてはならない。
「プラットフォームには完全無料でアクセスできますが、これはしばしば『プラットフォームには社会経済的な障壁がない』というふうに誤解されています」そう語るのは、ロンドン大学キングス・カレッジでジェンダーとメディアを専攻するクリスティーナ・シャルフだ。彼女は、クラシック音楽に関わる女性の自己宣伝の将来について研究している。
「この障壁はずっと見えづらいものです。実際には自分をプレゼンしたり、魅力的な見た目になる方法を知らなければならないのに」それだけではなく、これらの行為のせいでハラスメントと嘲笑に自らを晒すことにもなる。「少数派人種、女性、トランスジェンダーやその他のマイノリティグループに属する人々にとって、この状況はより困難なものになります。なにかしらの弱点を既に持っている場合、それが裏目に出るかもしれないからです」と、シャルフは付け加えた。
自身の活動が人生を破滅させてきたと述べるインフルエンサーが多くの懺悔をしてきたにもかかわらず、自己宣伝からは逃れられない。自身の生活に関する投稿で強い不幸感や抑鬱、不安感を覚えるようになったと複数のYouTuberが語っているが、しかし、彼らは休むわけにはいかないとも感じている。きっと、アルゴリズムにお仕置きされるからだ。筆者がインタビューをしたことのあるTikTokerはいつもほとんど全員が、自身の燃え尽き症候群について語りたがっていた。
かつてティーンYouTuberとして活動していたエル・ミルズは、「私は自分の人生でも最悪に壊滅的な瞬間を切り取って動画を作ってきました。その余波で、自分でも解決策がわからない私生活上の問題について、いつもコメントしなければいけないというプレッシャーを感じるようになったのです」と、YouTuber活動をやめた理由について綴っている。
タヴィ・ギャヴィンソンは自身とInstagramの関係について、こう書いている。「自分はライターであり、役者であり、アーティストだと思います。けれど、自分自身のセールスマンになってからは、己の意思が純粋であるとは信じられなくなってもいます」
コーネル大学でコミュニケーションを研究する教授のブルック・エリン・ダフィが自身の生徒に「起業家になりたい人?」と聞くと、全員が手を挙げた。「自分の好きなことで稼ぐ」キャリアがしばしば過重労働や過小評価につながっていく過程がブルックの著書の焦点であることを考えると、生徒たちのこの有様はどこか皮肉だ。
あるいは、これは皮肉ではないかもしれない。生徒たちは、年上の人々が理解したがらないものを理解しつつあるのかもしれないからだ。自分の生徒たちについてブルックは、「『自分の得意分野をマネタイズするための自己ブランディングはどうすれば学べるだろうか?』という感覚があるのです」と述べる。
「若者たちはそういうことを学びたいと要求していますし、教授陣が知っていることといま起こっている出来事がかけ離れているせいで、大学がその要求に応じられていないと感じています」
作家で作文教師のリー・シュタインは、クリエイターエコノミーは職業芸術家に敵対するものではなく、むしろコネクションを作る道具だと見ている。「私はシニカルになろうとするつもりはありません。もしこれがクリエイターエコノミーの現状というなら、より良い状態をどれほど求めているか訴えるのに時間を浪費するのではなく、"どうすればそこで成功できるか"が重要でしょう?」と彼女は言う。
「自分の考えを世間と共有したがらないせいで作家がソーシャルメディアの利用を忌避するのが、私が気に食わないもののひとつです。それってまるで、なんで作家になったの?ってことですよね。アイデアがあって、それを世間と共有するのが物書きの本質でしょう?自分の考えはいつでも世間と共有すべきです」
年上世代が若かりし頃に比べて現代の若者が自己宣伝にアレルギーを示さないのは、ソーシャルメディアと広告活動の避けられなさゆえかもしれない。この現象の萌芽は、2011年にデレシェーヴィチが「セルアウト世代」と題したオピニオン記事をニューヨークタイムズに寄稿したときにはすでに生まれていた。
これは、セールスマン精神を自然に身に着けたオレゴン州ポートランドのイカしたミレニアル世代たちのやり方にデレシェーヴィチが驚かされた話だ。数十年前のユースサブカルチャーとは異なり、彼らは行儀よく、フレンドリーで、拍子抜けするほど素直であることにデレシェーヴィチは気付いた──「商業的人格が第一なのだ」と。彼らは起業家を模倣しようとしており、また、社会的かつ経済的なモデルである個人事業で働こうとしていた。
記事を書いてから13年経ち、なにか変わったことはあるかとデレシェーヴィチに訊いてみた。当時を振り返って彼はこう述べる。「私は"セルアウトは悪"という観念をまだ持ったままでした」しかし、デレシェーヴィチが次の本を書くために調べ始めたときのことだ。「それが時代遅れで、特権意識的で、ひどく非現実的な態度であると気付きました。いまとなっては、選択肢はありません。だから"セルアウトは悪"という観念は消え失せてしまったのです」
デレシェーヴィチの著書では、本質的に起業家らしいものを芸術活動が追い求めるようになった問題に取り組んでいる。ソーシャルメディアのおかげでアートを追求する人がとても増えた一方で、芸術活動により自身を経済的に支えられる人は増えていないというのがその主張だ。
The Atlanticに掲載されたデレシェーヴィチの記事によると、アーティストが起業家のように考える世界とは「アーティストが音楽家兼写真家兼詩人兼作家兼デザイナーになる世界である……それが意味するのは、自分が選んだメディアのために10000時間費やす余裕はないということだ。しかし、重要なのは技巧や専門分野ではない。重要なのは多芸であることである。あらゆる優れたビジネスと同様に、アーティストは多角化しようとしているのだ」
この世界は同時に、芸術が「よりわかりやすく、画一的で、ユーザーフレンドリーで、しきりに楽しませてくれるものとなる世界である──エンタメにより近くなり、芸術からはより遠ざかっていく」
自己宣伝活動は芸術創作を劣化させているだろうか?そう主張するのは不可能だ。インターネットは、人類史上最大級の無数に増え続けるアートの創造と披露を促してきた。けれど、アートと商業の区切りはますます薄れていく。モンゴメリーは以下のように述べている。
「そうなると、なんらかの自己検閲が出てくる。広告宣伝についてよく知らない人は投稿スケジュールみたいなことに気を配りすぎるようになるし、そうなってしまえば、パンクをやっていくのはもはや不可能だ」
ベサニー・コセンティーノが2009年にインディーロックバンド『ベスト・コースト』を結成したとき、彼女は22歳だった。今年、彼女が自身の名を冠したアルバムをリリースするまでの間に、音楽業界は似ても似つかないほど変わってしまった。コセンティーノの説明によると、かつての時代にクールな新人インディーアーティストを見つけようと思ったら、なにがしかのブログを読んだりどこかしらのライブ現場に行ったり、なんらかの人付き合いをしたりしなければならなかった。新進気鋭のタレントを発見するのを助けてくれる小規模産業が存在したのだ。いまやその役割は、自分がすでに持っている趣味に合うようアルゴリズムにデザインされたプレイリストに追いやられている。
「誰でもどんな曲でもSpotifyにアップできるけれど、Spotifyはこれまで全世界で作られたすべての曲を持ってる。ビートルズやフリートウッド・マックを相手にしなきゃいけないってわけ」と、コセンティーノは言う。
@bethanycosentino Hi this is long but I wanted to tell you the truth ❤️ #dissapointment #fearoffailure #singersongwriter #believeinyourself #expectationvreality
♬ original sound - bethany cosentino
コセンティーノが──15年に及ぶ輝かしいキャリアを持ったミュージシャンが──置かれている状況は、そこらへんにいる期待の新人と基本的に変わらない。すなわち、オンラインでの絶え間ない自己宣伝だ。「まるで仕事の打刻をしてるみたい」と、彼女はソーシャルメディアについて語っている。
昨夏にリリースされた新譜のときは、コセンティーノは何を投稿したらいいか書かれたExcelスプレッドシートを使いつつ、起床から数時間はネットに張り付いていたという。それにもかかわらず、アルバムがリリースされた瞬間、商業的な成功からは「外れていた」という。もっとよく知られたバンドの名前ではなく自身の名前を使ったアルバムだったからか、音楽性が従来と異なっていたからか、バズを引き当てる運がなかったからか、それはもう分からない。ここで大事なのは再生回数だと彼女は言う。もしレコードの売上がコケたら、十分に宣伝していなかったとしてアーティストが責められるのだと。
コセンティーノが12月にTikTokで自身の苛立ちを表明すると、アーティストの権利や仕事、そして彼らに何が期待されるかについて、プラットフォームをまたぐ言論が引き起こされた。システムを構築するにあたってもっと良いやり方があるという希望を彼女は抱いている。
「たくさんのものが壊れてる。ひとりでに直るものはひとつもない。どうすれば物事を先に進められるか、誰もが積極的になって考え出さなきゃいけない。もちろんそれは大変だけれど、『まあこんなもんだよね』ってお手上げ状態になるのが答えだとは思わない。私は『こんなもんだよね』って言うタイプじゃないから。私が知りたいのは、どうすればこのシステムをより良くできるのかってこととか、神様にもらった一度きりの人生を生きる人間として少なくとももっと充実したシステムにできないかってこと」
時間の大半を自己宣伝に費やす代わりに、アーティストや学問(特に、個々のクリエイターを守ってくれるような業界全体の労働組合をひとつも持たない分野)における結束を生み出す方法を探すのに集中できる人はもっといるかもしれない。個人運営メディアを支援できる人もいる。また、フルタイム労働に限らないヘルスケア制度や安価な小児保育を求めたり、報酬が少なすぎたり支払われなかったりするアーティストたちの作品を盗んで利益をあげる企業と戦ったりすることで、アーティストがもっと生き延びられるように応援できる人もいる。
ちょうどアルバースが紹介した65歳の老婦人のように、自己宣伝の負荷がクリエイティブな人々にだけのしかかっているわけではないことは明白だ。いまや我々は皆、そうした手間をかけるものとされてしまっている。我々全員が被雇用者であれば、自分の会社が方針転換したりリストラすれば健康保険の快適さや給与はすぐになくなってしまうものだと分かるはずだ。テック企業によるプラットフォームもそれと同様で、移ろいゆく。我々がそこで築くオーディエンスは不安定で、一時的なものだ。しかし、他にどんな選択肢があるというのだろうか?
この件を良いこととして捉える人は多い。個人事業主となった人々で構成された社会は、なにはともあれ、自由市場資本主義の論理的帰結だからだ。現代に複製されたアメリカンドリームへ辿り着くためには、デジタル虚無に向かって叫び、自分がどんなにすごい人間かを皆に触れ回る必要がある。重要なのはただひとつ、どれだけの人がそれを信じてくれるかだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
