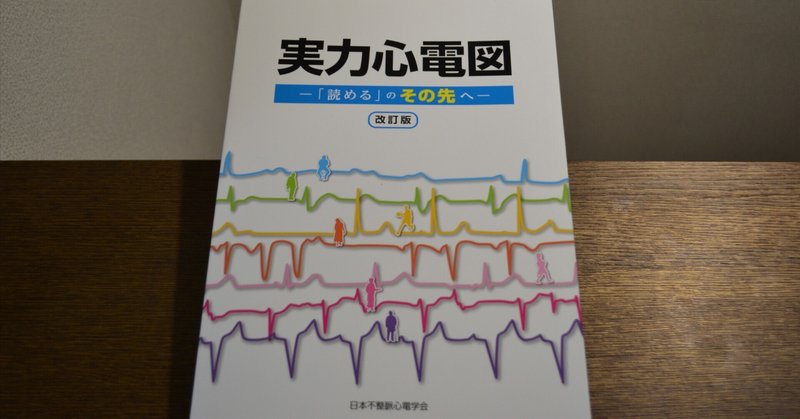
実力心電図を読んでみました
ご覧いただきありがとうございます。
実力心電図を2回通して読んだのでレビューを書いていこうと思います。
本の概要
今回ご紹介するのは「実力心電図」です。
副題として『「読める」のその先へ』とあります。
この「読める」のその先というところに少し惹かれました。
今回は改訂版を入手しました。
価格に関してはあまり言いませんが高いですね。
ページ数に関しては、序論や心電図波形以外の解説が70ページ程で、心電図波形の解説が載っているページが大体250ページです。
私が購入した目的としては心電図検定用という用途もありますが、いわゆる「教本」らしい本を持っていなかったので良い機会だと思って購入しました。
要点
目次の内容などを記してあるHPがあったので以下に貼り付けておきます。
構成としては心電図の基本的な知識とそもそもの心電計の構造、心電図検査時に気をつけることなどが上がります。
続いて、ホルター心電図や負荷試験の方法などが細かく書いてあります。
第6章からの心電図の判読では一つの心電図波形に対して「着目すべき心電図所見」としてリズムから始まり、QT時間まで全ての所見が載っています。
病態や疾患ごとで心電図波形が大きく1ページに載ってそれに対して所見や判読のポイントなどが書いてあります。
利点と欠点
まずは利点からです。
成人から小児の正常心電図、各種不整脈、先天性心疾患まで網羅されています。
各心電図波形ごとに鑑別すべき他の心電図との比較なども可能です。
本書にも書いてありますが、心電図のパターンを暗記するのではなく「発生のメカニズム」を理解するための解説が入っています。
結局のところパターンだけで記憶しても応用が効かないので何故そうなるのか?という視点を持つことが重要だと思います。
そう言った点ではこの「発生のメカニズム」の解説が入っているのはこの本を読むメリットになると思われます。
上記に関連して「よくある患者背景」が情報として記されているところも知識量を増やすという面で役立つと思います。
次に欠点です。
心電図波形以外の図による解説が多くはありません。
例えば、副伝導路の各束ごとの図はありますが、WPWケント束の局在の部分に関しては図がありません。
解剖学的な図が少ないという言葉が正しいかもしれませんが、序論で十分に解説されているので不要といえば不要かもしれません。
分かりにくいと感じるところは少ないですが、初めて心電図を勉強する人には少し難しく感じるところがあるかもしれません。
この理由として「鑑別すべき疾患」が解説内に含まれているのですが、関連する疾患が列挙されているので少し混乱しました。
文章量が多いので読んでいて少し疲れるかもしれませんが、知識量が増えてくれば読み進めるのも容易いと思います。
読んでいて意外だった点
意外だったのが序論の方で心電図計の構造図が電源回路周りや増幅部が出ている点や心電図波形の二次微分波形が解説されているところです。
臨床工学技士的には教科書には出てくる内容なのですが、今まで読んできたものの中で二次微分波形が出てくるのは見なかったので驚きでした。
各心電図の波形に対しての着目すべき所見について、あまり気に留めたことがありませんでしたが、P波の軸も表記されていました。
そう言った点も判読されているところに丁寧さを感じます。
どんな人に向いているか?
向いていると感じるのは初学者というよりは判読の技術を上げたい方、大判の本で心電図波形を見たい方にオススメです。
取り上げている心電図の範囲が広く、一つ一つが解説されているので判読材料を増やしたい方には向いていると思います。
最後に
ざっとですが記事にしてみました。
心電図検定用と考えていましたが、心電図を普段の仕事として扱う人にも向いていると思います。
「読める」のその先へという副題はその通りでステップアップしたい方にオススメしたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
CEねこやなぎ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
