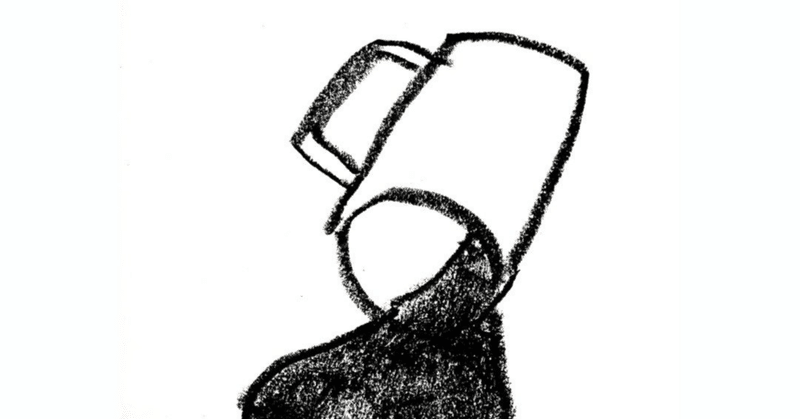
高瀬隼子「おいしいご飯が食べられますように」を自由に読んでもいいですか
●最初は拾い読み
栄えある今年の芥川賞受賞作である。拾い読みしたあと、審査員の選評を読み、はじめから読んでみた。
拾い読みは、砂を噛むようだった。物語を追う自信がでない。胸のうちに広がる空虚感をこらえ、飛ばし飛ばし流す。
審査員の選評を覗いた。平易な文章で綴り、怖い女性が出てくるらしい。食べ物ミステリー? 最近やっとミステリー食わず嫌いを克服したところだ。ちょうどいい。気をとりなおし、読んだ。
●通読一回目ーありがちな「怖さ」
会社の人間関係のありがちなごちゃごちゃ、食べ物これでもかオンパレード、愚痴にいじわる嫌悪感満載な世界。次から次へと手当たり次第に出てくる食べ物がどれも食指をそそられない。事件らしい事件はない。それでもお菓子事件なる変な出来事が起き、物語は終わった。三度三度の食事がどこまでも続くように、登場人物たちのごちゃごちゃもどこまでも続く。
気になったのは、何人かの審査員が言っている芦川さんの「怖さ」である。小説家のいう怖い人は一筋縄ではないはず。「怖い」も万能語で、どちら方向に伸びていくのか予測できない。でも「怖い」ならわたしにも分かるかもしれない。
二谷の目と押尾の目を通した芦川が「怖い」。芦川は、男性が支配する閉鎖的な組織のなかで弱弱しいが弱い自分を守る術に長け、周囲の同情をかいながら同性のライバルを遠ざけることに成功する、そんなタイプの女性にみえる。
だとしたら、使い古されたタイプだ。芦川にひきずられる二谷と、芦川が絡む変な事件で組織を追い出された押尾もありすぎる。
小説の面白さは、人物のタイプが魅力的かどうかより小説としての完成度にあるのかもしれない。ありふれた素材はいい出汁で美味しい一品料理になる。天下の芥川賞受賞作、上手く出来た小説と太鼓判を押された作品だ。
●通読二度目ーカップ麵は孤食の王様
平板でぱさついた全体がだいたい頭に入ったところで、選評を読んだ先入見を忘れ、もう一度通読する。ひとつひとつの出来事にも話の流れにも心ときめかないのは最初と同じ。ひとつだけ違った。カップ麺である。カップ麺が出てくるシーンだけは、なにもかもつまらないと言いたげな二谷に生気が宿る。カップ麺の蓋の隙間から湯気が出てくるシーンなど、もらい泣きしそう。
シンクの明かりだけの台所でカップ麵の蓋を開けると湯気が暗い天井にのぼるシーン。ぞわり。自宅キッチンの奥に防災食用に買い置きするカップ麵を引っ張り出して食べようかと思ったくらいだ。わたしの食生活は、毎日、ほぼ三度三度母と一緒にキッチンに立ち、二人分の食事をだいたい一緒につくり、一緒に食べる。一緒に、は母にとって重要らしい。なので、防災カップ麵の夕食はやらなかったが、白状すると、わたしはカップ麵派ではない。
カップ麵派といえば、深夜にカップ麵の蓋をあけて美味しそうとひとりつぶやく姿が浮かぶ。カップ麵派はおそらく孤食好きである。ひとりカップ麵にお湯を注ぎ、3分待ち、蓋をあける。湯気と汁と麺と容器に印字された〇〇味を想像しながらひとり味わう。湯舟に浸かりながらカップ麵を食べる強者もいるらしい。
妻の手料理を食べずにカップ麺をうまいと言ってすする夫はモラハラをしているというネット記事をみつけた。ここでもカップ麵は孤食の象徴だ。
本作、そこそこ大きな会社に勤める会社員の多忙な日々のなかでカップ麵とコンビニ食が随所にちりばめられている。芦川が二谷の家から帰った後でお湯を沸かしてカップ麵を食べるのをやめられないなら、孤食する行為を芦川に見せつけないだけで、心情は芦川を拒み、芦川への嫌がらせではないか。ハラスメントギリギリではないか。
二谷がカップ麺を食べるシーンはハラハラするほど印象に残る。健康にいい悪いはそっちのけで、二谷が背中をまるめ、芦川が嫌うカップ麵にひとり向かう姿が熱い湯気とともに伝わってくる。
二谷の姿は、かつて勤めた職場でよく見かけた光景と重なる。深夜近くに席を立ち、カップ麵にポットのお湯を注ぎ、汁がこぼれないように席まで運び、カップ麵を机のパソコンの前に大事そうに置き、お辞儀みたいに背中を丸めて椅子を引く同僚の姿が焼き付いている。焼き付いているといっても特別だったのではなく、いつもの光景だっただけだ。
買っておいたカップ麵をもち運ぶときのカラカラとした軽量感が、ほかに集中するなにかを思わせる。カップ麺は、忙しすぎる生活の象徴かもしれない。
●主役は三者三様のマイルール
たまに小説を読む程度のわたしが思うに、本作の軸は、二谷と芦川と押尾という三者それぞれのマイルールのぶつかりあいと交わらなさである。三人は職場で微妙な先輩後輩関係にあるが、上下関係、支配する関係はない。支配者は支店長だけで、ほかに決定的な上下支配関係はなさそうだ。主役は食べ物の三者三様なマイルール。互いに領域侵犯されないよう相互監視する自分だけのルールだ。
二谷はいう。「おでんが食べたいって日はあるけど、そのためにおでん屋まで行くのは、自分の時間や行動が食べ物に支配されてる気がして嫌」。二谷は独立自尊である。押尾は二谷の言動を細かく観察してマイルール同士の接点を探すが、さして熱心ではない。芦川が二谷とのあいだでさえマイルールの共鳴に関心がない。芦川は手作りお菓子を同僚にふるまうが、それとて、自分だけに向けられたマイルールだ。そのあたりが二谷にとって芦川の容赦なさであり、怖さだろう。
マイルール同士は互いに影響しない。マイルール保持者の3人はおそらく似た者同士である。
二谷は実は食べることすら嫌いという極端なマイルールの持ち主だ。彼の理想はロボットだろう。それでいて、なにを食べるか、その食べ物こそは二谷の究極的な自由を象徴する。夜遅くどんなカップ麵を食べるか、二谷はスーパーやコンビニの棚に並んだカップ麵のなかから自由に選択する。マイルールの支配する世界でこそ、完全に自由な選択を謳歌できる。押尾芦川もここはおなじだろう。
●怖さに隠れた弱さ
さて、芦川の「怖さ」である。二度目の通読で、「怖い」はずの芦川が消えてしまった。芦川は可愛く優しく、料理とお菓子作りが得意。組織のなかで弱さを理解され、特別に守られている。ほかの人なら容認されない中途半端な仕事振りも聞いてもらえる。仕事を離れれば二谷とちゃっかりつきあい、結婚の文字がちらちらしている。弱さのベールをかぶった怖さにムカつく心理は、一応わかる。
二度目の通読で、芦川なりのマイルールをますます強く感じる。ムカつきも半端ないわけだ。だが、ひとつ違ってきた。料理やお菓子作りが日常にあるわたしの贔屓目かもしれないが、芦川は、狭い檻のなかに閉じ込められた人に見える。芦川が前の職場で経験したというハラスメントが芦川を委縮させているのかもしれない。だとしたら、芦川の弱さは演技ではなく、傷つき、苦しむ人の弱さではないか。芦川の「怖さ」がピンと来なくなったわたしは、芦川(あるいは作者)にまんまと騙されている惨めな読者に落ちたのだろうか。
芦川のような人物が好きで、友達になりたいわけではない。勤め先に手作りお菓子をもっていきたいわけでもない。*ちょっと脱線しますが、5~6人ごとのチーム制をとっていた職場でチーム間のコミュニケーション不足に嘆く同僚に、月一でも手作りクッキーとか持ってきましょうかといったら、同僚たちがびっくりして互いに目を見合わせ、やんわりと引かれた経験があります。高瀬さんのこの小説の顛末をだれも知っているはずがないのに、あのときナイーブなわたしに遠慮しいしいみんなで引いてくれてよかったと同僚たちの賢さを再認識しました いま再会したら真っ先にこの小説の話をし、あらためてあのときのお礼を言いそうです。きっと盛り上がること間違いなし!・・(笑)。
脱線はここまで。話を戻します。
わたしはただ、彼女の笑顔の向こうに押し込められた弱さを感じる。芦川をマイルールに閉じ込める檻が内堀とすれば、上司らは芦川を守る外掘りである。二谷押尾は二重の檻の外側から芦川を眺めているだけだ。
芦川が離職したら、理解ある上司達の外掘りは失われる。二谷と結婚しても、代わりの外掘りではない。二谷と結婚するにせよしないにせよ、芦川は内堀だけの危うい自分に気づき、ため息をつく時が来るだろう。
●嗚呼、自由に読んでしまった
小説をどう読むかはあくまで自由だ。審査員の何人かが異口同音にコメントするからといって、縛られることはない。わざわざ天邪鬼を言って面白がる趣味もない。ただ、他人の指摘をいったん忘れて作品と一対一、虚心坦懐に読んでみたら、肩の荷から小石がポロポロ落ちた。過去の思い出にさかのぼり、ネット記事を拾って道草しながら、自分を好きなように投影し、自由自在に読むのもいいものだ。
天下の芥川賞受賞作にこんな情けない感想を書いてよいのか、迷います。いつまで迷ってもキリがないので、エイヤッと公開します☆
読んでくださってありがとうございます いただいたサポートはこれからの書き物のために大切に使わせていただきます☆
