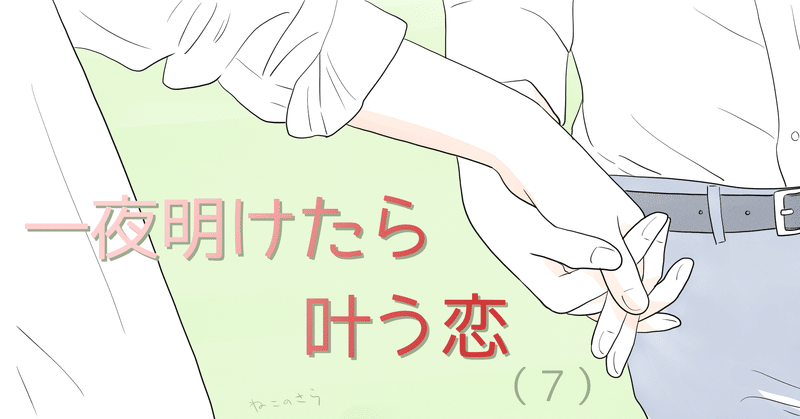
「一夜明けたら叶う恋」(7)
(これまでのあらすじ)
社内で密かに想いを寄せる宮内から、女友だちを紹介したいと言われた「僕」。宮内を落胆させたくなくて、彼女に会うことを承諾してしまう。行きつけのゲイバーのママからノンケは住む世界が違うと言われ、いまさら落ち込む僕だった。
(1)
思いもかけない人から連絡があった。
「いまからちょっと会えないかな」
懐かしい声を聞いたら、僕も会いたくなった。
「いいよ。あの店?」
「そう。待ってるからゆっくりおいで」
夕飯を食べ終えたところだった。僕はスウェットをチノパンに履き替え、ダッフルコートの上からマフラーを巻いて駅までのバスに乗った。
カウンターだけの小さなバー。
「相変わらず寒がりだな」
僕の姿を見て彼が笑った。ほかにカップルがひと組。僕は彼の左側へ腰かけた。
少し白髪が増えたようだ。
「尚樹もマティーニでいい?」
小さく頷く。ドライマティーニの味を、彼にここで教わった。
「やすえママでしょう?」
互いのグラスをかざしたあと、僕は彼にそう尋ねた。彼はやんわり微笑んだ。ピンキーのママは苗字が安江で、それが通り名になっている。
「心配してたよ、尚樹のこと」
「だからって人の元彼に電話するかな」
苦笑する僕に彼の手が伸びる。乱れた髪を整えるように軽く触れた。
「あの人らしいよな」
久しぶりのマティーニは、記憶よりも深い味がした。僕は彼の顔をまじまじと見た。
「白髪増えたね」遠慮なく言う。
「増えたさ。もう四十五だ」
「渋くなった。前よりいい感じ」
「そうかい」
言いながら彼がジャケットの内ポケットを探る。銀色のシガレットケースが現れた。
「いいかな?」
「もちろん」
ケースの蓋を開け、取り出した一本に店のマッチで火をつける。
「いまも自分で巻いてるんだね」
「ああ。これだけはやめられなくてね」
マンションのリビングで煙草を巻いていた彼の姿を、僕はありありと思い出した。専用の小さなローラーに、丸缶からつまみ上げた煙草の葉を詰め、薄い紙を差し入れて巻く。入れる前、紙の端を舌先で舐める仕草が妙にそそった。何度キスを迫ったかわからない。邪魔するなとあしらわれるとよけい意地になり、ソファの上に無理な姿勢で抱きついて、ガラステーブルの上に煙草の葉を撒き散らしたこともあった。
「思ったより元気で安心したよ」
「うん、ありがと」
元気に見えるのは、いまこうしてやさしいあなたの隣にいるからだと、本人には言わなかった。
ゆっくりと漂う煙。ほんのり甘い、バニラのような香り。銘柄はなんだっけ、もう忘れてしまった。
「尚樹はちっとも変わらないな」
「そう?僕だってもう三十だよ」
「私を振ったのは二十七のときだっけ?」
「その話はしないで」
彼にもたれかかるように、ふざけて腕を押す。彼も笑っているのが見なくてもわかる。
カウンターの上へ何気なく置かれた彼の左手に、指輪が鈍く光っていた。新しいパートナーがいることは風の噂で聞いている。その手の上に僕の手を重ねた。間髪入れずに彼が言う。
「これは光栄だ」
僕は笑って手を離した。二人で決めた泊まりの合図。誘うのはいつも彼だった。誘われるよう仕向けたのは僕。
一時間ほど話してバーを出た。彼が呼んでくれたタクシーの明かりが遠くに見える。僕は彼の頬に素早いキスをした。彼が僕の肩を一瞬だけ強く抱いた。
「元気でな」
タクシーの中で目を閉じた。
別れたばかりの彼の顔が浮かぶ。やわらかなまなざし。変わらないやさしさ。彼の幸福を僕は祈った。
いつかまた。僕にもきっと。幸せが訪れるはず。
「寒くないですか?」
運転手の声にまぶたを上げた。
「ええ、ありがとう」
笑顔でそう答えた。
金曜日、仕事を終えた僕は駅前の大通りを歩いていた。街路樹のイルミネーション、行き交う車やビルの明かりが夜を彩る。
隣で宮内が言った。
「あの信号の角です、レストラン」
寒いのと、約束の時間に遅れてしまったせいで、僕らは急ぎ足になっていた。
階段を上がって中へ入ると、店員が笑顔で近づいてきた。宮内が名前を告げ、テーブルまで案内される。全面に張られたガラスの向こうに、街の明かりが透けて見えた。いかにも表通りにふさわしい店。この裏道の雑居ビルにゲイバーがあるなんて、ここにいる誰もが想像すらしないだろう。
僕は二つの決意を胸に秘めていた。まず今夜会う彼女には、誠実かつ失礼のない態度で接すること。交際に発展する可能性がまったくないにしても、宮内の会社の先輩という立場がある。彼の顔を潰すわけにはいかない。
そしてこの「お見合い」が終わったら、僕は宮内にはっきりと言う。五年つきあった彼女と別れた本当の原因は僕にある。僕に好きな人ができたからだ。つまり君の女友だちとはつきあえない、ごめん。
本人を前にして「好きな人ができた」と言えるかどうか、まったくもって自信はなかった。だが言うしかない。言って宮内には「仲人」を諦めてもらう。僕も宮内を諦める。きっぱりと。
「こちらです」と店員が示したテーブルには、ショートヘアの女性が一人で座っていた。彼女の手元にはワイングラスがあり、クーラーの中に傾いたボトルの中身が半分ない。
「やっと来たわね」
ちらっと僕に一瞥をくれると、なんとも妖艶な笑みを浮かべた。
最後まで読んでくださってありがとうございます。あなたにいいことありますように。
