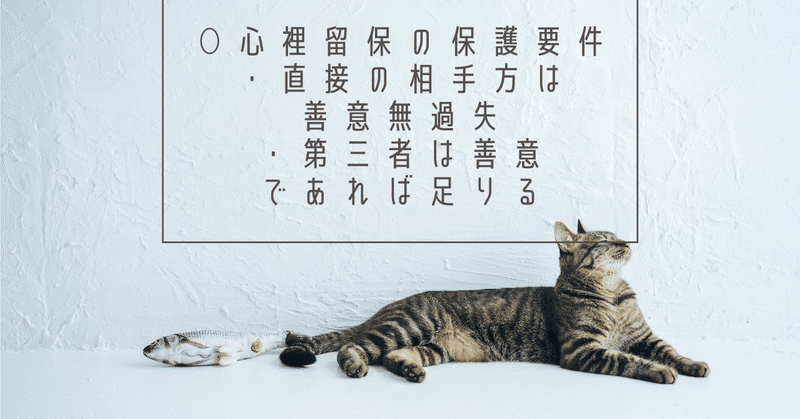
民法過去問論点
不法条件でも、法律行為が全体として不法性を有しない場合は、無効とならない。よって、当事者の一方が第三者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負ったときは、他方がその賠償責任を履行する旨の契約は無効とならない。
債権者は、債務者の資力が自己の債権の弁済をするのに不十分である場合には、その弁済に必要な限度において、債権者代位により、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる
保証人・連帯保証人は、主たる債務者が時効の援用をしないときでも、主たる債務の消滅時効を援用できる。
主たる債務者に対する履行請求その他の事由による時効の更新は、保証人に対しても効力を生ずる(457)。この点については、連帯保証であっても同様である。なお、主たる債務者がなした時効利益の放棄は、保証人・連帯保証人に対しては効力が及ばないことに注意が必要である。
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から
6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
しかし、遺産分割協議において、相続人の債務を承継する者を定めることは、直接これらの事由に該当するわけではない。
夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効は、婚姻解消の時から進行を始るのではない
婚姻が解消されなければ、権利行使ができないわけではないため
○期限の定めのない債権の消滅時効進行は債権成立の時
期限の定めのない消費貸借契約の債権は、催告から相当期間経過後もしくは催告しなかった場合でも相当期間経過後から進行する
〇寄託期間の定めのない場合
→寄託の時から消滅時効が進行する
・寄託期間の定めのある場合
→寄託期間満了の時から消滅時効が
進行する
Aがその所有する甲土地を深く掘り下げたために隣接するB所有の乙土地との間で段差が生じてて土地の一部が甲土地に崩れ落ちる危険が発生した場合には、Aが甲土地をCに譲渡し、所有権の移転の登記をしたときであっても、Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づく妨害予防請求権を行使することができない
物権的請求権の相手方は、原則として、現に他人の物権を客観的に侵害し又は侵害の危険を生じさせている者である。
限定承認時の不動産の換価は競売に限る
(不当な廉価で任意売却されたら困る)
ただし任意売却がされてしまったら取引安全を考慮して有効
他人の所有地上に建物を取得し、自らの意思に基づいてその旨の登記を経由した者は、当該建物を他に譲渡したとしても、引き続きその登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない
ただし、これは当該登記名義人が自らの意思で建物を取得し、自らの意思でその登記をした場合に限られる。
したがって、乙建物につき、Aの申立てにより処分禁止の仮処分命令がされ、裁判所書記官の嘱託によるB名義の所有権の保存の登記がされたときは、Bの意思でその登記をしたものではないため、Aは、Bに対し、甲士地の所有権に基づき、建物收去土地明渡しを請求することができない。
土地賃借人が甲土地の占有権原を失ったときは、土地所有者は、建物の占有を通じてその敷地を占有する建物賃借人に対し、建物からの退去及び士地の明渡しを請求することができる。
しかし建物賃借人には建物の処分権限はないため、建物の収去は請求できないことと区別する
A所有の建物をBがAから賃借して居住し、Cが賃借人Bの身の回りの世話をする使用人として建物で賃借人Bと同居している場合において、AB間の賃貸借契約が解除されたときは、所有者Aは、使用人Cに対し、建物の明渡しを請求することができない。
使用人が雇主と対等の地位において、共同してその居住家屋を占有しているものというのには、他に特段の事情があることを要し、ただ単に使用人としてその家屋に居住するにすぎない場合においては、その占有は雇主の占有の範囲内で行われているものと解するのが相当であり、雇主と共同し、独立の占有をなすものと解すべきではない。したがって、当該使用人に対し、その不法占有を理由として家屋の明渡ならびに賃料相当の損害金の支払を請求することはできない
Aが、その所有する甲土地をBに売却したものの、その旨の登記がされない間に、Aが甲土地をCに売却してその旨の登記がされ、その後、CがAに甲士地を売却してその旨の登記がされたときは、Bは、
Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
