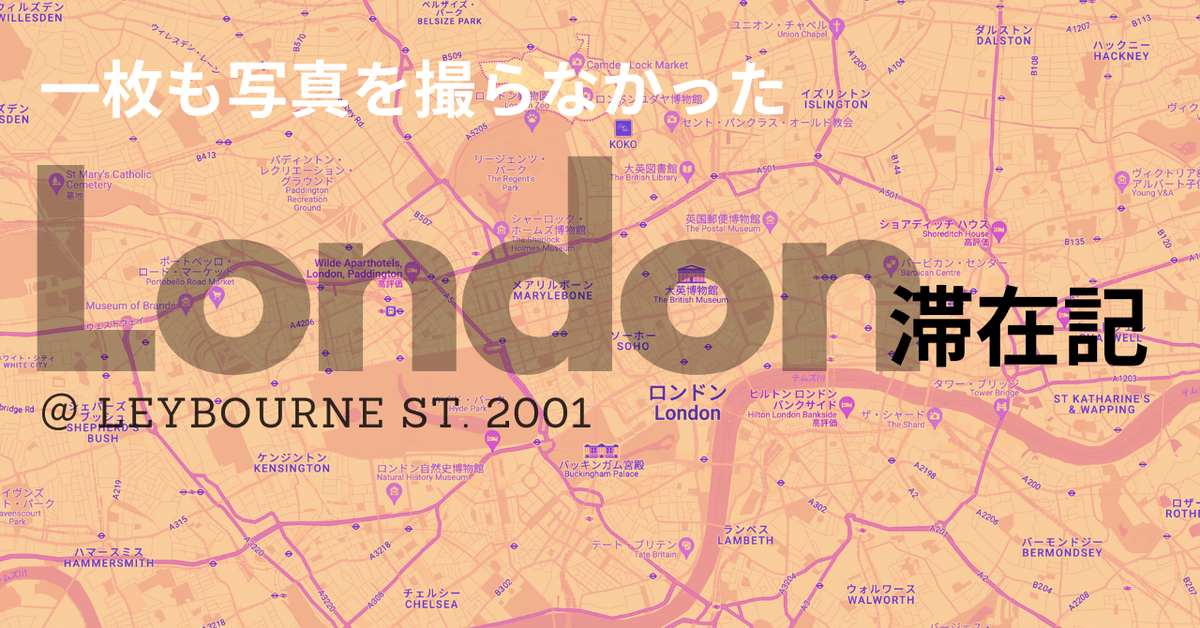
一枚も写真を撮らなかったロンドン滞在記
@はじめに
旅行記を書いてみよう、ということで、今回題材に選んだのは、22歳のときのロンドン滞在です。
ひとりで、ロンドンのカムデンタウンという街に、1ヶ月半ほど滞在しました。短期留学?違います。観光?違います。友人知人に会いに行った?違います・・・実はこのとき、渡航の明確な目的はありませんでした。もう少し正確に言うと、個人的な動機はもちろんあったのですが、あまりにも抽象的すぎて、自分でもよくわからず、他人にもうまく説明できるだけの解像度に落とし込むことができませんでした。語学留学に行った、観光で行った、友人に会いに行った、ロイヤルアルバートホールで開催されたレディオヘッドのコンサートに行った・・・など、わかりやすいストーリーがあれば良かったのですが、残念ながら、事態は混沌としていました。そのため、この記事も曖昧で、不鮮明で、趣旨を汲み取りにくいのものになってしまうかもしれませんが、世の中には、そんなふうに無目的、無計画にどこかに行ってしまう妙な人もいるんだなぁという感じで、ひとつの参考事例として楽しんで頂ければ幸いです。
また、一点、残念な点として、ここに載せられる写真が一枚もないということです。理由は、渡航時にカメラを持っていっておらず、写真を一枚も撮っていないからです。外国の街にせっかく1ヶ月半も滞在したのに、なぜ写真の一枚でも撮ってこないのか?いま思うと本当に何をしてたんだろうと無念でしかありません。ただ、当時は「別に旅行に行くわけじゃないんだから写真なんていらねえや」などとわけのわからない思想を持っておりまして・・・やっかいですね。もう弁明の余地もございません。
とはいえ、文章ばかりになるのも辛いので、せめてもの手書きイメージイラストを織り交ぜて、当時の足取りを追っていきたいと思います。
@そもそもなぜロンドンなのか?(Chiristmas 2000)
ここからもう説明が難しいのですが、少なくとも、ロンドンに行こうという明確な意思を持った時期だけは、はっきりしています。2000年の12月初旬の、冬のある夜11時頃のことです。私は当時21歳で、神戸で一人暮らしをしていて、専門学校に行きながら、居酒屋でアルバイトをしていました。そのアルバイトの帰り、三宮駅から、新神戸駅の近くまで歩いて帰る途中のことでした。三角公園(神戸の人ならわかるはず)の雑踏を通り過ぎながら、クリスマスムードのきらきらした街並みの中をひとりで歩いていくわけですが、その時に突然、頭の中にあるコンセプトが降りてきたんです。
「そうだ。来年のクリスマスはロンドンで過ごそう」
嘘みたいな話ですが本当なんですよねこれ。別にどこかに行きたいなぁとか、人生に刺激が欲しいなぁとか考えてたわけでもなく、ただアルバイトの帰りにぼーっと、いつもの帰り道を何食わぬ顔で歩いていただけなんです。よく、何かの啓示を受けた人が「雷に打たれたように」という表現を使いますが、そんな感覚に近い衝撃がありました。そのコンセプトが降りてきた瞬間のことは、20年経った今でもはっきり覚えてます。冷たい夜の空気、駅前のタクシーの列、誰かの笑い声、遠くの新神戸のビルの明かり・・・。

とにかく、その日からというもの、ロンドンに行くことが生活の主目的になりました。私は比較的、極端な性格ですので、こうなったら渡航費と滞在費のためにアルバイトに専念しようと思い、そそくさと専門学校を辞めようとするのですが、担任から「あのね、せめて3月まで在籍して卒業という形にしなさい」という賢明なアドバイスを頂いて、踏み止まります。そして、就職は棒に降りつつも、卒業だけはさせてもらい、4月からは一番稼ぎやすい深夜の時間帯に切り替えてアルバイトを続けました。昼夜逆転の生活で、毎日12時間くらい働いてましたが、目的があると人間凄いですね、まったく苦にならなかったです。今だったらもう8時間働くだけでもげっそりするのに・・・。とにかく、そんな風にして、次の冬が来るまでひたすら資金を貯めて、残高が100万円くらいになったところでそのアルバイトも辞めました。そして思惑通り、11月下旬から、クリスマスシーズンを含めた年末までの時期を目掛けて、ブリティッシュ・エアウェイズの航空券を手に入れたというわけです。
ちなみに、当時(2001年)はまだスマホもありませんでしたし、インターネットも一般普及してないので、近所の旅行代理店に行って、航空券やホテルの手配をしました。それから、パスポートを入手したり、トラベラーズチェックを買ってきたり、少しずつ準備が整っていく感じが楽しかったですね。一番悩んだのは、ホテルの予約でした。私は、観光ビザで滞在できる期間(1ヶ月半くらい)ぎりぎりまで滞在するつもりでしたが、完全ホテル暮らしだと、とんでもない金額になります。そこで旅行代理店で相談したり、旅行雑誌で調べたりしたところ、ロンドンにはB&Bというシェア・ハウスが沢山あることを発見。クールでヒップなバックパッカーたちが世界中から集まってくる、みたいな触れ込みでした。これしかないと思いました。そこで、ホテルの予約は最初の3日間だけにして、それ以降は現地でそのシェア・ハウスを探して住むことを前提としたアクロバット・プランにしたのです。旅行会社の人からは「本当に大丈夫ですか?」と心配されました。確かに、初めての外国旅行だし、一人だし、英語もろくに話せないし、1ヶ月以上という長期期間だし、結構チャレンジングです。でも、当時の私は謎の自信に満ち溢れており、その希望的観測に溢れた高リスクプランを強行します。お陰で酷い目に遭うんですが、それはこの先のお楽しみに・・・
@飛行機の中で見た風景(British Airways)
いまどれだけ一所懸命考えても、帰りの飛行機のことはまったく覚えてないのですが、行きの飛行機はのことは、ちゃんと記憶に残っています。まず、生まれて初めての機内食がとても新鮮でした。何があったっけ。パンと、チキンと、ヨーグルトと、オレンジと、スープと・・・大したものじゃないですけど、あれってやっぱり特別ですよね。硬いパンに、硬いバターを塗りながら、これから特別な場所に行くんだという気分にさせてくれます。
それから、夜景で2回、心を動かされた場面がありました。ひとつめは、しばらく眠った後で、ふと目が覚めて外を見たとき、夜の真っ暗闇のずっと下のほうに、ぼんやりとした町の明かりが見えました。座席についているモニターの衛星地図によると、飛行機はちょうどロシア上空を飛んでいましたので、見えたのはロシアのどこかの町の明かり、ということになります。飛行機で機内食を食べないといけないくらい長く飛び続けても、大陸はまだちゃんと続いていて、その謎の大地に、謎の町があり、謎の人々が住んでいる。そう考えるととても不思議な気分になりました。そして、いま見ているこの町は、今後もう二度と見ることもないだろうけど、それでもずっとそこに存在し続けるわけです。それについて、何を思えばいいのかよくわかりませんでしたが、「よし。この町のことはずっと覚えておこう」と思って、視界から消えるまでずっとその小さな明かりを眺めていました。

ふたつめは、飛行機から見たロンドンの夜景です。機内アナウンスがいよいよ着陸体制に入ったことを告げた後、しばらくは雲の中を飛行していたのですが、突然、機体が雲から抜けたかと思うと、眼下にばーっと、視界いっぱいに、巨大な街の夜景が広がったのです。機内の中で他に起きていた人たちも軽い感嘆の声(Wow, Look at that!)をあげていました。地図で見て覚えてしまっていたテムズ川の形がちゃんとわかるんですよね。すごい、ほんとに着いたんだ・・・と、私は素直に感動して、飛行機がヒースロー空港の滑走路に着陸するまで、ずーっとその夜景を眺めていました。
ヒースロー空港から、ホテルがあるピカデリー・サーカスまではタクシーで行きました。本当は電車で行く想定だったんですけどね・・・長時間フライトで疲弊して、路線を調べたりなんだりする気力を失っているところで、ロビーで出待ちしているタクシーの運転手に誘われるがままに、ふらふらと乗り込んでしまいました。ちなみに、このタクシーの運転手との会話が、イギリスでの最初の英会話です。「どこに行くんだ?」「ピカデリー・サーカス」「ホテルの名前は?」「⚫︎⚫︎(ホテルの名前)」「すぐ着くよ。乗ってく?」「うん」・・・明らかに怪しさ満点のタクシーでしたが、疲弊感とあわせて、「あ、会話通じた」という嬉しさも後押ししたような気がします。ただ、後で計算してみると、結構盛大にぼったくられてましたね!
@ピカデリーサーカスのホテルで起こったこと(Muffin? Scorn?)
ホテルの名前、確か「Palace」という単語が含まれてたんですが、正確な名前を忘れてしまいました。先ほど、Googleマップでそれらしい場所を探してみたんですが、見つけられず。すごく古いホテルだったのでもう無くなってるのかも・・・?場所もはっきり覚えてないですが、確かちょっと歩いたところにエロス像があったので、ピカデリー・サーカスのほぼ中心部だったと思うんですが。
ホテルはめちゃめちゃ古くて、やばかったです。たぶん外国のホテルあるあるだと思いますが、エレベーターは文字通りガタガタという不吉な音を立てて激しく揺れるし、部屋の壁が薄っぺらくて隣から歯磨きの音が聞こえてくるし、シャワーはどれだけ頑張っても水しか出てこないし、ソファーチェアは3年くらい物置に置いていたかのような奇妙な臭いがするし、部屋の壁紙はあちこちで剥がれているし・・・。ただ、ホテルに着いた時、私はもうそんなことを気に掛けることもできないくらい疲れてました。疲れてたというか・・・。とにかく、チェックインを済ませて、ロビーの売店でオレンジジュースとスコーンみたいなものを買い、やばいエレベーターに乗って、やばい部屋に入って、スーツケースをベッドの上に投げ出しました。不思議な匂いと、不思議な音。小さな窓の外には、隣の建物の煉瓦の壁が見えます。私は、ベッドの端に座って、オレンジジュースを飲み、スーツケースの中身を開けようとしたのですが・・・
そこで感じたことを説明するのは、ちょっと難しいのですが、ちょうど私が別の機会にその時のことを書いた文章があるので、そこから抜粋してみたいと思います。
私はピカデリーサーカスのど真ん中にある、小さくて古いホテルにいた。ヒースロー空港から、法外な金額を払ってタクシーでやってきたところだ。チェックインでたどたどしい英語のやりとりを終えた後、ロビーの脇の小さな売店で、マフィンとオレンジジュースを買った。古いエレベーターはガタガタと音を立ててゆっくりと昇っていった。私は薄暗いカーペット敷きの廊下を歩き、自分の部屋番号が書いてあるドアを見つけて、鍵をあけた。部屋はその空間のほとんどをベッドに占拠されていたけれど、それは部屋が小さいせいなのか、ベッドが大きいせいなのか、わからなかった。窓際には緑色のフェルト椅子が一脚。壁紙はあちこちで破れている。窓の外には煉瓦の壁と、巨大な排気口が見えた。私はスーツケースをベッドに置き、緑色の椅子に座って、硬すぎるマフィンと甘すぎるオレンジジュースを飲んだ。それからこれといった意図もなくスーツケースの中身を取り出そうとしたときに、ふと自分が泣いていることに気づいた。日本から九万キロ離れたところにある異国のホテル。この国では、私は誰のことも知らないし、誰も私のことを知らない。自分の存在を唯一、公的に証明するものはホテルのコンピューターに登録されている名前くらいのものだったが、そのホテルにしても三泊分しか予約していない。帰国できるのは二ヶ月後だったが、それまでどこで何をして過ごすのかは文字通りの白紙だった。私には語るべき過去もなく、待つべき未来もなかった。部屋の薄いドアの向こうでは、知らない人々が知らない言語で話をしている。壁の中のパイプを水が流れていく音が聞こえる。ホテルの外で車がクラクションを鳴らしている。私は世界から見事なまでに隔絶していて、どことも、だれとも、なにとも繋がっていなかった。純度百パーセントの自由。純度百パーセントの孤独。それはある種の麻薬物質のように、全面的に新しいやり方で、脳髄を揺さぶり、細胞の奥深くに染み込んでいった。そして、朝日が差し込む頃には、私の体の組成の基本原則がすっかり組み替えられてしまっていた。確かフランツ・カフカがそんなようなことを言っていたと思うけれど、旅人が戻ることができない地点に到達できるというのは、実に不思議なものだった
これを書いたのは数年前でしたが、「マフィン」って書いてるなぁ。マフィンんだっけ?どちらかというとスコーンだったような気がするけど・・・まぁどっちでもいいか。何にせよ、何かしらの小麦粉系の粉物の塊だったことに変わりはありません。それにここで重要なのはマフィンかスコーンかではなく、その後の部分です。

そうなんです。何だかわからないんですが、急に涙が出てきたんです。自分でもびっくりしました。びっくりしながら、しばらく泣き続けました。たぶん30分くらい。冬のピカデリー・サーカス、古いホテルの部屋でひとり、タクシーに軽くぼったくられた後で、パサパサのマフィンだかスコーンだかを甘ったるいオレンジジュースで流し込みながら。どうしてそんなことになったのか?わかりません。当時の感覚をなぞることしかできないですが、たぶんそれは「孤絶感」と関係していると思います。
「ここには自分が知っている人は誰もいないし、自分を知っている人も誰もいないんだ」
そんなことを考えたのは覚えてます。自分の国から離れて、飛行機から見たあのロシアのどこかよくわからない町さえも超えて、何とも繋がっていない、何にも守られてない場所に来たという事実。そして3日後には、仮の宿であるそのボロボロのホテルからも出ていかなくてはならないという状況。誰かに電話をしたくても、電話の掛け方さえわかりません。手紙の出し方もわかりません。・・・変な言い方ですが、私は当時、自分は孤独を苦にしないタイプだという思い込み(思い上がり)があったので、まさかそんな風に崩れてしまうとは、思いもよりませんでした。ある種ショックでもありました。朝になってもこんな酷い気分だったら、もうそのままヒースロー空港に戻って日本に帰ろう。何も無かったかのように何食わぬ顔で帰国しよう。そう固く決意して、ロンドン滞在初日の記念すべき夜が終わりました。
まぁひどい話ですね!
@インド人の不動産屋との電話(I want a room)
さて。一夜明けてどうなったか?
たぶん朝日の効用も大きかったと思いますが、前夜のような、全存在を揺るがすほどの気持ちの動揺は消えていて、代わりに、大地震の後で崩壊した建物を見ている時のような、ある種の諦めに近い茫然とした感覚に包まれていました。そして孤絶感の代わりに、切迫感というか、焦燥感というか、何だか異様に落ち着きのないものが胃の中でくすぶっており、すぐにでもなんとかしなければ、という思いにかられていました。・・・そうです。住むところを探さないと!明後日にはホテルを追い出されるぞ!?
B&B(Bed&Breakfast)というのは、要はシェア・ハウスです。旅行者や、学生や、出張会社員などの滞在者が、ホテルに払うお金を節約するために集まってくる場所です。普通に長く暮らしている人もいます。ロンドンでは、B&Bというより、フラット(Flat)という呼び方をしてました。1週間程度の旅行ならホテル暮らしのほうが安心安全ですが、1ヶ月以上となるとそんな贅沢もできません。今ならAirBnBみたいなプラットフォームで簡単に予約できそうですが、当時の旅行会社ではフラットを予約してくれなかったので(儲からもんな、そんなことしてたら)、滞在費を節約したいなら、現地で直接探すしかありません。どうやって探すのかというと、雑誌とか新聞に載っている広告を探して、電話をかけるんです。
そんなわけで私は、その異様な焦燥感に突き動かされるようにして、ベッドから出てホテルの売店に行き、新聞と、オレンジジュースと、またマフィンだかスコーンだかよく覚えてない小麦粉系の粉物の塊を買うとまっすぐ部屋に戻り、新聞と格闘を始めます。広告の中のわからない英単語(一杯ある)を英和辞典で調べ、地図で場所を確認し、金額を比較しながら、最終的に三つくらいの候補に絞りました。電話をかけようとフロントに行きましたが、電話なんてものはないから、外にある電話ボックスを使ってよ、とぶっきらぼうに言われました。水しか出ないホテルであることを忘れていました。そして、この時に初めて、朝日に輝くピカデリーサーカスの歴史ある、美しい街並みを目にしたわけですが、焦燥感のせいで、まるで興味を持てないんですよね。目は見ているんですが、意識は別のところに、数ブロック先に行ったところにある電話ボックスにフォーカスされています。いったい何をしに来たんでしょう・・・?
ちなみに、この時点の私の英語力は、TOEICだとたぶん400点くらいじゃないかなと思います。学生時代、英語のテストの点数は比較的良いほうでしたが、レッスンに通ったこともなければ、身近に英語を学べる環境もありませんでした。ただ公立学校の授業(それも20年前の公立学校の英語の授業・・・)を受けただけの状態です。そしてインターネットも普及してなければ、スマホもなく、頼るものは英和辞典だけという素朴な時代。そんな状況下のロンドンで、誰の助けもなく、不動産屋に電話をかけて、英語で会話をして、シェア・ハウスを短期で借りる・・・なんてことがよくできると思っていたなぁと、ただただ呆れる・・・ではなく、感心するばかりです。私がその時、電話をする前に念頭に置いていたのは、このフレーズだけです。
I'm from Japan. I'm Japanese. I want a room for a month.
これさえ言えれば大丈夫、なんとかなる・・・という風に闇雲に信じ切っていました。お祈りの文句みたいなものです。無知って本当に恐ろしいです。
一件目の不動産屋は、女の人が電話に出ましたが、何を言っているかわかりませんでした。ものすごく早口で何かを言われて、お祈りのフレーズを言おうにも、慌ててしまって、まごついている間に、電話を切られてしまいました。うーん、マジか。二件目は、何度かけても話中?営業時間外?か何かでまったく繋がらず。マジか・・・と思いつつ、三件目。そこでやっと会話になりました。これは本当に本当に嬉しくて、今でもまだあの電話ボックスから見た風景とセットで、会話の中身を覚えています。
Agency "Hello."
Me "Hello"
Agency "What do you want"
Me "I want a room"
Agency "Room? …OK. Are you traveling?"
Me "Yes, travel. I'm from Japan. Japanese. I want a room. I want to rent"
Agency "Japanese, OK, I'll show you the room. Can you come with me?"
Me "What?"
Agency "Well, I'll take you to the room. When do you want to meet?"
Me "Meet?"
Agency "Meet. You and me. You want to see a room?"
Me "Ah, You take me to the room?"
Agency "Yes. I'll take you. When you come?"
Me "Today?"
Agency "Hmm…OK, how about three?"
Me "Three o'clock?"
Agency "Yeah, three o'clock. And It's in the Camden Town"
Me "Camden Town, what is this?"
Agency "It's the tube station. We'll meet at there. Three o'clock."
Me "Ah, OK. Camden town, station, three o'clock, today, OK?"
Agency "OK."
Me "Thank you. I wait you. Three o'clock"
Agency "OK"
実際はもっと言葉の応酬を繰り返してますが、話の流れというか、雰囲気としては、こんな感じでした。インド人の不動産屋だったのですが、私が英語を満足に話せないしがない外国人だとわかると、話し方を変えてくれて(ゆっくり&繰り返し&カタコトっぽく)、そのお陰でなんとか会話が成立しました。ちなみに、紹介された部屋が新聞に載っていたのとは違う物件だったので、この時点では、カムデンタウンというのがどこにあるのかもわかっていません。あと「Three o'clock」を何回も繰り返し言ってますが、ここは不安で不安で何度も聞き返したのを覚えてます。だって間違えたらもう二度と会えないかもしれないし、もう藁にもすがる思いですよ・・・。

それにしてもこの会話、あらためてテキストに起こしてみると、今なら小学校の英語例文に出て来そうなレベルの内容です。発音だって酷いものだったと思います。ただ、このわずか5分程度の会話は、私にとって大きな意味を持ちました。電話ボックスを出た時に、見えた風景の印象が違ったんです。視界が広がって、ロンドンの街並みが、意識の膜に少しずつ染み込んでくるような感覚。本当に3時にインド人がやってくるのか?カムデンタウンがどんなところか?そんなに簡単に契約ができるのか?タクシーの時みたいにまたぼったくられるんじゃないか?・・・まだまだ不安はありましたが、なんというか、この電話の会話によって、新しい世界のとっかかりを掴んだような感覚がありました。何かと繋がれた感覚。世界に自分を認知してもらった感覚。それまで、気持ちはずっと後ろの方(ヒースロー空港)しか向いてませんでしたが、やっとここで前を向けました。これも全て、あのインド人のお陰です。でも残念、ある種命の恩人なのに、彼の名前を忘れてしまいました・・・。
そして、上昇の機運を掴んだ私のモチベーションですが、路線図片手にロンドン名物の地下鉄(Tube!)を乗り継ぎ、カムデンタウンの駅で降りて、改札の外に広がる町の風景を見たときに、まさかのV字回復、完全復活を遂げることになります。
@カムデンタウンの奇跡(What's the "Deposit"?)
この町が世界的にどれくらいの知名度があるのかわかりませんが、名前だけ聞くと、なんだか牧畜をやってるどこかの田舎町みたいな、パッとしない印象を受けます。地図で見るとこんな感じで、中心部から北に電車で30分もかからないくらいだったかな・・?東京だと、新宿から京王線に乗って、千歳烏山とか仙川あたりでしょうか。いずれにせよ、カムデンタウンの駅で降りたときは、まったく何の期待もしていなくて、ただ部屋が借りられればもうどこでもいい、なんでもいいから、とにかく屋根と壁がついてる部屋を貸してくれ・・・という切羽詰まった思いだけです。あとは、どうすればインド人からぼったくられないで済むかを考えてたくらいでしたが・・・

私のこんな人生(どんな人生?)にも、これまで素晴らしい瞬間が沢山ありましたが、この改札を出た時に見たカムデンタウンの風景は、人生でTOP5に入るくらいのハイライトシーンです。言葉にするのが非常に難しいのですが、道路に一歩踏み出して空気を吸った瞬間に「俺はここに住む」という確信を得ました。「住みたい」とかではなく「住む」です。インド人にぼったくられてもいいし、何ならインド人が来なくてもいい。野宿してでも、何があっても、とにかくここで暮らして帰るんだ・・・何の根拠もないですが、100%の確信を持って、全身のすべての細胞がそう主張していました。私はそのままフラフラと町の中に吸い込まれそうになりますが、ぐっと押さえて、駅前の雑踏の中で、幻惑されながら、3時になるのを待ちます。
3時ちょっと過ぎたところで、無事にインド人の不動産屋とうまく落ち合うことができ、彼の後ろをついて、町の中を歩いていきます。石畳で舗装されたハイストリート。レトロな街灯。道の両脇に隙間なくびっしり立ち並ぶ、カラフルな煉瓦作りの建物。その上には、青い空が突き抜けるように広がっています。いろんなオブジェで飾られているたくさんのお店。歩道にはみ出す勢いで陳列されている雑貨。古着屋、レストラン、パブ、アクセサリー屋、古着屋、古着屋、パブ、レコード屋、クラブハウス、古着屋、雑貨屋、パブ、ケバブスタンド、中華料理スタンド、刺青屋、本屋、レコード屋、ミリタリーショップ・・・。道ゆく人たちの服装には、60年代のヒッピームーブメントと、70年代のパンクロックムーブメントから、タイムスリップしてきたかのような雰囲気がありました。町の中心を横切っていく運河の、静かな水。運河に浮かぶ赤や緑のボードと、のんびりと横たわる橋。道路を跨いでいく高架鉄道の線路。「Camden Lock」の大きな文字。フリーマーケットの魅惑的なアーチ。迷路のように入り組んでいる煉瓦造りの倉庫群。アンダーグラウンドで、ディープで、オルタナティブな雰囲気。新しいものと古いものがごた混ぜになっている中で、人々の思想や想いが、脈々たる歴史の匂いと混ざり合って立ち上ってくる不思議な場所。当時22歳で、イギリス生まれのハードロック、ヘヴィーメタル、UKロック、パンク、なんかにハマっていた私にとって、もうそれは完全に夢の国でした。
そんな風にして、何か非合法の変な薬物でも摂取したかのような多幸感に包まれながら、インド人の案内で15分ほど歩いたところで、目的のフラットに着きました。ロンドンによくある二階建タイプのフラットです。彼はドアの鍵を開けて私を中に案内し、共用のキッチン&トイレ、シャワールーム、それから2階にある小さなベッドルームを見せてくれました。「どうする?借りる?」彼がそうきいたので、私は夢見心地でYesと即答しました。
するとインド人は鞄から何枚かの書類を出し、契約書の重要事項っぽいことを説明しながら(ほとんど理解できてません)、私にいくつか質問します。家賃は本当に払えるか?いつからいつまで借りるのか?いまどこに住んでるのか?パスポートは持ってるか?何の目的でロンドンに来たのか?・・・随所随所で躓きながらも、なんとか受け答えして会話は進んでいきますが、とあるトピックで事態が紛糾します。
彼が「家賃は明日でいいが、今日はDepositとして6万円払ってくれ」と言ってきたのです。家賃とは別に、なぜお金を払う必要があるのか、よくわかりませんでした。結論から言うと、「Deposit」は保証金のことなのですが、私はこの単語を理解できなかったので、こいつ、ぼったくろうとしてるな!と構えて、勝手に勘繰り始めました。Depositって何だよ?どうしてお金がいるんだ?家賃を払えばそれでいいだろ?今日お金をもらって、明日来ないつもりだろ?・・・私が疑念をぶつけ始めると、彼もイライラし始めます。彼の辛抱強い説明によると、払った6万円は退去する日に返してやるという話もありましたが、その言い分がまた余計に怪しいんですよね。辞書を持ってこなかったので、調べることもできませんし、膠着状態に陥ります。
しばらく「本当に返してくれる?」「もちろん返す」「本当に明日来る?」「来るよ」「本当?」「本当だ」「じゃあ6万は明日払う」「明日じゃダメだ」というような不毛なやりとりが続きましたが、最終的には諦めて6万円を渡すことにします。仮に6万円がぼったくりだったとしても、部屋を見つけられないまま失意のうちに地下鉄に乗り、ピカデリーサーカスのホテルに戻って、新聞広告を漁りながらもう一晩、この焦燥感と戦うよりは全然マシだったからです。そして、結局、ホテルに帰って辞書でDepositを調べてその意味を理解し(保証金のことかー!)、私の不安は完全に解消されました。そりゃそうだよな。どこの馬の骨ともわからない外国人に部屋を貸すんだから、保証金は欲しいよな。

ホテル滞在はもともと3日間の想定でしたが、そんなこんなで奇跡的に2日目で部屋を決めることができたので、最終日の宿泊はキャンセルして、翌日にはもう荷物を持って、カムデンタウンの部屋に移ることにしました。あの古くて陰鬱なホテルと、ピカデリーサーカスの取り澄ました雰囲気から、一刻も早く逃げ出したかったんですよね・・・。2日目の夜も、コンビニみたいなところで何か(覚えてない)を買ってホテルの部屋で食べて、絶対にお湯がでないシャワーを浴びて、そそくさと寝ただけで、何一つ思い出になるようなことはしていません。部屋が決まった安心感だけはありましたが、私はまだ心を閉ざしてましたね。
@窓から見えた風景(Leybourne St.)
そして滞在3日目(Deposit事件の翌日)、ホテルを永遠にチェックアウトし、スーツケースを引きずりながら地下鉄に乗って、カムデンタウンに行きます。インド人とはフラットの前で待ち合わせたのですが、彼は時間になるとちゃんとやって来ました。私は昨日「Deposit」のことで食ってかかったことを詫びて(彼は笑ってました)、滞在期間分の家賃をトラベラーズチェックでまとめて払い、部屋の鍵を受け取りました。彼は携帯電話の番号を書いた名刺も渡してくれました。"Call me if you want. Have a nice stay" 彼にそんな風なことを言われると、心のどこかで小さな窓が開いて、風が吹いたような気がしました。
インド人が帰った後、私はベッドルームでひとりになりました。5畳ほどの小さな部屋。ベッドと小さなテーブルと椅子を置いたら、あとは小さめのアリクイを一匹飼えるだけのスペースしかありません。2階の窓からは、石畳の道路と、小さな公園の木々を見下ろすことができます。陽の光に照らされた葉っぱ。地面で揺れる葉っぱの影。公園の向こうにある高架鉄道の線路。窓を開けると、すぐ裏にあるハイストリートの雑踏が聞こえて来ます。季節は11月の終わり。冷たい風と、路肩でカサカサと音を立てて踊っている落ち葉。道路脇には「Leybourne St.」と書かれた道路標識が見えます。レイボーン・ストリート。契約書にある住所にも、その名前が書いてありました。・・・そうか、もうすぐ12月になって、それからクリスマスが終わるまで、ずっと、ひとりでこのレイボーン・ストリートで暮らすんだ・・・そう思うと、本当に心から幸せな気分になりました。この記事の最初のほうで、ロンドンに行くことに決めた理由を説明できなかったと書きましたが、この時に初めて、自分が何をしたかったのかを理解しました。カムデンタウンの、レイボーン・ストリートにある、小さなフラットの部屋を自分で借りて、その窓からの風景を見たかったんです。
文章にするとなんだか陳腐な感じもしますが、私が感じたことをストレートに書くとそういう話になります。私たちの人生には、永遠に留まっていたい場面というものがありますが、それがまさにこの瞬間でした。できることなら本当に、ずーっとあの日の午後に、あの部屋から見えた景色の中に、留まり続けたいと今でも思います。そのくらい深い衝撃を感じていましたし、もっと言うと、実はこの時の感覚が、その後の私の人生の軌道を大きく変えることになるんですが・・・それについてはまたいつか!
@記事を振り返って
・・・ということで、この記事はこれで終わろうと思いますが、自分でも想定外の事態になっておりますし、読者の方も薄々気づいてらっしゃると思うのですが・・・
「1ヶ月半の滞在のうち、最初の3日間だけのことしか書いていない!」
そうなんです。書き初めの時は、もちろん滞在中の出来事を一通り書こうと思ってたのですが、最初の3日間の中身が濃すぎて、すべての時間とエネルギーを吸い取られてしまいました。書きたい出来事はもちろん他にもたくさんあるのですが、すでに文字数もかなり積み上がってしまっているため、一旦ここで幕を引かせて頂きます。ただ、消化不良気味であることも事実なので、エネルギーが充填されてきたら、残りの滞在中の出来事を「後編」としてまとめたいという想いはあります!
それにしても、改めて読み返してみると、なんだか全体的に陰鬱なトーンですし、ロンドンらしいことをほとんど書けてないですね(辛うじてカムデンタウンの風景描写くらいか)。観光名所満載のピカデリーサーカスからは、ほぼ何も触れないまま逃げ出して、どうでもよさそうなインド人の不動産屋との会話に何千字も費やして、やっと滞在がスタートというところでばっさり話が終わる・・・。これが果たして滞在記として成立するのか、心配になってきましたが、どうあがいたところで、私には「私にとってのロンドン」を書くことしかできないので、割り切っていきたいと思います。
ではまた!
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
