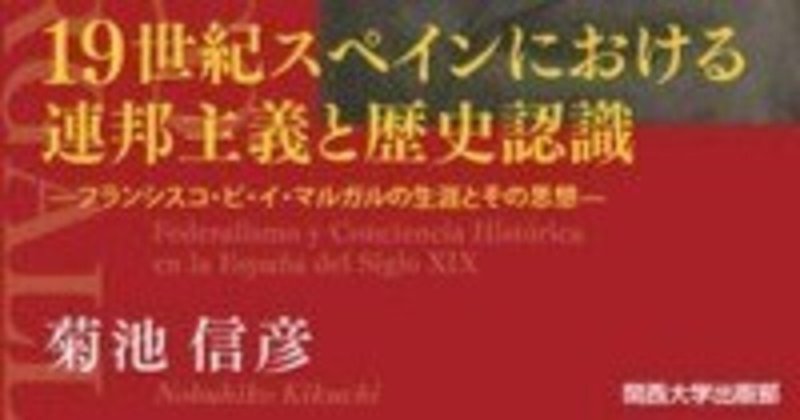
菊池信彦『19世紀スペインにおける連邦主義と歴史認識』

スペインのフランシスコ・ピ・イ・マルガル(1824-1901)という歴史家であり政治家であり思想家でもあった人物のことはこの本で初めて知ったのだが、こんな人がいたのかという驚きが、まずあった。
1877年、『諸国民性』という著作の中で、ピ・イ・マルガルは当時のヨーロッパにおけるナショナリズムを批判して、統一的な国民国家を「大国家」として退けているのだそうだ。大国家とは統一をめざすドイツとかイタリアとかの単位である。これに対して、ピ・イ・マルガルが主張するのが「小国家」のまとまりで、そうした「小国家」が連邦制を取ることを、スペインに最も望ましい政治体制として、主張したという(p.37以下)。
日本にも小日本主義というのはあるが、このような国家構想を描いた思想家は、廃藩置県後の明治時代にはちょっと思いつかない(もしかしたら幕末にはいたかもしれないが)。日本の場合、集権制をどう作るか、そしてその担い手をどう教育してくか、が基本的な議論の前提だと思われるので、このような各地域の多元的なあり方を容認した上で国民統合を目指そうとするスペインでの思想課題の難しさに、なによりも示唆を受けた。
このことは、終章で強調されている「19世紀の国民国家形成期に、近代歴史学が国民史という「装置」を構築し、それによって、国内の歴史的差異を統一的な語りのうちに押し込めた」という考え方があるが、ドイツやイタリアとかではそうだったかもしれないが、スペインではそうとはいえないという著者の史学史相対化の試みとつながっている(p.218)。日本の大学における近代歴史学の参照項が主としてドイツだったからでもあるが、このような視点は大事だと思った。
筆者はまた図書館勤務の時代からデジタルヒューマニティーズの研究を精力的に進めておられたが、その思いは、スペインの一次史料が他国のそれに比べて全然手に入らなかったことによるという。「必ずやこの史料の入手環境の不均衡を是正させねばならぬ」(p.223)という使命感(ここに著者があえて「ルサンチマン」とルビを振っていることに注目したい)が、本書に連なる著者の研究姿勢を支えていたのだということにも強く胸を打たれた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
