
『明るい部屋』共有されない物語
昨年末のイベント『明るい部屋』について考えをまとめておこうと思いながら、ずいぶん時間が経ってしまいました。書こうと試みては上手くいかず、まとまった記事に仕上げられていませんでした。
とはいえ、自分の中で読みの方向性は定まってきており、今回のアンティーカのイベント『見て見ぬふりをすくって』で、読み筋が見当違いでもなさそうだぞと確かめられたような気持ちと、そっちの方かというニアピンをかましたような気持ちとになりまして、なんとか書いていこうと決意した次第です。
さて、早速タイトルの『明るい部屋』についてですが、これはロラン・バルトによる同名の著作から持ってきたタイトルと思われます。イベント中で「明るい部屋」が単語としては出てこないため、テクスト内的にタイトル回収が不可能であることが消極的な根拠となります。また、バルトの著作が写真論でありシャニマスには写真が一つのテーマとして通底しているように思われるために相性は良く、総合的に考えるとバルトの著作が関係してくると考えて良いように思います。同意見の方は多数見かけますし、みなさん各々の理由で関係を認めているのではないかと思います。
しかし、それをどのように読み込めば良いのかは難しく、各人各様の読解が出るところになります。御多分に洩れず本記事も、自分なりに考えていたことを何とかかたちにしようという試みになります。
主題的に扱おうとしているのは、表題の通り「物語の共有不可能性」でして、それがどう写真論に繋がるんだという話についてはバルトの議論の簡単な要約とともに述べていく予定です。その前にまずは、問題意識の説明から行おうと思います。
物語の共有
いま問題にしようとしている物語とは、キャラクターについて語られ得ることのすべて、と言ったら良いでしょうか。例えば、『明るい部屋』で語られたはづきさんの過去や社長の独り言のほかにも、新規カードで何気なく提示される家族構成、あるいは、まだ明かされていない愛依のトラウマの原因となった過去の出来事なども含みます。
それらはサポートコミュのように、その場に居合わせていないにもかかわらず知ることができる性質のものもあります。聞けるはずのない言葉という意味では、心内描写や独白のような本来他人が立ち入れない領域が最たるものですが、我々はプレイヤーという立場ゆえの特殊なアクセス権を持っているわけです。
シャニマスは描写がリアルであると言われることも多く、自分も賛同してはいますが、このように物語へのアクセスについては極めて非現実的な手法に則っています。とはいえ手法としては小説でも極めて一般的に用いられますから、決してシャニマスの特徴とは言えないのですが、シャニマスが敢えてこの点に注目しているとすれば、その視座は特徴的と言ってよいでしょう。
シャニマスの視線は「我々には見えているが実際には共有されていない物語」という見逃しがちだが特殊な事情に焦点を当てているのではないか、それが『明るい部屋』を引用した一つの含意ではないだろうかと考え、今回の話につながります。
共有と一口に言っても誰と誰の共有を話題にするかによって、かなりの広がりがあります。「キャラクター(アイドル, はづきさんなど)─自分(プレイヤー)」「自分─他のP(プレイヤー)」「キャラクター─シャニP」などが挙げられます。
この重層性に注目すると、たとえば「限定で大事な話をするな」といった一時期よく言われた不満について、視座を変えながら多少整理をつけられそうです。「P同士」での会話に差し支えるために限定で良い話をされるともったいないという主張と、「自分による、アイドルに対する」理解に差し支えるからやめてほしいという訴えとでは、物語の共有についてまったく別の主張が繰り広げられています。
個人的に前者については同意しているのですが、こちらを掘り下げたとて得るものはそれほど多くなさそうです。そして今回扱おうとするのは後者、本人(アイドルやはづきさんなど)の物語を我々プレイヤーが知るという意味での共有です。というよりも、バルトの写真論について考えていてそこに接続したと述べた方が正しいかもしれません。
アイドルの理解に差し支えるから限定で大事な話をするな、という主張を真剣にしているひとが実際どれくらいいるのかは微妙で、誰も主張していない主張を相手にしているかもしれないのを恐れているのですが、ひとまず話題にしたいのは、普段ひとを理解するときにそれほど相手の過去は重要性を帯びてこないのではないか、ということです。
そもそも人間を理解するとはどのようなことか。とても一言では言い表せないですが、たとえば「ある場面でどうするだろうかと想像がつく」ような理解が考えられます。その場合、本人がどのような思い出を持っていようが究極的にはどうでもよくなります。しょうもない例を出します。僕が定食屋で迷っているとき、大抵の場合は秋刀魚にしようかどうしようかで悩んでいます。そういう気分じゃないときでも秋刀魚があれば選びたくなる人間なんですね。もし、僕が定食屋のメニューを眺めているときに、秋刀魚にしようか悩んでるでしょと言われたとしたら、心の中を読まれたかのようは気持ちになると思います。言い当てた人はある意味で僕という人間をよく理解していると言えるでしょう。好みを把握しているということで、僕についての理解の話はこれでおしまいとも言えます。
しかし、実は僕には明確に秋刀魚好きになったエピソードがあります。といってもこれも大した話ではなく、ひどい風邪をこじらせ空腹にもかかわらずお粥すら喉を通らなかったとき、目の前で父親がテレビを見ながら(味わいもせずに!)秋刀魚をつついていたのをひどく憎み、復帰後にとくと味わいながら念願の秋刀魚を食べたところ、めちゃくちゃ美味かったという思い出です。(しょうもない例を続けて申し訳ないです。)このエピソードまで含んで僕の秋刀魚好きを知っているとしたら、僕のことをより深く理解していると言えると思います。ですが、エピソードを知っている必要があるとか、それを知らないと何かが差し支えるとまで言われると微妙です。事実、エピソードを知らずとも定食屋での葛藤を言い当てることができるわけですし、なんならその方がよく僕を観察していると言えるかもしれません。夏目はこれこれの過去があるから秋刀魚に心惹かれているに違いないと凝り固まった見方をしていると、最近は秋以外の季節に秋刀魚を食べたがらないことに気づかないかもしれないのですね。また、エピソードに頼るしかその人が何をしそうか予想もつかないのであれば、他の場面では手も足も出ないということになります。僕が定食屋で秋刀魚を食べたくなることはわかっても、中華料理で必ず激辛を選ぶことを当てられないのであれば、僕の食の好みがわかるとは言えないでしょう。僕が何を食べたがっているかについては、毒にも薬にもならないのでどうでもいいのですが、エピソードは人間の理解の補強になるとしても、方法論として必須とは言い難いということが伝われば幸いです。
僕の話だけだと収まりが悪いのでシャニマスの話を出しておくと、愛依のあがり症が好例です。愛依がそうなった原因を知らずとも愛依があがり症についてどのようなスタンスをとるかを知ることは可能で、実際にプロデューサーはどうすべきか一緒に考えています。もし、対策を考えるためだからと何があったのか聞き出そうとするならば、今の愛依への配慮が足らず、かえって無理解をさらすことになるでしょう。
アイドルの過去を知ることは理解に資するけれども、必要不可欠であるとは言い難いと述べてきました。それでも出来事にこだわるならば、対話者というよりも消費者とみなすべき態度であると考えています。
ここ一年くらい、出来事にこだわる消費者を暴き出しているのではないかと思われる描写がシャニマスにあります。ストーリー・ストーリーでの暴力的な物語化はまさしくですが、最近の異様にリアルに再現されるSNS上のオタクなんかも消費者的に感じます。アイドルを理解するのに過去の経緯を知る必要があると主張する人がいるとすれば、それは理解の名のもとに物語を求める消費者なのではないかと思うわけです。
この場合の「理解」とはデータ収集に過ぎないもので、そうした態度の根底には、物語はデータのように蓄積可能で集めれば集めるほど優れている(よく知っている)とする考え方があるのではないかという印象を受けます。
存在するのかしないのかはっきりしない仮想敵への攻撃はこのくらいにしておいて、言いたいのは、人を理解するためには共有されない知られざる物語があることを常に前提にすべきなのではないかということです。
相手の物語には共有不可能な領域があることを前提とする場合、シャニPがしているように相手を人格としてみなすことができ、集積していけるようなデータとして消費をしている限りはSNSのオタク(消費者)と同様であると考えています。
遠回りになってしまいましたが、このような共有されない物語の存在が『明るい部屋』のイベコミュで重要であり、その重要性をバルトの写真論からも引き出してみようと目論んでいます。
『明るい部屋』はづきさん誕生
イベコミュについては内容の振り返りは不要と思いますが、少しだけ。蛾との攻防・シャニPのデート疑惑・ノクチルのバイト・聖歌隊などなど色々な話が織り込まれ、それら乱雑な話に軸を通しているのははづきさんでした。幼少期のクリスマスの苦い思い出が夢に出てきて、はづきさんの心の変化がしっかりと描かれていました。
個人的に『明るい部屋』について最も後を引いたのははづきさんで、考える足掛かりとしたのも「ログインボーナスをスキップできなくなった」という経験です。
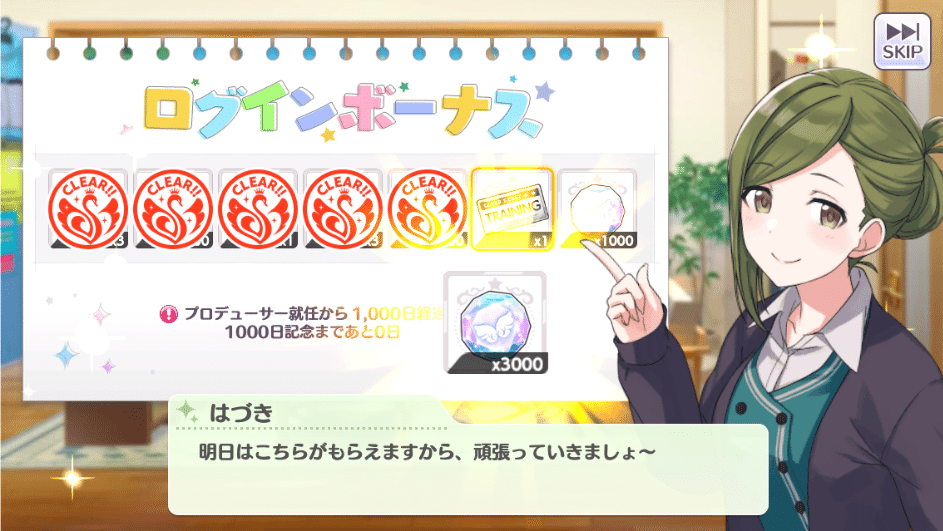
他にもwingの冒頭のはづきさんが床で寝ている場面など、ギャグ要素でしかなかったはずのやりとりに目が潤むようになったり、はづきさんが登場するたびにはづきさんの心情を伺うようになりました。
こういうツイート(↓)がそこそこ伸びたので、はづきさんに思いを寄せるようになったという変化は自然な反応として理解してもらえそうです。
去年の僕「はづきさん、どんな気分でサンタコスしてるんだ(へらへら)」
— 夏目P石 (@quelque_nanika) December 21, 2020
今年の僕「はづきさん、どんな気分でサンタコスしてるんだ......(迫真)」 pic.twitter.com/crJ3huZ1VT
サンタコスについて顕著ですが、はづきさんへの感情移入が真に迫ってくるようになったのは、とりもなおさず、はづきさんの過去を知ったことに原因があります。床で寝ているはづきさんを見て胸に込み上げてくるものがあるのは、はづきさんの日々の心労を知ったからです。
それまでも『薄桃色』の千雪さんと飲んでいるシーンなどで、単なるチュートリアルの人には収まらないキャラクター性を発揮していましたが、イベコミュを経て感情移入してしまうレベルにまで際立ってきました。人格として立ち上がってくるこの感じは、過去を知ったことに一番の原因があるでしょう。
過去を知ることと理解度を結びつけることに対して先ほどまで執拗に警戒感を示していましたが、ここに矛盾はありません。というのは、今とりあげている経験は理解を深めるという話をする以前の、感情を備え固有の来歴を持つ一人の人間だと気付かされた経験だからです。実際、個人的には過去を知ったこと以上に「はづきさんのことを何も知らなかった」という事実の方が強烈であり、未知の領域がたくさんあるという認定が七草はづきというキャラクターに深い奥行きを与えた感触でいます。
はづきさんが経験してきた苦労についての知識が「こういうことをはづきさんは考えているに違いない」と共感を助けたのではなく、はづきさんについて無知であったことの衝撃のために「はづきさんは一体なにを考えているんだろう」という問いのかたちでの共感を(達成不可能にもかかわらず)試みてしまうようになった、という感じでしょうか。
知らなかったことを突きつけられるとは、共有されない物語が存在していたという事実の突きつけであり、相手に未知の領域があると認めることが人物像に奥行きを与えるのではないか、と考えました。
そして、この点においてバルトの『明るい部屋』と接続します。
温室の写真
バルトの『明るい部屋』は写真論で、写真に写されているのは「かつてあったもの」であると結論づけるに至る議論を展開します。
「写真」が私におよぼす効果は、(時間や距離によって)消滅したものを復元することではなく、私が現に見ているものが確実に存在したということを保証してくれる点にある。(p.102)
当たり前といえば当たり前なのですが、事実としてそれがかつてあったのだと示されることで生じる効果は面白いものです。
勝手に持ち出す例で恐縮ですが、なにかの災害直後にライオンが街中を歩く画像が拡散されたとき、それが今回の災害の画像ではないことに気づかなかったり、気づくのが遅れたりしたことは、写真の持つ「事実として認めさせる力」を示しているのではないかと理解しています。
さて、この著作の厄介さの一つは、前半の最後に「私はこれまで述べてきたことを取り消さなければならなかった」と締めくくる点にあります。つまり、前半のどこまでを採用して良いかという問題が発生するわけです。後半は「温室の写真」という圧倒的な実在感をもった写真を見つけ、この写真やそれを見たバルト自身の分析が土台となっています。本記事では、問題関心の都合と前半の扱いづらさを回避するために、温室の写真をめぐる考察にスポットライトを当ててみます。
さてこの温室の写真が何かというと、バルトが母の遺品整理をしていたときに出会ったもので、自分が生まれる前に撮られた母の写真です。
この写真がどう特別であるかについて、バルトは言葉を尽くしています。
写真が、思い出と同じくらい確実な感情を私の心に呼びさました。(p.84)
私はついに、母のあるがままの姿を見出したのである…… (p.86)
それを見るなり、私はとっさにこう叫んだ。《これこそ母だ! 確かに母だ! ついに母を見つけた!》と。(p.123)
強調されるのは「あるがまま」であるということです。ほかのありきたりな母の写真では、母と似ているとか似ていないとかいった次元で、そこに写っているのが母であると述べます。似ているというのは「私が彼らに期待するものと写真が一致している」(p.126)ことですから、自分の中の母のイメージが先にあって、それと写真とを照らし合わせて母を母と認定しているわけです。自分のイメージが先行しているならば、写真には私にそれを母と認めさせるような母の本質が写っているのではないということになります。写真の母は「あるがまま」の母ではないということになります。
それゆえに「あるがまま」の母を感じさせる温室の写真には感動があるわけです。この写真は母に似ていないとすら言われます。どういうことか。またしても自分の理解した範囲で例を出してみます。
街中で知らない人に声をかけられたとします。話すうちに相手はどうやら自分の古い知り合いらしいとわかり、ついにかつての同級生の園田だと判明したとき、古い記憶やそこから連想される現在の姿などの、自分のイメージとは全く似ていない目の前の相手が、ありありとした実在感でもって自分のイメージの更新を迫ることになります。自分の記憶の中の園田と君とは似ても似つかないから、君は園田ではないよ、と言うことは許されない実在感が目の前の園田にはあるわけです。実在の人物と対面すると、自分の理解を改めざるを得ない局面が発生しますが、温室の写真はこのような実在ならではの力を、写真にもかかわらず有しているということなのだと理解しています。
写真なら普通は反対に「(目の前にいる)君の面影があるね」とは言うことになり、現実の模倣として実在性は劣ると考えられるでしょう。
すると当然、温室の写真が例外的に母そのものを写しているのはなぜかという疑問が生じます。バルトは「雰囲気」に答えを求めます。要素によって分解されず、不確かで、雰囲気としか言いようのないものをバルトは主張します。
雰囲気は、自負しないかぎりでの主体を表す。あの真実の写真にあっては、私の愛する母、私が愛してきた母は、自分自身から分け隔てられることなく、ついに自分と一致したのだ(p.134)
ほかの母の写真では、類似点や相違点から似ていると判断することでそれが母だと認定していました。雰囲気による把握はそれとはまったく異なるものであると言われます。ポイントは要素に分けることができないという点です。目の形で判断してるかというと、目元を隠してもその人とわかったりもして、髪型が変わっても気付けるから人の顔をパーツの集積として認識していると考えるのは不適切なのではないか、という提言です。
バルトの場合「母の実体をとらえそこなっている」「母のすべてをとらえてはいない」という感想が出てくるのは、母らしさみたいなものを捉えてもいないし、母の本質を汲み取れていない実感なのではないかと考えています。
しかし、雰囲気についてはあとは家族がなんとなく似ていることと重ねるくらいで、バルトの分析はいかにも尻切れ気味です。
共有されない歴史
ここから自分の解釈に突入します。写真が単に要素の集合にしか見えないのであれば、温室の写真のような実在感が立ち上がってくることはありません。雰囲気を宿した写真は単なる像とするわけにはいかない実在感をもって立ち上がってくるのですが、この立ち上がりとは、まさしく『明るい部屋』を経て我々がはづきさんに対して経験したことです。
(という風に、温室の写真と我々の経験を重ねてしまっていいのかという懸念はあり、言ってしまうと僕の議論の弱いところです。しかし、そもそもバルトの経験がいったいどのようなものなのか正直わからず、自分の経験に落としこもうとすると、こうなってしまうかなぁというところです。写真論として一般的に語りうる種類の経験であると考えられますし、二次元の画像が圧倒的なリアリティをもって現前するという一致にすがって話を進めていきます。)
はづきさんの画像について言えば、イベントコミュ前後でなんら変わりありません。付け加わったのははづきさんの心内描写や過去についての話です。それが人物像を人格として立ち上げる効果をもたらしたのではないか、という手応えがあります。くどいですが、理解を深めたかどうかとはまったく別次元の話で、人間を人間として認められるようになったという話です。
さて、我々の経験と重ねて良いのであれば、人格として「立ち上がってくる」ことの説明として雰囲気では役不足に感じます。そもそもバルトの議論でも、温室の写真の特殊さについて、雰囲気という言葉を投げっぱなしにしており、分析不十分な感がありました。雰囲気以外に「温室の写真」を特殊なものたらしめる重要な要素があると考えるのは妥当です。
ここでバルトの議論に戻り、バルト自身がそれほど深めていない「歴史」に注目してみたいと思います。
バルト自身は歴史をネガティブに捉えています。というのは、自分が生まれていなかった頃の写真を見ると、なじみのない服飾の方に注意が行ってしまい、人物が歴史のなかに埋もれてしまうからです。とはいえ、肝心の温室の写真もまた幼少期の母の写真ですから、注意が逸れることによって歴史を否定的に捉えるのは見落としがあるように思います。
バルトは数多くのありきたりの写真を見てようやく温室の写真にたどり着きました。このことは意外と大事なのではないかと推測しています。つまり、ありきたりな写真にノイズとして写り込んでいる未知の情報は自分の中の母のイメージとの差異を露わにしますが、母についての莫大な量の知らない情報にさらされることで、要素には還元されない同一性の根拠である雰囲気に辿りつけたのではないかと。
こうした筋立ては憶測の域を出ないのですが、バルトが歴史についてどのように述べているかを確認しておきましょう。
「歴史」とは、単にわれわれがまだ生まれていなかった時代のことではないであろうか? (p.76)
「歴史」とは、ヒステリーのようなものである。誰かに見られていなければ、成り立たない──そしてそれを見るためには、その外に出ていなければならない。 (p.78)
歴史のなかの自分の生まれていなかった時代に注目していますが、図らずもバルトが述べているように、自分の知らない歴史を見るためには外に出る必要があります。外に出るとは、自分の持つ情報の内部で理解するのではなく、相手を未知のものと認め、相手が生きてきた物語から離脱してしまう経験だと捉えています。
歴史についての考察の直後に、バルトが「私は母を本当に再認・認識しているのか?」と自問しています。これは、写真の人物が母とわかるのは自分の持つイメージとの照合させているからだとしたら、自分の概念体系から逸脱してる幼少期の母をどうやって母と認められるのか、という問いであるように思います。
(本文のここの箇所のつながりが論理的には繋がらないような印象を受けたのですが、こういった解釈を持ち込めば筋が通りやすそうです。通りの良さが自分の読解を補強してくれないかなと期待しています。)
さて、このように歴史という未知の情報に晒されて母を自分の理解の外側に追いやったことが、結果として温室の写真を見つける準備が整えたと考えることはできないでしょうか。つまり、情報として母を母たらしめる本質を掴むつもりが無くなって、未知の領域を多く含んだものとして認めることで、かえってありのままの母を受け入れる用意ができたと言えそうであるということです。
ここで、温室の部屋が母を知らないバルト以外にはただの写真になってしまうと言って公開していないのを指摘しておきます。これはつまり、写真を見る側になんらかの資格が想定されていることを意味します。その資格というのは、被写体と見る側との関係にまつわるものであることは間違いなく、良く知っているからこそ際立ってくる未知の領域が必要とされている、という見方と整合性はとれています。
先に出した久しぶりに会った同級生の例のように、目の前の人物は自分の理解を更新を強いてきます。ありのままの母もまた生きた人間ですから、こちらの理解に従うのではなく、むしろこちらの理解の更新を強いるはずで、だからこそ「これが母だ」としか言えず要素に分析できない全体的な雰囲気によってしか母を指摘できなかった、というのがバルトの「温室の写真」についての自分なりの補足です。
はづきさんについての我々の経験もまた、はづきさんについての知らない情報にさらされたことに、きっかけがあります。はづきさんのことを本当は知らないのではないかという懸念を抱き、はづきさんがどのような人物なのかと問えるようになったと考えると、バルトが温室の写真を発見した経緯とちょうどパラレルになります。
ここで重要なのは、過去の話についての情報の中身ではなく、未知の領域があるという認知です。冒頭で述べたように、情報を知らないからその人のことを理解できないと述べるのは、むしろ人間を知りうる対象とみなしており、その人と向き合っていないということになります。
本人を前に「こいつってこういう奴だから」と第三者に紹介するのは、分かってないことが分かってないのだなという印象を与えると思います。目の前の相手には知らない側面が、それも大量にあると前提することは、相手を人間として認める条件でしょう。
追記:なぜ『明るい部屋』なのか
結局なんで『明るい部屋』というタイトルなのか、についてあんまり考えを示せておりませんでした。
初投稿の時点ですっかり書き忘れていたので、本論の終わりでまとめを挿入しつつ回答を与えることにします。
冒頭からくどくど述べてきた問題意識の通り、SNSや番組製作者の都合で作られた物語というのは、アイドルたちを理解しようとしていない人間たちの描写ではないかと考えています。悲しくもメディア露出にはそういったリスクがあります。勝手に解釈されてしまうということですが、それは写真にそもそも潜んでいる構造でもあります。
写真を撮られたら最後、自分の意思を離れて思い思いに解釈されてしまって、自分は解釈の場に居合わせることができなくなります。
兄弟と歩いているところを写真に収められて「デートか?」などと見出しをつけられてしまえば、噂が一人歩きしてしまいますし、きっぱり否定したとしても「いやでも本当は...」などと再解釈されてしまいます。弁明の余地なく解釈可能な材料を提供してしまう点では、『ストーリー・ストーリー』の物語化も同様です。カメラを通して提示されたものは、バルトの言葉を借りれば「かつてあったもの」として現れ、事実として受け入れさせる力があるために、一層やっかいになります。
カメラに映る仕事をする限り、仕方のないことなのだから我慢しろ、と言うわけにはいきません。いわゆる有名税などもそうなんですが、有名になる代償として変な奴に絡まれるくらい受け入れろと言うことは、ちゃんちゃらおかしいですよね。どう考えても悪いのは絡んでくる方、勝手に分かったつもりになる方です。
(そう言えば、『The Straylight』のキンキラ動画配信者が変な奴立ち位置ですね)
そういうわけで本記事では、勝手に解釈していることを自覚しなくてはならず、相手について知らないことがたくさんあると認める必要があるだろうと、我々見る側の資格を問い直してみました。
SNS上のオタクについてしばしば言及したのも、我々に対する警告として受け取ったからでした。
しかし、そうした批判的精神で終わるのではなく、もっとポジティブな要素があったのではないか、とも考えています。
撮影された写真は、たしかに自分の手の届かないところで勝手に解釈されてしまいますが、もし撮られた写真に本人の雰囲気が、あるいは魂が宿るのならばどうでしょう。なおも見る側の人間に主導権はあるけれども、解釈可能性に甘えずにアイドル自身を見つけ出してくれる可能性が残るんじゃないか。彼女はたしかに商品でもあるけれど、消費される以外の可能性も残るんじゃないか。
写真の実在性を訴える『明るい部屋』をタイトルに持ってきたのは、そういう期待が込められていたのではないかなと考えてます。
見て見ぬふりをすくって
本記事では、バルトの写真論から相手についての共有されない物語があることを認めることが人物を人格として立ち上げるのではないか、ということを考えてみました。ここからはおまけです。
僕は以上の話を、我々がアイドルをどう見るかという側面から考えていました。未知の領域を認めて人格として扱うのであればシャニP寄りであるし、情報の蓄積にこだわるのであればSNSのオタク寄りであろうといった話はここから出てきます。
我々が問いかけられているのではないか、という発想は以前に行った【ハウ・アー・UFO】の考察に一番の根拠を置いていて、こちらもまたカメラが重要ですから、写真論から派生した今回の議論とそれなりに響きあうものだろうと考えていました。
ところが今回のアンティーカイベントで、なるほどと思わされました。咲耶が「みんなのことを知らないのではないか」と少し悩む話でしたが、これは盲点で「我々→アイドル」ではなく「アイドル→アイドル」で上記の問題が取り扱われています。
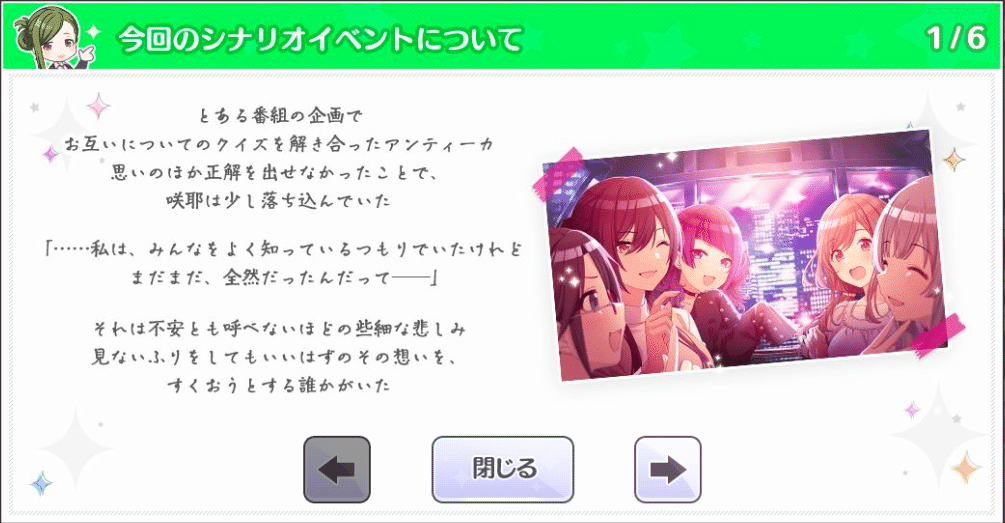
咲耶はみんなのことを知らなかったと、しょげてしまいます。本記事ではデータ収集にこだわるのは消費者的態度だと先に批判していましたが、無知を恥じたからと言って、咲耶がその消費者的だとは考えてはなりません。咲耶の落ち込みの原因は「みんなと真摯に向き合っているなら、みんなについて詳しく知っているはずだ」という思い込みに見るべきでしょう。この前提に立てば、ちょうど対偶の「みんなについて詳しくないならば、みんなと真摯に向き合っていない」ということになりますから、いかにも咲耶の気持ちを折りそうな結論に至ります。
ですが、前節までで見てきたように、相手に未知の領域を認めるのが相手を人間として迎え入れる条件でした。
咲耶は君のことを聞かせてよという態度で人に寄り添いますから、ここは当然クリアしているのですね。ことさら確認するまでもなく、咲耶はみんなと真摯に向き合っているのですが、咲耶だけが落ち込んでいる。それはなぜかというと前提が間違っているからです。
要するに「みんなと真摯に向き合っているなら、みんなについて詳しく知っているはずだ」ではなく、「みんなと真摯に向き合っているなら、みんなについてもっと詳しく知ろうとするはずだ」などに考えを改めるべきということになります。
イベントのシナリオでもアンティーカの仲の良さが試されるゲームとしてではなく、この機会を楽しむようにと切り替えていました。
なお、『ストーリー・ストーリー』はアンティーカと真摯に向き合ってくれない番組スタッフたちが勝手に彼女らの物語を作ってしまう話でした。
あの時もSNSではアンティーカについて物知り顔で語るオタクたちがいて、番組は彼らのデータ消費を煽るように設計されていました。
あそこにあった不正義は人間を理解可能なものとして扱う態度として読み取れ、今回のイベントとちょうど裏返しになっているように思います。
個人的に『明るい部屋』は去年一年間の総括のようなポジションかなと思っていたのですが、『くもりガラスの銀曜日』からの周へとバトンをつなぐ役割もあったのかなと考え始めています。
共有されない物語があるということの意味が『明るい部屋』から読み取れそうだぞと、ここまで頑張って述べてきたのですが、それをどう練り上げていくかと言われると僕には難しかったです。その点、『見て見ぬふりをすくって』では、真摯に向き合うほどに理解不可能だと分かってしまうのは決して悲しいことじゃなくて、果てなく深めていく余地があることなんだよ、素敵なことなんだよと、良さを上手く描ききった優しい話でした。
追記2:プラニスフィア
『明るい部屋』のタイトル回収について説明したなかで簡単に触れた「見つけてくれる可能性」というのが、実は新たなテーマではないかなと密かに感じています。
このことは「プラニスフィア」に感動したあまりに書いた記事で少し話しているのですが、余談ついでに改めて語り直してみます。
本記事では、番組によって変形されて一意な読み方を強いる物語を一貫して批判していました。それはデータ収集にこだわる消費者を前提とし、アイドルたちを犠牲にして成り立つものだからです。
『見て見ぬふりをすくって』で示されたのは、消費者的ではなく人格として向かい合うことの尊さという、正反対のことであったように思います。つまり、物語と言っても、私と見つけてくれたあなたとで紡ぐ物語であれば一転、尊いものにならないだろうかということです。
『ストーリー・ストーリー』での「生きてることは物語じゃないから」という霧子の発言から、いかなる物語も否定していると考えるのはやりすぎで、実際にところどころ物語を肯定するセリフや歌詞があります。肯定される物語は人格として認めるものどうしの物語ではないだろうかと考えているわけです。
「プラニスフィア」だとこういう感じに書かれます。
満天のスクリーン映ってる
物語はいくつあってもいいんだ
これは星(アイドル)どうしの物語とも、星と見ている人との物語とも受け取る余地があってとても広い含意のある歌詞です。
本記事で焦点を当てたのは「アイドルと我々(ないしファン)」とのあいだの関わりで、適切な物語を紡ぐために我々に求められるのはアイドルについての未知の領域を認めるということでした。
では、アイドルの方に求められる資格は何か。
それはもう自分の色で精一杯輝くことに尽きるのではないでしょうか。自分の輝きがあなたという一人の人間に届くかどうかは運に任せるほかはなく、ほとんど祈りのようなものになるのだと思います。もし、星空の無数の星たちのなかから一つの星を見つけ出せたのだとしたら、それは奇跡的なことで、そこで紡がれる物語は尊いものになり得るのではないでしょうか。
そうだよ、数えても数えきれない
ほどの煌めきのなか
出会えたっていう奇跡を
ジブンだけの色にしよう
キラリ光れ!その瞳に映るように
見つけて欲しい わたしたちのStella
人格としてアイドルを認める用意のある人のもとに自分の色で輝く星(アイドル)の光が届く、そういった可能性に賭ける「見つけて欲しい」という祈りは、番組製作者を筆頭とする消費者的動向への抵抗となるのではないでしょうか。
『明るい部屋』は終盤で部屋を介した「つながり」に注目しています。一方的な解釈の暴力性への対抗措置として、つながりを取り上げているのかもしれません。いまやそういう含みも読み取りたくなっているのですが、シャニマスに対する見方を一つ提案できたことにしてこの記事は終わりにしておきます。
※記事のなかで引用した『明るい部屋』の文章はすべて、花輪光訳(みすず書房)を使用しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
