
「ミニマリスト」に感じてしまう“気持ち悪さ”の正体
いくら新鮮であろうと、一定の浸透をみた後で理論が魅力を失うことは、古来繰り返されてきた。それだけに、俺は常にブームなるものに、どちらかというと冷ややかな目線を向けている。爆発的なミニマリストブームが起こったときも、自分には関係のないことだと思っていたし(近藤麻理恵の二番煎じに思っていたし)、ブームが落ち着き、メディアで「ミニマリスト」という文字を目にする機会が減った頃には、「さもありなん」と感じていた。
ミニマリズムは一時のブームにすぎず、ブームに踊らされたミニマリストはいなくなった。そんな風に思っていたのだ。
この記事は「東京西側放送局」という音声配信番組の放送後期として書いたものです。配信は以下のリンクから聞けます。よろしければぜひ。
ミニマリストの現在
しかし、上の配信を収録し終えたタイミングで調べてみると……「ミニマリスト」は今も実在することがわかった。
“カリスマミニマリスト”として知られる佐々木典士さんは、いまもミニマリストとして積極的に情報を発信し続けているのだ。
「物を極力減らすこと」に主眼がおかれていた当初から、「本当に“自分にとって”必要なものを選ぶこと」へと、スタイルそのものはシフトしているように感じるが、ミニマリストとして息の長い活動を続けられている。Twitterのフォロワー数も12000人と多い。多くの人から人気を集めていることはゆるぎない事実だ。
これには正直驚かされた。ミニマリストは、流行ではなく、ひとつの定番として一定の層に定着したのだ。新たな生活スタイルの萌芽に付いていけてなかったのは俺の方だったのだ。
ただ、いまだに、ミニマリストという言葉に「むずがゆさ」「生理的拒否感」みたいな何かを感じてしまう気持ちも、正直ある。いったいどうしてなのだろうか。
ミニマリストが切り捨てた価値観を称揚する思想戦争的方向(*)ではなく、ミニマリストの抱える矛盾みたいなものに迫りながら、明らかにしていきたい。
* 実際にミニマリズムに反対する意見として、「無駄を愛することの意義」みたいな価値観をぶつけるというコンテンツが数多くある。多様な価値観を紹介する場合を除いて、つまり、反対意見としては、有効なものでないように思う。
そもそも、ミニマリストとはいったいどんな人を指すのだろう。改めて整理すると、
持ち物をできるだけ減らし、必要最小限の物だけで暮らす人。自分にとって本当に必要な物だけを持つことでかえって豊かに生きられるという考え方で、大量生産・大量消費の現代社会において、新しく生まれたライフスタイルである。「最小限の」という意味のミニマル(minimal)から派生した造語。(知恵蔵から引用)
とある。
異様な「広報」ビジュアル
少ない物で豊かに暮らすという考え方自体は以前からあった(環境問題の深刻化などを背景に巻き起こった断捨離ブーム)。では、なぜミニマリストは新たなムーブメントとして、もてはやされたのだろう。それはひとえにビジュアルの強さがあるだろう。
部屋には一つの机、いや、収納ボックスを机としたものがあるのみ。布団すら持たず、カーテンもない。そんな強力なビジュアルをもってして、ミニマリストの生活が多くの人に「拡散」された。NHKでの特集についての感想をまとめた「togetter」を見てみると、ビジュアルについてのリアクションが多く記録されていることがわかる。
ある種の珍妙さをもって、ミニマリストが認知を広げたことは確かだ。実際にNHKの特集放送後、ミニマリストの検索数は急増している。リーチが高まるとエンゲージメントも高まるのが世の摂理なので、自分もミニマリストを実践したいと思った人も多くいただろう。

しかし、ミニマリストの生活を知るためにはミニマリストの本を購入しなければならない(もしくはミニマリストについての情報にアクセスしなければならない)というミニマリスト的な価値観に反した行動(*)が求められるという矛盾がある。
*きっとミニマリストからは「これは本当に必要なものだから」の一語を返されるだろうが、本当に必要なのかどうかは本を読むなり、情報を得なければわからない。
レトリックに依りすぎた指摘ではあるが、どこか宗教やマルチ商法の集金システムに近い何かを感じてしまう。配信で語られた大丘の言葉を借りれば「経典」としての「書籍」とでもいえるだろうか。大まかになるべく物を買わないことが志向されているのに、教えを見聞きするためには物が必要なのだ。
特権階級に許された生活スタイル
また、配信の中で鹿間が発言した「所有しうる前提がなければ、所有しないという選択はできない」という指摘も、俺がミニマリストに抱く気持ち悪さを説明するうえで外せない。
ミニマリストは決して貧乏ではないし、清貧を志向してるわけではない(なんとなく似てるけど)。無理に物を追い求めることはせず、本当に必要な物のみを揃えているだけだ。しかし、ここにこそ、ミニマリストの持つ特権性が見え隠れする。
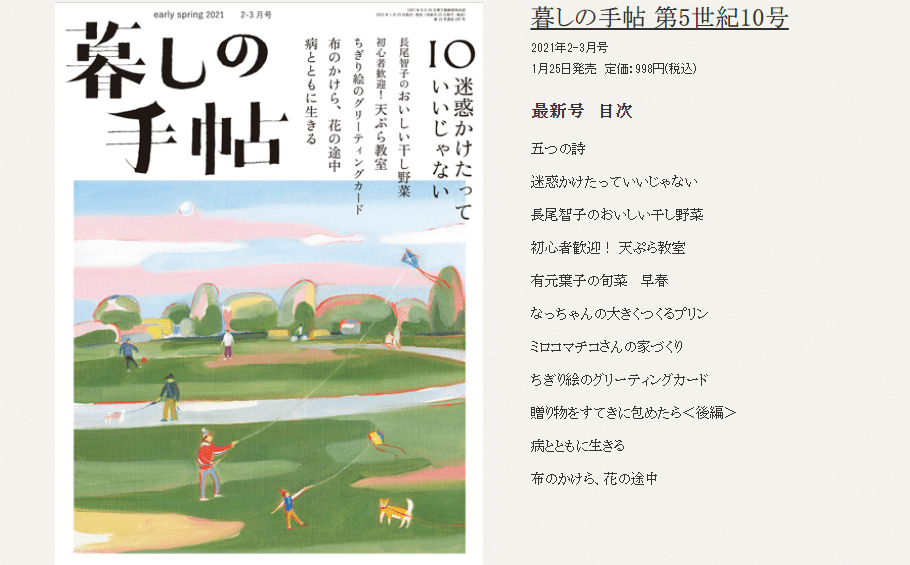
阿古真理氏の著書『母と娘はなぜ対立するのか』によると、「ていねいな家事」がうまれるきっかけになったのは、高度経済成長期に生活インフラが整備され、家事が格段にラクになり、時間に余裕ができたからこそとある。余裕が生まれたことが、新たな生活スタイルの創造・選択につながるというわけだ。「ミニマリスト」も余裕があるから、選択できる生活スタイルなのだ。その余裕は金銭的であったり、時間的であったり、さまざまな形の「余裕」。
個人を攻撃する意図はないが、佐々木典士さんがクリエイティブディレクターの沼畑直樹さんと運営するホームページのキャッチフレーズは「Less is the future」とある。金銭的・時間的余裕がない(貧乏)人からは決して出てこない発想だろう。
生活スタイルと自己規定
もちろん個人の生活スタイルのあり方として、ミニマリストを実践することは否定しない。するつもりもない。しかし、上に記したような矛盾があるという思いもある。そこに、自分自身が感じている生理的嫌悪感の由来があるように思う。

「ミニマリストはこういう生活をするのだ」という自己規定的な生活スタイルの選択で人は幸福を得られるのだろうか。ある人にとってはそれが有用なのかもしれない。しかし、俺は画一化された“スタイル”にならう生活(ミニマリストの愛用品を紹介するコンテンツがインターネット上に多数存在する)が、果たして本当に豊かなものなのか、と疑問を持たずにはいられないのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
