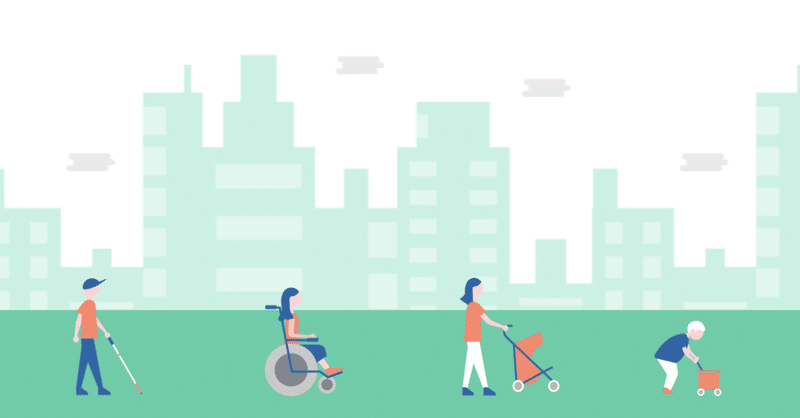
誰もが使えるナビに何が必要か考えてみた
この記事は、NAVITIME JAPAN Advent Calendar 2020の 19日目の記事です。
こんにちは、ジャムにいさんです。ナビタイムジャパンでアプリ用地図フレームワークの研究開発を担当しています。
突然ですが質問です。アクセシビリティという言葉ご存知でしょうか?恥ずかしながら私は2年前までは、パソコンにそう言った項目があるけど何かはよくわからない、といった程度の認識でした。ただ、実はこのアクセシビリティは「誰もが使える」を実現しようとしたときに非常に重要な役割を担っていることがわかりました。この記事ではナビゲーションにおけるアクセシビリティやアプリケーションにおけるアクセシビリティについてお話します。
アクセシビリティとは
アクセシビリティ(Accessibility)とは、利用しやすさ、近づきやすさ、などの意味を持った英単語です。そこから転じて、ハンディキャップなどにかかわらず全ての人がサービス・情報を手にすることができる状態やその度合いを表した用語としても知られています。
さまざまな情報をウェブやアプリから入手している現代では、アクセシビリティの観点がないと容易にハンディキャップが原因で情報格差が発生してしまいます。
例えば、文字の色に意味を持たせた場合にもそれは起こります。ホテルの予約画面で空き・予約済みの状況がそれぞれ緑色・赤色などの色でのみ表現しているサイトがあったとします。この場合、色を認識できない/間違えやすい方は空き状況を正確に把握することができません。
他にも限られた人にしか情報が正しく伝わらないケースはたくさん存在します。ここで、改めてナビタイムジャパンの本分であるナビゲーションについても考えてみようと思います。
ナビゲーションでのアクセシビリティってなんだろう
ナビゲーションとは、より目的地に辿り着きやすくするための案内を指します。アクセシビリティの本来の「アクセスのしやすさ」という意味を考えるとナビゲーションにおいてもアクセシビリティは非常に重要な要素だとわかります。ウェブやアプリのアクセシビリティとは内容が異なるため、ここで、いくつかのシーンを例にどういった対応があると良いか考えてみます。
階段を使うのが困難な場合
⚫︎ 車イスを利用されている
⚫︎ ベビーカーを押していたり
⚫︎ 怪我をしている
このように様々な理由で階段の利用が難しい方々がいます。そういったときエレベーターやエスカレーターを優先して案内できれば目的地への辿り着きやすさは向上します。実際に「NAVITIME」ではエレベーター/エスカレーターを優先した経路検索機能を提供しており、移動しやすい道案内につなげています。
坂道をなるべく避けたいシーン
階段と同様に坂道は移動を困難にする要因の一つです。様々な事情によって坂道を嫌う方は多いと思います。例えば車イスを利用される方。坂道を登る場合も降る場合もした方向に転がっていってしまう危険があります。そういった場合、坂道を避けた経路は目的地への行きやすさを向上させます。
音響式信号機をなるべく利用したい場合
音響式信号機とは、視覚障害者の方が事故に遭わないように信号が青の間「カッコー、カッコー」などの誘導音を出している信号機のこと。誘導音があると、信号が青かがわかりやすいだけでなく、渡るべき方向もわかりやすくなります。そのため、音響式信号機を優先した経路案内が実現すると目的地までの移動がよりわかりやすくなります。
まだまだ色々なシーンが考えられそうですが、一貫しているのは身体属性や状況によって移動の難易度が上がる場合に、原因となる状況を避ける道案内ができればアクセシビリティが向上することです。
ナビタイムジャパンでの取り組み事例
ナビタイムジャパンではこれまでに様々な形でアクセシビリティ向上に努めてきました。その中で自分が直接携わった「パーソナルナビゲーション」について紹介させていただきます。
「パーソナルナビゲーション」は、ナビタイムジャパンの提供する複数交通機関を組み合わせた経路検索サービス『NAVITIME』をベースに、視覚障がい者、車いす使用者、ベビーカー使用者、高齢者といった交通制約者の特徴に応じて最適かつ安全な案内を目的としたナビゲーションサービスです。
※ ただし、こちらのサービスは実証実験の成果物として一時的に公開したものであり、現在はご利用いただけません。
実際のアプリの画面は以下のようになっております。

このサービスでは、身体属性に合わせ経路検索の際に優先する条件や音声ナビ中に発話する内容を切り替えています。これらを実現するための情報には、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の4ヵ年に渡る研究成果を利用しています。
この研究では、交通制約者の方々に協力してもらい、段差・傾斜などのバリア情報や、音響信号・視覚障がい者誘導用ブロックなどのバリアフリー情報を収集しています。これらの情報をもとにパーソナルナビゲーションでは身体属性に合わせた経路案内を実現しています。特に各種優先条件が検索結果に反映されるよう検索エンジンのチューニングなど複雑な調整も実施しています。
実験を通してわかった難しさ
実証実験を通して、身体属性に合わせた経路案内が役に立つことがわかりました。しかし、同時にバリア情報やバリアフリー情報の収集や経路案内のチューニングの難しさもわかりました。バリア情報やバリアフリー情報は膨大で、現在も更新され続けています。正確な情報を網羅的に整備することは一朝一夕では実現できません。加えて、情報を整備するだけでは足りず、それを活用し必要な人に必要なだけの情報を提供することが求められます。
下手をしたら事故につながること
実際に協力くださった方々とともにサービスを利用・評価してみて、誤った情報を提供することがユーザーを危険に晒しすことを認識しました。例えば音響式信号機の案内です。アプリが認識している位置情報と進行方向が、実際と異なっているのに、誤った状態のまま音響式信号機の案内をしてしまうと、車道を横切らせてしまう事態を招く恐れがあります。
アプリの使い勝手も重要だったこと
私はこの取り組みにiOSアプリの開発者として参加しました。アプリのアクセシビリティ向上はこの実証実験で私が注力したことのひとつでした。なので、アプリのアクセシビリティについても掘り下げてみようと思います。
アプリのアクセシビリティ
モバイルOSにはスクリーンリーダー機能が標準搭載されており、全盲の方々はそれを使ってスマホを使用しています。
スクリーンリーダーとは
スクリーンリーダーは、画面に表示されている情報を読み上げる機能のことで、AndroidであればTalkBack、iOSであればVoiceOverという名前で機能提供されています。ここで画面に表示されると記載しましたが、以下のような情報をメインに読み上げが可能になっています。
⚫︎ テキスト
⚫︎ 画像のタイトル
⚫︎ ボタンの名称
⚫︎ ボタンなどに設定された操作のヒント
上記以外にもアプリ側で各種View(アプリの構成要素)に設定したテキストやヒントを読み上げることが可能です。
私はパーソナルナビゲーションを利用した実証実験で初めて全盲のかた(以降Yさん)がスマホを利用している姿をみました。自分が想像していたよりも何倍も高速に読み上げ音声を駆使しアプリを操作されていました。この実証実験で実際に以下をはじめとしたさまざまなフィードバックをいただきました。
⚫︎ アプリのここの発話内容がわかりにくい
⚫︎ このテキストの読み上げ順序を変更して欲しい
これらをもとにアプリの改善を行いました。私にとってこの改善作業は目から鱗の連続でした。
たった一行のこの設定で全盲ユーザーの使い勝手が格段に向上するのか…
これがこのスクリーンリーダーの改善を通して素直に私が感じたことです。
Yさんに教えていただいたことですが、世にあるアプリの多くはスクリーンリーダー対応がされておらず、いざアプリをダウンロードしてもどのような操作をすればサービスを利用できるかわからない場合が多々あるそうです。ボタンやアイコンなどにたった一行テキストを入れることで、何ができるかわかるようになるのです。意外とアクセシビリティの対応はこういった小さなことの積み重ねなのだとこのとき理解しました。
これがきっかけで、アクセシビリティというものに興味を持ち、少しでも改善していきたいと思うようになりました。だからこそ、アクセシビリティ対応を継続していきたいと今でも強く思っているのだと思います。
ここでは、スクリーンリーダーに焦点をあてましたが、アプリのアクセシビリティはスクリーンリーダー対応のみではなく、その方法は多岐に渡ります。Appleのアクセシビリティに関するサイトが非常にわかりやすいのでぜひそちらも確認してみてください。
実際に全盲ユーザーにヒアリングしてみた
せっかく記事執筆の機会をいただいたので「NAVITIME」アプリについていまだに親交のあるYさんら4人の全盲のかたにヒアリングをさせていただきました。快く協力くださった皆様ありがとうございました。
音声案内のきめ細やかさが良い
トータルナビを利用する決め手は徒歩の音声案内のきめ細やかさ。その差は歩き始めに現れるそうです。進むべき方向はナビ開始時はどのサービスでも分かりづらく(端末の方位特定能力が問題の場合もあります)たびたび進行方向を間違えるそうです。NAVITIMEは音声案内の間隔が10mと他社と比べ短いため、間違いに気がつきやすいそうです。
候補の経路情報の読み上げ順序を変更して欲しい
現在のNAVITIMEでは以下の順番で情報が読み上げられるようになっています。
1. 所用時間
2. 早い/安い
3. 料金
4. 徒歩などの経路情報(移動順)
しかし、実際に移動において知りたい情報の順番とは異なるそうで、以下のように移動の難易度に関わる情報がまずわかるのが嬉しいとのことでした。
1. 乗り換え回数
2. 経由駅
3. 乗り換え時間
時刻表一覧の一覧性が低い
頭の中で経路ができているとき、経由駅の全部の時刻表がわかれば改めて余裕を持った経路を考えることができるのでこの機能は結構使うそうです。その際に現状の読み上げ順では一覧性が低いので以下のような改善があると使いやすいという意見をいただきました。
現状の読上げ順:時刻>詳細>時刻>詳細>...
要望:読上げは時刻のみにして、詳細を知りたいときに時刻を選択して詳細が確認できるようにして欲しい。
他にもたくさん改善点を教えていただきました。共通しているのは我々開発チームが日々試行錯誤しているUXと観点が似ていることです。UXとの違いは、ターゲットのユーザーが求めている情報や操作方法に違いがあるという点だけです。ユーザーがより使いやすいアプリにしていく努力にはなんの変わりもありません。
誰もが使えるナビを実現するために
ヒアリングしただけで終わってしまうとサービスは何も改善されないので、ヒアリング内容は全てトータルナビアプリの開発・運用メンバーに共有させていただきました。
共有内容の一つ一つに対してしっかり検討していきたいという話になりました。ただ、こういったご意見もそのままサービス反映が難しい場合もあるようでした。例えば音声案内の発話の間隔が良い例です。ユーザーによっては現状の案内間隔が短すぎて煩わしいと感じているようで、サービスとして落とし所をどこにするかの判断は難しいです。
それでも、誰もが使えるナビを実現するために、UXだけでなくアクセシビリティについても継続して取り組んでいく必要があります。
おわりに
この記事では、ほんの一面ではありますがアクセシビリティについてお話ししました。誰もが等しくサービスができるようにするためにアクセシビリティが必要不可欠であることがおわかりいただけたかと思います。
我々は今後もサービス改善に努めて参ります。引き続き、ご意見などいろいろな形でご協力いただけますと幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
