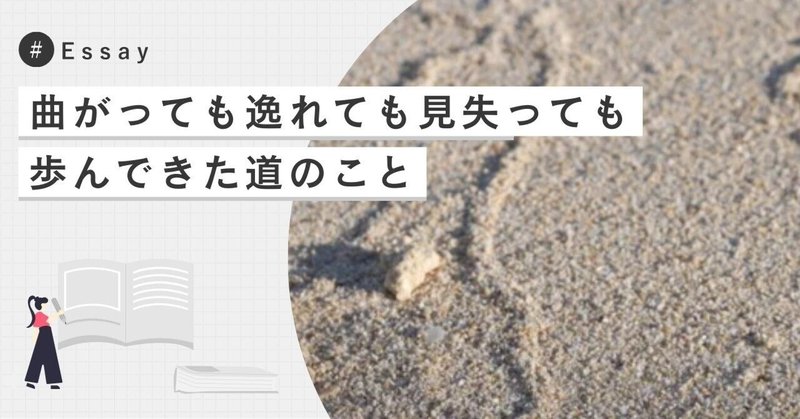
曲がっても逸れても見失っても歩んできた道のこと
私の専門領域では夏休みにメジャーな学会の締め切りが押し寄せることが多く、7月末、8月中旬、そして9月いっぱいと、じつに3連続で締切を乗り越えました。
このくらいのテンポでアウトプットしていると身体と脳にサイクルができてくるのか、「せっかくだし1月締め切りの〇〇学会にも出すか」みたいな気持ちになっていて、習慣化の大切さを実感します。
(偶然なことに、仕事のほうでもまったく同じような体験をしました。これに関してはまた年末にでも振り返りを書きたいと思います)
とはいえ博論の締切も迫っているので、先日はこれまでに行ってきた口頭発表をまとめるなどしました。学会の口頭発表(+プロシーディングス)を業績に含めるかどうかには議論がありますし、私自身はもうちょっと頑張るべきだったなと反省していますが、過ぎた日をグチグチ言っても仕方ありません。今ここにあるものが現時点で私が使える材料なんだよな。と割り切って、博論の骨子を作っていくことにしました。
こうやって整理してみると、博士課程、なんにも成果ないと思ってたけど、少なくともゼロではないやんという気持ちになってきます。少なくとも死んではいなかった。なんとかしがみついていた。うまく表現できないけれど、そういう感慨があります。

大きな大学にいたので、「研究のためなら寝食忘れちゃうぜ」って人が実際にいることはよくよく知っています。「天才」としか形容できない人も実在します。
その裏で、この世界では生きていけないと、ときに傷つき、ときに揉め、ときにひっそりと去っていった先輩、同期、後輩も多く見てきました。
だけど私はどうしても諦められなかった。手に職をつけ、会社を作って、食べていけるだけのキャリアを手に入れても、どうしてもしがみつきたかったんですよね。
私の歩んできた道は、努力・友情・勝利的なキラキラした道ではなかったかもしれない。でも、やめたくてもやめられないことを才能と呼ぶのなら、一種の才能があるのだと今は自分を認めたい。恥ずかしい出来であっても、いまこの時点でのベストを尽くして、たとえ不合格になるとしても、正面から堂々と「NO」と言われたい。
こんなことを言えるようになったのは、30代になったからかもしれません。かつて満期退学するときにもらった寄せ書きで、指導教員から「自分らしい場所を見つけて強くなりましたね」と声をかけてもらったときは泣きました。そうかあ、もう自分の居場所を自分で作れる歳になったんだなと。
まだ本文に着手してすらいないのにエモいことを言ってる場合ではないのですが、うっすら冷え込むこの時期になると、ついつい留年したときのことを思い出して、語りたくなってしまいました。明日からも、秋にも負けずやっていきます。
エモい話はこのくらいにして、研究が捗り出したきっかけを備忘的にまとめておきたいと思います。
ひとつは、何より仕事との良い相乗効果です。このnoteでも書いたとおり最近はPMや各種マネジメントの仕事をいただいているのですが、こういう仕事を円滑に進めるためには、定期的な報告(典型的には定例会議など)が必要になります。
私の場合は週に1回の定例会議がよき刺激になっていて、
定例で報告するために、1つくらいは何かを進めないと!
……「サボり」の防止どれだけ進捗が無くても、定例会議には出ないと…
……「抱え込み」の防止
につながっています。
私の専門分野はなまじ一人で完結できるだけに、サボってしまったり、詰んだときに抱え込んでしまったりしがちです。
そのなかで、仕事において上記のサイクルが効果的にワークすることがわかったので、最近では積極的に親しい研究者に声をかけてセルフ報告会をセッティングし、それまでにアジェンダをまとめるようになりました。
とくに後者の「詰んだとき対策」はかなりワークしていて、つい昨日まで戦っていた応募原稿などは、じつに4回ものボツを乗り越えました。その都度話を聞いてもらい、「ちょっと何を言っているか分からない」とか言ってもらいながら、最終的に骨子がまとまったのが10月1日(締め切りまで2日!)。
もしも自分ひとりで組み立てていたら、きっと諦めていたことでしょう。いつも付き合ってくださっている皆さん、本当にありがとうございます。

(Notionの活用も始めました。具体的にはこんな感じに。)
ただ、これも仕事で気付いたことですが、こうした報告会を効果的な場にするには、雑談の機会もやっぱり大事です。それで最近は、意図的にレジャーや、ゲームのオンライン通信などを行いながら雑談する機会を創出しようとしています。
とくにコロナの時期にM1になった後輩などは、学外どころか学内ですら横のつながりがないそうなので、ひとつでもできることがあればと思っている次第です。(いやまず博論出せよ、人の世話してる場合じゃないだろというのは置いておいて)。
それとつながる話ですが、研究のモチベーションが向上したのも、やはり人とのコミュニケーションがきっかけでした。夏休み中はいろいろな学会やイベントがあったのでまめに顔を出していたのですが、先輩や先生方から「面白いじゃん」とひとこと言ってもらえるだけでも元気が出ました。
それだけでなく、具体的な課題図書なども紹介していただいたので、最近はアウトプットの手が止まってきたら読むようにしています。とくに直近で勧めていただいたとある本は、最近読んだなかでは一番刺激的で、自分の研究にもすぐさま取り入れたい知見でいっぱいでした。
まとめると、結局のところ、(少なくとも私においては)人と関わり続けることがハードルを乗り越えるきっかけになってくれるのでしょう。
これは修論を出せずに留年したときと同じ気づきではあるのですが、キャリアを積んだことで、より幅広い関わり方を知れたのは博士課程の良さでした。何度も言うようにまだ本文のほの字もないので気は抜けませんが、ひとときだけ息抜きをして、ガシガシ書き進めていきたいと思います。
とっても嬉しいです。サン宝石で豪遊します。
