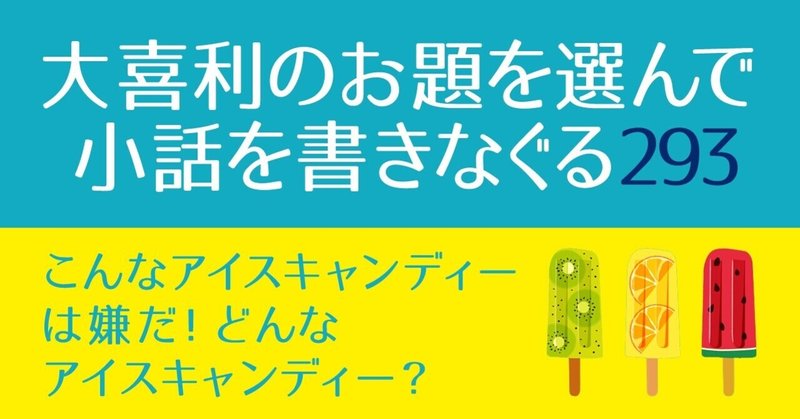
【大喜利のお題を選んで小話を書きなぐる293】こんなアイスキャンディーは嫌だ!どんなアイスキャンディー?
本日も昨日に引き続き、首の調子があんまり良くないせいで、なかなか大変な感じでした。昨日の夜に、いつの間にか寝落ちしてしまったせいで数回寝なおしたからなあ・・・そういうのもう、大人なのだから卒業したいんだけどね!
そういえば、昨日会社でやったLTでnoteのことを発表していて思い出したのですが、私ってSNSとかブログとか、インターネット上で自分をPRするのってとっても苦手だったんですよね(過去形ではく、現在進行形で苦手なままです)。今もフリーマガジンや自作アナログゲームの宣伝や広報をウェブ上ですることもあるのですが、まあ~苦手。なんていうか、どう書いていいか散々悩みまくってしまって、なっかなか投稿できないのよ。どうせそんな細かいところまで見る人は少ないんだからやればいいのに、けっこう本当に、下書きで止まってしまうことが良くあります。しかも、本文にはこだわるくせに写真やハッシュタグは全然工夫されていないところとかね・・・(フリーマガジンの方のSNSは、最近加入してくださったメンバーがインスタ運用を開始してくれて、それがすごいオシャレな感じで投稿されていて、『そうか、こういうことだったのか』って思いながら見ています。オ、オシャレ・・・!!)。
「ストーリー」みたいなリアルタイム発信は怖くてやったことがなかったりしますからね、私・・・(やってから言いなさいよね、ほんまに)。
さて、本日のお題は、「こんなアイスキャンディーはイヤだ!」です!アイスキャンディーかあ~、そろそろ暖かくなってきたので食べごろかもですね!冬はアイスキャンディーというよりはハーゲンダッツの季節だからなあ。
アイスはアイスでも、アイスキャンディーとは
あえての「アイスキャンディー」というのがきっとポイントなのでしょう。ちょっと、アイスキャンディーの定義を確認したいと思います。いでよウィキペディア!
アイスキャンディーは、棒状の氷菓を指し、日本ではアイスバーとも呼ばれる。英語ではアイスポップ (ice pop) とするのが一般的であり、また、アメリカ合衆国では登録商標のポップシクル (Popsicle) が一般名称化している。フィリピンなど東南アジアでアイスキャンディー (ice candy) と言えば、主に自家製氷菓を指し、原料液をアイスキャンディー専用の細長いビニール製の袋に流し込み、口を縛って冷凍するだけの簡素な物で、棒などは差さず袋からそのまま食する。
水・果汁・牛乳などに、砂糖などの甘味料・香料・着色料、固形の原料などを加えて、型に流し込み、木製やプラスチック製の棒を差し入れて凍らせたもの。固形の原料としては、果肉、小豆やチョコレートなどが使われる。凍らせたあとで、溶かしたチョコレートやアーモンドクリームなどに漬けて、表面を覆う場合もある。
アイスクリームに比べ、より安価・簡単につくれ、また屋外での飲食に便利な形状から、夏の野外での小売がさかんに行われた。氷旗を立てたクーラーボックスを自転車に載せ、カランカランと手で鐘を鳴らす「アイスキャンディー売り」は、かつてどこにでも見られた夏の風物詩だった。
商品によっては、棒が2本刺してあり、2等分でき、2人で分けて食べたり、ひとりで2本食べたりして楽しめるものもある。これらは子供達が楽しめるよう、工夫されたものである。
アイスキャンディーに使用される棒には「あたり」「はずれ」の焼き印が押されたものもあり、「あたり」が出ると販売した店舗などでアイスキャンディーと交換してもらえる、または製造販売元に郵送することでノベルティグッズが当たる製品といったキャンペーンが行われることがある。
出典: アイスキャンディーフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
これは良いウィキですね。読んでいるだけでアイスキャンディーの魅力がぐんぐん伝わってきました!なるほど・・・アイスキャンディーとは、基本的には「棒状」の「氷菓」のことを指すのですね。つまり、ガリガリ君やセブンティーンアイスのマスカットシャーベット的なやつはアイスキャンディーであり、ホームランバーやチョコバリはたぶん、アイスキャンディーではない?あずきバーやスイカバーの場合はアイスキャンディーなのかな・・・「氷菓」ってどこまでを指すのだろう。もしかして、今は棒さえささっていたらアイスキャンディーなのかな。
そういう意味では、フィリピンの事例である「自家製氷菓」は分かりやすいですね。「原料液をアイスキャンディー専用の細長いビニール製の袋に流し込み、口を縛って冷凍するだけの簡素な物」、と。本当にキャンディーみたいな形状で凍らせているのも、いいですね・・・。
一応、対比で「アイスクリーム」も見てみます。
牛乳などを原料にして、冷やしながら空気を含むように攪拌してクリーム状とし、これを凍らせた菓子である。
国によっては「アイスクリーム」製品の規格を規定する場合がある。例えば日本では乳固形分及び乳脂肪分が最も高いアイスクリームと、アイスミルク、ラクトアイスの3種類を合わせて広義に「アイスクリーム類」と称す。乳成分をほとんど含まず、クリーム状でない氷菓もアイスクリームに括られることも多い。
16世紀初頭にパドヴァ大学の教授だったマルク・アントニウス・ジマラが常温の水に多量の硝石を溶かすと溶解熱により吸熱反応を示し、水の温度を下げることができることを発見した[4]。また16世紀中頃にはベルナルド・ブオンタレンティ(Bernardo Buontalenti, 1536年 - 1608年)が氷に硝石を加えることで-20℃程度まで温度が下がることを発見した。この原理を利用することで雪や氷を使用しなくてもシャーベットのような食品を人工的に凍結させることが可能となった。もちろんその水溶液から硝石は何度でも回収できる。
初期のアイスクリームは、冷たいボウルの中で手を使い造られたため、製造は大変に困難であった。これを改良する発明は主に18世紀に移民によってアイスクリームが伝わったアメリカ合衆国でなされた。1846年、アメリカのナンシー・ジョンソンという主婦によって手回しのクランク式の攪拌機が発明された。1851年にはメリーランド州ボルチモア市の牛乳屋ヤコブ・フッセルが、余った生クリームを処理するために世界初のアイスクリーム製造工場を造った。
出典:アイスクリーム フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
う~む、氷菓との違いというよりは、「昔、冷凍庫がない時代にアイスってどうやって作ってたんやろう?」という疑問が解消できたことの方が嬉しいな。なるほど、「常温の水に多量の硝石を溶かすと水の温度を下げることができる」のですね・・・高校時代化学はやらなかったからなあ。1つ賢くなりました!
お題に応えてゆきましょう
要するに、あんまり乳成分がリッチではない、棒状のアイスを想定しておけば良さそうなので、それでお題に応えてゆきたいと思います!
・ある時とない時で、ご家庭の雰囲気がガラッと変わってしまう
アレです、551のアイスキャンデーが・・・ある時~!!ってやつです。あのCM、全国区じゃないのであれば分からない人もいるのかな・・・?
極端にいうとこんな感じです。このCMは結構すごいな。極端です。
551のアイスキャンディーは普通にめっちゃ美味しいので、夏のおでかけで梅田に出る時は買って食べてから帰ったりしていました。良い夏の風物詩!
・2本棒が刺さっているにも関わらず、絶対にいびつな割れ方になるように綿密に計算されている
大人の遊び心が暴走するとこうなってしまうのかもしれません。それでも、子どもたちは大きいほうを譲り合ったりして、アイスはいびつでも尊い友情を育んでゆくと思いますが・・・。
・釘が打てるレベルで硬い
これは「あずきバー」のことでしょうね。実際に検証してみた記事がありました。この写真を見る限り、かなり年季の入った「あずきバー」のようですが、それでも無傷なのはすごいですね。
・よく味わってみて気づいたが、これサラダチキンを凍らせたやつや
サラダチキンだったことはさすがにないですが、葛餅アイスバーとか、コンニャクゼリーを凍らせて食べるとかは「アイスキャンディー」の定義にかなり近くなると思うので・・・凍っていると、どんな食べ物も一瞬氷菓っぽくなるので、意外と最初のうちは気づかれなさそうな気がします。
・製氷皿でアイスキャンディーを作っているのかと思ったら、「作り置きスープの素」だった
さきほどの「サラダチキンアイス」もそうですが、しょっぱい食材を凍らせたものを「アイスキャンディー」と呼んでも大丈夫そうですよね・・・。デイリーポータルさんでそのような記事がありました。やっぱり甘いほうが美味しく感じるものらしい・・・むむむ。
さて、明日は水曜日・・・なんか3月もあっという間ですね。毎年この時期はドタバタしちゃいますが・・・幸せな4月を夢見て頑張るぞー!
「大喜利のお題」は以下のサイト様より拝借しています
もしおもしろかったら、♡(スキ)押してもらえたら嬉しいです!
📅特に深い意味のない記事を毎日更新する試み
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
