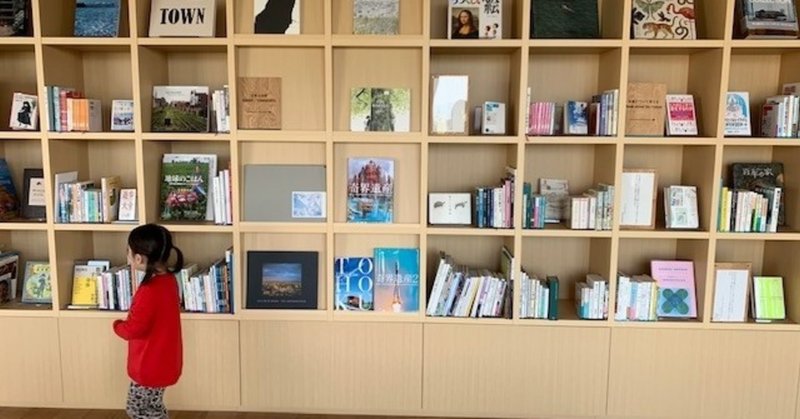
娘はもう「日本語<英語」でもいいかなと思ったきっかけ(2)
前回記事を投稿してから、少し経ちますが、娘の日本語教育は迷走中です。スクールは英語、本やアニメ、そのほかYouTube動画など、好きなコンテンツもすでに英語、独り遊びのときも英語でブツブツ言っているので、日本語のおもしろさと重要性を親の立場から説くのが難しく…。
もちろん、まだあきらめているわけではないし、「英語ができれば日本語はもういいじゃん」と言うつもりはまったくありません。でも、ちょっと前に、私が今年からどハマりしている、amazonのオーディオブック、audibleで出会った本によって、子どもの教育についてウダウダ考えている自分の頭をまさにガツンと殴られたような衝撃を与えられました。
New York Times紙のベストセラー作品『Educated: A Memoir』は、作者/タラ・ウェストオーバー自身の人生、受けてきた教育についての回想録です。といっても、彼女は1986年生まれ、まだ30代前半。まず、この本の何が衝撃かというと、
タラは、ユタ州にあるBrigham Young Universityに入学するまで、学校に行ったこともなかったし、まともな教育を受けたことがなかった。
ということです。
え? それってホームスクールとか、学校に馴染めずに不登校だったってこと?
違います。
どうしてそうなったかというのには、彼女の両親が鍵なのですが、両親は、
狂信的なレベルのモルモン教徒で、サバイバリスト(世界の終末に備える人々)。
現代的な医療、学校、連邦政府を信じていない。よって、病気や怪我をしても病院に行くこともなく、7人いる子どもたちを学校に通わせることもなく、また、政府を信じていないため、末っ子のタラに至っては、出生証明書も9歳になるまで未提出。ちなみに家族がどんなに大怪我(瀕死レベル)をしても、治療は自宅で、母親の作ったフラワーレメディやエッセンシャルオイルを使用する代替療法のみ。痛み止めのアスピリンすら「悪」です。
(特に父親が)学校を信じておらず、現代教育そのものも軽視しているため、タラがまだ小さかった頃は、母親が家で自ら読み書きなどを教えてはいましたが、父親にとっては、タラも含め子どもたちは労働力。自宅敷地内にあるジャンクヤードで、危険な肉体労働に従事させます。重労働のあまり、帰宅後、勉強したくても体力が持ちませんでした。
第三者から見て、簡単に言うと、宗教的・肉体的虐待です。タラは、この他にも、あるひとりの兄から凄まじい暴力を日常的に受けていました。
おそらく、彼女本来の知識欲の強さと、不幸中の幸いにも、彼女には、勉強して進学する大切さを自ら実践して示してくれた、また別な兄がいたことで、そんな厳しい環境にいながらも、独学で大学進学を目指します。
そして彼女は自力で、ACT(American College Test)を受け、いい点を取り(マークシートすら初めてで、最初はどうしたらいいか戸惑った)、Brigham Young Universityに入学。
もちろん、一度も学校へ行ったことがないため、基本的な知識が欠落しているうえ、同世代の子たちと密に接したこともないので、最初は学校生活に苦労します。ある授業では、教室で「ホロコーストって何ですか?」と教授に質問し、その場の全員を凍らせたり、「ヨーロッパ」は国だと思っていたり…。
でも、アメリカ(そしてイギリス)の学校の懐の深さ、すごいところだなと思ったのは、
彼女の経済的困窮(学校反信奉者の両親は、もちろん学費は一切出さない)を見かねて、資金援助を行った教会関係者
その人に繋いでくれた親切なルームメイト(タラは、社会経験のなさから、他の学生から見るとかなり”不思議ちゃん”な存在で、毎日シャワーを浴びないなど特異な生活習慣を持つことから、少し距離を置かれていた)
めきめきと知識をつけた彼女ならではの着眼や考察を評価し、ケンブリッジ大学のあるプログラムに推薦してくれた教授
「今まで読んだ中で最高レベルの論文」と彼女を評したケンブリッジ大学の担当教授
などなど、彼女の真の能力を見抜いて評価し、支援してくれた人の存在。特殊な環境からやってきた彼女を、色眼鏡で見ることなく、実力で受け入れた大学。(ちなみにケンブリッジ大学では、彼女は「人気のディナーゲスト」だった。なぜなら、エリート階層の同級生たちにとって、学校に行ったこともなく、独学で大学入学を果たした彼女のストーリーは、ものすごく珍しいものだったから)
そこで、ふと思ったのです。
「学校に通った経験すらなかったのに、アメリカの大学、ケンブリッジ大学、ハーバード大学のフェローシップ、そしてケンブリッジ大学のPhDまで行けたというのは、結局、母国語が英語だったからでは?」と。
もちろん、彼女は恐ろしく地頭が良いでしょう。育った環境は最悪でも、遺伝子は勝利した…的な。
でも、どんなに地頭が良くても、彼女の母語、そして唯一話せる言語が、たとえば日本語だったら? ヒンディー語だったら? インドネシア語だったら…? 彼女が享受したチャンスと同じものが受けられただろうか?
彼女が日本で同じような境遇にいたとして、高等学校卒業認定試験を受けて、そこから大学に進学するのがどの程度実現可能なのか? 入学できたとして、奨学金はどの程度カバーしてもらえるのか? そこからケンブリッジ大学に推薦で行けるようなチャンスは…?
タラの家には、小説もノンフィクションも存在していませんでした。彼女が繰り返し読んでいたのは、宗教関係の古い本のみ。だから、大学入学当時の彼女の読解力はアメリカ人にしては低かったし、エッセイだって、そもそも書き方がわからなかった。でも、そのあとの伸びは推して知るべし。それも彼女の母語が英語だったから可能だったのでは?
この本を聴いて、改めて教育(それを受けられる機会)の大切さ、家族といえども人生を踏みにじる存在なら、ぶった切ってよし、とか、いろいろと思うところはありました。でも、いちばん感じたのは、英語ができることによって広がる可能性、つかめるかもしれないチャンス、だったかもしれません。
最初にも書いたとおり、子どもの日本語教育はあきらめていないけど、海外に暮らしているなら尚更、英語を頑張ってもらうのが先かなというのと、結局、親ができるのは、機会を与えてお膳立てをすることだけで、あとは本人次第なんだよな……と妙な達観を得ました。
追記:シリアスな内容で、作者にどうしたって感情移入するので、彼女の両親はまさに「毒親」だなと思うのですが、ちょっとウケたのは、彼女がケンブリッジに行くと決まったとき、父親が真面目に「なんでお前は、俺たちの祖先が必死に海を渡ってアメリカに来たのに、わざわざ戻るようなことをするんだ」(要約)と言ったこと。
現在、タラと両親は絶縁状態にあるらしいのですが、母親が昔から作っていた自家製エッセンシャルオイルなどが、(彼女が進学のために家を出て以降)バカ売れして、経済的成功を収めているそうです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
