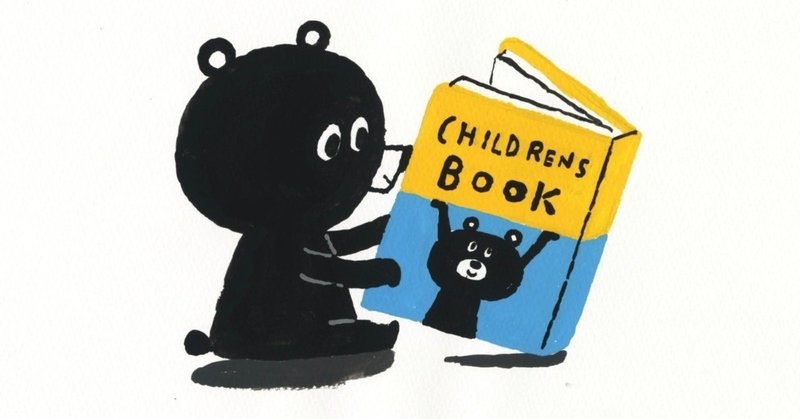
娘はもう「日本語<英語」でもいいかなと思ったきっかけ (1)
セミリンガルって聞いたことがありますか?
簡単に言うと、2ヶ国語を同等に完璧に使いこなせるバイリンガルとは違い、母語ともう1ヶ国の両方が中途半端なままな人、その状態を指します。初めてその言葉を聞いたとき、娘のことを思い、とても他人事には思えませんでした。
我が家はもともと家庭内では日本語です。その言葉を聞くまで、私が漠然と考えていたのは、「英語で授業を受ける学校に通うようになれば、そのうち自然と英語が強くなる(=メインの言語になる)から、家では日本語をしっかり教えよう」ということでした。
しかし、現実はそんなに甘くなく。
そもそも家庭での日本語リソースが私自身と、日本から持ってきた絵本、ベネッセの「こどもチャレンジ」のみ。日本に一時帰国したときは、日本のテレビの幼児番組を観ることもあったけど、4歳過ぎた頃から、それにもあまり興味を示さなくなり…。
毎晩の日本語絵本の読み聞かせはともかく、それ以外に何から教えていけばいいのかもよくわからず、娘が4歳の夏休みに一時帰国したときに、くもん教室の見学に行ってみました。あわよくば、滞在中の2ヶ月弱でも教室に通えないかなと思ったのです。結局、教室には通えなかったのですが、そこの先生には大事なポイントを教えていただきました。それは、
*4歳(日本の幼稚園の年中)時点で、ひらがなが書けなくてもまったく問題なし。焦らないで。
*それよりもまずは読み!
ということでした。そこでおすすめされた、くもんのひらがなカードをamazonで購入し、娘と毎日やり始めたところ、本当にひらがなは短期間で読めるように。同じようにカタカナもできるかな(できればラッキー!)と思ったのですが、それは苦戦。
苦戦の理由は、娘が2019年の7月から通い始めたインターナショナル校で教わり始めた英語のフォニックスにありました。(北インドの学校は、学校・地域によってもバラつきがあるのですが、酷暑期の5月終わりから7月半ばくらいまでが夏休みになり、7月終わり頃から新学年、または新学期が始まります。)
ひらがなカードは、例えば「あり」の「あ」、「いぬ」の「い」といった具合に、カードの一面に「あり」の絵、もう一面に「あ」の文字が書いてあって、イラストとセットでひらがなの文字を覚えていく、というものです。カタカナも仕組みは同じなのですが、「アイスクリーム」の「ア」だと、英語では「ice cream」で、「i 」のフォニックス読みは、(あえてカタカナで表記すると)「イ」なのです。
つまり、ひらがなと同じ方式で、外来語の多いカタカナを覚えてもらおうとすると、フォニックス(英語)と混同してしまう!
というわけで、カタカナはしばらく放置することにしました。
もともと日本で暮らす日本人の子と同じペースで日本語を覚えるのは無理だなとわかっていたので、うちはマイペースでいいと思っていました。なので、カタカナは放置しつつも、「日本語も英語も!」の気概を私は持ち続けていました。
英語の再学習に目覚めた私が、あるオーディオブックに出会うまでは…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
