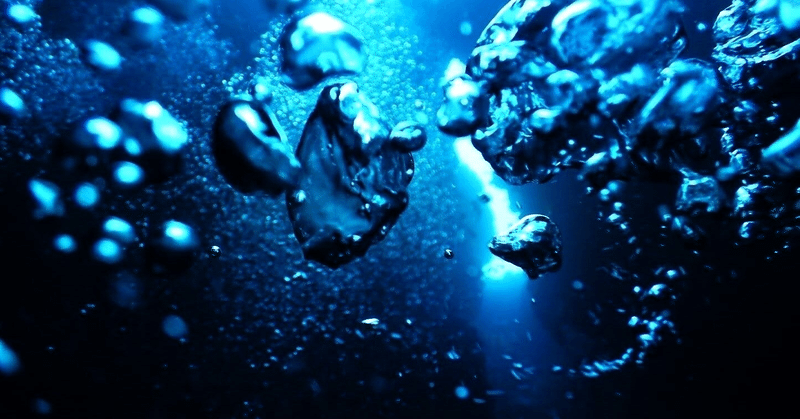
夢の復元者、ソウルダイバー
「ありがとうございます、本当に、本当にありがとうございます!」
「いいんだよ仕事でやってるんだし。そんじゃま、お疲れさん。また何か入り用でしたら当事務所にご一報を。探偵に探せないものだって探してみせますよ」
御大層に写真を抱きしめて泣きじゃくる老女をやんわりと押し返すようにドアの外に追いやる。
築数十年のコンクリートビルの一室に間借りした事務所に静寂が戻る。机の上の空き缶にはリラクゼーション効果に定評のあるバイオヘンプシガーの吸い殻が敷き詰められていて、今新たな一本が残り火と共に押し込まれる。
俺はぎしっと音を立てながらキャスター付きの椅子の背にもたれかかって、天井のヒビを見上げる。
「ちょっと割に合わねぇよな、このバイト」
ちょこっと記憶にダイブして依頼者の覚えていた伴侶の顔をスキャンして、画像データとして写真に書き出すだけの些細なバイトだ。全てのデータが火事で失われたのでどうにか復元してほしいと頼み込まれてやったらあの感謝のされようだ。
ソウルダイブとは、人の深層心理に潜って精神を操作する技術だ。
富裕層からすれば微々たる金額だが民間一般にとっては少し高い。とすれば裏稼業の人間の良いシノギになるのは必然であり、免許を持たないソウルダイブ技術の悪用はまたたく間に裏社会に広まっていった。
ソウルダイバーになれなかったら孤児の俺は野垂れ死にか戦場行きだったはずだ。曲がりなりにも事務所を持てたのはカシラのおかげだし、今でも恩義を感じずにはいられない。
ノックの音に慌てて駆け寄る。さっきの女を追い返して正解だった。
ドアを開けるとカシラがいた。約束と時間を正確に守る人だ。黒い帽子に黒いスーツに黒い杖。
いつも同じ格好だけどいつもとは違い、カシラの隣には白い長髪の少女が佇んでいる。目は虚ろで瞳の色が血のように赤い。
「仕事だ。潜れ」
カシラの持ち込む仕事は、いつだって碌でもない。
【続く】
私は金の力で動く。
