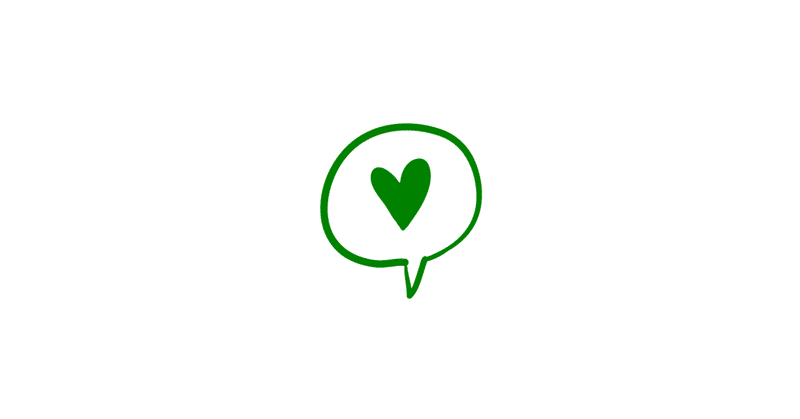
グッドハートの法則
グッドハートの法則をご存知でしょうか。私は最近知りました。
「グッドハート」。とてもポジティブな響きです。ポジティブさを感じてのぞきにきてくれた方もいらっしゃるかもしれません。申し訳ありませんが、グッドハートは人名です。
「管理のために用いられる測定はすべて信頼できない」
これがグッドハートの法則です。
グッドハートの法則(Goodhart's Law)は、1975年にイギリスの経済学者チャールズ・グッドハートが提唱した概念で、以下のように定義されています:
**「ある指標が政策目標として使われると、その指標は有効性を失う」**
言い換えると、特定の指標が何かの成果やパフォーマンスを測るための目標として設定されると、人々はその指標を達成するための行動を取るようになり、その結果として指標そのものが本来測定していた意味や価値を失ってしまうという現象を指します。
### 具体例
1. **教育の例**
- 学校で生徒の学力をテストの点数で評価し、その点数を上げることを目標とすると、教師や生徒はテストの点数を上げることに集中します。結果として、実際の学力向上よりもテスト対策に力を入れるようになり、本来の教育の目的が失われることがあります。
2. **ビジネスの例**
- 企業が営業スタッフの評価を売上高に基づいて行うと、営業スタッフは短期的な売上を上げることに注力し、顧客満足や長期的な関係構築をおろそかにする可能性があります。この結果、長期的には顧客離れやブランドの低下につながることがあります。
3. **医療の例**
- 病院が医師の評価を患者の治療回数や検査の数で行うと、医師は不必要な検査や治療を行うようになるかもしれません。本来の患者の健康や治療の質が犠牲になることがあります。
### 要点
- **指標の歪み**:政策目標や評価基準として設定された指標が、目的達成のために歪んで利用される。
- **本質の喪失**:指標そのものが、もともと測定していた意味や価値を失う。
- **行動の変化**:指標を達成することが目的化し、本来の目標から逸脱する行動が促進される。
### 対策
グッドハートの法則に対処するためには、単一の指標に過度に依存することを避け、複数の指標を組み合わせて総合的に評価することが重要です。また、定性的な評価や長期的な視点も取り入れることで、目的の本質を見失わないようにすることが求められます。
心当たりはありますでしょうか。私はあります。つまり、目標管理制度(MBO)を人事査定と結びつけると、それはすべて信頼できないと云えます。
考えないようにしていましたが、MBOは人事評価には向いていません。しかしマネージャーとメンバーが合意した目標を評価に使って何が悪いという気持ちもわかります。
ですが、本来のマネージャー足る人材がいてこその制度です。真摯なマネージャーがいてこその水準が担保できます。そういった方がいなければ年々劣化していく制度です。
マネージャーの定義も数多くありますが、参考としてマネジメントの父であるドラッカー氏の言葉を引用します。
マネージャーにしてはいけない人
①強みよりも弱みに目を向ける者をマネジャーに任命してはならない。できないことに気づいても、できることに目のいかない者は、やがて組織の精神を低下させる。
②何が正しいかよりも、誰が正しいかに関心を持つ者をマネジャーに任命してはならない。仕事よりも人を重視することは、一種の堕落であり、やがては組織全体を堕落させる。
③真摯さよりも、頭のよさを重視する者をマネジャーに任命してはならない。そのような者は人として未熟であって、しかもその未熟さは通常なおらない。
④部下に脅威を感じる者を昇進させてはならない。そのような者は人間として弱い。
⑤自らの仕事に高い基準を設定しない者もマネジャーに任命してはならない。そのような者をマネジャーにすることは、やがてマネジメントと仕事に対するあなどりを生む。
「管理」すれば解決すると考えがちです。その考えは改めなければなりません。管理することにより指標が信頼できなくなる。PDCAも信頼できません。自動車会社で相次いだように、「偽装」が起こり得ます。しかし「管理」しか手がないようにも思えます。難しいです。
グッドハートの法則は、重要な示唆だと感じます。
光を当てれば影ができる。影の部分に命運を左右するようなコトがあるかもしれない。管理指標をつくる側の人は、ご注意いただければ幸いです。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
スキ、フォローなど、足跡を残していただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
