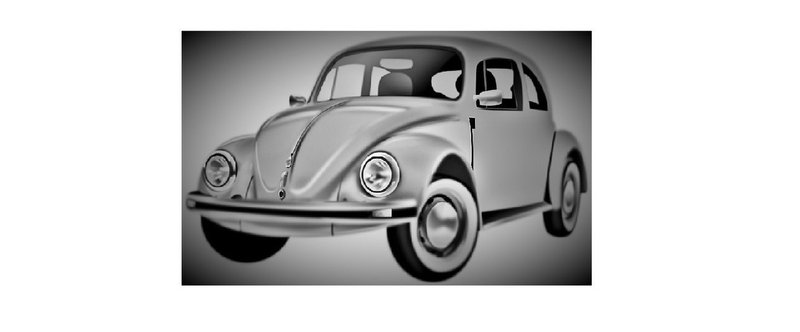
となりの芝
自分のやっている事がうまく行かなくなると、他人の事が良く見えてくる。
頑張ってもせいぜいこの程度かという意識が、他の人は良い思いをしているに違いないと言う確信になってきて、やっかみを覚える。
ファミリーレストランで、子供が口一杯に頬張りながらも他人の食べ物が気になって、きょろきょろしているようなものだ。あっちの方が美味しいかな?と迷っている図である。たいして変わらないよ、同じようなものだよ、と子供に対しては諭すことができても、いざ、自分の事となると他人が気になるのは子供と同じである。
企業が多角化を考える時も、だいたい本業の行き詰まりを感じ始めた場合が多い。今は良いがこのままでは早晩行き着くという危機感が、「他の分野へ出なければならない」との思いを抱かせる。最初は多少の損を出しても良いと思って、辺りを見回してみると、いろんな業界があって、あちこちで好業績をあげている会社が見つかる。「迂闊だった。こんなに広い沃野があったのに」と思う。こうして他の分野へ出る事になるが、出て行った先には、そこはそこで長い間頑張ってきた先発組がひしめいていて、いわば満席である。プロが揃っているところへ素人が手を出しても、よほどでない限り百戦百敗、手傷を負って引き下がるのがおちである。
西武もダイエーも百を超える企業をグループに持ちながら、結局多角化にはほとんど失敗しているのを見ると、新規事業の困難さは我々のような中小企業と同じようなものなのだろう。
従来の分野でやろうと改めて心を引き締めても、ただ今までと同じ事を同じように、同じ設備でやっていては駄目で、何の工夫も革新もなければじり貧のまま落ちてゆく。
その点ではワーゲンがいい例だ。フォルクスワーゲンほど長期にわたってモデルチェンジをしなかった車は無い。あのカブトムシは「変わらない」ことがステイタスだった。ドイツでは祖父から受け継いだワーゲンといえば大変格好よかったそうだ。だが、外観こそ不変でも、実はマイナーチェンジは毎年のようにやっていた。目に見えないところでは次々と革新的な改良を加えて現代社会に合う優秀な車に変身していたのである。
毎日同じようなことをやっているが、実は日々改善改良を蓄積している会社、こういう製品こそが社会に受け入れられて、その会社は存続できる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

