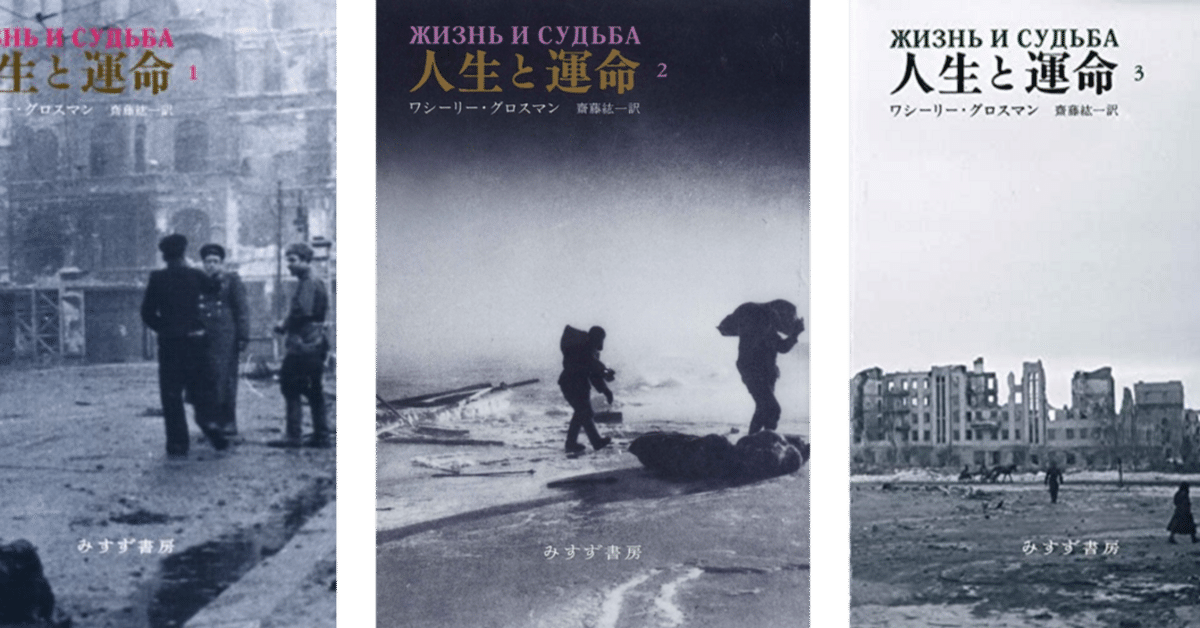
人間としてのスターリンの生態(その1)―グロスマン『人生と運命』、フレヴニューク『スターリン』に見る
1.はじめに
「政治家」というラベルを貼って済ますにはあまりに桁外れな存在であるように思える「スターリン」という人物―1945(昭和20)年8月9日から9月2日にかけて、北海道北部占領という目標を持って一方的な軍事的攻撃を日本に対して仕掛け、結果として日本領土の一部を不法占領した点で、日本と日本人にとっては未だ「生ける存在」でもある人物―については、最早人間扱いすることをやめ、(最大限の悪辣さと邪悪さを持った)「神」として遠ざけでおきたい気分になるというのが正直なところであるが、神話や伝説ではなく、数々の「伝記」が刊行されていることからも分かるように、スターリンも一人の人間であった。人間としてのその存在は、吉本隆明による、人間と最も広い意味での社会との関わり方の三つの側面に関する用語を援用すれば、共同幻想に関わる部分だけでなく、個人幻想や対幻想と関わる部分をも当然のことながら併せ持っていた。ここで見て行きたいのは、スターリンという存在における個人的な部分である。
上記共同幻想とは、共同的・集合的な対象そのものが現実に対して具体的な影響を与える主体であるかのように振る舞う場合のその存在であり、国家はその代表的形態である。個人幻想とは共同幻想性に回収されない私的な領域のことを指し、吉本隆明は詩や小説などの文学作品の本質的な役割の一つを個々人の個人幻想の表出に見ていた。もう一つの対幻想とは、個人どうしの関係としての領域であり、「家族」がその典型的一形態であるが、これを共同幻想や個人幻想とは異なるもう一つの総体的に独立した領域として措定した点はその理論的枠組みの独自の特徴であるとされる。
私が興味を持っているのは、一般に、その存在そのものが国家や社会そのものであるという意味で、共同幻想的な存在としてのみ多くの場合取り扱われているスターリンという一人の「政治家」(上述のように、そのような規定にスターリンは全くそぐわないという印象を与えるのであるが)の、人間としての側面についてである。これはしかし「人間的な側面」という意味ではない、と強い註釈を付けることは当然であると思われる一方で、政治的「業績」と呼ぶにはあまりにも禍々しいものを多量に含んでいるとしか思えない政治家としてのスターリンの事績にも拘らず、その存在が、スターリン批判の時期やペレストロイカの時期を乗り越えて、未だに、簡単な言葉で言えば「人気」があり、その種の存在を待望する人が絶えず、現に、プーチンによってその行動様式の一面がなぞられてしまっている始末であるという事実と現実を見ると、(当のスターリンから国土を一方的に略奪された側の)我々日本人にはなかなか理解もできず見えもしないものの、スターリンには明らかに、ある種の魅力があるのであろう、ということは推測できる。
「農奴制国家」の復活を伴うレーニンの暴力革命によって、結局ロシア帝国の新規バージョンとして成立したソヴィエト社会主義共和国連邦を、ロシア帝国以上の巨大国家に拡張し、曲がりなりにもヒトラーを打倒し日本から領土を奪取した上で、アメリカと拮抗する強大国に育て上げた政治家としての「業績」の一方で、想像を超える程の激烈な悪事の数々を働いた人間であったが、スターリンが「神」ではなく、ヨシフ・ヴィッサリオーノヴィチ・ジュガシヴィリという名前を持った一人の人間であったことは、おそらく確かなことであろう。スムーズに接続ないし移行し合うものではないのかも知れないが、スターリンの共同幻想的な側面と、個人幻想的な側面や対幻想的な側面とは、相互に何らかの関係を持っていたはずである。但し私の興味は、スターリンの共同幻想領域における特に弾圧や抑圧の側面を、その個人幻想的な側面における何らかの特徴―特に性格的偏りや障害のようなもの―と結び付けようとすることや、あるいは対幻想的側面における困難や危機のようなものに単純に結び付けようとすることにあるのではない。私は単にスターリンの個人としての側面、人間としての側面に対して関心を持っており、まずはスターリンの伝記やスターリンが登場する小説の中にそれらを探ってみようと思っているだけなのに過ぎない。
ところで、最初に考えたこの小文のタイトルは、「人間としてのスターリンの生活と仕事」というものであったが、それだと何か「スターリンにおける人間的な部分」のような「共感的なニュアンス」が混じってしまうようで気に入らず、考えているうちに「生態」という言葉を思い付いた―「人間としてのスターリンの生態」。生態という言葉を使えば、スターリンの日々の仕事や生活、その個人レベルでの思索や読書について、あたかも一個の動物を観察するような視点で眺めることができるのではないかと考えられる。もっとも、この言葉を思い付いたのは、この小文の文章の下書きをすべて書き終わった後なので、全体をその言葉によって統御するという段階には達していない。将来何かもっと長い文章の一要素として「人間としてのスターリン」の問題を扱う機会があれば、その時はその「生態」という色合いをより濃くした記述を実現したいと考えている。本小文はそのための一つの草稿でもある。
2.(部分的に)紹介する二冊の本
本小文では、次の二冊の書物を紹介するが、それぞれの全体の紹介ではなく、「人間としてのスターリンの生態」に関わる小さな部分のみの紹介に留まる。
① オレーク・V・フレヴニューク/石井規衛 訳 (2021).『スターリン―独裁者の新たなる伝記』白水社.
② ワシーリー・グロスマン/斎藤紘一 訳(2012).『人生と運命 1-3』みすず書房.
以下、②→①の順で紹介して行くが、人間としてのスターリン、その生態という問題を強く意識化するようになったのは、①の文献に触発されてのことであったので、先にフレヴニュークによる『スターリン』について触れておきたい。
この本は、変わった構成を採用している。スターリンは、1953(昭和28)年2月28日土曜日の晩、「五人組」での最後の晩餐の時間を過ごし、翌3月1日の早朝にお開きとなったが、その日の夜、私室で倒れているのが発見され、3月4日の夜、死んだ。
ここで五人組とは、スターリン体制における最後の六か月間の政権中枢グループのことを意味し、スターリンの他、ゲオールギー・マレンコーフ、ラヴレーンチー・ベーリヤ、ニキータ・フルシチョーフ、ニコラーイ・ブルガーニンが含まれていた。(人名表記は本訳書に従う。)
フレヴニュークの『スターリン』には、この2月28日から3月4日に至る時間幅の中で、スターリンの日々の執務と生活、読書と思索、インナー・サークル、家族などの主題を記述する章【A】と、スターリンとソ連社会の経時的伝記/歴史を辿る章【B】とが交互に現れる。比較的短い時間範囲の中に、より長い時間範囲における多数の事象を、回想・追想などによって凝縮するという技法は小説や映画などの物語において多用されるが、フレヴニュークは研究書においてこの技法を用いたのだ。本書は以下のように、【A】と【B】が交互に現れる構成を持っている。なお、【A】と【B】は本小文における独自の記号である。

序文
スターリンの権力の座【A-1】
第1章 革命以前【B-1】
スターリンの権力の防塁【A-2】
第2章 レーニンの陰にあって【B-2】
読書と思索の世界【A-3】
第3章 彼の革命【B-3】
インナー・サークルの不安【A-4】
第4章 テロルと差し迫る戦争【B-4】
患者番号ナンバーワン【A-5】
第5章 戦時下のスターリン【B-5】
家族【A-6】
第6章 大元帥【B-6】
崩壊する独裁体制【A-7】
葬儀―首領、システム、人民【B-7】
この目次からも見て取ることができるように、【A】の部分は主にスターリンを巡る共同幻想の側面についての記述であり、【B】の部分はその個人幻想や対幻想の側面についての記述を主としている。この本は、それぞれの部分を交互に配置してその全体構成を構築している。本小文の中でも紹介するように、人間としてのスターリンの性格的特徴とその政治的政策とを関連付け接続させて論じる部分もある。しかし、例えば文学理論における精神分析批評や心理学的解析といったものに特段の興味を持たない私は、その種の接続の部分に必ずしも強い関心を持つわけではない。結果としての桁外れの「業績」を達成したスターリンという人間の生態自体にかなりの興味を持つ、というただそれだけのことである。
私は、このような個人的問題意識に基づきフレヴニュークの『スターリン』の一部分を紹介しようと執筆を始めたところ、前々から頭の片隅にいつもありながら読みそびれていて、昨年2022(令和4)年2月24日のロシア・ウクライナ戦争勃発後に慌てて読み通したワシーリー・グロスマンの長編小説『人生と運命』(全三巻)の中に、スターリンの生態を生き生きと描き出した幾つかの箇所があったことを思い出したので、本小文でそちらも同時に紹介しようと考えた。
以下、フレヴニュークの『スターリン』中の「人間スターリン」を巡る記述の最初の一部の紹介に入る前に、『人生と運命』の中に描かれた、具体的な・生身の人間存在としてのスターリン(及びヒトラー)の幾つかの描写を、私なりの考察も多少加えながら、紹介して行く。
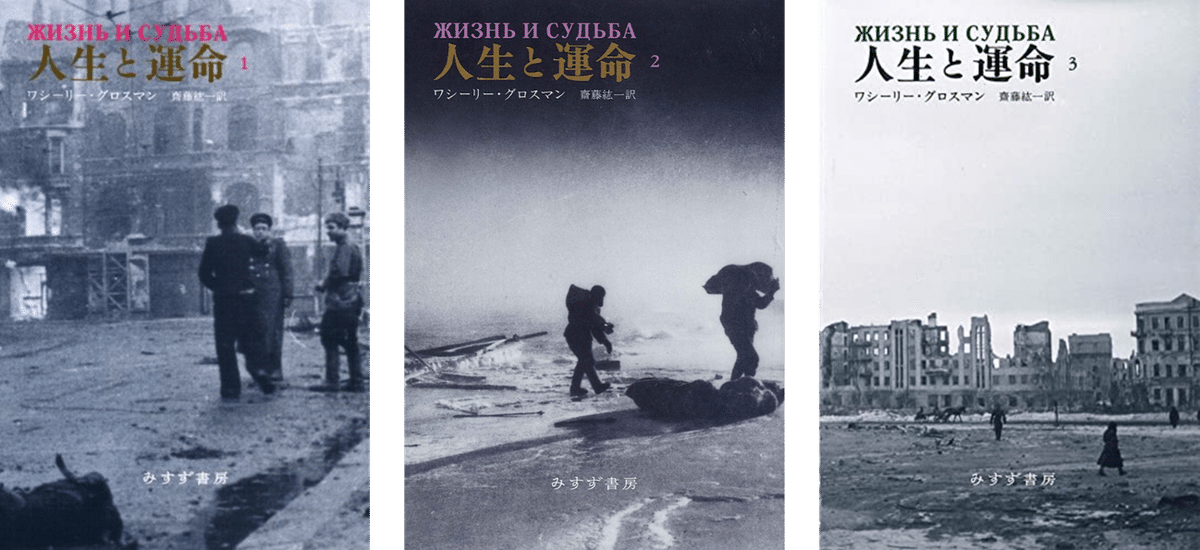
3.『人生と運命』の中のヒトラーとスターリン
グロスマンの『人生と運命』全体についての説明はここでは省略する。詳しい情報は、日本語翻訳版『人生と運命』第一巻末尾に掲載されているスミルノワによる解説や、同じく第三巻末尾の訳者斎藤紘一によるあとがきを参照していただきたい。また私も、近刊『物語戦としてのロシア・ウクライナ戦争―物語生成のポストナラトロジーの一展開』(新曜社)における一つの節でグロスマンを取り上げ、『人生と運命』についても幾つかの角度から分析と論評を試みたので、こちらも参照されたい(2023(令和5)年9月に刊行予定)。
ワシーリー・グロスマンは、ウクライナのジトーミル近くのベルディ―チェフという町に生まれたユダヤ人で、使用言語はロシア語であった。理工系の大学を出て、東ウクライナのドネツクで働いていたこともある。初期の小説に特に反体制的な記述が見られるわけではなく、独ソ戦時には志願して従軍作家となり、戦争の現場や経過をつぶさに観察した。従軍記者としてのグロスマンについて詳しい情報は、アントニー・ビーヴァーの『赤軍記者グロースマン―独ソ戦取材ノート1941-45』(川上洸訳. 2007, 白水社)が提供している。特にスターリングラード攻防戦の取材に力を注いだが、その後ソヴィエト赤軍の西方への進撃と共にウクライナやポーランドを経てベルリンに達し、最終的なソ連の勝利を目撃した。従軍メモや作品の中には、「ソ連人」としての愛国心の発露を示す多くの記述が見られる。しかし、西方への従軍取材の中で、グロスマンはウクライナにおけるドイツ軍によるユダヤ人虐殺に関する生々しい声や語りを聞いた。故郷ベルディ―チェフでの大虐殺において、以前から予感していたように、自らの母親も殺されていたことをこの時知り、大きなショックを受けた。その後、ポーランドのトレブリンカでのナチスドイツによるガス殺収容所の跡地を訪れ、そこで何が行われていたのかを知り、世界でも最も早くその悲惨に関する迫真の報告を公表した。ワルシャワゲットーにおけるソ連も関与する悲劇的な状況や、さらに進軍行路における赤軍の敵に対する残虐行為も見聞した。

これらの経験を通じて、グロスマンは敵国ドイツによるユダヤ人大虐殺についてリアルに知るだけでなく、それにウクライナ人も深く関与していたことや、ソ連側の犯罪的行為も認識するに至る。グロスマンの書くものの中には徐々に、ソ連やスターリン、さらに遡ってレーニンのロシア革命自体への批判の棘(さらには刃)が増えて行った。それに伴ってグロスマンに対する抑圧の程度も強まって行った。少数の擁護者の存在や、何よりもスターリンの死によって、処刑や収容所送りは免れたものの、スターリン死後も抑圧は続いた。コンスタンティン・シーモノフらによって徹底的な修正の手が入れられたと言われている、もともと『スターリングラード』という題名で書かれた、『人生と運命』と殆ど同じ規模の長編小説『正義の事業のために』の続編として、『人生と運命』は1960(昭和35)年頃には書かれていたが、原稿のみならずタイプライターなどもソヴィエト政権によって略奪されてこの小説の出版の機会は失われた。しかし幸運にもそのコピーが作家ウラジミール・ヴォイノビッチの手によってソ連国外に持ち出され、1980(昭和55)年にスイスのローザンヌで初めて、不完全ながらも出版された。
さて、何れもそれ程長くはないが、この小説において、スターリンが、名前を挙げられるだけではなく、特定の場面の中に登場人物として現れるのは、三箇所であると思われる。これらの場面では、非常に具体的で、生き生きとした人間のイメージとして、スターリンが描かれている。そのことは、この小説全体において、特定の場面の中に、一回だけ現れるヒトラーの描写と比較すると、より明らかとなる。そこでまず、ヒトラーが現れる小説中の一箇所を紹介してみたい。
3.1 ヒトラーの描写
特定場面中の登場人物としてのヒトラーは、第三巻(第三部)、第17章(pp.75-78)に現れる。
場所は、東プロシアとリトアニアの境にあるゲルリッツの森である。高い木々の間の小道を、灰色のレインコートを着た中背の男、総統アドルフ・ヒトラーが一人で歩いている。季節は秋。雨が降り、辺りには湿った空気が漂っている。小道は、柔らかい落ち葉によって敷き詰められている。
この場面において、現実世界の登場人物として現れるのは、ヒトラーの他に、歩哨たちと護衛連隊の多数の者たちであるが、何れも具体的な姿形を表すわけではない。歩哨たちはヒトラーの姿を目に留めて驚き、護衛連隊の者たちはヒトラーの姿を、四方から、本人には気が付かない仕方で、見守っているだけである。
この場面でのヒトラーは、一人で散策しながら、取り留めのない思索を巡らす。一しきりの散策と思索の後、ヒトラーは野戦総司令部の建物に戻って行く。ジェイムズ・ジョイスやヴァージニア・ウルフに代表される「意識の流れ」派の小説、あるいはヘミングウェイの小説だと、この種の登場人物による思索は完全な一人称視点に入って展開されるだろうが、表現技法においてより保守的ないし古典的なグロスマンの場合、そこまで過激な描写法が採用されることはない。作者ないし語り手による記述の統御はぎりぎり保持されている。
現実の場面における登場人物は、前述のように、ヒトラーと、はっきりと前面に現れることのない歩哨たち、護衛連隊の人々だけであるが、ヒトラーの思索の中には、すなわちその心理内部には、様々な人々―野戦総司令部の人間たち、スターリン、チャーチル、ナポレオン、第六軍の者たち、ツァイツラー、ゲッペルス、党指導部の者たち、母親―が、入れ替わり登場する。
この場面の描写の中心は、ヒトラーの心理である。その心理(思索)は、
野戦司令部の人間たちへの苛立ち
スターリンへの軽蔑
チャーチルへの期待
スターリングラードからの撤退に固執した第六軍の者たちへの腹立ち
ツァイツラーやゲッペルスへの苛立ち
ナポレオンへの嫉妬を超越しているとの自己認識
自分自身への自信喪失と自信過剰との間で往復し揺れ動く心
おとぎ話の中の小人になった気分
森の中に迷い込んだ子ヤギになった気分
子どもの頃の恐怖の記憶
母親を求める不安な心
いくつもの収容所で燃える炉の火への人間的な恐怖
と揺れ動き、移り変わって行く。
以上のようなものとしてのヒトラーの描写は、生身の人間のしかも意識の内部を除き込んで見るという、極めて個人的な性格の強いものである割には、湿気の多い秋の雨の日の描写であることを考慮に入れなくとも、あるいはそのような状況によって強調されて、神秘的な、茫漠と霧に包まれたもののような印象を与えるものとなっている。
3.2 スターリンの描写①
私の印象では、ヒトラーの場合とは対照的に、『人生と運命』における現実上の登場人物としてのスターリンの描写は、より現実的で、いわば臨場感の強いものとなっている。ざっと数えたところでは、この小説の中にスターリンは三回登場する。ここで言う「登場する」とは、物語中の特定の場面の中に、その一人の登場人物としてスターリンが実際に現れることを意味する。他の登場人物達によってスターリンのことが話題になる場合はもっと多いが、それらは勘定に入っていない。
スターリンが最初に現れるのは、第二巻(第二部)第7章(pp.216-217)の短い場面である。
場所は、共産党中央委員会が開催されている会議場(ホール)であり、この会議にスターリンも出席している。会議の参加者の中には、明示されていないが政治家達の他、招かれた科学者達も含まれている。どうやら科学政策を巡っての会議らしい。スターリン以外の主要な登場人物は政権側のシチェルバコフであるが、しかしその発言の一部がスターリンによって反駁されるという形で取り上げられるだけである。
会議に出席しているスターリンの行動を中心にこの場面は描写される。スターリンは、パイプを片手にホールを歩き回ったり、途中で考えて足を止めたりしているが、その間会議の参加者達が演説を行っている。特に注目されるのは、シチェルバコフによる、恐らく科学政策に関連する演説であり、スターリンは、シチェルバコフの話を途中で止め、それに対する反論を述べる。但し、シチェルバコフの演説内容自体が記述されるわけではなく、それはスターリンが反論する対象として示されるに過ぎない。また、観念論と科学に関する演説が行われるが(演説者は明示されない)、その途中でもスターリンは演説を止め、自分の意見を述べる。スターリンのこれらの反論や意見は、それ自体としては科学者達にとって有利なものであり、会議後彼らがそれぞれ、会議中のスターリンの様子を噂したり、楽観的な感想を述べたりすることが、物語の語り手によって言及される。
また、この会議に参加した科学者達による、スターリンの外貌についての具体的な噂話も紹介される。それらによれば、スターリンは、白髪で、口の中に黒い虫歯があり、疱瘡のせいであばたがある。しかし細い指の美しい手をしている。
数日後、科学者達の楽観的な予想や期待に反して、著名な植物学者で遺伝学者が逮捕された。
これは非常に短く小さな挿話的場面に過ぎないが、前記ヒトラーの描写と比べるとはるかに現実的で生々しい印象を与えるものとなっている。またスターリンの政治家としてのある意味小賢しい「やり口」を象徴する場面ともなっている。
3.3 スターリンの描写②
次に、第三巻(第三部)第11章(pp.53-57)は、もう少し長い場面である。おそらく、この小説全体において、スターリンが登場する最も長い場面であると思われる。
この場面の枠組みは、スターリンがイライラしながら、クレムリン内部の執務室で、独ソ戦におけるスターリングラード攻防戦の最終局面の戦況報告を伝えるエリョーメンコからの電話を待っている状況である。スターリンはヴァトゥーチンとこの場面の10分前に会い、そのことについて話している。
しかしこの場面における作者の目標は、このような枠組みを借りて、スターリンの遊動する意識を辿り、さらにスターリン自身の内的視点を超えて、作者によるその批評(批判)にまで筆を及ぼすことである。揺れ動く心理の流れを追う、という点では前述のゲルリッツの森でのヒトラーの描写と類似しているが、そこから作者そのものに限りなく近いと思われる語り手による、痛烈なスターリン批判が噴出する点で異なる。このスタイルは、『人生と運命』のその他の場面でもしばしば現れるが、それが全面展開されるのは、『万物は流転する』(齋藤紘一(訳). 2013, みすず書房)においてである。
私の『物語戦としてのロシア・ウクライナ戦争』(前掲)は、その一節において、『万物は流転する』の中で数十ページに渡って展開されているグロスマンによる「レーニン・スターリン・ロシア批判論」を要約しているので、参考にされたい。
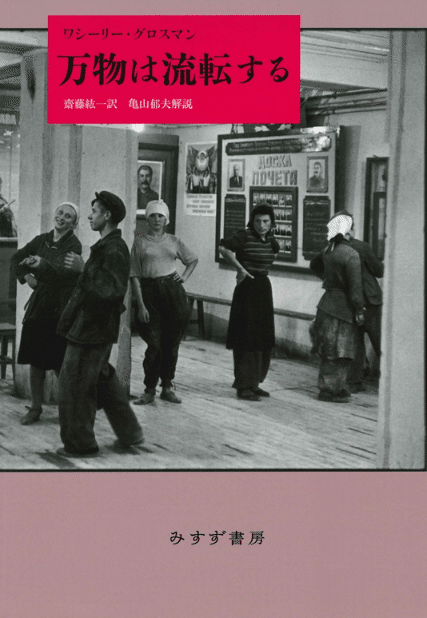
スターリンの心理内部には、ヒトラー、チャーチル、ルーズヴェルト、トロツキー、モロトフ、ジューコフ、ルイコフ、カーメネフ、ブハーリン、ベリヤが現れる。これらの人物は、スターリンの一人称的な意識のプロセスと共に現れては消える。
もう一方で、語り手としての作者自身は、ドイツ人捕虜、ソヴィエト人捕虜、カルムイク人、クリミアのタタール人、バルカン人、チェチェン人、ミホエルス、ズースキン、ベルゲリソン、マールキン、フェフェル、クヴィートコ、ヌシーノフ、ヴォシフ教授、ユダヤ人、といった人物、民族、グループを物語の中に召喚するが、これらは、作者自身としての語り手による「スターリン批判」の言説の中に現れる対象である。
この場面におけるスターリンの外的行動の流れは、以下のように辿ることができる。前述のように、この場面に入る10分前にバトゥーチンと会話していたスターリンは今、スターリングラード方面軍からの電話での戦況報告を待っている。電話が来るまでの間スターリンは取り留めのない思索に耽るが(この思索がこの場面の主内容となっている)、ようやくエリョーメンコと電話がつながり、エリョーメンコからの報告を聞くと、悪態を吐いて受話器を置く。スターリンが直接登場するのはここまでである。
電話を待つ間、スターリンの心の中では、彼との間で種々の関係を持つ様々な人々が浮かんでは消える。
最初に浮かび上がるヒトラーには、敵でありながら一種の共犯関係を感じている。そして、チャーチルとルーズヴェルトが本質的に、スターリンを軽侮していることへの苛立ちを感じ、そこからトロツキーのスターリンに対する軽蔑の目の思い出に連想は流れる。この時スターリンはトロツキーを殺戮したことを初めて後悔するが、それは人間的な同情心からではなく、スターリングラード攻防戦に今や勝利を収めようとしている自分の姿を、(かつて軍事的側面で自分を攻撃し引きずり下ろした)トロツキーに見せつけてやりたいからであった。
引き続き、自己過信と不安―人々の密かな軽侮への不安―の間で揺れ動くスターリンの心理へと記述は進むが、どうやらこの辺りから、物語の語りは、スターリン自身の視点を離れて、作者自身と思われる語り手の側へ移行して行く。この語り手は過去の出来事を呼び起こし、かつてスターリンがモロトフに対して見せた戦争指導における優柔不断な行動や、極度の緊張と興奮のせいで冷静さを全く保つことができなかったあるラジオ演説、そして部下であるはずのジューコフの意見に隷従してしまった情けない事態の顛末が紹介される。
さらに同じ筆致で、スターリンが時に、自ら殺したルイコフ、カーメネフ、ブハーリンへの戦争指導の責任転嫁の誘惑に今更ながら駆られること、スターリン自身が弾圧した人々が蘇るのではないかとの恐怖の念、ベリヤの態度に対する我慢ならなさと不安が記述される。
しかしながら、自信と不安の間で目まぐるしく揺れ動くスターリンの「人間的な心」は、最終的に、自分こそが権力の具現なのだという絶対の自信が勝利する。
そしてそれ以降、語り手はほぼ作者自身に完全に移行する。語られる内容は、スターリン自身の思考の中身ではなく、それを離れた未来の予言である。未来の事象を先取りして現在に導入するという予言法の語りである。
語り手の予言によれば、間もなくヒトラーによる占領国家や強制収容所が崩壊し、ドイツ人捕虜やソヴィエト人捕虜を悲劇的な未来が待ち受けている。様々な民族がやがてソ連において迫害される運命にあるが、予言の語りの焦点はユダヤ人の運命に移って行く。ミホエルスその他ユダヤ人芸術家らを待っている悲劇的な運命や、ユダヤ人医師達の例の如くでっち上げの恐怖裁判が予告される。さらに、ポーランドその他の国の将来も続く苦難の運命が語られ、ソ連の農民や労働者が突き落とされる未来が予言される。これらの予言は、スターリン自身の思索とも微妙に交じり合い、この時スターリンは激しく興奮している。
この章の最後の部分で作者と思われる語り手は、この時代の後、スターリンの哲学がやがて真の意味を持つに至るということを述べる。これはおそらく、「スターリンによる強権政治と抑圧体制の終わり」という、独ソ戦終結時にソ連国内の多くの人々が抱いたに違いない期待が、脆くも壊れて行く近未来のことを言っているのだろう。スターリンは、ヒトラーとナチスを打倒した暁にこそ、自国民のみならず国外の人々にも多大な犠牲と苦痛を強いる共産主義サディズムを、撒き散らそうと待ち構えていたということだ。
以上のように、この章では、「人間としてのスターリン」内部の迷いや揺れ動く心が前半で描かれるが、後半では、徐々に自信を取り戻して行くスターリンの心理内部の高揚感と興奮が描写される。その二段構成はさながら、静かで暗い雰囲気の音のくぐもりから金管楽器が高らかに鳴り響くクライマックスへと至る音楽のようである。最後に作者による批評が来るが、それは悲劇的な未来の予言という形を取っている。
3.4 スターリンの描写③
『人生と運命』のスターリンが登場する場面で最も強烈な印象を与えるのは多分、第三巻(第三部)、第42章(pp.242-244)の挿話であろう。ここに登場するスターリンは、電話越しのその「声」だけである。
この場面の登場人物は、まず、特定の(一人ないし少数の)主人公がいないと考えられている『人生と運命』の中でも、最も頻繁に登場する、殆ど主人公格であると見做して良いと思われる、物理学者ヴィクトル・パーヴロヴィチ・シュトルームである。その妻リュドミーラ・ニコラーエヴィチ・シュトルームも、スターリンことヨシフ・ヴィッサリオーノヴィチの声を電話越しに聞く。
場所は、ヴィクトルの自宅、時間は夜と思われる。スターリンが登場するその他の場面と同じように、この場面もその枠組みはほんの短い一挿話に過ぎない。
出来事と行動・心理をまとめれば、ある日、ヴィクトルが自宅でリュドミーラと話をしている時、電話が来る。最初に受話器を持ち上げて相手に応答したのは妻の方である。(よくある日常生活の一コマのように見えるが、ヴィクトルはこの頃、発表した物理学の論文のせいでひどい運命が待ち受けていることを、予感し覚悟する状況になっているので、ヴィクトルとその妻にとってこのところの日々は、少なくとも日常的な平穏さに満たされたものではなかった。)驚くことに、それはスターリンからの電話であった。スターリンは、ヴィクトルにとってラジオなどで聞き覚えのある声で、ヴィクトルに挨拶する。最近常に、逮捕されるか収容所送りになるかと怯えながら暮らしていたヴィクトルは、これで(悪い)運命が決まったという感覚を抱くが、挨拶をしたスターリンに対して、自分でも驚く程自然に、挨拶を返している自分に気付く。その時、ヴィクトルがスターリンの声から受けた印象は、ゆっくりしていて、喉にかかったような発音で、特定の音節がひどく強調されている、というものであった。
挨拶に続く電話越しの話の主要部分は、スターリンがヴィクトルに対してヴィクトルの科学者としての仕事についての質問を短く投げ掛け、ヴィクトルがそれにやはり短く答える、というものでしかなかった。具体的には、ヴィクトルが勤める研究所において、予算は十分足りているかという問いをスターリンが発し、それに対してヴィクトルは不満はないということを答える。その会話の間、リュドミーラはそわそわして、立ったまま会話を聞いている。スターリンとヴィクトルとの会話の内容はほぼそれだけである。スターリンは暫くの間沈黙した後、別れの挨拶をする。ヴィクトルもそれに応じてスターリンに別れの挨拶をする。すぐに、ヴィクトルは受話器を置く。
スターリンからのこの電話が一体何を意味していたのかは、その後のヴィクトルが再び研究所に確固とした地位を得たこととの関わりにおいて、やがて明らかになって行く。ヴィクトルは、『人生と運命』の作者グロスマンと重なる部分が多い。ヴィクトルの母親は、物語の中で、グロスマンの現実の母親と同じように、ウクライナでナチスによって虐殺される。ヴィクトルに宛てた母の最後の手紙は、グロスマンの母の最後の手紙を下敷きにしている。そこに書かれていた「生きるように」という母の願いに従ったのか、ヴィクトルは結果として生き延びる道を選択することになる。
以上見て来たように、『人生と運命』中の幾つかの場面に直接現れる、登場人物としてのスターリンのイメージは、ヒトラーのそれと比べてよりリアルで生き生きしているように感じられる。まさに「人間としてのスターリン」が描かれているように感じることができる。
グロスマンは、『人生と運命』や『万物は流転する』その他の小説に見られるような、激しい「ロシア批判」の作家として、近年日本でも認識されるようになっている。同時に彼は、ソ連に住んだロシア語作家として、素朴な愛国心を持った人間でもあった。そのような「ソ連人」としてのグロスマンにとって、スターリンが、ヒトラーと比較して、より身近な、生々しい人間としての存在であったことは事実だろう。それが、グロスマンによる、ある意味生き生きしたスターリンの描写と造形につながっていると考えられる。
