最新ではなく最適を
“新しいアイデアをどんどん取り入れろ!”
”流行のものをどんどん試してみよう!”
たまにこんなことを言われたり、聞いたりします。
スポーツ科学は日進月歩で発展するものなので、新しい知見には触れておいたほうが良いし、より良い仕事を行うには新たなアイデアや流行のものを率先して取り入れる必要も時にはあると思います。
しかし、学生時代から思っていた疑問があります。
最新のものを取り入れるのではなく、最適なものを取り入れるべきでは?
今回はそのことについて触れていきたいと思います。
新しいものやアイデアはどのように生まれるか
新しいもの・アイデアなどってどうやって生まれるんでしょう。
思うに、新しいものって二つの異なる既存のものを融合させることで生まれるのかなと思います。
つまり、全く新しいものが急に閃くことはなく、それまで培ってきた知識や経験を融合させた結果で出てくるものなのかなと思います。
手段か目的か
新しいもの・アイデアの導入は何かを達成する手段としてだと思います。
しかし、上述のように“新しいアイデアをどんどん取り入れろ!”や”流行のものをどんどん試してみよう”の解釈を間違えると、それら新しいものの導入が目的となってしまう可能性があります。
それって導入する意味が無いのでは?
現場は最新ではなくその時々の最適を求めている
例えば、“最近ちょっとケガが増えているから、そこを減らしたい”という要望があったとします。この場合、目的は「ケガを減らすこと」となります。
ケガを減らすためには、まず第一に現状を分析しなければなりません。
受傷状況、受傷した際の環境面のコンディション、それまでの活動スケジュール、体力レベル、トレーニングの進捗状況、身体の疲労度(睡眠時間など)、スキルレベル、練習・トレーニングの量、etc.
いろんな方面から分析を行う必要があります。
分析を行ったうえで、その時々での最適な改善策の実践に移ります。それはトレーニングのプログラムに若干の修正を加えるのか、身体の疲労度を考慮した練習計画の再修正なのか、時と場合に応じて変わります。
しかし、「ケガを減らす」という目的や分析を差し置いて、最新や流行のものを取り入れる(例えば、「ケガを減らす有効性が報告されている最新の○○トレーニングを取り入れる」)というのは、手段が目的化してしまう第一歩になりうるかなと思います。その心として、最新のものをそれっぽく提供していれば、競技指導者や選手からその時点では喜ばれ、その結果、提供した当人は嬉しくなり、”最新の”ものを提供することが仕事だと勘違いします。しかしそれは本来の目的を達成するにはあまりにも短絡的です。
仮に、ケガを減らす有効性が示されている○○トレーニングがあったとしても、現場によってはそれがマイナスになるケースもあります。
ケガが多い原因として、練習・トレーニング量の多さによる疲労度の蓄積があるかもしれません。しかし、最新科学に基づくとか流行という謳い文句に引っ張られて、現状分析をせずに○○トレーニングを導入したら、余計に疲労が溜まってケガのリスクを上げてしまいます。
となると、マイナスの結果へ導いてしまいますね。
最新のものは選択肢として扱う
日々発展するスポーツ科学の知見を取り入れることはとても重要です。新しいアイデアを練ることも発展には重要です。そして、最新の科学的知見を見聞きしたり、新たな着想を得ると、取り入れたり実践したくなる気持ちはわかります。しかし、それぞれの現場で使えるかどうかを精査するフィルターを持つ事もとても大事だと思います。
つまり、最新のものを選択肢に入れつつ、現状分析を経て最適なものを実践するという思考を持つことが良いのかなと思います。
今回のnoteは以下に示す本の一文を読んで書いてみました。
「考え」は「作る」「構築する」という動作を加えないと、「使える考え」にならないのである。つまり、筆者の言う「考えを作る」とは「新しい考えを作る」ということだけでなく、「使える考えを作る」ということでもあるのである。
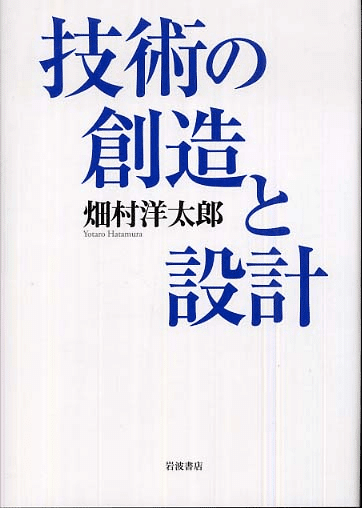
Amazon.co.jp - 技術の創造と設計 | 畑村 洋太郎 |本 | 通販
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
