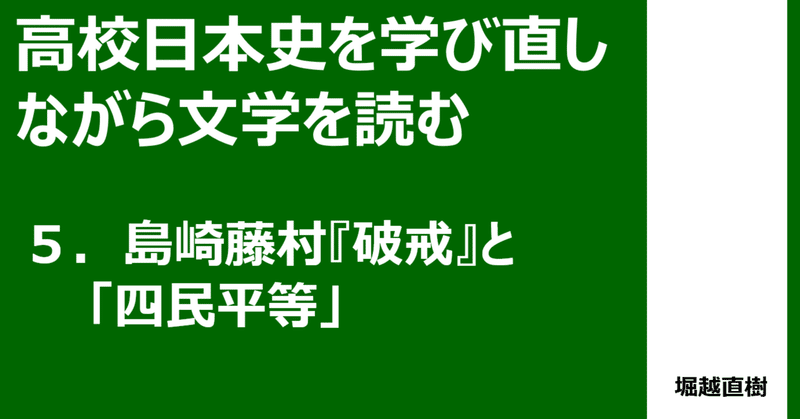
島崎藤村『破戒』と「四民平等」【高校日本史を学び直しながら文学を読む5】
今回は島崎藤村の『破戒』を取り上げます。被差別部落出身の瀬川丑松を主人公とし、自然主義文学を代表する作品です。これまで3回も映画化されていて、1948年に木下恵介監督、1962年に市川崑監督、そして2022年には前田和男監督(主演は間宮祥太朗)が60年ぶりに映画化しました。
いつもと同じように、理解を深めるための高校日本史の講義を紹介し、そのあと作品そのものに触れる、という流れをとります。
近世社会の身分制をあらわす言葉として「士農工商」という言葉が使われることが多かったのですが、現在、この言葉はあまり評判の良くないものとなっています。士農工商は古代中国から用いられた言葉であり、紀元前1000年ごろにはすでに使用が確認されています。そのような言葉を、江戸時代の日本に無理にあてはめて使用したために、たくさんの不都合が生じてしまうのです。
日本の近世社会の身分制を理解するためには、四つの身分に分けるのではなく、まず支配身分と被支配身分という二つに分けて考えるとよいでしょう。支配身分は、領地の住民に年貢や諸役を課す側の人間と考えればわかりやすいかもしれません。将軍以下の武士、天皇・公家、上層の僧侶・神職などが支配身分に該当します。被支配身分としては、百姓、町人、一般の僧侶・神職、山伏・陰陽師など、えた・非人などの賤民などがいました。
「農工商」は、古代中国においては土地にねざした「農」が重視されたために、身分序列のように考える場合もありましたが、日本の近世社会においては被支配身分の中に明確な序列はなく、中国に影響を受けた儒者の一部に身分序列と考えていた人がいただけです。字面から「農」は農民、「工」は職人、「商」は商人と考える人が多くなってしまいますが、日本の近世社会では職業よりも住む場所で被支配身分を区別していました。まず、村に住む人を百姓と呼びます。村に住んでいれば、農業に従事していても、漁業でも、林業でも、職人をしていても、商人をしていても、百姓です。城下町などの都市には武士も住んでいましたが、武家地と町人地がしっかり分けられており、町人地に住んでいるのが町人ということになります。町人地の中に大工町・鍛冶町などの職人町がありますが、同職集住の原則はしだいに崩れていき、町は様々な人が行き交う場所という性格を強めていきます。
江戸時代の賤民の中で大きな位置を占めていたのは、「えた」と「非人」の二つの身分でした。この二つはほぼ全国的に存在しており、人口も大きなものでした。
えたは、17世紀半ばに幕府が差別的意味をもつ「穢多」の称を用いたことで広がりましたが、畿内から西日本では「かわた」、関東・東北などの東日本では「長吏」の称が一般的でした。農業をおこなう一方で、牛や馬の死体処理の特権を持っており、皮革製品の加工に従事していました。これらは中世以来の武具・馬具の製造に関わる産業であり、戦国大名の領国では欠かせない必需産業を担う存在でした。近世の社会的分業の中で被差別民が生み出され、ケガレの観念が広がっていく中で差別観が強められていったと考えられています。条件の悪い土地に居住させられ、結婚や交際、服装などできびしい差別を受け、この差別が近現代の部落差別の起源となっています。
非人は、芸能者、百姓・町人が生活に窮し物乞いや浮浪者となる場合、刑罰により刑罰により非人とされる場合などがあり、村や町の番人として治安警察の末端を担う者もいました。非人は事情によってはもとの身分に戻ることもあり、えたに比べて身分は流動的でした。
明治新政府は、身分制を解体します。生まれによって職業や地位が決まる身分制は、近代化をすすめるには不適切でした。新たな税制システムを全国一律に施行する地租改正への準備として、統一的な戸籍を編成して国家が直接に国民を把握する必要があったのです。1869年の版籍奉還後、公家や大名を華族、旧武士を士族と卒(1872年に廃止)、百姓・町人など被支配者階級であった者を平民としました。かつての支配者階級の特権は解消がはかられ、平民については苗字を許し、居住・職業・通婚の自由を認めました。この政策によって、いわゆる「四民平等」が実現したといわれます。先ほど「士農工商」という言葉は近世社会の実情にあっていないという説明をしましたが、四民平等の「四民」というのは、「士農工商」を前提としてしまっている言葉ですね。平等といっても、戸籍で華族・士族・平民と明確に区別され、社会的な序列は容易に解消されませんでした。
賤民については、1871年の太政官布告により、えた・非人の呼称を廃止して、身分・職業を平民と同じにするという方針が示されました。この太政官布告は、のちに「解放令」と呼ばれるようになります。しかし、政府は身分制の解体を重視したものの、被差別部落の解放については考えていませんでした。差別を解消するための施策はおこなわれず、実質的差別が根強く残ることになります。差別を維持しようとする側は、「新平民」のような呼称をつくり出し、旧身分にもとづく差別を続けました。被差別部落襲撃も頻発しています。根強い差別意識に加え、被差別部落の人々が自らと対等になることへの脅威や恐怖があったことがうかがえます。風呂屋では、被差別民が来ると他の客がいなくなるという理由で、風呂屋の店主から入浴を断られることもあったそうです。また、生業上の既得権を剝奪されたことで、社会的差別に加え、経済的な貧困も深刻なものになっていきました。
『破戒』は、明治時代後期に信州の被差別部落に生まれた瀬川丑松を主人公としています。丑松の父は「たとえいかなる目を見ようと、いかなる人に邂逅(めぐりあ)おうと決してそれとは自白(うちあ)けるな、一旦の憤怒悲哀にこの戒を忘れたら、その時こそ社会から捨てられたものと思え。」と教えます。つまり、被差別部落出身であることを隠せ、というのが戒めの内容でした。
丑松は師範学校を出て、尋常小学校の教師となります。勤務先の校長は、教育は即ち規則であると考え、軍隊風に児童を薫陶したいと考えるような人でした。一方、丑松は新しい思想を持ち、人間主義の教育によって不合理な社会を変えていきたいと願う青年教育者です。丑松は子どもたちから慕われ、師範学校時代からの友人で同僚の土屋銀之助という理解者もいます。校長は丑松や銀之助のような新しい教育観を持つ人間を煙たがり、郡視学の甥の勝野文平とはかって丑松を学校から退けようと考えます。
丑松は、被差別部落に生まれた解放運動家の猪子蓮太郎を慕うようになります。蓮太郎は「我は穢多なり。」と世に公言して社会の実情を告発するような人で、丑松はそんな蓮太郎には自分の出自をうちあけてしまいたくなるのですが、葛藤の末、父の戒め通り出自を隠し続けます。
やがて、丑松が被差別部落出身であるという噂が学校で流れます。新平民を「下等人種」と認識している勝野文平との会話の中で、校長は「見給え、彼の容貌を。皮膚といい、骨格といい、別にそんな賤民らしいところがあるとも思われないじゃないか。」と述べます。教育に関わる人物がこのような認識であるということから絶望的な気持ちになる場面ですが、本当の絶望は、尋常一年の教師と土屋銀之助の会話によってもたらされます。
「穢多には一種特別な臭気があると言うじゃないか―嗅いで見たら解るだろう。」と尋常一年の教師は混返すようにして笑った。
「馬鹿なことを言給え。」と銀之助も笑って、「僕だっていくらも新平民を見た。あの皮膚の色からして、普通の人間とは違っていらあね。そりゃあ、もう、新平民か新平民でないかは容貌で解る。それに君、社会から度外にされているもんだから、性質が非常に僻んでいるサ。まあ、新平民の中から男らしい毅然した青年なぞの産れようがない。どうしてあんな手合が学問という方面に頭を擡げられるものか。それから推したって、瀬川君のことは解りそうなものじゃないか。」
丑松をかばう立場の銀之助から、強烈な差別意識を含んだ言葉が出てきています。校長や文平と比べると新しい思想を持っている銀之助がこのような考え方であることから、部落差別の根深さがわかります。被差別部落の人々は身体上の特色があるということが前提にされており、そのように種族が異なるかのように認識されていた人々への差別を当然視する風潮がそこにあります。
追い詰められた丑松は、自分の教える児童たちの前で土下座して自らの出自を告白し、教壇を去ります。その後、アメリカのアメリカのテキサスでの事業を持ちかけられ、逃げるように海を渡るという選択肢がほのめかされてこの物語は終わります。
なぜ主人公は悪いことをしたわけでもないのに土下座をしなければならないのか。戒めを破って出自を告白した後、不合理な社会を変えるために行動することはできなかったのか。なぜ遠く離れた場所へ逃げて暮らさなければならないのか。今日の視点からみれば、大変問題のある終わり方であるように感じます。また、部落差別で苦しんでいた人たちから見ても救いがなく、むしろ傷ついたり、より苦しめられたりした人が多かったようです。しかし、他方では、当時の部落差別の背景や問題点を映し出している作品と見ることもできます。
不合理な社会とは、差別する側よりも差別される側の方に問題があると認識し、被害者本人が自分にも非があるのではないかと思い込まされてしまう社会でした。
『破戒』の出版は明治末期の1906年ですが、大正時代に入ると被差別部落の側から大きな動きがおこります。1922年、被差別部落民による運動団体である全国水平社が創立されました。創立宣言では、「我々がエタである事を誇り得る時が来たのだ。」と主張し、自らの出自を隠さずとも差別の解消が可能であると考えました。また、差別の原因は被差別民の側にあるのではなく、各時代の社会状況の側にあると認識しました。それは、今後社会状況が変化すれば、被差別部落民の立ち位置も変化する可能性があるという、将来の希望が含まれる考え方でした。
しかし、水平運動にも思想的限界がありました。水平運動に関わった人々の多くは、天皇の下での「臣民」としての「平等」を追求していました。これが「平等」と言えるのか。そして、「天皇」とは何なのか。日本の歴史を学ぶ上で避けては通れない問題が出てきましたが、これについて考察するのは別の機会としましょう。
現代では残念ながら部落差別はなくなっておらず、インターネットを使って醜悪な差別発言が拡散される時代となっています。ヘイトスピーチの対象は在日コリアンだけでなく、被差別部落に対しても差別的言動が繰り返されています。
『破戒』は今日から見れば問題点の多い作品ではありますが、それも含めて、差別について考えるきっかけになるのであれば、やはり読む価値のある作品だと思います。まだ読んだことがない人には読んでみてほしいですし、読んだことがある人は再読してさらに深読みしてみるというのはいかがでしょうか。
主要参考文献
・島崎藤村『破戒』(岩波文庫)
・高校教科書『日本史探究』(実教出版)
・黒川みどり『近代部落史』(平凡社ライブラリ―)
・黒川みどり『被差別部落認識の歴史』(岩波現代文庫)
・黒川みどり・藤野豊『差別の日本近現代史』(岩波書店)
・高橋貞樹『被差別部落一千年史』(岩波文庫)
・喜田貞吉『被差別部落とは何か』(河出文庫)
・奥田晴樹『維新と開化』(日本近代の歴史1 吉川弘文館)
・山口輝臣・福家崇洋編『思想史講義【大正篇】』(ちくま新書)
・朝治武『全国水平社 1922-1942』(ちくま新書)
・藤野豊『水平運動の社会思想史的研究』(雄山閣)
・藤野豊・黒川みどり『人間に光あれ―日本近代史のなかの水平社』(六花出版)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
