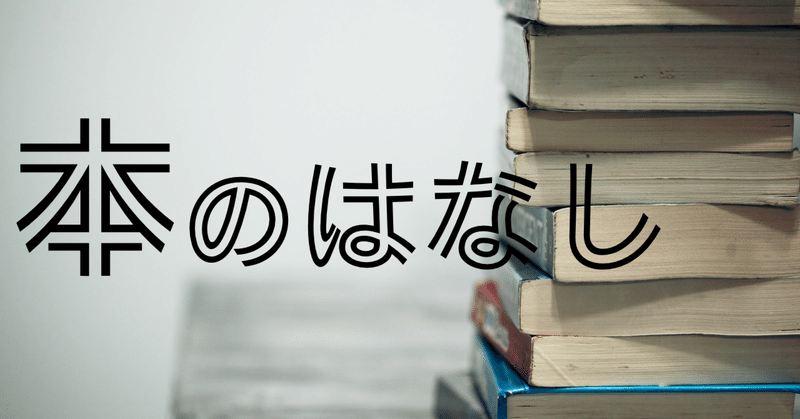
賢さについて書かれた本を読んでみた
「可愛いはつくれる」っていうキャッチコピーあったなぁ。とか思いながら軽い気持ちで読んでたんですが、めっちゃくちゃ好物の本でした。
そもそも、賢いっていうのはどういうことなのかっていうのは、昔バイトで交通整理しながら日がな一日考えたり、その後も折に付けて考えていたことなので、こうやって同じようなことを真剣に考えている人がいたことと、さらにそれが綺麗にまとめられている本に出合えて興奮しました。
著者は思考を「具体と抽象の往復運動」と定義し、頭が良いというのはその具体と抽象との間の距離が長く、移動速度が速く、回数が多いと定義されていました。個人的には、同じ距離でも違う角度から見ることが出来たりするので、もう一つ次元を足したいところではあったりしますが、それでもこの本を読んでみると、著者の定義が思いの外、強力で使い勝手のいいものであることが分かります。
つい最近もある問題が起こって、この本で言うところの具体から抽象で色々な解決策を検討していたわけです。
例えば、現状のルールに則って対応するとか、今回の物はイレギュラーとして扱うとか、この機会にルールから設定するとか、そもそも、全然違う解決策をもってくるとか。
ただ、私の検討に時間がかかり過ぎてしまったため、現場で具体よりの現行ルールを破らないがユーザーフレンドリーではない対応が選択されてしまったということがありました。
著者も書かれてましたが、オプションを色々思いつければつくほど、反応は遅くなってしまうので色々な視点が持てるようになったらなったで、仕事ができない人になったりします。まぁ、そうなっても速度が落ちない人ってのも結構いるんですけどね、私はめちゃくちゃ遅いです。残念ながら。
ただ、頭が良いを構成している3つの内に誰しも得手不得手を持っているのではないかと思います。私の場合は距離は普通、速度は遅い、回数は人より多いんじゃないかと思っています。他の記事も読んでいただいている方はご存じかもしれないですが、私は結構どうでも良いことをこねくり回して考えるのが好きだったり、こねくり回して放置していい感じの回答が突然浮かんだりするのが好きだったりします。そんな性分なので考えること自体は全く苦ではなく、行ったり来たりを繰り返す回数は人より多かったりします。逆に速度は人よりだいぶ遅いので、会話の時に当意即妙な受け答えなんかは望むことが出来ません。
こうやって考えてみると自分の強みや弱みがわかっておもしろかったりするのではないでしょうか?
そんな人がどの程度いるのかはわからないですが、頭が良いってなんだろう?とか、賢いってどう定義したらしっくりくるだろうなんて考えている人は一読してみることをお薦めします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
