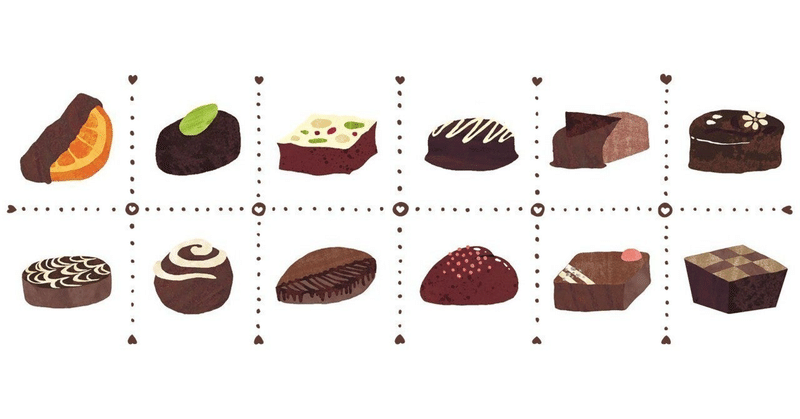
はじめまして、の代わりに小説を。
はじめての記事に何を書けばいいのか悩んでしまったので、自己紹介がわりに小説を置きます。
文学フリマ東京37で配布した、フリーペーパーの中身です。
「✕✕✕✕のチョコレートを毎月プレゼントしてくれる人となら結婚してもいい」と鹿乃子が言ったので、「じゃあ私と結婚して」と間髪入れずに返した。
✕✕✕✕はフランスの有名なショコラティエが手掛けるチョコレート専門店で、日本でこの店の品を手に入れようとすると、個人輸入か、バレンタインの時期に百貨店のイベントで買うかくらいの選択肢しかない。後者を選ぶと小さなプラリネが一つあたり九百円にもなる。一番小さい九個入りの箱で、八千円を超えるのだ。
アパートの電気代すら滞納しがちな貧乏画家の鹿乃子がこれを言うのはただの空想、というより現実逃避だったのだけれど、私はこれ幸いと鹿乃子に迫った。
鹿乃子自身は一箱二百五十円のスーパーのチョコレートさえ買えない身分でも、画家というのは、気に入りさえすれば何十万何百万もの絵画をぽんと買ってしまえる金持ちに囲まれている。もし鹿乃子が彼らといるときにそんなことを言ったらどうなるだろう? 私は彼女の発言が私たちふたりきりのときに発せられたものだったことに感謝する。
世間に疎い鹿乃子は知らないけれど、✕✕✕✕の店は来月、日本への初出店が決まっていた。銀座で月に一度行列に並ぶくらいのことで彼女が手に入るなんて思わなかった。
ずっと、鹿乃子の孤独に恋をしていた。
大学二年の夏、付き合いで顔を出したグループ展の、他の人たちが見向きもしない油絵の前で立ち尽くした。昏い色で端から端まで塗りたくられたキャンパスに、けれど確かに、赤く揺らめく炎が見えた。
ひとつのさびしい星が烈しく燃え上り、宇宙をも呑み込んでしまう絵だと直感した。
誰が書いた絵なのかはすぐに分かった。ギャラリーの隅に立つ女の子の目の中、絵とおんなじ炎が燃え盛っていた。
その日から十年が経った。
私たちじゃ結婚できない、と戸惑う鹿乃子に、婚姻届なんてなくても✕✕✕✕のチョコレートは食べられるでしょ、と答えた。仕事をリモートに切り替え、ローンで都心から離れた一軒家を買った。お金は私が稼ぐから、鹿乃子は好きに絵を描いていいよ。
生きていくことに疲れた鹿乃子は、簡単に私に流された。
朝起きて、鹿乃子は✕✕✕✕のチョコレートをつまむ。もう電気代の督促に追われることもなく、何を表現しなくても居場所がある。鹿乃子は絵を描かなくなった。
安寧に曇る鹿乃子の目を、私は注意深く見つめ続けた。鹿乃子の炎は、すっかり✕✕✕✕のチョコレートに鎮められていた。
鹿乃子は私のものになった。
ように、思えた。
「チョコレートは、もう、いい」私の差し出した十八個入りのチョコレートに、鹿乃子はある日首を振った。目にはちろちろと揺れる赤が見えた。
それから鹿乃子は檻の中の動物みたいに家の中をぐるぐると回り、やがて、家で一番小さな、物置きと化している部屋に閉じこもった。彼女の持ち込んだ、絵の道具を詰め込んだ部屋だった。
数日後、絵を描き上げ部屋を出てきた鹿乃子の目に宿っていたのは、満足でなく、あの、烈しい孤独だった。
私の胸は歓喜に震えた。ああ、これ、これが私の愛したもの!
描けば描くほど、鹿乃子という女は孤独になる。
彼女自身の魂を削り取り、彼女は描く。削り落とされた魂は、余すことなく彼女の孤独へ焚べられる。
誰とも共有できない鹿乃子の孤独。それを、私が、私だけが、いつまでも間近で見ていたい!
まくった袖に油絵の具をつけたまま、鹿乃子はソファへ倒れる。彼女が眠りに落ちているのを確認して、私は寝室へ毛布を取りにいく。深く寝入った鹿乃子は毛布をかけても身じろぎ一つしない。まるで死んでしまったかのように白い顔の、固く瞑られた瞼だけは、皮膚の奥の炎をうつしてほんのりと赤く見えた。
スツールに腰掛け、テーブルに肘を乗せて頬杖をつく。肺の底から、甘く、深いため息を長々と吐き出さずにはいられなかった。
箱のまま出しっぱなしになっていたチョコレートをつまむ。鹿乃子の食べなかったチョコレート。フルーツの酸味とチョコレートの甘みが口の中にふわりと広がり、次の瞬間には跡形もなく消え失せる、とっておきのひとくち。上品で、洗練されていて、……鹿乃子に愛され続けるには、きっと随分、物足りない味。
箱に蓋をして、私は目を閉じる。祈り。ねえ鹿乃子、そうやって魂を燃やして燃やして、あなたは孤独に描き続けてね。
そうしていつか、私を置いて死んでしまって。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
