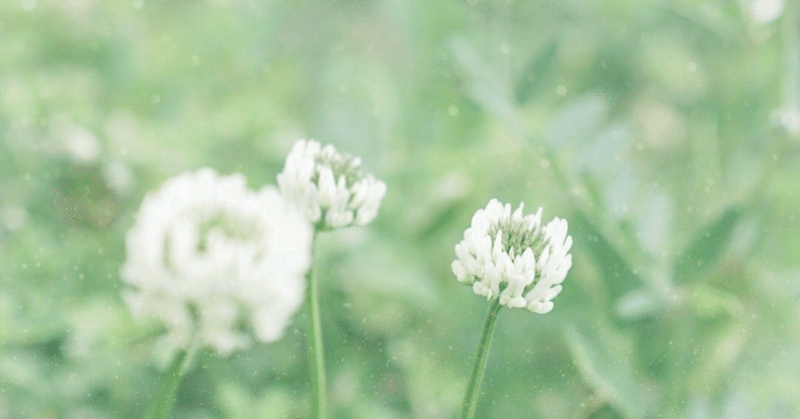
「マリーについて」第3話
「……ありがとうございました」
テーブルの上に置かれたマリーの写真集を見つめたあと、四郎は静かに席を立った。
「え、もう行くの?」
「はい。……もしマリーを見かけたら、連絡ください」
「ちょ、ちょっと、待ってよ!」
そのまま足早に立ち去ろうとするので、美鈴は慌てて四郎を呼びとめた。まだ何も聞いていない。突然目の前に現れた、マリーを知っているこの男のことを。
「あなたにとってのマリーは何だったの? 教えてよ、ねぇったら!」
美鈴の叫びを置き去りに、四郎は喫茶店をあとにした。
*
外に出た途端、夏の面影を残した太陽が容赦なく体を焼きつけてきた。俺は煙草に火を灯し、美鈴が撮影したマリーの写真をじっと見つめた。青空の下でやわらかく微笑むマリー。無邪気で、楽しそうで、幸せそうで。だけどどこか神秘的で、神々しい。
こんな表情、見たことなかったな。煙草を口から離して、ため息とともに白い煙を吐き出す。誰よりも長く深く、知っているつもりだったのに。
――俺が知っているマリーのすべて。
マリーはもう、どうしようもなく、おそろしいほどに、「さみしがり屋」だった。
さみしがり屋のマリー
その冬は近年稀に見る大寒波が襲来し、来る日も来る日も灰色の雲がはち切れて、重たげな丸い雪が視界を真っ白に染め上げていた。そうなると、出不精な俺は猫のように家から出なくなり、その代わり、毎日のように都合のいい女を呼び寄せては、空白の時間を塗り潰していたのだった。
「……シロ」
リビングのソファに腰をかけ、とある女と映画を見ながら談笑していたら、幽霊のようにか細い声が、俺と女の会話に割り込んできた。
振り向くと、リビングのドアが遠慮がちに開いている。その隙間から、ビー玉のような青い瞳がまっすぐに俺たちを見ていた。俺は隣にいる女に目配せして、しかたなく腰を浮かせた。
「部屋にいろって言っただろ」
ドアからのぞく小さな影に近づいて、戒めるように声を低くする。人形のようなそれはさみしげに俺を見上げて、
「……まだ?」
「まだ。順番」
「……分かった」
諦めるようにうつむく、その仕草を確認してから、俺は乱暴にドアを閉めた。
マリーと暮らし始めたのは、三年ほど前のこと。
その日は目も眩むような夏の盛りで、嵐みたいに鳴り響く蝉時雨がやけに印象に残っている。長らく連絡の取っていなかった両親が、突然、人形のような少女を連れてやってきたのだ。
大きな麦わら帽子。亜麻色の長い髪。青い瞳と、人間味のない透明な肌。まるで絵画に描かれた人間のように、生命のにおいがしないその少女は、失踪した姉の子供だった。十年以上前に実家を飛び出した姉は、また性懲りもなく自分の所有物を放り投げ、泡のように跡形もなく消えてしまったらしい。そして姉を毛嫌いしていた両親が、独り身という理由だけでマリーを俺に押しつけたのだ。養育費は両親持ち。学校の手続き等も両親がすべて行った。ただ衣食住だけは俺にすべて任せたい、ということだ。要するに、面倒は見てもいいが、マリーの顔は見たくないらしい。
ひとりの生活を好んでいた俺は、突如押しつけられた子供に困惑したが、行き場のないマリーを放り出すこともできず、しかたなく共同生活を始めることにした。マリーはおとなしく、聞き分けのいい子供だったので、思ったほど手はかからなかった。ただ一緒に住んで、飯を食い、寝る。ペットのようなものだと思えばいい。
遊びにきていた女が帰ったのは二十三時を過ぎた頃だった。俺は思い出したようにパソコンを開き、やりかけの仕事を片づけるため、ひたすら文字を打ち込んだ。
フリーライターと言えばなんとなく恰好がつくが、不安定かつ不規則な生活を送っているということだ。ふと来る仕事の締め切りに追われたり、仕事がなくて暇をもてあましたり。それはとても自由で、縛られることをきらう俺にとっては、とてつもなく気楽だった。
日付が変わる時刻になって、ようやく最後の一文を書き終えた。眼鏡を外してうーんと大きく伸びをしたはずみで、ふと、マリーのことを思い出した。ああ、すっかり忘れていた。
部屋のドアをそっと開けると、真っ暗闇の中で、マリーがベッドに横たわっていた。眠っているかと思ったけれど、隙間から漏れる光に反応するように、青い瞳がぱちっと俺を捉えた。
「マリー」
ありったけの甘さを含んで名前を呼ぶ。マリーは勢いよく起き上がる。主人を見つけた子犬のように、小走りで駆け寄ってきて、じっと俺を見上げるのだ。ほら、やっぱりペットみたい。
「寝てるかと思った」
わざと意地悪く言ってみると、マリーは慌てたように首を振った。
「待ってたの?」
黙って、小さくうなずく。その弱々しい仕草がどうしようもなく愚かしいので、とりあえずご褒美に抱き締めてやる。そうするとマリーは安心しきったように微笑んで、甘えるように体を預けてくる。子供の体温は妙に高くて、寒い冬にはちょうどいい。
「……おなかすいた」
くぐもった声で、マリーがつぶやく。そういえば、夕飯を与えていなかった。自分が済ませたのですっかり忘れていた。
「何も食べてなかったのか? お前、自分で作れるだろ」
「……シロの作ったものが食べたい」
「夜中に食うと太るぞ。パスタくらいしか作れないけど」
「それでいい」
「しかたないなぁ」
頭をくしゃりと撫でてやると、マリーは俺を見上げて、嬉しそうに目を細めた。そんな顔をされたら、こっちまで口元がゆるんでしまう。
――ああ、本当に、
ばかだなぁ、マリーは!
何でもできるはずなのに、俺がいないと何にもできない。食事も、買い物も、生きることだって俺任せ。ちょっと抱き締めるとすぐに喜んで、突き放したら泣き出しそうに顔を歪める。
桃色の唇を指でなぞったら、マリーは小さく口を開けた。血のように赤い舌が、ねっとりと俺の指を舐めていく。その、異常なくらい従順な仕草に、胸の中心がぶるりと震えた。
――当時の俺は、どうしようもなく愚かで、冷徹で、残忍だった。
マリーが俺に抱いている好意や、誠意や、依存心を、うまくうまく利用し、もてあそび、気まぐれに扱いたかった。時にはすべてを受け入れてみたり、わざと突き放して傷つけてみたり。この汚れを知らない少女の純情を、踏みにじりたかったのだ。
わずか十五分ほどで作り終えたパスタを、マリーは幸せそうに口に運んだ。テーブルの向かい側から、作り物のように整った顔立ちをじぃっと見つめる。火をつけたばかりの煙草を口から離すと、白い煙がふたりの間でゆらりと揺れた。
「お前、こんな遅くまで起きてて大丈夫か? 学校は?」
「おとといから、冬休み」
「……昨日もいた?」
「いた」
……全然気づかなかった。こいつ、部屋から出ないから。
パスタを食べ終えたら、マリーはさっさと洗い物と歯磨きを済ませ、ちょこんと俺の隣に腰かけた。真夜中のテレビ画面に映るのは、くだらないバラエティかつまらないニュースばかりだ。大あくびをすると、マリーにも眠気が移ったのか、大きな瞳をごしごしと手の甲でこすった。
「そろそろ寝るか」
テレビの電源を消して立ち上がると、マリーもふらふらと腰を浮かせる。リビングの電気を消そうとして、ふと、思いついた。
「一緒に寝る?」
マリーの顔がぱっと輝いた。素直すぎる反応を見て、喉の奥がくっくっと震える。
「うそ。ひとりで寝な」
咲きかけの花を摘むように、残酷に突き放す。そうすると思ったとおり、マリーの笑顔は波のように引いていった。
「……うん」
悲しそうにうつむくマリーを残して、俺はリビングの照明を落とした。
愛はいつも、順番待ち。
さみしがり屋のマリーにとって、それはどんなに苦痛だっただろう。そう、今となっては思う。だけど、マリーはわがまま一つ言わず、涙の一滴すら流さず、ただひたすら耐えてきたのだ。
マリーは、愛に飢えていた。
その飢餓感をおもちゃにするのは、呼吸をするように容易く、どんな映画を見るよりも楽しかった。好意を向けられるのは心地がいい。適度な束縛と、依存と、嫉妬と。それをうまい塩梅で与えてくれるのがマリーだった。自分は必要とされている。愛されている。愛を与えてくれる人間は数多くいたけれど、マリーはどの女とも違う。マリーには俺しかいないのだ。俺がいないと生きていけない、弱くて儚い少女。マリーは俺の自尊心を満たすのに、ちょうどいい存在だったのだ。
ベッドに横たわり眠りにつこうとしていると、きぃ、と部屋のドアが軋んだ。主人を求める猫のように、ひそやかな足音が近づいてくる。気づかないふりをして、背中を向けて眠っていたら、それは蛇のように布団の中に潜り込んできた。
「……どうした」
しかたなく振り向いて聞いてやる。マリーは布団に潜ったまま、熱いくらいの体温を、俺の体に押しつけてきた。
「眠れないの」
「……さみしがり屋」
嘲るように吐き捨てる。マリーは両腕を俺の腹にまわすと、甘えるように足を絡めてきた。体温は高いくせに、足先だけは妙に冷えている。布団の中で蠢くそれは、目の前にいる無邪気な子供とは違う、卑猥さを秘めているようで、少し背筋がぞっとした。
「子守唄、歌って」
そうやって、子供のふりをして。
マリーは無邪気に愛を求める。ばかだなぁ、と罵って、俺は要求に応えてやる。子守唄は決まって、スピッツの「ロビンソン」。一度、暇つぶしにギターを弾いてやったら、マリーはひどく気に入って、幾度となく俺に歌ってくれとせがむようになった。
マリーは今年で十八になる。だけど、小柄な体格と弱々しい性格から、十四歳くらいに見える。本当はたぶん俺が思っているよりずっと大人で、だけど俺に甘えたいから、子供のふりをしているのだ。胸の膨らみとか、すらりと伸びた足、とか。出会った頃より確実に、マリーは「女」に近づいている。それを、計算尽くの無邪気さで隠して、上手に上手に甘えてくるのだ。賢さと愚かさ。大人と子供。そのアンバランスさが、二面性が、時折、どうしようもなく気味悪く、おそろしいものに感じるのだった。
翌日は、インターホンの音で目が覚めた。気だるさを振り払って上半身を起こすと、隣で寝ていたはずのマリーがいない。冴えない頭をガリガリと掻いていると、寝室のドアが開いて、マリーがひょっこりと顔をのぞかせてきた。
「シロ、沢木さんが来た」
「沢木? ……何で」
「打ち合わせだって」
壁にかかった時計を見ると、ちょうど十三時を示している。……しまった、寝すぎた。あくびを押し殺しながら洗面所へと行き、洗顔と歯磨きを済ませる。伸びっぱなしの無精髭が目についたが、まぁ、今はこのままでいい。寝室に戻ると、ベッドの上に着替えが置かれていた。きっと、マリーが用意してくれたのだろう。スウェットを脱ぎ捨てて、セーターとズボンに着替えを済ませる。書斎のドアを開けると、ソファに座っていた男が、俺を見てあきれたように笑った。
「よくこんな時間まで寝られるなぁ!」
「……寝たのが遅かったんだ」
反対側のソファへ腰を下ろし、用意されていたコーヒーに口をつける。ちょうどいい加減に冷めていて飲みやすい。
沢木は大学時代からの友人で、今は小さな芸術系の出版社に勤めている。適度に仕事を与え、適度にサボらせることで、社会適合能力の低い俺をなんとか一端の「社会人」にまで引き上げようと健闘しているのだ。こいつがいなければ、俺はきっとありあまる親の財産に埋もれながら、今よりもっと自堕落な生活を送っていただろう。
打ち合わせなんてものはいつだって名ばかりで、大抵の時間は仕事の愚痴やくだらない話題に終始する。仕事のスケジュールなんて、別に電話やメールでも済むのだが、わざわざ家まで訪ねてくる理由はただ一つ――マリーだ。
「それにしても、ますますきれいになったなぁ、マリーちゃん」
……始まった。
俺はソファの背に体を預け、大げさに肩を落とした。身内を褒められるのは悪い気はしないが、打ち合わせの度に同じ言葉を聞かされると、いい加減鬱陶しくなってくる。
「もう十八歳だっけ? 一緒に暮らし始めた時はびっくりしたけど、案外なんとかなるもんだな」
「まぁ、手がかからないからな……」
「そりゃ、お前みたいな男と暮らせるくらいだからなぁ。高校卒業したら、どうすんの? もし就職するんなら、ファッション関係の知り合いに紹介してもいい? きっと気に入ると思うんだよなぁ」
「あいつにモデルなんかできるわけないだろ」
ふつふつと湧き上がる苛立ちを抑え込むように、俺はすっかりぬるくなったコーヒーを一気に飲み干した。マリーの進路なんて知らない。興味もないし、相談もされていない。あいつがどうしようが、俺には関係のないことだ。
「でも雑誌のモデルならしゃべんなくていいし。なんなら笑わなくてもいいしさぁ……お前がだめって言っても、本人がやりたがるかもしれないだろ」
「それは、ない」
「何で」
「あいつ、俺の言うことしか聞かないから」
「……何それ、主従関係?」
「そんなんじゃ、ねぇよ」
否定しようとしたその瞬間。
興奮に似た悪寒が、足の先から心臓まで、ぞわっ……と駆け上がっていくような感覚がした。慌てて沢木から顔を背け、右手で口元を覆う。こうしておかないと、この、愛とも欲ともつかない何かが、ぽろっと溢れてしまいそうだった。
そう、マリーは、俺の言うことしか聞かない。
――ああ、なんて、優越感!
沢木は俺の様子を不審に思うこともなく、諦めたように「まぁ、いいや」とつぶやいた。
「それよりお前、たまにはマリーちゃんをどっかに連れてってあげたりすれば?」
「は? 何で俺が」
「俺が見る限りいつも部屋にこもってるし、友だちとか少なそうだし……一応、お前、保護者だろ」
「保護者って言ったって、小学生じゃないんだぞ? 今更こんなおっさんと出かけたくないだろ」
「いやいやそんなことないって。だってあの子、お前にめちゃくちゃ懐いてるじゃん。たまには保護者らしいことしてやれよ。……おーい、マリーちゃん」
「あ、おい……!」
沢木は突然立ち上がると、書斎のドアを開けて大声でマリーを呼んだ。しばらくすると、マリーが警戒する猫のように、おずおずと姿を現した。
「クリスマス、四郎が遊んでくれるってさ。マリーちゃんの行きたいところ、どこでも連れてってくれるって」
そんなこと一言も言っていない。否定しようと立ち上がったら、「……ほんとに?」という、マリーのか細い声が聞こえた。
「ほんとだよ。俺がよーく言っといたから。クリスマスくらい、わがまま聞いてもらいなよ」
マリーは俺の顔色をうかがうように、ひょいっと沢木の後ろから顔を出す。困惑とわずかな期待が混じった瞳で俺を見る。なんだか否定するのも面倒になって、俺は再びソファに腰を下ろした。
「すきにしろよ」
途端に、マリーの顔にぱっと花が咲く。目を細めて、唇を弱く噛んで、うつむいて。そうやって、幸せを胸いっぱいに広げている。
「……ありがとう」
マリーの感謝の言葉を聞いて、沢木は満足そうにうなずいた。
クリスマスにふたりで出かける、とか。そんな、恋人同士のようにばかげたことを、マリーとするとは思わなかった。昼間は仕事が入っているが、いつも遊ぶ女たちは各々本命の男と過ごすため、夜の予定は何もない。俺とマリーが並んで街中を歩いていたら、周囲はどう思うだろうか。親子とも恋人とも取れない微妙な年齢差。なんてちぐはぐなのだろう。
俺たちは既存の枠にはあてはめることのできない、特殊な関係だった。血は繋がっているけれど親子ではない。一緒に暮らしているけれど恋人ではない。完璧な「家族」ではないから、最優先の存在ではない。マリーが何を考えているかなんて気にしたことは一度もないし、正直いなくてもかまわない。俺の人生は遊びで色濃く塗り潰されていて、そこに誰かが入る隙間なんて、はなから持ち合わせていなかった。
マリーはそう、例えて言うなら、砂糖菓子のようなもの。
食べなくても生きていける。でも、たまに食べたくなる。口さみしい時に噛み砕きたくなる。時には舌の上で転がして、溶けるのを待ってみたり。そうやって気紛れに味わいたくなる。別になくてもかまわないが、そこにあれば手を出してしまう。そんな、美しく作られた飾り物。
彼女の意思なんて関係ない。だって、マリーはここにいる。気が向いた時に名前を呼べば、マリーはすぐに駆け寄ってくる。邪魔な時は追い払えばいい。マリーが俺をどう思っているかなんて関係ない。家族愛でも性の対象でもどっちでもいい。俺にとってはいずれにせよ、都合のいい暇つぶしでしかないのだ。
クリスマスの天気予報は、最高気温五℃、夜は雪模様という、平凡なものだった。
「じゃあ、七時に駅な」
靴を履きながらマリーに言うと、彼女は素直にうなずいた。先ほど起きたばかりのため、髪の毛が四方八方に跳ねている。大きな瞳は半分ほどしか開いておらず、今にも倒れてしまいそうだ。どれだけ整った顔立ちをしていても、やはりこうしているとただの子供だ。そう考えたらおかしくて、無意識に白い頬に手が伸びた。マリーの肌は陶器のようになめらかで、綿菓子のようにやわらかい。途端に、マリーがびっくりしたように目を見開いた。どうしたの、とでも言うように、ちょっと首を傾げる。何をこんなに驚いているんだ、こいつは。そう考えて、すぐに、ああ、と答えを見つけた。こんな風に俺から触れること、めったにないからか。火照った頬をするりと撫でてやると、マリーは嬉しそうに、俺の手に小さな手を重ねた。
これ以上、甘やかしてはいけない。
愛を与えてはいけない。
自分を諌めるように手を引っ込め、俺は玄関のドアを開けた。
「じゃあな」
「……いってらっしゃい」
しつけをされた犬のように、マリーは俺を見送った。
沢木が編集を担当する「渓谷」という芸術専門誌で、あらゆる芸術家の記事を書き上げるのが、俺の仕事の一つだ。
今日の取材先は、八乙女佐里という画家だった。御年七十になるという彼女は、今まで誰の取材も受けたことがなく、ただひたすら表現することで己の信念、思想を伝えてきた、美術界の重鎮である。そんな人物がなぜ俺ごときの取材を受けようと思ったのか。それは、俺の祖父に起因する。
「幻想的な絵ですね」
アトリエに並べられた八乙女氏の作品を眺めると、思わず単刀直入な感想が口から漏れた。
「気味が悪いっておっしゃる方もいますわ」
口元を隠して、ふふ、と笑う。現代には似合わない、上品な仕草だ。
気味が悪い。その感想は俺が伝えたものよりも直球に彼女の絵を表しているのかもしれない。作品にはどれも黒髪の少女が描かれているが、それはただの人物画ではなく、ある時は少女の下半身が枝葉となっていたり、またある時は内臓が花弁のように飛び散っていたりと、グロテスクかつエロティックな雰囲気を醸し出していた。幻想的、と言ってみたものの、少々オブラートに包みすぎた表現だったかもしれない。
「なぜ少女をこのようにお描きになるんですか?」
「さぁ、特に理由はないのです。いつの間にかこうなっていたというか……」
八乙女氏はぼんやりと答えた。なんだか、思ったよりふわふわした婆さんだな。こんなグロテスクな絵、本能で描いているとしたら相当イカれてるぞ。
「この少女にモデルはいるんですか?」
「そうですね、おそらくりっちゃんだと思います」
「りっちゃん?」
「ええ。わたくしのご近所に住んでいたお姉さんで、それはもうお人形さんのように美しくて、愛らしくて……。わたくしは彼女がうらやましかったのです」
「……なぜ、彼女を?」
「わたくしもはっきりとは分からないんですが、そうですね……」
八乙女氏は銀色のおくれ毛を指でくるくると弄り回しながら、小首を傾げた。それから穏やかに微笑むと、
「美しいものって、汚したくなるじゃないですか」
「……なるほど」
俺は持っていたカメラを構え、ファインダーをのぞき込んだ。四角い世界に、死んだように眠る少女の首が横たわる。美しいもの。汚れのないもの。この世に完璧なものなんてないからこそ、それらを自らの手で壊したくなるのかもしれない。まばたきをするたびに、なぜか目蓋の裏にマリーがちらついた。純粋無垢なその姿をかき消すように、俺はカメラのシャッターを押した。
玄関のドアを開くと、冷たい風が頬をぴりぴりと刺激した。いつの間にか日は暮れて、黒々とした雲が今にもはち切れそうに空を覆っている。ああ、もうすぐ雪が降る。
「ありがとうございました。すみません、長々と……」
「いいえ。橘劉生さんのお孫さんに取材に来ていただけるなんて、ありがたいことですよ」
祖父の名前を出され、俺は苦く笑った。橘劉生は、芸術界に生きる人間なら知らない者はいないほど有名な彫刻家だった。八十年の生涯で三百以上の作品を創り、日本のみならず世界的な賞まで数多く受賞した、近代美術における巨匠。
要するに、俺がこうして数多くの重鎮を取材できるのは、祖父のおかげというわけだ。どんな芸術家も祖父の名を出せば途端に態度が豹変し、他の雑誌には伝えない情報を次から次へと教えてくれる。「橘劉生の孫」に取材されるということは、芸術家たちにとって名誉であり、また、俺自身にも利益があるというわけだ。
「そうだ、よろしければこれから夕飯をご一緒しませんか? 近くに行きつけの小料理屋さんがあるんです。日本画家の林正親さんとか、野村美紀さんも時々いらっしゃるんですよ」
「そんな方たちが?」
有名な芸術家たちの名前を聞き、驚いた。名前はもちろん知ってはいるものの、実際にお目にかかったことは一度もない。左手首に巻いてある時計をちらりと見た。十八時。少し待たせるかもしれないが、まあ問題はないだろう。程々で切り上げればいい。
「はい、ぜひ」
俺の返事を聞くと、八乙女氏は嬉しそうに目を細めた。
食事会は思いのほか盛り上がり、なんと幸運なことに林正親にも会うことができた。元々仕事意欲があるわけではないが、一応これでも芸術家の孫だ。昔からいやというほど見てきた作品の作者と酒を交わすことができるとくれば、興奮もやむを得ないだろう。酒は進み、それと同時に時間も過ぎる。一時間くらいで切り上げよう、などという考えはすぐになくなり、気軽な食事会は気づけば本格的な取材と化し、最後には固く握手を交わすまでとなった。
――マリーが、待っている。
そのことを思い出したのは、家に帰り荷物を置き、煙草を一本吸い終わった頃のこと。壁にかけてある時計が、二十三時を示していた。ああ、そういえば、十九時に待ち合わせをしていたんだった。酒のせいで頭がまわらない。マリーの部屋をのぞいてみたが、しんとした暗闇が広がるだけで、人の気配はなかった。
……もしかしてまだ駅にいるのか?
ありえない、と言い切れないのがおそろしい。もう四時間以上も過ぎているのに。普通だったら帰るだろ。機転を利かせるということを知らないのだろうか、あいつは。短くなった煙草を灰皿に押しつけて、俺は家を出ることにした。
大通りでタクシーを拾い、マリーと待ち合わせをした駅へと向かった。クリスマスの夜は心なしか普段より明るく、街も眠る気配はない。きらきらと輝くイルミネーションは地上に落ちた星のようで、疲れた両目には眩しすぎた。
タクシーを降りてマリーを探した。空から降ってくる粉雪がちらちらと視界を邪魔して鬱陶しい。はしゃぐ人混みに目を凝らしながら進んでいくと、遠くの方で、見覚えのある長い髪がふわりと揺れた。腰まであるウェーブした亜麻色の髪。引き寄せられるように近づいていくと、その隣に、知らない男が立っていた。動かしていた足が徐々にスピードを落とし、やがてとまった。
マリーは楽しそうに笑っていた。一体何を話しているのか。男が身振り手振りを添えて伝える話にうなずいている。よく知っているはずの少女は、まったく知らない顔をしていた。
その笑顔を見た瞬間、周囲から聞こえる騒音が、突然静寂に変わったような錯覚に陥った。小雪が降り積もるクリスマスイブ。楽しげな会話も、心揺るがすBGMも、もう耳には入ってこない。
俺はマリーに背を向けて、早足でその場を離れた。目を背ける瞬間、マリーの青い瞳が俺を捉えた、ような気がした。
どれだけ煙草に火をつけても、荒波のような心は一向に落ち着く気配がない。二度目の帰宅をしてもまだ眠る気にはなれず、こうして電気もつけずにリビングのソファに腰かけている。気を紛らわせようとテレビをつけてみたものの、ちっとも内容が入ってこない。さっきの光景がちらついて、バラエティとニュースの見分けがつかない。見知らぬ男と笑う、楽しそうなマリー。ああ、なんだかいらいらする。
深まった夜を妨害するように、玄関から物音がした。いつものように、遠慮がちにリビングのドアが開く。
「……シロ」
おそれているような、怯えているような、小さな声が耳に届く。俺は聞こえないふりをする。一歩一歩、確かめるように近づきながら、俺が振り向くのを待っている。いつもと同じだ。弱虫で、さみしがり屋で、俺の顔色ばかりをうかがっている、いつもどおりのマリーだ。
「……ずいぶん楽しそうだったな」
煙草の火を灰皿に押しつけ、怒りをぶつけるように吐き捨てた。肩越しに振り向いたら、マリーの白い肌が幽霊のように浮かび上がっていた。
「あいつ、誰?」
「……クラスメイト」
「あいつと朝まで遊んでもらえば? 俺といるよりずっと楽しめるだろ」
「違うの、たまたま会っただけ。わたしはシロと……」
「もうやめろよそういうの!」
体の中で何かが弾けた。俺は衝動的に手元にあったコップを思い切り床に叩きつけた。金切り声のような音を立てて、透明なガラスが粉々に砕ける。一度大声を出したら胸の奥に抑えていた怒りと苛立ちが堰を切ったように溢れ出して、気づけばソファから立ち上がっていた。
「ほんとは俺に飽き飽きしてるんだろ? 今だってほんとは怒ってるんだろ? 何で俺を責めないんだよ。いつもいつも泣きそうな顔して何も言わない。言いたいことがあるなら言えよ。そういうところがいらいらするんだよ!」
マリーの顔はみるみるうちに青ざめていった。大きな瞳がどんどん潤んでいく。それでも涙をこぼすまいと、ぐっと唇を噛み締めて、小さな肩を震わせている。いつもそうだ。こいつは俺の前では絶対泣かない。
泣いてしまえばいいのに。「ごめんなさい」と謝って、「きらわないで」と抱きついて、そうやって俺に縋ればいい。だってマリーは、弱いから。弱くて、さみしがり屋で、俺がいないと生きていけない。マリーとは、「そういうもの」だ。
「……お前、もう十八だろ。もう立派な大人だよ。俺が世話しなくても生きていけるだろ」
「シロ……」
「出ていけよ」
マリーを拒むように、背中を向けて吐き捨てた。
「早く出てけよ!」
しん、と、部屋が黙り込んだ。どっぷりと更けた夜が部屋中に染み渡ってきたように、家具も、つけているはずのテレビさえも、もう何も発さない。
やがて、小さな足音がゆっくりと俺から遠ざかっていった。パタン、と微かな音を立て、リビングのドアが閉まった。
再びひとりになった俺は、全身の力が抜けたように、どかりとソファに腰を落とした。肺にある空気をすべて吐き出して、両手で頭を抱え込む。
目蓋を閉じたら、先ほど駅で見たマリーの笑顔が、ぼんやりと浮かび上がってきた。あんな顔、俺に向けたことは一度もないのに。それを見ず知らずの男に向けていたことが、なぜだか無性に腹が立った。
マリーのことは何でも知っていると思っていた。猫のようにくるりとした髪も、雪のような肌も、熱いくらいの体温も。知らないことなどないと思っていた。マリーには俺しかいない。そう、思っていた。
だからこそ、俺は苛立ったのだ。マリーは雪の降る夜に、全身を震わせながら俺を待っていなければならなかった。俺を見てぱっと目を輝かせ、主人を見つけた犬のように駆け寄ってこなければならなかった。悪いな、待たせて。寒かっただろう。そんな俺の心のこもっていない謝罪に、ううん、と健気に首を振る。それが、俺の知っている「マリー」のすべてだ。
――その日を境に、マリーは俺の前から姿を消した。
そう、マリーは俺の言うことは何でも聞くのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

