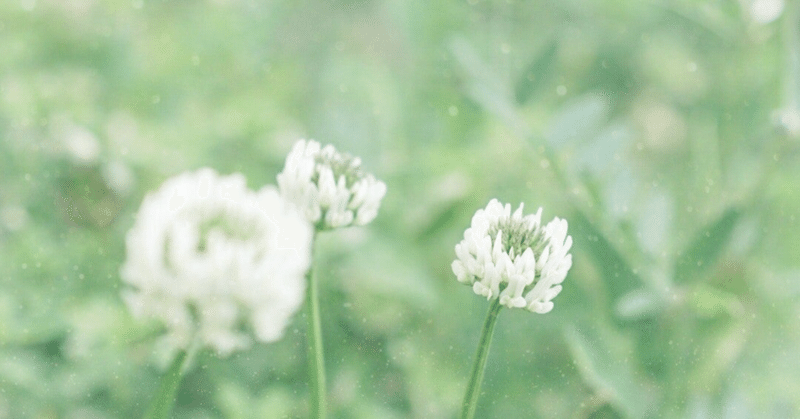
「マリーについて」第2話
「そっかぁ……結局、登坂くんのところからもいなくなっちゃったんだ……」
健人の話を聞き終えた美鈴は、さみしげに肩を落とした。四郎は考え込むように、テーブルの一点を見つめて黙り込んでいる。
「結局、マリーのことはあんまり知れなかったんですけどね。涙の意味も、笑顔の理由も。どうして俺の前からいなくなっちゃったのかも、まだよく分からないし……」
健人は悲しみを紛らわせるようにむりやり笑顔を作った。乾いた笑い声は喫茶店のBGMに紛れて、ふたりの耳にはうまく届かない。
マリーがいなくなった朝、健人は必死に彼女の姿を探した。「帰る場所がない」と言ったマリーに行くあてなどあるはずがない、そう思ったからだ。しかしマリーを見つけることはできず、キャンパスで歌を歌い続けても、マリーが現れることは二度となかった。彼女がどこから来たのか、どこへ行ったのか。それを理解するには、マリーについて知っていることが、あまりにも少なすぎたのだ。
「そうだ、これ」
健人は思い出したようにカバンからCDを取り出し、四郎に差し出した。
「これは?」
「マリーのために作った歌です。あの時は途中までしかできてなかったけど、完成したから。もしマリーに会えたら、渡してもらえますか」
四郎は一瞬ためらったあと、「……分かった」と小さくうなずいた。健人から受け取ったCDを、そっとカバンにしまう。健人はほっとしたように微笑んだ。
「本当、後悔ばっかりですよ。今考えると、俺は本当のマリーを見てあげられなかったんじゃないかなって。天使みたいなマリーも、普通の女の子みたいなマリーも、どちらもすきになったつもりだったけど、やっぱり最初の印象って強烈だから消えなくて。そういう考えが、マリーに伝わっちゃってたのかなって思ったんです。マリーはそれがいやだったのかなって。ちゃんと彼女自身を見てあげてたら、もっとできることがあったんじゃないかなーって……」
「ううん、君は最大限のことをしてあげたと思うよ。私なんて、マリーのために何もしてあげられなかった。一つ屋根の下に住んでたくせにね……」
「えっ、マリーと一緒に暮らしてたんですか?」
「うん、そう。……って言っても、ほんの三ヶ月だけど」
美鈴はへへ、と照れくさそうに笑って、残りのアイスコーヒーをストローで一気に飲み干した。すいませーん、と近くの店員を呼びとめて、おかわりを注文する。
「あなたたちはいいの?」
美鈴から問いかけられ、健人と四郎は同時に首を振った。ずっと話していたせいで、健人のアイスコーヒーはまだ半分も減っていない。四郎は四郎で、開いたノートにメモを取ることに真剣で、喉の乾きを感じる暇もなかったのだ。
「園原さんからも聞かせてもらえますか」
四郎は再びペンを取ると、健人から美鈴に視線を移した。
「あなたが知っている、マリーについて」
しっかり者のマリー
マリーについて私が知っていることはほんの少しだ。記憶の中のマリーはいつだって健気で、一生懸命で、優しくて、そして気配り屋だった。出会った時は少しでも目を離したら死んでしまいそうなほど弱々しかったけれど、一緒に過ごす時間が長くなるにつれて、しっかりした面があるってことに気づいたの。
マリーと出会ったのは、去年の十二月二十五日。忘れもしない、クリスマス本番。
世の中はホワイトクリスマスで浮かれモードだっていうのに、仕事以外特に予定もない私は、職場の同僚と飲んだ帰りに、ふらふらとひとりで駅前を歩いていた。暗い空から降る雪が花柄の傘をどんどん湿らせていくし、冷たい風はみるみるうちに体温を奪っていく。そんな心まで凍えそうな夜にね、ひとりの女の子を見つけたの。
深夜0時をまわった頃かな。終電から降りた直後だから、たぶんそのくらいだったと思う。シャッターの閉まった店の前で、フランス人形みたいにきれいな女の子が、膝を抱えて座っていた。暗闇でも分かるくらい、彼女の顔は真っ青だった。かわいそうに、寒さで小刻みに震えている。
都会って冷たいやつらばっかりで、こんなにかわいい子が震えているのに手を差し伸べる人なんてひとりもいないのね。もしかしたら、ただの家出少女って思われてたのかもしれない。私は元々かわいい女の子がだいすきだし、それにその清楚な身なりから、不良娘にも見えなかったので、迷わず彼女に近づいていった。
「ねぇ、大丈夫?」
話しかけると、彼女はうつろな瞳で私を見上げた。その時にね、あ、この子、宝石みたいにきれいな目をしてるって思ったの。仕事上、きれいな女の子は星の数ほど見るけれど、その子たちとはなんていうか、毛色が違う。どんなに暗くても分かる。この子、擦れていないというか、汚れていないっていうか、純度百パーセントの水みたいな、そんな透明感があった。彼女は怯えたように黙り込んで答えない。うーん、どうしたものか。私はきょろきょろと辺りを見渡して、「ちょっと待ってて」と彼女に言い残した。自販機に全力ダッシュして、ココアと、ミルクティーと、お茶と、ホットレモンを購入する。
「はい!」
私は彼女の元へと戻って、ありったけの飲み物を差し出した。
「寒いでしょ。ほら、すきなもの飲みな!」
彼女は警戒心を胸に抱き締めたまま受け取ろうとはしない。ホットレモンの蓋を開けて、ほら、と強引に押しつけたら、彼女はおそるおそる手を差し伸べ、遠慮がちに口をつけた。一体いつから飲まず食わずだったのか、と思うくらい、ごくごくと一気に飲み干す。私はしゃがみ込んで、彼女と目の高さを合わせた。
「あなた、いつからここにいるの? 行くところはある?」
彼女はペットボトルを小さな手で包んだまま、やっぱり何も答えてくれない。こういう場合、警察に連れてった方がいいのかな。でも、警察ってなんだか信頼できないなぁ。私はうーんと考えたあと、そうだ、と両手を合わせた。
「よかったら、うちにおいで」
駅から歩いて数分のところにある五階建てのマンション、そこの三階角部屋。誰かを招くことなんてめったにないこの部屋に、突然こんなにかわいい女の子が来るなんて。自分で誘っておいてなんだけどさ、ちょっと信じられないよね。そして、大人しくついてきてくれたことにもびっくりよ。
「適当に座って。すぐお風呂入れるから」
暖房をオンにすると同時に電気ケトルでお湯を沸かし、浴槽の蛇口を捻って部屋に戻る。
「寒いでしょ。これ、羽織って」
カーディガンを肩にかけてあげる。彼女はまだこちらを見ない。深く傷ついた捨て猫のように、ぶるぶる震えて目を伏せている。よっぽど辛い思いをしたのかな。誰も信用していないような、そんな様子だ。私はふたり分のミルクティーを用意して、彼女の反対側に腰かけた。
「私、園原美鈴。とある広告系の会社でカメラマンやってるの。カメラマンって言っても事務作業がほとんどで、たまーに現場で写真を撮ったりするだけなんだけどね。本当はフリーでやっていきたいんだけど、なかなかそうもいかなくてさぁ。十八の時に上京してきて、かれこれ十年以上ひとり暮らし。あ、年は聞かないで、傷つくから。もしあなたが行き場に困っているなら、いくらでもここにいてくれてかまわないわ。仕事があるからひとりにさせちゃうかもしれないけど、うちのものは自由に使ってくれていいから。はい、次、あなたの番!」
一気にこれだけしゃべって強引にバトンを渡すと、彼女はあっけにとられたようにマグカップを持ったまま固まった。いけない、ついついしゃべりすぎちゃった。もしかして、ドン引きしてる? ちょっと心配になったけれど、ここで怯んでなるものか。脅迫するようにじっと見つめると、彼女は観念したように「……マリー」とつぶやいた。
「マリー? それがあなたの名前?」
肯定も否定もしない。たぶん、それが答えなんだろう。マリー。日本人らしくない名前だけれど、もしかしてハーフかな。目鼻立ちがはっきりしているし、肌も透けるように白いし、何よりこの青い瞳。うん、なんだかそんな気がする。
聞きたいことが、むくむくと心の中で芽吹いてくる。どこから来たの。年はいくつなの。どうしてあんなところにいたの。だけどそれを聞いてしまったら、今のマリーにとっては尋問になるだろう。そう思ったので、今はやめた。
「これからよろしくね、マリー」
安心させるように微笑んで、手を差し伸べる。マリーは遠慮がちに、だけどしっかり、その手をつかんでくれた。とりあえず、この冷えた手を早くあっためてあげなくちゃ。
翌朝。いつものように七時のアラームで目を覚ますと、わたしのベッドに超絶美しい女の子が眠っていて度肝を抜いた。何だっけ、昨日、どうしたんだっけ。一瞬頭の中がパニックになったけれど、すぐに昨晩の出来事を思い出して、ああ、と納得した。
そうだ。昨日マリーと出会ったんだ。寝ぼけた頭で理解して、会社に行くため身支度を整える。お金と、鍵と、それと簡単なメモを残してから、マリーの寝顔をのぞき込んだ。
私はかわいい女の子がすきだ。女の子の笑った顔とか、幸せそうな顔を見るのがだいすきだ。女の子を撮るために写真を始めたようなもん。むずむずと好奇心が疼いて、愛用の一眼レフをカバンから取り出す。ファインダーをのぞき込んだ、瞬間。
マリーの頬に涙が伝っていることに気がついた。
「――ロ……」
何と言ったのかは聞き取れない。誰かの名前だろうか。縋るようなその声に、なぜだかぎゅうっと胸の奥が締めつけられた。
私はカメラを下ろし、そのまま仕事へと向かうことにした。
今日の仕事は、とあるアルバイトの体験レポートを作成するというものだった。かわいいモデルさんにウェイトレス姿になってもらい、アルバイト業務を行っている風の写真を何枚も撮る。ライターさんがそれっぽい文章を載せれば、立派な体験記のできあがり。現場は、最近できたばかりのおしゃれなカフェ。今日撮影するのは私ではなく、後輩の北村くんだ。店長の指示を受けてうなずいているモデルさんを見てにやにやしている。こういうところまで私に似なくてもいいのに。
「いや、あの子かわいいっす。めちゃめちゃタイプっす」
「うん、そうだねぇ……」
「どうしたんすか。いつも俺より興奮して女の子を見るくせに」
言い方に語弊があるが、今の私には突っ込む気も起きない。目の前にいる女の子も確かにかわいい。私の一億倍くらいかわいい。きらきらしていて、なんというか、女子力に満ちている。でも、なんか違う。マリーはもっとこう、ただかわいいだけじゃなくて、きれいだけどどこかさみしげで、危ういくらいの儚さがあるのだ。少しの刺激ですぐに消えてしまうしゃぼん玉のような、尊さがあるのだ。
「ねぇ、北村くん」
「はい?」
「私、女の子拾った」
「……は? 何すかそれ」
北村くんは怪訝そうに眉をひそめた。
「拾ったって、家出少女的な?」
「うーん、そうなのかな。そうかもしれないけど、そうじゃないかも……」
「何にも知らないってこと? それ、やばいっすよ。その子、もしかして今も美鈴さんちにいるの? 貴重品とか盗られてるかもしれないよ」
「そんなことするような子には見えなかったけどなぁ……かわいいし」
「いやいやいや、かわいくてもアブないやつはいるし、逆にブスでも超性格いいやつはいるの! 家に帰ったらもぬけの殻かもしれないっすよ。もしいたとしても絶対関わらない方がいいですから。俺の知り合いにいますもん。美人局みたいなのに引っかかったやつ……」
「美人局ぇ? 何よそれ、どこの世界よ」
私は思わずぷっと吹き出した。もしそうなら、とんだ美人局がいたものだ。あんなに小さくかわいらしい女の子になら、ハメられても悪くないかも。笑いごとじゃないっすよぉ、と、なぜか北村くんが泣き出しそうな顔をする。どうやら本気で心配してくれてるらしい。まったく、かわいらしい後輩だこと。
「とにかく、ちゃんと警察に引き渡すこと。家族が捜索願出してるかもしれないんですからね!」
「そっかぁ……そうだよねぇ」
いつになく真面目な北村くんの話を聞いていたら、なんだかどんどん不安になってきた。確かに、ライトノベルじゃあるまいし、突然見た目も中身も百点の美少女と出会うなんて、あまりにもできすぎた話だ。帰ったらいなくなってるかもしれないなぁ。別に、盗られて困るものなんて何にもないけれど。いなくなってたら、少しさみしいな。マリーについて、まだ何も知らないから。
仕事を早めに切り上げた私は、コンビニでカップヌードルをまとめ買いしてからマンションに戻った。カバンの中をまさぐって、おや、と首を傾げる。鍵がない。どこにやったんだっけ、と記憶を辿って、すぐに思い出した。ああ、そうだ。鍵はテーブルの上に置いてきたんだっけ。玄関を開けると、見慣れない靴が一足あった。いつも真っ暗なはずの部屋は眩しいくらい明るくて、あったかい。――マリーがいるんだ。わたしはこみ上げてくる喜びを、ぐっと歯を食いしばって押し込んだ。どうしよう、顔がにやける。
「ただいまぁ!」
必要以上に声を張り上げてリビングに飛び込む。予想どおり、そこには天使のような女の子が、ソファにぽつんと座っていた。
「……おかえりなさい」
ぎこちなく、でもしっかりと私の目を見る。昨日よりは顔色がいい。用意していた私の服もちゃんと着ている。机の上に置いていたお金がない。ということは、ご飯もちゃんと食べたみたいだ。ほっと胸を撫で下ろす。と、同時に、部屋の中がきれいに片づいていることに気がついた。
「あれっ、私の部屋、こんなんだったっけ……?」
カーテンレールに干しっぱなしだった洗濯物とか、床にまき散らした写真とか、机の上に放置していたカップ焼きそばが、きれいさっぱり消えている。まるで、私の部屋じゃないみたい。マリーは少し怯えたように、「……片づけた」とつぶやいた。
私は思わず持っていたカバンを床に落とした。ドスン、と鈍い音が鳴る。ああ、なんということでしょう。ねぇ、北村くん。いたよ、天使はここにいた。
「ありがとう、そんな気遣わなくていいのに! あっ、ご飯ちゃんと食べた? お金、用意してたので足りた?」
「シチュー作った」
「へっ?」
予想外の言葉を聞いて、素っ頓狂な声が出た。マリーは黙ったまま、じっと膝を抱えている。もしや、と思いキッチンを見ると、コンロの上に、めったに使わない鍋が置かれていた。おそるおそる蓋を開けてみると、そこにあったのは、じっくりコトコト煮込んだシチューだった。
私が渡したなけなしのお金で、この子はこんなものを作っていたのか。愛しさと感謝が体の底からこみ上げてくる。抱き締めたい衝動をなんとか堪えて、天使が作ったシチューをあたため直す。
手料理を食べるのも、誰かと向かい合って食べることも、一体いつ以来だろう。もう、昔すぎて覚えてないや。
「……おいしい。すっごくおいしい!」
素直な感想を口にすると、マリーは心なしか、ほっとしたように表情をゆるめた。
「マリーって料理上手なのね。普段からよくするの?」
「……必要な時だけ。あんまり、作らないようにしてた」
――作らないように「してた」?
ちょっとだけ気になったけれど、あまり問い詰めるのもよくないか。昨日よりだいぶ顔色はよくなったけれど、やっぱり声は小さいし、せっかく作ったシチューもちょっとしか食べ進めていない。体力的というより、精神的な疲れがたまっているんだろうな。
それにしても意外なのは、掃除と料理をしてくれたことだ。人間離れした美しさを持っているから、生活感なんてまったくなかったのに。やだ、この子。あんなに捨てられた子猫みたいだったくせに、私より生活力あるじゃない。何なの、そのギャップ。
最高に謎めいていて、最高に魅力的。
「……わたし、明日出ていく」
シチューを食べ終えたあと。マリーが漏らした言葉に、私は飲んでいたお茶を吹き出しそうになった。
「えっ? 何で? 行くところあるの?」
「ない、けど。何も返せないから……」
マリーは恐縮したように肩を縮めた。私は手の甲で口元を拭い、観察するように彼女を眺めた。
雪のように白い肌。宝石のように青い瞳。きらめくような亜麻色の髪。こんなにきれいで、神々しくて、なんというか、「普通」じゃない雰囲気をまとっているのにさ、考え方がびっくりするくらい常識的なのね。だってさぁ、私、思うんだけど、かわいい子って何しても許されるじゃない。多少わがままでも、頭が悪くても、美しさに甘えていられるっていうか。それなのにマリーってば、こんなにしっかりしてるんだもん。だって、昨日会ったばかりの女のために、掃除と料理までしてくれるのよ。真面目というか、いい子っていうか……きっと、頭の中でいろいろ考えちゃうタイプなんだなぁ。
私はうーんと唸ってから、「じゃあ、こんなのは?」と提案した。
「昨日もちょっと言ったけど、私、写真がすきなの。だから、練習用のモデルになってくれない?」
「モデル……?」
「別に、難しく考えなくていいの。ポージングなんてしなくていい。ただ、写真に撮られるだけ。どう?」
マリーは戸惑ったように目を逸らした。長いまつげの影すら、品があるなぁと、ごく自然に思った。こんなきれいな女の子をそばに置いておけたら、男は幸せだろうな。彼女はしばらく考えたあと、観念したように「……分かった」とうなずいた。
「ほんと? やったー! じゃあ、早速明日撮りにいこう。どこがいい? どこか行きたいところとかある?」
「……有楽町の、イルミネーション」
「えっ? イルミネーション?」
明確な答えが出てきたことに驚いた。イルミネーション、かぁ。確かにきれいだろうけれど、クリスマスは昨日終わってしまった。東京ってものすごく切り替えが早いから、もしかしたら、もう撤去されてしまっているかも。クリスマスが終わればお正月、それが終わればバレンタイン。季節に応じてころころと街の景色は変わる。そういうものなのだ。
「イルミネーションが見たいなら、他の場所もあるよ? 恵比寿とか……」
「……有楽町がいい」
マリーは小さく、だけどはっきりと主張する。もしかして、思い出の場所なのだろうか。私は腕を組んで考えたあと、「分かった」とうなずいた。
「じゃあ行ってみよう。それに、マリーの服も買わなきゃね。私のじゃちょっと大きいし」
ぶかぶかの私の服を着ているマリーは、ちょっと照れくさそうに微笑んだ。
翌日、私は愛用のカメラを首から下げて、マリーとともに有楽町へと向かった。途中でマリーに似合う服を何着か購入し、百貨店で軽くメイクをしてもらった。やっぱりいくら素材がよくても、撮影の時はおめかししなくちゃね。そうしたら、マリーはますますきらめいて、本物の天使みたいにより一層美しくなった。
「やっぱりイルミネーションはもう終わっちゃってるねぇ」
目的地にたどり着くと、案の定、おとといまであったはずのクリスマス・イルミネーションは跡形もなく撤去されていて、普段と何ら変わりない街並みが広がっていた。たった二日しか経っていないのに、もう街には年末モードが漂っている。そういえば、さっきの百貨店でもおせち料理とか、お正月の飾り物がたくさん売っていたなぁ。その日が終わればすぐ次の行事、って、日本人って結構薄情よね。ま、どこの国でも共通か、そんなのは。
「なんだか雑然としてるなぁ。もっといい場所知ってるから、そっちに……」
その場を離れようとした私とは反対に、マリーはふらふらと、イルミネーションが撤去された枯れ木の前に歩いていった。もうそこには何もないのに。マリーは私の方を振り向くと、
「……ここで、撮って」
弱々しい、でも強い口調だった。その、形容しがたい威圧感に気圧されて、気づいたらカメラを構えていた。
ファインダー越しに見る彼女は、抱えきれない悲しみを溢れさせているようだった。何かを訴えるように。誰かを責めるように。さみしげなその瞳は、きっと私じゃない誰かを見つめている。
ねぇ、マリー。あなたにそんな顔をさせるのは誰? どうしてあなたは、雪の街で震えていたの?
もっと距離が縮まれば、いつか話してくれるだろうか。彼女の悲しみを少しでも減らすことができたなら。このさみしげな瞳も、悲しげに揺れる髪も、全部幸せな笑顔にすり替えることができるだろうか。
――マリー、笑って。
心の中で叫びながら、私はカメラのシャッターを切った。
次の出勤日。
私は職場のパソコンで、先日撮ったマリーの写真を眺めていた。木のそばに佇むマリー。空を見上げるマリー。ランチを食べるマリー。どれもこれも美しいけれど、笑顔の写真は一つもない。ここにいない誰かを想うみたいに、虚空を見つめているものばかり。あのあと、写真を見せたら、マリーはちょっとだけ嬉しそうに目を細めた。そして小さく、「……よかった」とつぶやいたのだ。「よかった」って一体どういう意味なんだろう。きれいに撮れていて「よかった」ってことかな。それとも、写真を撮ってもらえて「よかった」?
結局笑ってくれたのはその時だけで、慣れない撮影に疲れ果てたのか、家に戻るとマリーは泥のように眠った。長いまつげを濡らして、聞き取れないくらいの微かな声で、誰かの名前を呼んでいる。あんなかわいい子を苦しませるなんて、一体どこのどいつだろう。もし見つけたらぶん殴ってやりたい。
「何見てるんです、美鈴さん」
隣の席の北村くんが、ひょいっと写真をのぞき込んできた。
「うわ、超美少女。どこの天使?」
「うちの天使。どうだ、美しいだろう」
「うちの、って……もしかして、この間言ってた例の家出少女? 結局かくまっちゃってるの? どうするんですか、事件とかに巻き込まれてたら」
「いや、そういうんじゃないよ」
「何で分かるんですか」
「うーん、そうだなぁ……女の勘」
「何それ。適当すぎ」
北村くんはあきれたように息を吐く。入社当初は初々しい後輩だったのに、最近態度がどんどん大きくなっていって、今ではたまにばかにしたような眼差しを私に向ける。最初は無性にいらっとしたけれど、言うだけむだだ、ということを理解してからは、頭を思い切り叩くことにしている。北村くんはいてっ、と大げさに頭を押さえながら、まじまじとパソコン画面を見つめた。
「かわいいっていうより、きれいな子っすね。でもかなり幼いなぁ。十四歳くらい?」
「そういや聞いてないなぁ。未成年だとは思うんだけどさ、見た目のわりにしっかりしてて、毎日ご飯作ったり洗濯したりしてくれるのよ。こっちが申し訳なくなるくらい」
「えっ、うらやましすぎるんですけどー」
ふたりでマリーの話に花を咲かせていたら、突然、視界に影が落ちた。振り返ると、上司の清水さんがじぃっと私のパソコンを凝視している。眼鏡の奥にある細い目をさらに細めているから、悪人面に拍車がかかっていて、かなりこわい。
あれだけおしゃべりだった北村くんが、突然ぐっと唇を結んで、ゆっくりと自分のデスクに戻っていく。私のことは舐めきっていても、清水さんのことはまだこわいらしい。清水さんはじぃーっとマリーを見つめたあと、
「園原、そのデータ何枚かちょうだい」
「え? 何に使うんですか」
「別に、何も……見たいだけ」
私の返事を聞く前に、すぅーっと足音を立てずに自分のデスクに戻っていく。まぁ、使わないならいいか。私はしぶしぶマリーの写真をメールに添付した。
それからというもの、私は定期的にマリーを写真におさめるようになった。仕事がある日にかまってあげられない分、休みの日は必ずマリーを外へ連れ出した。そのたびに新しい服を買い与えて、メイクもして、景色のきれいな場所に連れていってやる。そうしているうちに、マリーの表情は少しずつやわらかくなっていった。何気ない会話が増えて、一歩ずつ距離が縮まっていった。
だけどマリーはいつまで経っても、自分のことは一切話そうとしなかった。年齢も、住所も、あの夜何があったのかも。少し踏み込もうとすると、さっきまでの笑みは消え、すぐに私から離れていく。だから私も諦めて、マリーに何かを尋ねることはなくなった。私がそうしているからこそ、マリーも安心して一緒にいてくれたのだろう。今となっては、そう思う。
そして、マリーについて知らないことが多ければ多いほど、その美しさは神秘の色をまとうのだ。神聖で、不可侵で、何色にも染まらないまっさらな少女。それが、私にとってのマリーだった。そのイメージを汚したくなかったのだ、きっと。
それはマリーと出会って一ヶ月ほど経ったある日のこと。
「もうちょっと遠出したいなぁ」
こたつで丸くなりながらぽつりとつぶやくと、キッチンにいたマリーが振り返った。今日もマリーは甲斐甲斐しく、私のために肉じゃがを作ってくれている。あれから料理の腕もめきめき上達して、いつ嫁に出しても恥ずかしくないくらいだ。いや、出さないけど。
「近場の雰囲気あるところは結構行ったしさ。もうちょっと別の場所で撮りたいなぁって。横浜とか、鎌倉とか……って言っても、こうも寒いと遠出するにはちょっとねぇ……」
テレビから流れる天気予報は、今日も「今季一番の寒さ」を私たちに伝えている。室内での撮影もいいけれど、できれば雑然とした風景の中で撮りたい。何気ない日常の中でこそ、彼女の神々しさが引き立つ気がする。私はごろりとテーブルに頬をつけてマリーを眺めた。
あれほど神秘的な雰囲気をまとっているのに、今は普通の女の子みたいに、キッチンで料理を作っている。もちろん十分かわいいんだけど、やっぱりこの子は、写真に撮られるからこそ味が出る。しっかり者のマリー。それはものすごく庶民的で、親しみやすいけれど。でもね、私は、それじゃ満足しないのよ。
「マリーは、写真撮られるの楽しい?」
「……楽しい」
「どうして?」
「安心、するから」
「安心?」
予想外の言葉に顔をしかめた。マリーは玉ねぎを包丁で刻みながら、小さくうなずいた。
「ちゃんと、『マリー』でいられてるんだ、って。確認できるから、嬉しいの」
「……変なの。マリーはマリーじゃない」
言っている意味がまったく分からない。マリーは振り返って、「そうだね」と、はにかんだ笑みを浮かべた。そう、それよ。理由なんて、その笑顔だけでいいの。
「じゃあ、これからもいっぱい写真撮ろうね。マリーの行きたい場所とか。見たいものとか。いっぱいいっぱい写真に残そう。春になったら、桜がきれいよ。桜吹雪の中にいるマリー、撮りたいなぁ。ついでにお花見もしたいね」
「桜って、いつ頃咲くの?」
「そうだなぁ、この辺だと、四月に入ったくらいかなぁ……」
こたつのぬくもりに包まれていたら、だんだん目蓋が重くなってきた。あ、だめだ。眠いなぁ。もう一月末だっていうのに、どこからかクリスマスベルが鳴っている。幻聴だ。眠りの世界に入り込もうとしたら、マリーが私の体を揺らしてきた。
「美鈴、電話」
「うーん……」
なんだ、ベルじゃなくて電話か。目を閉じたまま電話を受け取り、いやいやながら通話ボタンを押す。
「悪いな、休み中に」
大して申し訳なさそうでもない、上辺ばかりの言葉が耳に届いた。
「清水さん? どうしたんですか」
電話の相手は清水さんだった。休日に上司から電話とか、正直勘弁してほしい。電話越しに聞こえる彼の声は、いつもよりもっと無機質に思える。だけど次に聞こえてきたのは、予想だにしない報告だった。
「前に送ってもらった写真あるじゃん。あれ、フォトコンテストのグランプリ受賞したから」
「……はっ?」
「それで、選考委員の川端って人が、今度お前にカメラ頼みたいって言ってるんだけどさ、ちょっと出てこれる?」
わけが分からなかった。勝手にコンテストに送られていたことも、グランプリを受賞したことも。夢の世界に片足を突っ込んでいた私は、突然別の夢に両手を引っ張られたような感覚に陥った。あれ、これも、夢? 思い切り頬をつねってみる。痛い。違う、夢じゃない。まったく意味が分からないけれど、たぶんこれは喜ぶべきことだ。
「……行きます! すぐ行きます!」
私は眠気をこたつに置いて、勢いよく立ち上がった。ジャージを脱ぎ捨てて服を着替え、ぼさぼさの髪を手で撫でつける。メイクをしている暇はない。
「美鈴、ご飯は?」
「ごめん、取っといて!」
マリーの声を背に受けながら、私はどたばたと玄関を飛び出した。
その日を境に、趣味程度にとどめていた撮影を、仕事として行うことが多くなった。元々カメラマンを目指して上京してきた私にとって、カメラの仕事をたくさんもらえることはこの上ない幸せだったし、合わせて、マリーの素晴らしさも認められたようで嬉しかった。商品撮影、記事の撮影、それももちろんきらいじゃないけれど、やっぱり自分のすきなものを撮りたい。一つの作品を作り出したい。それって、写真がすきなら当然でしょ。今までは「これをこういう風に撮って」って指示されることが多かったけれど、「あなたはどう思いますか」「どんな写真が撮りたいですか」って聞かれることが増えていって、心の底からじわじわと喜びが湧き上がってくるようだった。ああ、わたし、社員としてじゃなく、「園原美鈴」として必要とされてる。そんな気がしたんだ。
マリーの写真を撮りたい、っていうオファーも数多く発生したけれど、マリー自身他の誰にも撮られたくない、と拒否したこと、そして、彼女の神聖さを保つためにも、マリーを人目に晒すようなことは避け続けた。
みんなの目に映るマリーは、しっかり者で、料理上手で、優しい女の子じゃなくて、神々しく、謎めいた少女にしていたかったのだ。私はいわば「マリー」という偶像を作り出していた。周囲の大人たちは偶像崇拝のようにマリーに惹かれ、それはすなわち私の写真への興味や好奇心に変換された。その化学反応をうまく利用したおかげで、私の仕事は多忙を極めた。それは皮肉なことにも、マリーとの時間を少しずつ奪うことになっていった。
お天気お姉さんが知らせる気温もだんだん高くなっていった、三月末。
「ただいまぁ」
私はその日も深夜二時くらいに、疲労感をどっさりと背負って帰宅した。部屋の明かりはまだついていて、眠たい目をこすりながら、マリーがわたしを玄関まで出迎えてくれた。
「おかえりなさい」
「まだ起きてたの? 寝てなっていつも言ってるのに」
「いいの。ご飯、どうする? お風呂は?」
「ごめん、ご飯は食べてきちゃった。お風呂は明日にする……。今日はもう、限界……」
私はかろうじてメイクだけ落とすと、服をその場に脱ぎ散らかしてベッドへと倒れた。マリーがよくできた嫁のように布団をかけてくれたけれど、もう感謝の言葉を述べる体力すら残っていない。マリーはちょこんとベッドのそばにしゃがみ込んで、嬉しそうに話し始めた。
「あのね、美鈴。今日買い物に行く途中で、桜が少し咲いてたの」
「桜……? ああ、もうそんな季節かぁ……」
「あと二週間くらいで見頃って、ニュースで言ってた。約束したでしょ。満開になったら、一緒に……」
「ごめん、マリー。その話、また今度聞く……」
私は襲いかかる睡魔に抵抗できず、マリーの話を中断し、そのまま布団に吸い込まれるように眠りについた。この時期の私はご飯を食べる時間もないくらい仕事に追われていて、体力も、眠気も、精神も、もう限界突破していたのだ。マリーに申し訳ないと思いつつも、それをうまく彼女に伝えることすらできなかった。遠くから、「……おやすみ」という、泣き出しそうな声が聞こえた、ような気がした。
思えばこの時にはもう、マリーの写真を撮ることはなくなっていた。それどころか、一緒に暮らしているはずなのに、マリーと顔を合わせることすら少なくなっていた。マリーが起きるより早く家を出て、マリーが深く眠りについたあと帰宅する。家に帰らない日も多くあった。マリーがいつもどんな風に部屋で過ごしているのかなんて気にも留めなかった。私をここまで押し上げてくれたのはマリーなのに。春になってからはもう、マリーがどんな顔をしていたのかすら思い出せない。写真を撮られている時のマリーは、確かに楽しそうだった。過去の辛い思いを忘れたように微笑んでいた。その笑顔を思い出すことになるのは、四月の半ばになった頃。
「お疲れ様でしたー!」
その日のことは、今でも鮮明に覚えている。携わっていた長期のプロジェクトがようやくひと段落し、職場近くの居酒屋で打ち上げが開催されたんだ。連日の睡眠不足でへろへろだったけれど、そんな疲れが吹っ飛ぶくらい成功したことが嬉しくて、私の気分は有頂天だった。
「お疲れさん、園原。よくやったよ」
「ありがとうございます。めちゃくちゃ疲れたけど、すごく楽しかったです!」
直属の上司からのお褒めの言葉に、私は喜びを噛み締めた。ようやく肩の荷が下りたためか、ビールのおいしさも格別だ。仲間との話も盛り上がるし、酒の肴もどんどん進む。一人前のカメラマンを目指して上京したのははるか昔。今の会社に入って、いろんな写真を撮ったけれど、自分らしい作品を撮る機会はまったくなかった。コンテストに応募しても入賞なんてすることもなく、やっぱり仕事ですきなように撮ることはできないんだ、なんてへそを曲げていたけれど、今は続けてよかったなぁと心の底から思う。じんわりと滲む涙を振り払うように、目をしばしばさせていると、北村くんが隣の席に移動してきた。
「あれ、美鈴さんどうしたの。疲れ目?」
「ばか、違うわよ。……お疲れさん」
相変わらずの北村くんと、小さく乾杯を交わす。腹が立つ部分は多々あるけど、なんやかんや、かわいい後輩なのよね。今回のプロジェクトでもすごく手伝ってもらったし、なかなか直接は言えないけど、感謝していたりもする。
「そういや、最近どうなんです? あの子」
だらだらと取るに足りない話をしていたら、思い出したように北村くんが言った。だいぶお酒がまわっていた私は、働かない頭を傾げた。
「あの子?」
「ほら、写真の。まだ一緒に暮らしてるんでしょ? 最近撮ってないみたいじゃないですか」
――あ、そうか。マリーのことか。
北村くんに言われて、私は久しぶりにマリーの存在を思い出した。
「そういや、そうだなぁ。最近死ぬほど忙しかったから……」
最後に顔を見たのはいつだっけ。マリーの料理も全然口にしていない。そういえば、結局あの夜、何を伝えようとしていたのだろう。桜がどうとか言っていたっけ。口に運ぼうとしていたビールグラスを、テーブルの上に置く。
あ、れ?
出会った頃は、あんなにマリーのことを撮っていたのに。マリーの美しさや健気なところ、謎めいたところやしっかり者のところ。マリーのすべてがすきですきでたまらなくて、一秒足りとも目を離したくなかったのに。私、いつから、マリーのことを後回しにするようになったんだろう。マリーのことを考えれば考えるほど、胸の奥がきゅうっと苦しくなった。……私、なんて薄情なんだろう。
仕事もひと段落したし、明日は久々の休みだ。今までかまってあげられなかった分、たくさん写真を撮ってあげたい。さみしい思いをさせてごめんね。そう謝ったあと、たくさんシャッターを押してあげたい。そうしたらきっと、マリーは笑ってくれるだろう。想像したら、無性にマリーに会いたくなった。
「……ごめん、ちょっと今日は帰るね」
「え? まだ始まったばっかりですよ」
「適当にごまかしといて! 今度おごるから」
先輩という立場を存分に使い、私は急ぎ足で居酒屋をあとにした。
なんとなく、帰る途中のコンビニで小さなケーキを二つ買った。マリーは甘いものがすきだから。たまに、仕事帰りにデザートを買って帰ると、マリーはとっても喜んでくれた。あんなに神秘的な美しさを持っているのにね、その時は、普通の平凡な女の子に見えるのよ。ぱっと花が咲くように、顔全体が明るくなるの。あんな嬉しそうな表情、もうずいぶん見ていないな。いつから私は、マリーの優先順位を落としてしまったのだろう。こんなにすきなのに。大切にしたいと思っていたのに。ごめんね、ごめんねマリー。また、あなたのことを撮りたいよ。あの美しい微笑みを、もう一度見せてよ。
「マリー!」
私は大きく叫びながら、勢いよく玄関のドアを開けた。まだ二十二時を過ぎたくらいだというのに、部屋は真っ暗で、人の気配がしなかった。しん、と凍てついた空気が満ち満ちていて、春だというのに、なんだかとっても寒く感じる。
マリーはどこにいるのだろう。もう眠ってしまったのだろうか。電気をつけて、「マリー?」ともう一度名前を呼ぶ。リビング、寝室、お風呂、キッチン。どこを探しても、マリーの姿はない。いやな予感が体の奥底から湧き上がって、急にこわくなった。
以前のマリーなら、どんなに遅く帰っても、必ず私を待っていてくれた。眠たい目をこすりながら、ソファに座って、私のためにご飯まで用意して。長年ひとり暮らしをしていたわたしには、それがとってもとっても嬉しくて、そのたびにマリーを抱き締めたり、頭を撫でたりして、「ありがとう」をいっぱい伝えた。
いつからだろう。マリーの用意してくれたご飯を食べなくなったのは。いつからだろう。「ありがとう」と言わなくなったのは。マリーはいつも私を待っていてくれたのに。いつからないがしろにしてしまったの。
――マリーは、どこにもいなかった。
いつマリーがいなくなったのか。情けないことに、私はそれすら分からなかった。だって昨日も、その前も、それ以前も、私はマリーの顔を見ていない。それどころか、最後に交わした会話すら覚えていなかった。
マリーと暮らし始めて、もう三ヶ月以上経っていた。それなのに結局、マリーについて知っていることなんて、ほんの少ししかなかったのだ。
彼女のいなくなった部屋で、私はひとり、ぼんやりと昔のことを思い出した。
――すっごくきれいに撮れてる!
ああ、これは初めてマリーを撮影した日の記憶だ。マリーに写真を見せてあげると、彼女はびっくりしたように目を丸くして、そして嬉しそうに微笑んだ。
「この写真、見せたい人っている?」
好奇心から尋ねると、マリーはためらいながらもうなずいた。そして、雪のように儚い声でこう答えたのだ。
「……一番、すきな人に」
――だから私は、写真集を出すことにした。本当はもっと別のものを発売する予定だったのだけれど、それをすべてマリーの写真に差し替えたのだ。おしゃれに決めた写真から、日常の何気ない一コマまで。私が見てきたマリーを、私が知っているマリーを、マリーが伝えたい誰かに届けるために。
私が知っているマリーのすべては、たったこれだけ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

