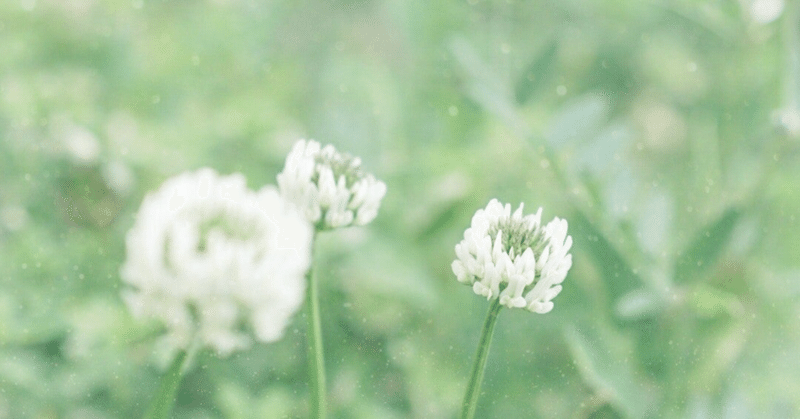
「マリーについて」エピローグ<完>
喫茶店をあとにした俺は、自宅に戻る気にもなれず、あてもなくふらふらと河川敷を歩いた。そうしているうちにいつの間にか時間は過ぎて、気づいた頃には西の空が赤く染まり、夜を迎える準備をしている。ああ、俺はいつの間にこんなにセンチメンタルな男になったんだ。自分を客観的に見て苦笑する。
マリーを探し始めたのは、年が明けたあとのこと。初めはすぐに戻ってくるだろうと思っていたのだが、数日経ってもまったく帰ってくる気配がない。高校の新学期が始まると、マリーが登校してこないと担任から連絡があった。俺は言葉に詰まり、それからようやく、マリーを探すことにした。しかしどれだけ探しても、死期を悟った猫のように、マリーの行方はつかめなかった。警察に捜索願を出したものの、経緯を話したら単純な「家出」と判断され、本腰を入れて探す様子はなかった。金もなく、頼る人間もいない。そんなマリーが一体どこに行くというのか。そこで初めて気づいたのだ。俺はマリーのことを何も知らないと。
マリーを探し始めて半年以上が経とうとしていた、ある日。ふらりと本屋に寄った俺の目に飛び込んできたのが、園原美鈴の写真集だった。
そこに写っていたのは紛れもなく、俺の知っているマリーだった。長い髪。憂いを帯びた瞳。白い肌。すぐに園原美鈴に連絡を取り、そうしたら、芋づる式に登坂健人にも巡り会えた。しかしいざ話を聞いてみると、ふたりの知っているマリーは、俺の知っているマリーとは似ても似つかなかった。あんなにわがままを言われたことはない。泣かれたことはない。元気だったこともない。俺が知っているマリーは、彼女を構成するごく一部でしかなかったと、ようやくそこで理解した。
俺にとってマリーは、自分の価値を認識するにふさわしい、弱くて脆い少女だった。わがままも言わない。不満も漏らさない。そんなマリーが俺に向ける愛情を、うまくうまく利用していた。
それが紛れもない独占欲だと気づいたのは、雪が溶け、桜が美しく咲き誇る季節になってからのこと。マリーという存在を失って、ようやく俺は悟ったのだ。依存していたのは、俺の方だったと。
――マリー。
声を出さずに、名前を呼ぶ。
お前のいない世界はとてもつまらないよ。マリーについて、知らないことがたくさんあるよ。
マリーはもうどこにもいない。だけどきっと、同じ空を見上げているのだろう。素直に気持ちを伝えたら、お前は俺のことを許してくれるだろうか。いつもと同じように、泣き出しそうな顔で微笑んでくれるだろうか。
今日も俺は空を見上げて、この世界のどこかで生きる、お前を想うよ。マリー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

