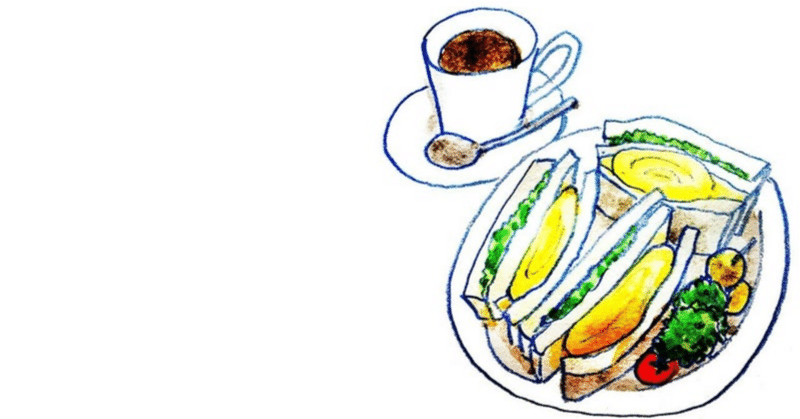
言葉に代わるもの
その喫茶店には病院の帰りに足を踏み入れた。ネットの口コミで周到に調べただけあって、一目惚れだった。わたし好みの喫茶店だ。カフェというより『喫茶店』と呼びたくなる、どこか懐かしい空間。開放的な高い天井に大きな窓が並び、隣のテーブルとの距離も充分に保たれた座席。趣のある年季の入った木のテーブルの温かみに心が踊った。
それは、その日が3度目の訪店だったときのこと。
角の窓際のテーブルに空きを見つけ、そこに腰をおろした。遅いランチを食べながら窓の外に視線をやると、自転車の後ろに子供を乗せた女性が脇目も振らずに漕いでいく。幼稚園生だろうなと思ったのは、その子が紺色のブレザーに黄色の、所謂幼稚園バッグを斜めがけにしていたからだ。その母子を横目で追いかけたのだけど、すぐにわたしの視界からいなくなった。店の前には片側一車線の道路があるが、車の通りは多くない。
ランチセットをほぼ食べ終え、少しだけ残っていたサラダに手を伸ばしたとき、女性と70代半ばくらいの男性が店に入ってきた。女性は推定43歳。その2人を見て親子だとは思わなかったのは、どこか余所余所しかったからだ。男性の頭は白髪にグレーが混じっていて、背筋は張っていたがどことなく弱々しかった。二人が座ろうとしていたのは4人テーブルで、わたしの席からは斜め右の位置にあった。こんな年の差の他人の二人が、この喫茶店に来る理由に考えを巡らせる。あれしか思いつかない。わたしはさっき水を注ぎにきたウエイトレスを目で探したが、見当たらなかった。その二人のあとを追うように、さらに男女二人が入ってきた。男性は杖をついていて、右足を庇うように歩いている。その男性を気遣うように女性が彼を支えていた。どちらも70代前半に見えた。先に着いた二人の元へあとから来た二人が合流すると、その異年齢の4人はテーブルで向かい合うようにして座り、オーダーを取りにきたウエイトレスに推定43歳の女が全員分をまとめて注文した。
女性の二人は横並びに座っていて、わたしに背を向けている。合コンスタイルの座り方だが、とてもじゃないが合コンには見えない。推定43歳が生命保険のCMに出てくるような黒い鞄から何かを取り出し、テーブルに置いたようだった。やっぱりそうだ、あれはパンフレットでこれから老人3人を相手に、明るい老後の提案を始めるんだ。手持ちの資産を増やそうと投資話を持ちかけるんだろうか、それとも提携先の老人ホームを斡旋する営業だろうか。まさか何かの商材を売りつけるわけじゃないだろう。いやなところに遭遇してしまったと思った。斜め後ろから見ているわたしには分かりづらかったのだが、それはパンフレットではなくタブレットだった。今は営業もタブレットなのだろう。それを老人3人が覗き込むような仕草をしていたが、すぐに顔を戻していた。その様子を見ていたら、この人達は大丈夫だろうと解釈し、視線を反らした。珈琲はとっくに冷めきっていた。
わたしの右隣は空席で、その隣には口数の少ないご夫婦。向かい側のテーブルには新聞を読む高齢の男性が座っていた。そこに現れた4人グループは、これから話に花を咲かせるんだろう。少々騒がしくなるのを覚悟しなくてはならないが、午後3時半を回っていたし、珈琲カップは空になっていた。そろそろ帰宅の途につこうかと、グラスの水を一口飲んだ。4人グループの方に視線を戻したのは、何か違和感を覚えたからかもしれない。息遣いは漏れてくるのに話し声が殆どなかった。その声の主は推定43歳のようだったが、他の人の声は聞こえてこなかった。
顔から下に視線をずらした。ああそうだったのか。なるほど、と思ったのはその人達が皆、手話を使って話していたからだった。わたしの位置からも鮮明にわかる白髪グレーの男性の、ゆったりとした手の動きと柔らかな表情に、それがすぐには手話だと気づけないほどに流暢だった。言葉を手から発するのか、口から発するのかはあまり関係のないことに思えるほど、そこに流れる会話は穏やかに弾けていた。時折推定43歳がタブレットを隣の女性と共有していたのは、手話を指南してもらっていたのかもしれない。ベテラン三人の会話には、うまく入れていないように見えた。
人と通じ合うことの尊さを知ったのは、今から10年以上前になる。この世に元気に誕生した息子は発語が遅く、言葉の理解も遅い子だった。やっと単語が出たと思ったら、「パマ」というパパとママを掛け合わせた造語を発し、夫とわたしを同時に呼び寄せるという荒技をくり出した。3歳児健診では語彙を増やすようにと指摘してきた人もいたけれど、親でさえ発語を聞く機会など滅多になかったのだから、ハーイ、と適当に頷くしかなかった。語彙が増える魔法でもあるのなら、教えてくれれば良かったのに。
そんなときに、なかば強制的に出会ったのが絵カードだった。一日のスケジュールを冷蔵庫の扉に貼りつけて、その日どんなことが起こるのかを目で見えるようにした。子供にとっては全てが予定外で不安なんだからねと言われ、それはパニックとなって表れていたし、こちらとしても声が枯れるまで泣き続ける横で耐える毎日に限界だった。だから絵カードを介して接触を図ってみたけれど、まあ見やしない。「次はお昼ごはんだね」とカードを指差したところで、わたしの一人芝居だったし。そもそも息子は聞いていなかった。
4歳のとき息子は初めて虫歯になった。こんなにめでたくない「はじめて」は他にない。できてしまった虫歯はどうしようもない、治すしかない。だから虫歯の絵カードを見せて歯医者に行くことにしたのだけど、反応がない。感覚に鈍麻なところもあったから、歯医者はさらっとこなすタイプかもしれないと楽観視したのはまずかった。不安の塊のような子なのだから、大丈夫であるはずがなかったのに。当日の末路とは、医師が口を開けて虫歯を確認するだけでも椅子から飛び降り暴れまわって大騒ぎの惨事という有様だった。
歯医者こそ一度の治療で完治させて下さいと神に祈るのに、
「次回はいつ来れそうですか」
と微笑む受付のお姉さんを前に、果たして次回は無事に連れてこられるだろうかと身を案じた。
歯医者がどういうところかを知ってしまったのだし、嫌がるのは当然で、けれど放っておいても虫歯は治らない。結局予約の二週間前になってから再び治療に行くことを告げた。これは月のスケジュールで。
そうしたら予想通りというかパニックになったのだけど、わたしは虫歯の絵本を持ってきて、
「治さないとこうなるからね、だから歯医者さんは行く。でも怖いなら隠しておくよ」
と、一日のスケジュールとは別に作っていた月毎のカレンダーの、次の予約日を示す歯のイラストのところに白い紙を上から被せて隠した。これで歯のイラストは見えなくなった。
ところが、静かになったと思ったら今度はその紙を剥がそうとする。
「隠したらダメなの?」
息子は上から被せた白い紙を自分で外し、部屋を走り始めた。そしてまた歯のイラストを見にきては、癇癪を起こしてまた走る。
走っては見る、見ては走る。それを繰り返した。
歯のイラストに声を上げ部屋を走るという一連の流れは、予約日当日まで行われた。
あれ、もしかしてこれは通じてるんじゃないの?
なにかに取り憑かれたような危険な匂いのする儀式のようでいて、自分なりに分かっていないとそんな行動にはならないんじゃないか。会話の成り立たない親子では、すべては憶測でしかないんだけどこれは「伝わった」という初めての感覚だった。その初体験に心から喜んだし、とても便利だと思った。
そうだった、言葉でやり取りできることは便利だった。それまで便利かどうかなど真面目に考えたことはなかったが、息子が産まれてからは「話の通じない相手」に切羽詰まっていた。そこに救世主となって現れたのがイラストで、これは息子とわたしを繋ぐ有力な『言葉』となり、通訳のような役割を果たした。言葉には幾つもの『言葉』があって、それは人によって違ったりする。互いに伝えたいことを伝え合う手段になるのなら、わたしのなかでは全てが言葉だ。
そろそろ席を立たなくてはと、もう一度グラスに口を運んだ。4人グループの席を横目に喫茶店を後にした。すでに推定43歳の声は聞こえていなかったし、手話をしてるような素振りもなかった。会話に入れているんだろうか。あの人は恐らく健常者だろうけれど、その4人グループの中では言葉をうまく使えない不便な人のように見えた。
帰りの道は午後の陽射しも落ち着いていた。
白髪グレーのあの人の、流暢な会話の残像がしばらく頭から離れなかった。あの人達のあの言葉。『言葉』はたしかにあの場所にいた。
スキしてもらえると嬉しくてスキップする人です。サポートしてもいいかなと思ってくれたら有頂天になります。励みになります。ありがとうございます!
