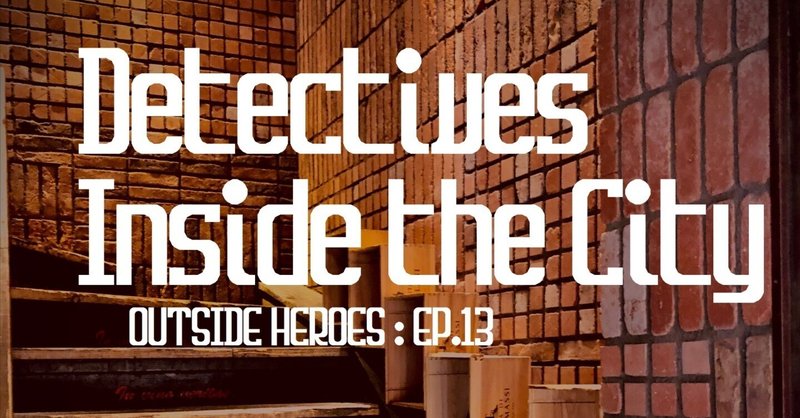
アウトサイド ヒーローズ:エピソード13-5
ディテクティブズ インサイド シティ“ミュータント風邪”の感染者が山あいの町で初めて確認されてから、1カ月が経とうとしていた。医師とナースたちによる治療が進められていたが、運び込まれてくる患者の数は増えるばかりだった。
「うん……しょ、うんしょ……」
カガミハラ・フォート・サイト、商業エリアの第2地区。大きな荷物を両手に抱え、肩からトートバッグを提げた四つ目の娘が、ふらつきながらゆっくりと大通りを歩いていく。
修理を頼んでいた店のミール・ジェネレータの部品を取りに来たものの、想像していた以上の重さに腕と腰が悲鳴をあげていた。
目の前にやって来たスーツ姿の人影に、娘は慌てて道を譲る。
「あっ、あっ、ごめんなさい!」
「……ミュータントは、家ん中で大人しくしてろよ」
すれ違いざまにこれ見よがしの舌打ち。投げ捨てるような男の声。行き交う人々は様子をうかがうように視線を向けては、そそくさと通り過ぎていく。娘が固まりついていると、
「おーい、大丈夫か?」
「よっちゃん、手伝うよ!」
道の両側から男女の声が飛んでくる。四つ目の娘は驚いて、きょろきょろと見回した。
「アマネさん! それに、探偵さんも!」
「……げっ!」
娘に駆け寄ってきたスーツ姿の男女は、互いの姿を認めると立ち止まった。ことさらに嫌そうなうめき声を漏らす探偵を、巡回判事・滝アマネが睨みつける。
「“げっ”ってどういう意味ですか、キリシマ探偵」
「いや、それはその……よっちゃん! 俺が持つよ、荷物!」
「あっ、はい、ありがとうございます! ……でも、大丈夫ですか? 重くありません?」
誤魔化すようにテンションをあげながら、探偵は荷物を右腕で受け止めた。肩にめり込むような重さに目を白黒させながら、慌ててサイバネ義肢の左腕を添える。
「大丈夫、左手は力持ちだからな! よい……せっ! ……ふう」
荷物を機械仕掛けの左腕に持ち替えると、キリシマは人心地ついてため息をつく。アマネは四つ目の娘の隣に並んだ。
「よかったね、よっちゃん。これから“止まり木”に帰るの?」
「そうなんです。お店のお使いの途中で……」
娘二人が一緒に歩き始めると、荷物を抱えた探偵が慌てて追いかけた。
「二人とも、ちょっと待ってくれよ! それと刑事さん、あんたも手伝ってくれるんじゃなかったのかよ!」
「えー?」
噛みつくように不満の声を投げる探偵を、巡回判事は軽く聞き流す。
「一人で荷物を運べてるのに、私が手を出したら却って邪魔になりません?」
「そりゃ、そうなんだけど……納得いかねえなあ……」
キリシマがぶつぶつと文句を言っていると、アマネは探偵が持った荷物の更に上に、自分が手にしていた書類鞄をひょいと載せた。
「あっ、おい! 何を勝手に!」
「私もランチで“止まり木”に行きますし。どうせ行先同じだからいいでしょう?」
胸を張って言い放つアマネの顔を、四つ目の娘がもじもじしながら見ている。
「あの、アマネさん……」
「んー? どうしたの、よっちゃん」
「昨日からお休みです、お店……」
「ええっ!」
アマネは口をあんぐりと開けて、四つ目の女給を見つめていた。
「本当に? どうして……」
「流行ってますからねぇ、“ミュータント風邪”」
申し訳なそうに言う女給の横で、居候の探偵が「ふん……!」と不満そうな鼻息を漏らす。
「クレームがあったんだと。地区の商工会に」
「お店に直接じゃなくって?」
「店に直接だったら、ママがうまくあしらうさ」
アマネの疑問に、キリシマ探偵は忌々しそうに唸りながら説明を続けた。
「だからクレーマーは商工会にしつこく絡んで、会長を使って店に圧力をかけてきた、ってわけだ。やらしい手を使いやがるぜ、まったく!」
「探偵さん……」
「事実だろ、よっちゃん」
探偵が一緒に怒ってくれていることをありがたく思いながら、しかし申し訳なさそうな四つ目の女給。キリシマはなおも、ぷりぷりと思っている。
「おかげでしばらく、俺も商売あがったりだぜ! 早くいつも通りに戻ってくれねえと、新しい仕事を受けられないんだからな」
「その割には探偵さん、まだまだ余裕ありそうじゃない」
「だぁかぁらぁ、これまで受けてきた仕事の報酬を集金して回ってるんですよ!」
白目を向けるアマネに、キリシマはむきになって言い返す。
「はいはい、それは失礼しました。あまりにもいつも通りで、のんびりしてらっしゃるように見えたので!」
巡回判事の言葉に、探偵は「ぐぐぐ……!」と悔しそうな声で唸りながら歯ぎしりをしている。アマネはキリシマの様子など気にせず、四つ目の女給とおしゃべりを続けていた。
「それにしても陰湿ね、回りくどいやり方だし……」
「どうしても、仕方ないです。お店の子の中には出てないですけど、“ミュータント風邪”が流行ってるのは事実ですから。お客さんの中には、“ミュータント風邪”にかかって大変なことになっちゃった人もいましたし。……私のお父さんも陽性になっちゃって、検査結果が出るまで隔離するって……」
女給は話しながらため息をついた。
「お店の子も皆、いつかかるかな、って不安になってる子もいますから。重症になっても、なかなか治療を受けられないって言いますからね……」
「全く、病院にはもっと頑張ってほしいもんですよ。新しい薬も使われるようになった、って話なのに!」
不安そうに小さな声でつぶやく女給の横で、キリシマは口を尖らせてぼやく。
新しい薬だって? アマネは目を丸くした。
「そうなんですか?」
「えっ、ええ、まあ……」
「ふーん、初耳ですけど……」
しどろもどろになる探偵を、じっと見つめる巡回判事。
「病院の関係者と知り合いでしてね、話を聞いていて……ハハハ……」
「まあ、いいんですけどね」
T字路に差し掛かるとアマネは足を止め、キリシマに持たせていた書類鞄を手に取った。
「それじゃあ、私は軍警察の宿舎を借りてるので、この辺で」
探偵は露骨に「ほっ……」とため息をつく。
「へーい、お疲れさんでーす……」
「はい、それではまた、お店にお越しくださいね」
四つ目の女給は名残惜しそうに手を振っていた。後ろに束ねた髪を揺らしながら巡回判事の背中が小さくなっていくのを見送ると、荷物を持った探偵は再び歩き出す。
「じゃあよっちゃん、俺たちも帰ろうぜ。……戻ったらコーヒーフロート、よっちゃんのおごりな!」
「えっ! そんなの、聞いてないよ!」
「はっはっは!」
「ちょっと待って! おごんないからね!」
探偵は愉快そうに笑い、女給に追いかけられながら大股で歩いていく。スーツの肩口には、いつの間にか糸くずにまみれた小さな機械部品がとりつけられていた。ゴミくずか虫かと見紛うような超小型発信機は、インジケータの赤い光をゆっくりと明滅させていた。
「それで、先生」
カガミハラ軍病院の片隅、人気のない搬入口。もうこれで3回目になる荷物のやり取りを済ませると、キリシマは荷物を偽装用のクーラーボックスに収めたホソノ医師に尋ねた。
「治療は順調ですか?」
「そうですねえ、研究がなかなか進まなくてねえ」
探偵は朽ちかけていたベンチにどかりと腰を下ろす。遠くで搬入用ドローンのタイヤが床を擦る音が聞こえていた。
「相変わらず患者は増えていて、街中はピリピリしてます。ミュータントへの風当たりもきつくなっている……」
「そうねえ、まだまだ広がるのを抑え込めてないのが現状ですねえ」
ため息をつきながら隣にそっと腰を掛けた医師の横顔を、キリシマはじっと見ていた。
「先生、俺はこの3週間、随分な量の薬を売りましたが」
「ええ、ありがとうございます。これがなければ、今頃どうなっていたか……」
「この薬のことは、まだ市民には全然知られていない。まだまだそんなに使っていないんだろう。いっそのこと、全部使い切るくらいの気持ちで使っていたら今頃はもっと……」
「探偵さん」
ホソノ医師はじっと、キリシマの顔を見ていた。
「な、何すか……」
「この薬、とても効果があるものですが、二つ大きな問題がある」
「二つ? 副作用のことだけじゃなくて……?」
「そう、一つ目は副作用のことだ」
医師はうなずいて、キリシマの目をじっと見ながら説明を続ける。
「この薬を重篤化因子のない患者に投与すると、強い毒となって却って患者を苦しめることになる。特に、ミュータントの患者には。副作用は、一時的なミュータント変異の強化と極度の興奮状態。……我々としても、そんな物を簡単には使えないんだよ」
「だからって、このままにしておくわけには……遺伝因子さえわかれば、薬は使えるんだろう?」
キリシマが食って掛かると、ホソノ医師は静かに首を横に振る。
「二つ目の問題は、その遺伝因子のことだ。遺伝因子を持っていても、一目見てミュータントとわからない人もいる。ミュータントであることを隠して生きている人もいる。それに、重篤化因子を持っていなくても、色々な理由で重症化する人もいる。そんな中で、“ミュータントにしか使えない”とされる薬を使うことは、なかなかハードルが高いんだよ」
「それは……」
探偵はもごもごと言ってうつむく。ホソノ医師は「よいしょ」と声を出しながら立ち上がると、足元に置いていたクーラーボックスを持ち上げた。
「あなたも探偵ならわかるだろうがね。だが、とにかくあなたが持ってきてくれた薬はありがたかった。それは事実だ。お陰で重症化した患者も救うことができたし、重篤化因子を持つ人も、そうでない人も救うための治療法を探す手がかりもできた。これからも、よろしくおねがいしますよ……それでは」
薄暗い搬入口から顔を出すと、陽射しが目に突き刺さる。
路上に出る。行き来するトラック。行き交う人々。ざわめき。砂埃を含んだ風。探偵はしばらく立ち止まっていた。
周囲に流れるものが、どこか遠い。意識がどこかに、置き去りになっているような感覚。
キリシマは深くため息をつくと、大通りを大股で歩き始めた。
それから数日後、カガミハラの街中に一つの噂が流れ始める。
猛威を振るうミュータント風邪、その重症者をたちどころに癒す特効薬がある、と……
(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
