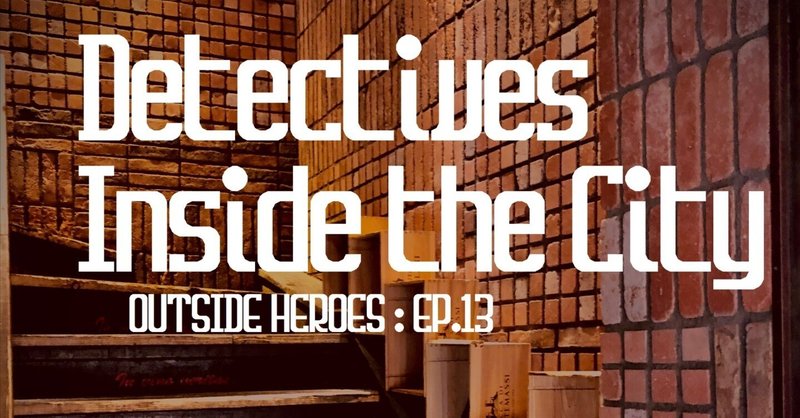
アウトサイド ヒーローズ:エピソード13-2
ディテクティブズ インサイド シティ昨夜はいい気分で仕事ができた。報告書だってうまい具合にまとまったし、“プレゼン”もうまい具合にできた。依頼人も納得してたし、このままいけば2割増くらいで報酬をふっかけても、文句は言われないだろう。だが……
義腕の探偵、キリシマは敷石のタイルを大股で踏みながら、カガミハラの大通りを歩いていく。昼下がりの陽射しを浴びながら肩を怒らせ、首を突き出して。
酔っぱらった刑事が絡んできたせいで、気分は最悪だ。都合の悪い過去のやらかしをほじくり返されちゃかなわないし、俺のことを探っていやがるのが、何よりも腹が立つ。
板状の包みを脇に抱えしっかりと両手で守りながら、探偵は目の前の人波をすり抜ける。
大型トラックが風を切る勢いで真横を走り去っていくと、男は「ひょう」と小さく声を漏らし、手にした包みを抱きしめた。小さくなっていくトラックを見送ると、深くため息をつく。
「ったく、気をつけろよな」
運転手には聴こえない程の小声で愚痴るように呟くと、男は再び歩き出した。真新しい商業ビルが並ぶ第二地区を抜けて官公庁が集まる第一地区へ。
別に、俺は、何もやらかすつもりなんかないんだ。オーサカやナゴヤのセントラル・サイトから離れたこの静かな町で、面倒ごとにも関わらないで、慎ましく小銭を稼いで……
すれ違う人から向けられる視線をはねつけるようにうつむきながら、ひたすら真っ直ぐに、大通りを進んでいく。
官公庁前では、守衛からの視線がことさら強くなっている気がするが、もう慣れたものだ。“向こうさん”だってこちらの事情を知らないわけじゃないから、いちいちパクられることはない。……ただ、サツの本能的に受け付けないだけなんだろう。でも、そんなの俺だって同じだ。必要がなけりゃ、こんなところになんか……
男は歩き続け、ついに“カガミハラ軍病院”と彫られた金属板が掲げられた白い建物の前にたどり着いた。がむしゃらに歩いてゆるんだネクタイを締め直し、裾を軽くはたいて砂埃を落とすと、「おほん」と小さく咳払いして自動ドアをくぐる。
「すみません、面会希望の者なんですが……えっ?」
すっかり顔なじみになった受付のナースに声をかけようとしたキリシマは、滅菌シートとテープで覆われた呼び出しカウンターに目を丸くした。
そして目の前に立つのは、ずんぐりとした白いシルエット。
「ジョウジ・キリシマさん、面会希望ですね! この一週間、発熱や体調不良はありました?」
威勢のいい声が飛んでくる。白い丸いものは、防護スーツに身を包んだナースだった。そして銃口のように突きつけられる細長いノズル。
ナースが手にしたノズルは極太のホースによって、足元の大型タンクに繋げられていた。
「えっ、ええっ? いえ、何もないですけど……」
探偵がものものしい雰囲気にすっかり困惑して固まっていると、
「消毒、開始!」
「ぶはっ、ぶっ、もごもご……!」
ナースの叫び声とともにノズルから大量の消毒液が飛び出し、探偵に噴きかかった。
消毒液で頭の天辺から爪先までぐっしょりと濡れた男は、ナースから受け取ったタオルで全身を拭きながら真っ白い廊下を歩いていた。
「ひどい目にあった。何なんだよ全く……」
通り過ぎる患者は勿論、ナースやドクターの姿も、普段よりも少ない様子だった。がらんとした廊下をぶつくさ言いながら歩く探偵の耳に、子どもたちの笑い声が聞こえてくる。近くの休憩スペースに、入院中の子どもが集まっているようだった。
「おっと、いかんいかん」
探偵は顔を拭いた後のタオルを丸めると、ぽいとリネン回収箱に投げ込んだ。右手をポケットに突っ込むと、早足で休憩スペースに向かう。
「おおい、元気だったかお前たち……」
言いかけて、男は再び固まった。スツールの並ぶ広々としたスペースにいるのは絵本を持ったミュータントの少女が一人。そして大きな画面を備えたコンソールには、沢山の子どもたちの顔が映されている。
「あっ、じょうじ!」
振り返った薄桃色のミュータントが、探偵の顔を見て嬉しそうに声を上げる。画面の中の子どもたちも、少女の声を聞くとモゾモゾと動きだした。「おじさんが来た!」「おーい」などの声がスピーカーから聞こえてくる。
どうやら、それぞれの病室にいる子どもたちと通話回線をひらいて、絵本の読み聞かせをしていたらしかった。
「おう」
探偵はポケットの中に詰め込んでいた飴玉に触れていた手を離すと、脇に抱えていた包みを少女に差し出す。
「見舞いに来たぞ、イオ。これ、新しい絵本」
院内の食堂も閑古鳥が鳴いていた。入院患者のために設置された小型ミール・ジェネレータには軒並み“使用禁止”の札が貼り付けられている。
静まり返った室内に穏やかさを強調する音楽が流れ続ける中、探偵とミュータントの少女は並んでテーブル席に腰かけていた。
「……それで、何だって? “ミュータント風邪”?」
少女が絵本を読み終えたタイミングを見計らって、探偵が声をかけた。
「うん。この1週間で一気に増えたんだって。おかげでお医者さんもナースさんも大忙しなの。絵本の読み聞かせ会も、リモートでやらなくちゃいけなくなって……」
「それで、モニターに向けて話をしてたのか」
「うん。本当はみんなに集まってもらって、目の前で絵本を見せた方が楽しいんだけど……」
少女はため息をつき、新しい絵本の表紙に目を落とした。長期入院中の彼女にとって、リハビリと社会に出るための勉強を兼ねて担当医から提案された“読み聞かせ会”をすることは、最大の生きがいと言っても過言ではないのだった。
「それはそうだろうけど、まあ、難しいよなあ」
実際のところ、各病室と通話回線をつないで“読み聞かせ会”をするためには医者やナースの協力が不可欠だろう。少女の気持ちも分かるが、男にはそれ以上の言葉を続けられなかった。
「ところで、そんなに大変な病気が流行ってるなら、イオも気をつけなくちゃいけないんじゃないのか? 見た感じ、いつもとあまり変わらないような……」
「うーんとね、あたしは大丈夫なんだって!」
「何でわかるんだよ」
キリシマが尋ねると、イオは顔に手を当てて首をひねった。
「先生が言ってたんだけど、何て言ったっけ、ええと……」
「イオ君は、重篤化因子を持っておらんことが分かっているからなあ。と言っても、今はなるべく、病室から出ないようにしてほしいんだがねえ」
朗らかな老人の声が後ろから飛んでくると、イオは背筋をぴんと伸ばして振り返った。
「先生!」
「ほっほ」
いたずらを咎められた子どものように畏まるイオを見て、細身の老医師は穏やかに笑う。探偵は席を立つと、深々と頭を下げた。
「いつもお世話になってます、ドクター・ホソノ」
「そんな、こちらこそ仕事をいただいて有難い限りですよ。イオ君もリハビリを頑張っています。入院中の子どもたちにも人気でしてねえ。朗読会も、子どもたちたっての希望でリモートでも続けようということになりまして。毎回、とても評判がいいんですよ」
「ちょっと、先生! いつから聞いてたんですか!」
「ほっほっほ」
イオが真っ赤になると、ホソノ医師は楽しそうに笑った。
「それでドクター、その“重篤化因子”というのは……」
「ああ、そうだったね。まず“ミュータント風邪”というのは通称で、特定のミュータントに重い症状が出るウイルス性の感冒……風邪の一種なんだが」
キリシマの質問に、ドクター・ホソノはとうとうと説明を始めた。眉毛は困ったように“ハ”の字になっているが、心なしかうきうきしているようにも見える。一人の研究者として未知のケースを研究し、その成果を説明するのはこの上なく楽しい事なのだろう。
「我々の研究の結果、重症化するミュータントたちは、いくつかの共通する因子を持っていることがわかった。この因子すべてが重症化の原因になっているかはまだ分からないのだが……ひとまずこれらの因子をまとめて、“重篤化因子”と呼ぶことにしたんだよ。そしてイオ君は、この因子はどれも持っていない、ということだ」
「なるほど」
「うーん、何となくわかった気がするけど……」
頷きながら話を聞いている探偵の横で、ミュータントの少女は小首をかしげる。
「ええっと、先生、私やじょうじは“ミュータント風邪”にはかからない、ってことですか?」
「いやいや、そんなことはない。重症化する可能性が低いというだけで、感染しないわけではないからね。むしろこのウイルスは感染力が強い方だから、重篤化因子を持っていなくても予防を徹底しなければいけないんだよ。もちろん探偵さんも、体調にはお気をつけくださいね」
「わかりました。……それじゃあイオ、俺はそろそろ帰るから」
「えーっ、もう行っちゃうの?」
少女が不満そうに頬を膨らませると、キリシマはイオの頭にポン、と手を置いた。
「仕方ないだろう、怖い病気が流行ってんだから。それに、イオが読み聞かせをしてる子どもたちの中には、“ミュータント風邪”にかかったら、大変なことになる子がいるかもしれないんだぞ。その子らに、イオが病気をうつしたらどうするんだよ」
「うーん……うん、わかった……」
少女はしぶしぶながら納得して頷き、頭を撫でられるがままになっている。
「ほほほ……ん?」
二人のやり取りを見守っていたホソノ医師が笑っていると、インカムから鋭い呼び出し音が響いた。
「はい、ホソノです。……えっ、緊急外来で! ……わかりました。すぐに行きます」
「お忙しいんですね、ドクター」
「ええ、いつの間にやら専門家になってしまって、大忙しですよ。まだまだ薬も全然足りなくてねえ。ナゴヤ・セントラルからの輸入ができれば、すぐにでも使えそうなものはいくつかあるんだが……おっと、失礼しました。そろそろ行かせてもらいますよ」
そう言って会釈すると、ホソノ医師はさっさと廊下を歩き去っていく。
「じょうじ、帰る前に、もっと~」
「しょうがねえなあ。……さて、どうするかねえ」
探偵は少女の頭を撫でまわし続けながら、忙しそうな医師の背中を見つめていた。
(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
