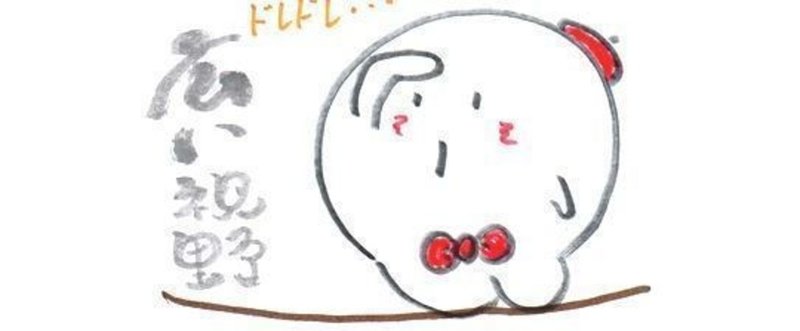
お香のこと
東洋の医術では、漢方薬を用いる際、生薬の成分だけでなく、口に含んだときの味覚の刺激でも、体内に働きかける力があると考えます。
五味といって、酸味、苦味、甘み、辛味、しおから味、の5つの味覚が、体内の五臓にそれぞれに働きかけを行います。
この味覚の刺激がつよければ、五臓という内臓の働きに負担をかけることになりますし、また、味覚の刺激が不十分であれば、体内の働きが緩慢になったり、十分に機能しなくなってしまいます。
こうした味覚の半分は、じつは香りの働きだったりします。
鼻をつまんで食材を口に運んだ時の味のインパクトと、香りを感じながら食べた時の食材のインパクトには実感として差があります。
飲食を口に運べば、香りを含んだ味覚の刺激とともに、食材の負担がかかります。食べ物が胃袋に収まると、消化、吸収、解毒、排泄などの内臓の手間がかかります。
ただ、味覚同様、体内の働きや内臓の働きに刺激を与える「香り」をたのしむだけなら、消化器の「食べこなす負担」をあたえることはありません。

先日、日本橋三越にて開催された「松栄堂のてしごと展」という催しに出かけました。
香りのことや生薬のことは、東洋医学という視点から関心があり、学び続けていましたが、「香道」という世界にはまったく首を突っ込んだこともなく。
それでも、機会があったので会場へ足を運ぶこととしました。

香木で一般的な白檀をはじめ、高価な沈香の香りを、灰をかぶせた香炉にて、本格的に体験させていただきました。
線香のように直接火をつけて燃やしてしまう方法とは異なり、香炉の灰の下にうずめた炭のそばに、ほどよい距離を保ち香木を置くことで、ほのかな熱により精油成分が揮発して、香りがたちのぼる「聞香(もんこう)」という香りの楽しみ方は、燃えたりいぶされたりする香ばしさを含まないため、素直な香木の香りを味わえます。
最後に「伽羅(きゃら)」という沈香のなかでも一層高価な香木も、聞香で楽しませていただく貴重な経験をさせていただきました。

会場について、香道の初歩を体験させていただくつもりでしたが、体験講座はすでにいっぱい。
係の方に声をかけての「聞香」体験となりました。
当日は松栄堂の方々が見えられていたようで、展示やお香づくりの仕組みなどについて、くわしく時間をかけて説明いただくことができました。
香りをつくりだすことの繊細さ、手軽に手に入るものもありますが、こだわればこだわるほど、奥の深い工程に頭が下がります。
当日は、香炉や香木の販売もありましたが、線香でのお香も取り扱いがありました。
やはり身近に楽しめるのはコチラかなぁと。

展示販売では、「源氏香」をモチーフにしたお香がたくさんならんでいました。源氏物語のストーリーを思いだしながら、手にとって線香の香りをたのしみます。
体内の働きに作用を及ぼす香りの力。
当日は少々香りで酔ってしまうほど、息を満たしココロ憩う時間を楽しませていただきました。

あいにくの曇り空でしたが、桜が満開で風もあったため、舞い散る桜の花びらを楽しむことができたのは、これはこれで良い景色。
風に運ばれてくる桜の香りは、先始めよりも散り際がはっきりして楽しめます。

屋内でも屋外でも、香りに身を置いて過ごす楽しみを満喫した日本橋でのひと時でしたとさ。

季節とカラダと暮らしをむすぶメルマガ
メルマガ・鍼灸師・のぶ先生の「カラダ暦♪」
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
