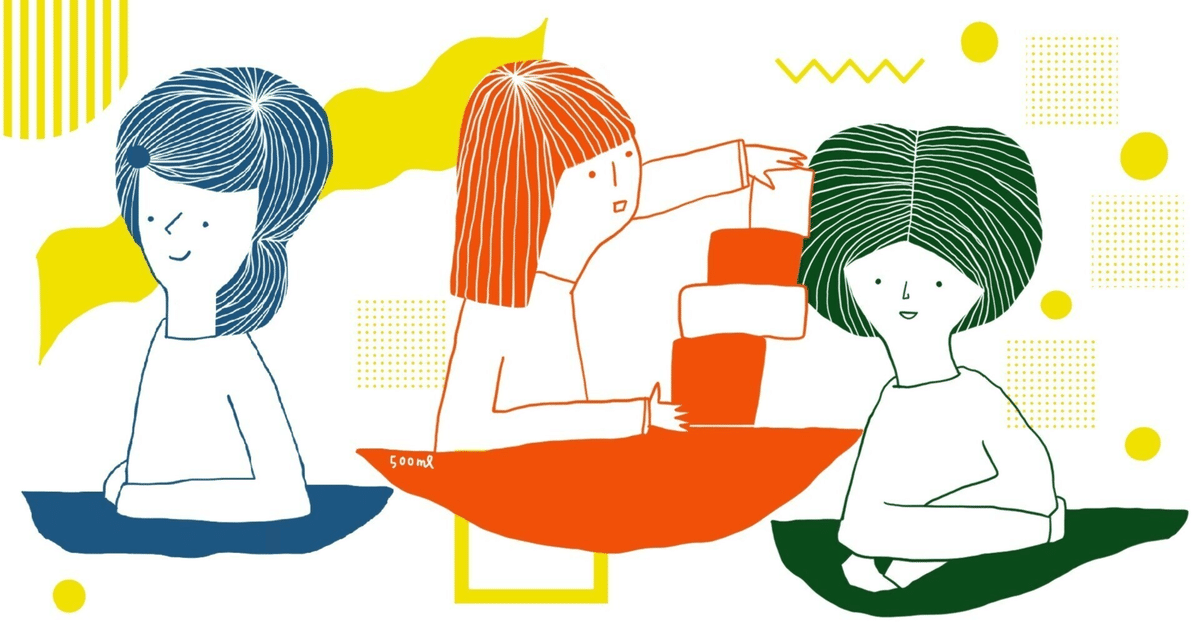
その20 小説家になりたい人へ 著作権エージェント夢野律子がお手伝いします
【編集者に合う前に、編集者の情報を知るといいです】
週が過ぎて木曜日になった。
律子はパンツスーツ姿で高弁社から最寄りの地下鉄の出入り口に立ち、直美と香織を待っていた。昨日は美容室に行ってきた。編集者に会うために美容室に行くなんて久しぶりだな、と思っていたら、
「先輩。こっちーでーす」
とタクシーから直美と香織が降りてきた。二人ともパンツスーツ姿の直美と香織が現れた。タクシーは見覚えのある個人タクシー。
またかいな、と思いつつも意識は香織に向いてしまう。
直接見る香織はオーラのようなものが漂っている。神秘的な仏像を目の前にして手を合わせて拝みたくなるような気持ちだ。画面越しでは伝わらなかった美しさに圧倒される。
逆に美人すぎて地下アイドルに向いていなかったのかもしれない。
と思って直美と見比べてしまい、己を恥じた。トップキャバ嬢もトップアイドルも劇的な美人は少なく、話し上手や盛り上げ上手が多い。旦那に保険をかけて殺す女も美人はいない。映画のような「魔性の美人」なんてものはいないかもしれない。
私のように美人でも裏方向きな女性は多いし。北条香織さんもそんなタイプなんだろう。
軽く挨拶を交わし、彼女に高弁社のビルを眺めさせた。
「どうです? 県庁舎のような立派なビルでしょう」
「やっぱり大手はすごいですね。自社ビルなんですよね?」
「大ヒットが出れば自社ビルを建てるのが出版社ですし、担保にして融資も受けられやすいですから」
クリエイターの血と汗の結晶で、神殿のようなビルを建造したがるのが出版社。
高弁社から出た大ヒット作品「突撃の巨兵」がこのビルをぶっ壊したらさぞかし爽快だろう。
直美はタクシーの領収書を律子に渡すと口を開いた。
「ところで先輩。早朝、Discordで『事情が少し変わった』とメッセージが来ましたけど、どういうことですか?」
「ちょっと予期せぬ出来事が起きたの。詳しい話、というか作戦会議をしましょう」
三人は近くの喫茶店に入り、角席に座った。三人ともアイスコーヒーを頼んだ。律子と直美はミルクと砂糖を入れたが、香織はブラックだった。
ブラックを飲む女は絵になるな、と律子は心の中で独りごち。
美人描写が下手な作家にそんなアドバイスをしとこう。
そして律子は小声で事情を語りだした。
当初は推理作品に強い高弁社の編集者に売り込み、すんなりと採用が決まった。しかし出版スケジュールを聞くと、有名な推理作家が出す警察モノとバッティングすることが分かった。
編集者は「その作家は発売日に似たジャンルが出るのを嫌がる」と言われ、子会社を紹介された。
「えー。レベルダウンじゃないですか」
直美は口を膨らませた。
「でもね、その子会社の社長が一ノ瀬坂道さんやラノベのメインストリームを変えたと言われる、見出した熊谷(くまがい)編集者なの」
香織の眉が少しだけ動いた。対して直美は口が半開きになっている。
「ラノベのメインストリーム変わる作家なんているんですか?」
律子は頭を抱えそうになった。
「直美ちゃんはもう少し勉強をした方がいいと思うけど。業界ではかなり有名人よ」
「えー、でも出版業界って毎年200人ぐらいデビューしているんですよね。裏方の編集者の名前なんて表に出ないんで覚えられませんよ」
「まずは有名どころからチェックしとけばいいから」
「それでそのラノベ作家さんってどんな人なんですか?」
そっちかよ! これから会う編集者の話を聞こうよ! という言葉をぐっとこらえて直美は親切丁寧にラノベ作家と熊谷編集者の説明を始めた。
熊谷編集者が高弁社のラノベを出版する文芸局にいた頃、彼が手掛ける作品はどれもコケていた。局長から「次、増刷がかからない作品を出したら異動だから」と最後通牒を受け取ると、新人賞で応募されたラノベ作品を「これは絶対に売れる」と猛プッシュした。すると彼のデビュー作が大ヒットし、首の皮一枚つながった。その功績で一般文芸に栄転した。
次の一般文芸の新人賞も彼だけが一ノ瀬坂道の作品を猛プッシュし、受賞させて出版。そしてベストセラーのドラマ化。
その2つによって彼の発言力は高まり、次々と物議を醸す作品を出してヒット作を連発した。その功績を認められ、彼が担当した作家だけを集めた文芸誌を創刊して最年少編集長まで出世した。高弁社創立以来の天才と評価が変わった。
特にラノベ作家とのコンビは有名で、全てがヒットしてアニメ化を連発させた。初版は五万部が当たり前だった。中堅作家でも初版は五千部前後なのに、熊谷が見出したラノベ作家の初版は右肩上がりが続いた。
やがて彼ははラノベ界ではトップスターになったが、一般文芸の知名度は低かった。
熊谷編集者は彼をスターダムにすべく、一般文芸を無理やり書かせた。販売部にゴリ押して初版を五十万部も刷り、宣伝費を5億円かけた。本の価格は特別仕様のハードカバーで二千円。
「そしてどうなったと思う?」
律子の悪巧みのような顔を浮かべ、直美も釣られて悪巧みな顔になった。
「爆死したってことですね?」
「そう。既存のファンから『一般文芸の仲間入りさせるな!』って、ネットで不買運動が起きたの。九割返品の大赤字で役員会議まで発展したのよ」
往々にして大コケした人物は失態を取り戻そうと大きな博打をする傾向がある。高弁社の役員たちは子会社を作って熊谷編集者を社長にして左遷させた。「高弁社創立以来の天才」の異名は、同期の淡路島(あわじしま)編集者に移った。
「あ、その人知っています。月面旅行を目指す『宇宙シスターズ』や、京大を目指す受験漫画の『タイガー鈴蘭』を手掛けた人ですよね」
「……そこは知っているのね」
「うちと同じエージェント会社を経営しているのも知っています」
「勉強していて偉い」
とりあえず、褒めといた。出版業界に勉強の順番はない。得意な分野を極めるスペシャリストから、苦手な分野を克服して何でもこなすオールラウンダーまで幅広い。
「先輩の話を聞いていると熊谷編集者って人をディスっているみたいで心配なんですけど」
「まあ、かつては天才と言われたから功罪ある人物よ」
彼の持論は「叩けば叩くほど、作家は成長する」である。彼は速読のスキルを持っていて、編集長を務めた文芸誌の新人賞作品は下読みを通さずに全て読んでいる。さらに全ての書評を文芸誌に載せていた。
最低でも800文字以上の書評を書いていたが、落選作品を「声に出して読みたくない日本語」で酷評していた。その酷評をバネにして再チャレンジして受賞した作家が何人もいるので、高弁社の編集者は担当している新人賞の選評や総論を乱暴な言葉で発するようになった。
しかも50文字程度の選評で。典型的な「人は悪い部分から真似てしまう。なぜなら悪い部分は目立つから」である。そのせいで高弁社の新人賞の応募数は毎回減っている。高弁社の編集者は「今はネットでスカウトが当たり前だから、応募はコスパが悪いと思っているのでしょう」と的外れな分析をしている。
原則、紙のワープロ原稿しか受け付けないストーム文学賞の応募数は右肩上がりなのに。あそこは一次通過以上の作品は丁寧な選評が送られてくる。応募者はそれに基づいて次作に繋げるというのに。高弁社の編集者は「毒舌がかっこいい」と思い始めた小学六年生ぐらいの意識で選評をしているのだろう。
可哀想に。
「結局、熊谷編集者に周りに残っている作家なんて『叩いても生き残れる人』しかいないのよ。赤坂庄司のように高弁社からデビューして、二冊目は他社から出す作家は多いのよ」
そういえば赤坂庄司って高弁社からデビューしたんだっけ? 興味ないからどうでもいいや。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
