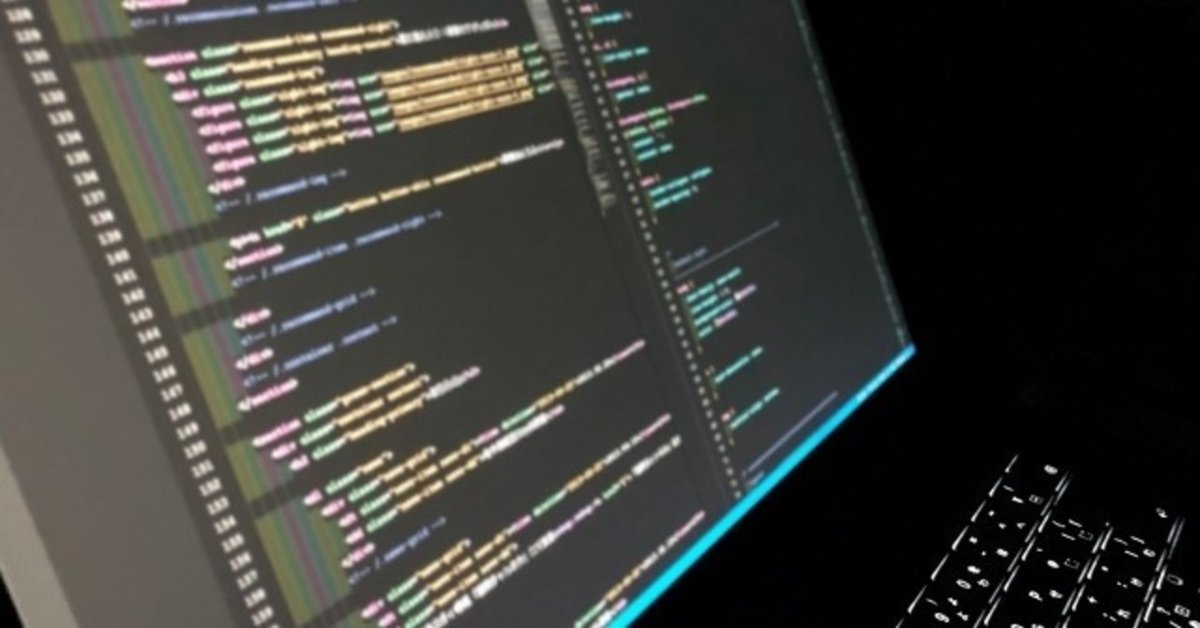
プログラミング教育は何を生むか
ひょっとして、強烈な格差社会がエスカレートして、社会が二分していくんじゃないかと考えている。
プログラミング教育が始まった
小学校で、プログラミング教育が必修化されたということで、数年前から、該当する業界ではずいぶん盛り上がっていた。
数年前に聞いた東京からきた教育関係者の講演でも、関東ではずいぶん盛り上がっているけど、みなさんの地域ではどう?という話をしていた。
札幌市の様子はわからないけど、少なくともここ江別市では、プログラムのプの字も聞こえてこないというのが現実で、学校もだからなんだということはないし、それで焦っているような保護者も見かけることはない。
それで、実際に学校ではそれらしいことをやっているのだけど、今までもパソコンを触らせる授業はあったし、その延長という感じかな。それほど、特別感ははない。
息子に聞くと、簡単なプラットフォームで、命令文のブロック並べさせる程度のことをやったらしい。
IT関係の塾や教材やさんは、親の世代がわからない次世代の勉強が新しく始まるというような売り口で宣伝していたけど、授業自体はたいしたことではない。これから小学生に上がるというお子さんがいる方も、ついて行けなかったらどうしようなんてまったく心配する必要は無い。
小学校の先生は、大変だ。どんどんやることが増えて、仕事がかなりブラック化しているというのは、想像に難くない。
良い意味でも、悪い意味でも言いたいけど、そんな状況で、それほど高度な内容のプログラミング教育が出来るはずがない。仮に、教員免許とは関係なく高度なプログラミング技術を持った先生がいてもそこまで指導要領に含まれていないし、それ以前に、個別指導するわけでもなければ、個々のパソコン操作自体に雲泥の差がある教室だ。マウスのクリックの仕方から教えなければいけない。
今の50代、60代くらいの世代になると、IT業界というというと、成長産業でホワイトカラーの代名詞の様にイメージする人もいるかもしれない。
だから、今時の子どもは、プログラミングは身につけておいた方がいい、というのは、ちょっと、想像がずれているように思う。
たしかに将来、プログラマーは絶対に不足することは間違いない。
IoTが進むと、今まで想像もしなかった業界でもプログラマーが必要ということは考えられる。
プログラマーは肉体労働
プログラマーとは、どんな職業かというと、じつは肉体労働者である。
僕も、2年弱のごく短い期間だけど、プログラマーとして勤めていた時代があった。その時の実感である。
営業やSEと呼ばれる人がいて、その下で黙々と指示されたプログラムのカスタム作業をするのは、指先しか動かないとはいえ「力仕事」と呼ぶのが相応しい。
結果的に指示通りに動くプログラムにも、見た目の美しさ、精度の良さ、スピードということもあり、それを知識と経験とセンスで作るプログラマーは「職人」という一面もある。
だから、プログラムが出来たら、経済的に恵まれた未来があるということではなくて、将来食いっぱぐれないための手に職という感覚だったら、ある意味ではその通りだと思う。
僕は、子ども達に積極的にIT機器に触らせて、プログラミングももちろんどんどんやらせている。
その理由の一つは、僕がお金に困ったとき、日雇いのイベント設営や農家仕事で食いつないだように、未来の肉体労働の手段であるプログラムはできて損はないということ。
実は、もう一つ、本当の理由は別なところにある。
思考する人、しない人
人間には2種類いる。
思考を好み楽しめる人と、思考を停止した方が楽に生きられる人だ。
noteを読んでいる人は、きっと前者が多い。
noteだけを褒めてるわけじゃなくて、SNSを積極的に利用する人は、概ね思考をする人だ。
情報を発信したり、他人の言葉に触れるのは結構エネルギーを消耗する。必ず思考を伴うからだ。
人間は、自然と省エネモードなるようにできているので、思考することが、生きるために不要と判断すれば、ますます思考にはエネルギーを使わなくなる。
そういえば「人間の本質はものを考えることにある」・・て、オーディオブックのCMで聞くよね。だれの言葉なのかは、よく知らないけど。
命令する人、される人
ここで、プログラミングの話にもどるけど、プログラミングって何をやっているかというと、正確に命令する技術なわけだ。
AIに仕事が奪われるというのは時々話題になるけど、僕はぜんぜんそう思っていない。相変わらず人間しかできない事はあるし、AIよりも、人間の方がコストが安いために代替されない仕事もある。
それで、何が起きるかというと、思考して命令手順を考えるグループと、命令に従って働いた方が楽だと考えるグループに分かれると思うのだ。
昔話のように王様と奴隷という関係ではない。命令されている方は、支配されているなんてまったく考えていない。そちらの方が楽だから、好んでそちらの人生を選んでいるだけで、その生き方を強いられるわけではない。
この差が、そのまま経済格差になるかどうかはわからない。
ましてや、幸福度はどちらが高いかわからない。
しかし、少なくとも、命令できる側には選択肢があるように思っている。
あるところでは指示通り働き、あるところでは自分が思考するというハイブリットな生き方もできる。
プログラミン教育で得るものは、パソコン技能ではない。論理思考を手に入れることだ。
実際にプログラミングをやってみると、単に命令の羅列をする作業ではなく、いかに自分の抽斗を駆使して客観的に問題を解決するかという、クリティカルシンキング的な発想が大事になる。
まとめ
プログラミング教育というと、なんだか真新しい響きだ。しかし、たくさんの言語があるし、何かひとつできたからといって、それ自体が人生をよくするわけではない。
小学校のプログラミングの授業を、たとえて言うなら、家庭科で味噌汁を作ったり、工作で本棚を作ったりするのと同じように、プログラムを生活の一部と考えて、作ってみる実習が増える程度の事だ。
小学校教育に採用されたというのは、授業で得ること自体よりも、国の方向性もそちらに舵を切ったと捉えるべきだろう。
長らく英語を習っても、大人になって使える日本人はほとんどいないというのはよく言われること。そして、英語を自分で勉強し、使いこなせる一部の人は、国際的な目線で世界を捉えている。
プログラミングも、きっと同じようなことが起きる。
10年後、20年後には、だれもが学校で習ったはずなのにほとんどの大人はできない。自分でスキルを獲得した一部の人にだけ、開ける・・という世界がきっとある。
最後までお読みいただき、ありがとうございます^^ いただいたサポートは、今後もよりよい記事を書くための情報集計費に充てたいと思います。よろしくお願いします。
