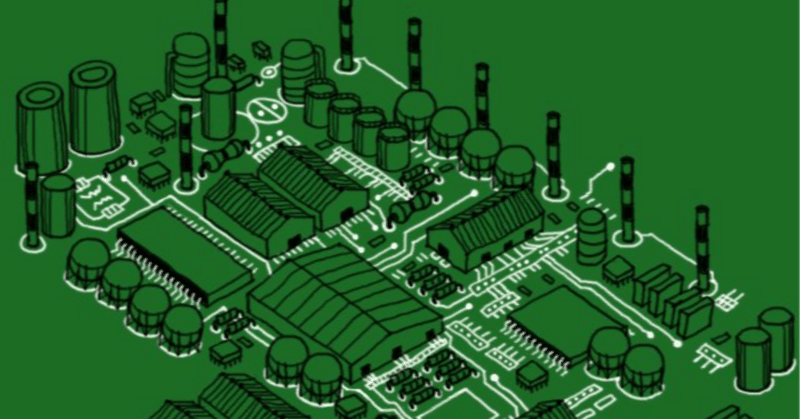
メタバースとキャラクターのAIに向けて、仮想現実の箱庭のスケールと「非」箱庭ゲームを考える
D&D(ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズ)のコンピュータ化にはじまった、アドベンチャーやRPGをルーツにもつゲームのほとんどは、おおむね箱庭ゲームと非箱庭ゲームに大別することができます。
箱庭ゲームはオープンワールドゲームと言い換えることもでき、一方で非箱庭ゲームはシナリオ重視の、もしくはステージクリア型のゲームと言い換えることができます。
オープンワールドゲームという用語は比較的新しいものですが、この2つのスタイルは常にお互いを牽制しながらゲームを進化、あるいは変化させてきました。その歴史と、スケールというキーワードからメタバース世代のゲームとキャラクターAIのありかたを考えるのがこの文です。
序) 神さまの視点からみた世界
われわれの生きるこの世界は何者が作ったもので、自分は神さまのような存在に覗き込まれているのではないか?
誰もがこう考えたことがあるはずです。
イギリス人ゲームデザイナー、ピーター・モリニューの代表作であるポピュラスというゲームがあります。

これは「神と悪魔の戦争」を描いた名作で、なにかというと、プレイヤーは神様の視点でゲームをプレイするという斬新さで有名になりました(当時、普通ゲームといえば、プレイヤーは物語の主人公や、それに近い何かを操作するものと考えられていました)。それぞれの陣営の信者が戦うのを直接操作するのではなく、地形を造成したり天変地異を起こして自分の陣営に有利なように支援する。それがとても新しかったのです。
この作品が大ヒットしたので、モリニュー氏はポピュラスを進化させた作品に取り掛かりました。パワーモンガーは、よく似た画面とシステムを持ったゲームですが、今度はプレイヤーは神ではなく、自らの王国の再建を目指すリーダーです。
パワーモンガーに出てくる人々は、武器の強さなどを除けば無個性だったポピュラスの信者たちと異なり、血統を持ち、親を殺された子供は大きくなってから復讐しようとしたりします。すごく面白そうなゲームです。
しかしパワーモンガーは失敗作でした。実際にプレイしてみると、みんな人間のディテールが実際の面白さにつながっていないことにすぐ気付きました。ゲームの中には無数の人々がうごめいており、プレイヤーは生産し、補給ラインを整え、戦争をしなくてはならないので、悲劇や喜劇が起きていようとも、そんなものを見ている暇はありません。じきに、個性的なはずの人々はトークンの集合に見えてきます。

人類が疾病や核戦争に苦しんでいるのに、神さまにしてみればタイルたった4つ分の出来事
子供だった自分はパワーモンガーで初めて、神さまの気持ちを味わいます。創造主がいるとすれば、今まさにこの世界を眺めているのかもしれませんが、豆粒のような存在である自分に降り掛かった悲劇や喜びを認識する余地はきっとないはずです。
多くの映画や小説の物語は、狭い狭い世界での話だったりします。美女と野獣のようなロマンスなんか、登場人物3~4人だけで成立してしまうこともあります。豆粒のような世界に視点を置き、舞台を書き割りにしたとしても、しかしそこにはそこだけの心躍る物語が描かれます。
アート、映画、マンガ、ゲーム、小説、そして仮想現実。ありとあらゆる媒体において何かを表現しようとしたら、どのくらいのスケールで見るのか? という問題は必ずつきまといます。
西洋のRPGと日本のRPGの違いって?
コンピュータゲーム前夜。
米国で、1970年代に元祖RPGといえる卓上ゲームのD&Dが大ヒットします。これは、乱暴にいうと、当時すでにあったウォーゲームの各要素をそれぞれ能力に差のあるプレイヤーキャラクターが洞窟に行って敵をやっつけて宝を取って帰る、という世界観に置き換えたものです。
1970年代後半になり、メインフレームコンピュータ(大学などに置かれている、ネットワークでつながれた共用のコンピュータ)が登場すると、本来学生の研究用であったPLATOでD&Dを模倣、あるいは再現することを目的としたゲームが大量に生まれました。
PLATOは当時としては破格の512x512のスクリーンを持ち、ネットワークにつながっていました。これは、世界初の個人用コンピュータと呼ばれているアルテアが画面すらないことを考えると本当に破格のスペックです。また、ネットワークによって容易にコピーが可能(当時はソフトウェアに著作権という概念もなかった)だったため、一度作られたソフトウェアは爆発的にコピーされ、改造されて広まりました。

ここからコンピュータゲームにおける仮想現実・箱庭の追求の長くて短い歴史が始まります。
卓上ロールプレイングゲームのことをTRPGと呼びますが、これは米国ではTabletop Role-playing Game、すなわち卓上でロールプレイするゲームと銘打っていました。一方、日本にRPGが輸入された時、これがテーブルトーク・ロールプレイングゲームと言い換えられました。
この2つの言葉の響きには、小さいようで大きな違いがあります。
テーブルトップ(卓上)RPG:
卓上という言葉がウォーゲームやモノポリーや人生ゲームのようなボードやマップを連想させる。
※ 映画E.T.の冒頭、子供たちがD&Dをプレイしているシーンでもミニチュアとマスタースクリーン(ついたて)が机の上に広げられている。
テーブルトークRPG:
「トーク」という言葉が机を囲んで役者となるプレイヤーがお互いに言葉を交わしながら進めていくゲームを連想させる。
コンピュータにおいて「テーブルトップ」のゲームを表現したといえるのが今のRPGで、当初はD&Dのウォーゲーム、ミニチュアゲームとしての性質に主眼を置き、上からダンジョンにいるキャラクターを見下ろして操作するようになっていました。そう、DQやFF、ウルティマやローグライクゲームのようなスタイルです。

一方で「テーブルトーク」の部分に、結果として主眼をおいたと言えるのがAdventure/Colossal Cave Adventureにはじまるアドベンチャーゲームです。これは「郵便受けを開ける」「手紙を取る」といった行動を直接タイプ、後には選択肢から選んでゲームを進めていくもので、コンピュータをゲームマスター(司会進行役)に見立てて作られています。
日本にはD&Dがなかった
1980年代にパソコンが進歩し、ある程度のコンピュータRPGが(それでもすごく高いお金を出せば)自宅でも遊べるようになります。当時の日本のコンピュータゲーム雑誌である遊撃手/バグニューズをみてみると、「パソコンを買うと何やらRPGというすごいゲームができる」という扱いです。

日本ではD&Dがブームになったわけではないので、いきなりコンピュータRPGやアドベンチャーゲームが輸入されてくることになります。そして初期~90年代初頭までの西洋のコンピュータRPGには、基本的にバーチャルリアリティの箱庭をつくることを意識する共通のコンテキストがあります。たとえば、ウィザードリィのほぼ直接の元ネタと思われるOublietteは、ダンジョンRPGですが、ネットワークゲームでもあり、あるサーバーの中で流通できる貨幣の量は一定になっていました(ウィザードリィの商店の在庫が限られていて、売ったアイテムが陳列されていくのはここから来ているのでしょう)。あるいは、ウルティマが導入した昼夜の概念もその一部と言えるでしょう。
この世代のRPGやADVに共通していえるのは、実は多くのゲームがすでにオープンワールド的な作りであるということです。ウィザードリィ1の何の意味もない地下5階~地下8階は、日本人の感覚からするとおかしく見えます。ウルティマの多くの作品には特に行く必要のない場所が多大量にあるし、作品によっては地下世界の大半の部分は意味がありません。超重厚路線のマイト・アンド・マジック2はいきなり広大な地上世界に放り出され、クリアには必要のないサブ世界やダンジョンが大量にあるゲームです。

当初の日本のRPGは、当時のコンピュータRPGを直接模倣して作られたものです。ハイドライドや覇邪の封印といった作品をみてみると、やはり、いきなり広大な世界に特に順路のヒントもなく放り出され、意味のないロケーションが多く存在するゲームになっていることがわかります。あのファイナルファンタジーも、1はかなり自由度の高い、オープニングが終わると世界に放り出されるゲームになっています(6の世界崩壊後の自由さも有名ですね)。ゼルダの伝説も、最初の1作はだだっ広いマップを、いきなり自由度の高い状態で探索しなくてはなりません。
アドベンチャーゲームにおいても、ポートピア連続殺人事件やさんまの名探偵といった80年代の作品は、いずれも比較的自由にマップを移動して進めていくようになっていますね。

ここで、西洋のテーブルトップと日本のテーブルトークの違いをもう一度再確認してみましょう。前者は箱庭の仮想世界やダンジョン(のミニチュア)を連想させ、後者はプレイヤーが演じるキャラクターを連想させます。ミニチュアのゲーム、つまりD&Dをやったことがない日本人にとって、後者のほうが自然に思えます。
日本のコンピュータRPGは、比較的早く箱庭のゲームからキャラクターやストーリーのゲームに変化していくことになります。
一度は死んだ西洋のコンピュータRPG
日本でRPGがプレイしやすく整備され、ある程度順路のきまったシナリオ性のあるゲームとして隆盛を極めていた90年代初頭~半ば、一方欧米ではコンピュータRPGは家庭用ゲーム機の世界ではアクションゲームやスポーツゲームなどに押され、マイナージャンルになりつつありました。
D&Dから一本通った歴史を持つことがあだとなったのか、それとも家庭用ゲーム機で主流ジャンルにならなかったからか、西洋のRPGは一直線にマニアック化していってしまいました。
フランスのゲームで、日本でもスーパーファミコンで出て一部で有名になったドラッケンというRPGがあります。スーファミ版ではだいぶ簡単になっているそうですが、それでも「いきなり広大な3Dの箱庭に放り出されるわけのわからないゲーム」と評価されることの多かった作品です。元のバージョンでは、まずマニュアルに書いてあるドラッケン語と呼ばれる言語を読めなければ呪文すら唱えられません(当時はコンピュータRPGでは呪文名を直接タイプして詠唱するゲームも、まだ多く存在していました)。
余談ですが、これはまた当時の事情で、ドラッケン語がマニュアル参照型コピープロテクトになっているという意味合いもありました。日本でもスナッチャーやポリスノーツで、ゲーム中必要な情報がマニュアルを参照しないとわからないというような仕掛けがありましたが、それに近いものがあります。

欧米のコンピュータRPGが重厚路線だったその頃から、日本ではRPGの要素を換骨奪胎することにほとんど抵抗がありませんでした。
アクションRPG、つまりアクションゲームにステータスやアイテムといったRPGの要素を取り込んだものが、例をいくつか挙げるだけでもドラゴンバスター、イシターの復活、イース、ゼルダの伝説、メトロイド、ワルキューレの伝説と日本では次から次へと出てきています。一方、西洋のそれはダンジョンマスターです。作品自体は名作といっていいものなのですが、これはアクションRPGというより、RPGアクションつまりダンジョンRPGをリアルタイムのアクション化といったほうが近いものです。


日本では92~94年頃、ギャルゲーまたは恋愛シミュレーションゲームというRPG・アドベンチャーの派生ジャンルが出てきます。ややこしいことに、同級生やときめきメモリアル、あるいはプリンセスメーカーのようなゲームは今の、キャラクターを中心として作られた作品とは大きく異なり、まず箱庭があってその中にキャラクターを配置するような作りになっています。
これらの作品は、RPGの「ダンジョンに行って敵を倒して強くなって宝を手に入れる」という世界観を、システムをほぼそのままに「町や学校に行って会話をこなして強くなってキャラクターを攻略する」という図式に落とし込んだものです。ときめきメモリアルにおいて、ゲームのメインループの主体はその実、女子生徒ではなく学校と、主人公のパラメータでした。

ギャルゲーが流行りはじめた頃、日本のRPGはほぼ非箱庭的になりつつありました。サブクエストなどがあっても基本的に一本道のストーリーを進めていくのが、DQ・FFといった当時のメジャーなRPGのスタイルでした。ギャルゲーはそれに対するある意味でのカウンターパートとして現れたものと考えることもできます。
CD-ROMの時代、そしてFF7
90年代後半になると、欧米ではダンジョンクロウラー型のRPGを(当時の)現代化してネットワーク対応にしたディアブロと、MMORPGの世界を切り開いたといわれるウルティマオンラインが、箱庭タイプのゲームとして再びヒットします。一方で、CD-ROMの標準化により、スペースシップ・ウォーロックからはじまる、ガジェット、The 7th Guest、デイダラス・エンカウンターといった、3Dや実写のグラフィックとムービーシーンを売りにしたゲームが急速に伸びてきます。

これらの「CD-ROMゲーム」のほとんどは、あまりゲーム性が高くありません。The 7th Guestにいたっては、簡単にいってしまえばパズルを解いてムービーでストーリーを見るそれだけのゲームなのですが、パズルをスキップすることもできてしまいます(そのかわり、ペナルティとしてムービーが見れなくなる)。

日本でも米国でも大ヒットしたファイナルファンタジー7(実は、FFが英語圏で売られるようになったのは4と6からで、4の英語版の翻訳はかなりでたらめ。現地に合わせてきちんとローカライズされて売られたのは6からという事情があります)は、今になって考えてみると、このCD-ROMゲームの流れをうまく換骨奪胎し、再解釈して完全に自分のものにしてしまった作品です。なにしろ、下手なCD-ROMゲームより美しいグラフィックと魅力的なキャラクターがあり、CD-ROMゲームに比べてずっとゲームとしても作り込まれていたのです。
FF7の登場で、箱庭ゲーム対非箱庭ゲームというせめぎ合いは、少なくとも家庭用ゲーム機の世界では非箱庭ゲームの完封勝利に一度おさまったのかもしれません。この後、箱庭ゲームはPCゲームの世界で、ネットワークRPGやFPSという形でしばらくの間育っていくことになります。それは圧倒的にメジャーな家庭用ゲーム機の世界に比べると、やはりマニアックな世界であったことは否めません。

FF4(英語版)にはテラの「You spoony bard!」という迷言がある
ゲームが本当に3Dになった日/FPSの勃興
今となっては信じられないことですが、Xboxが出るくらいまではFPS(主観視点のシューティングゲーム)というのは欧米の世界でも比較的マイナーなジャンルでした。
かつて「パソコンを買えばRPGというすごい(ハイエンドな)ゲームができる」と言われていたのが、ある時「PCを買えばFPSというハイエンドゲームができる」に置き換えられます。この時代は、Xboxが開発環境の互換性をウリにして登場し、やがてソフトウェア的にもハードウェア的にもPCゲームと家庭用ゲームの境目が薄くなっていくその時まで、長く続きます。
FPSの源流はRPGやアドベンチャーと全く異なります。元になっているのはアーケードゲームの流れで、BerzerkやGauntletといった上から見下ろし型のアクションゲーム(Gauntletは、世界観的にもアクションRPGということができます)です。これを主観視点のグラフィックにしたのがCatacombe 3Dやウルフェンシュタイン3Dでしたが、縦横奥行きの3軸を自由に動けるフルに3Dのゲームというわけではありませんでした。

完全に3Dのゲームというのは、長いあいだ超ハイエンドのゲームジャンルとして位置づけられてきたフライトシミュレーターやドライビングシミュレータ(レースゲームとは異なる)の特権と考えられてきました。DOOMは一見フルに3軸の概念を持つようでいて、縦方向の照準をあわせなくても敵に弾が当たるようになっていましたし、内部的には凸状のポリゴンに床の高さと天井の高さのパラメータが割り当てられた空間を歩くようになっていて、橋をくぐったり、足のついたテーブルを地形として表現することができませんでした。
3Dのゲームが本当の意味で3D化するのは、早くともジャンピング・フラッシュ、本格的にはスーパーマリオ64を待たなくてはなりません。



DOOMが家庭用に移植され、ゴールデンアイ007といった作品も出る中で、なかなかFPSがメジャー化しなかったひとつの理由として、操作性の問題があります。PCの世界で育まれたジャンルであるFPSは、キーボード(Quake IIIやUnreal Tournament以降は、さらにマウス)でプレイすることに特化して設計されてきました
当時のFPSは同時に使える武器が7~10種類もあったりします。フルキーの12345…90で一瞬で武器を持ち替えられるので、問題ないというデザインです。さらに左右へのサイドジャンプや、マウスを使った移動と照準の別々な動き。これを家庭用ゲーム機の限られたボタンで表現するのは至難の業です。ニンテンドー64の一見奇怪なコントローラ(初めて家庭用ゲーム機でアナログ操作を標準化した)は、家庭用ゲーム機でこのようなゲームもプレイできるようにと配慮されたものであるように見えます。
FPSはまた、もっともAIの進歩の恩恵を受けたジャンルのひとつであると言えそうです。その昔のFPSは、図体だけデカく、タフだけどバカな悪魔が猪突猛進に向かってくるゲームでした。物陰に隠れればこちらに突っ込んでくるか、その場でミサイルを撃ってくるので、サイドステップを使ったヒット&アウェイ、上級者であればサイドステップのリズムを覚えてその場でボス敵を倒せてしまいます。
元Microsoftの社員が立ち上げたゲーム会社であるValveは、ゲームデザインにコンピュータサイエンス的なアプローチを大々的に取り入れた初期のデベロッパーです。それまでゲームデザイナーが勘と経験で調整していたゲームの各パートの難易度を、彼らはテストプレイヤーが各区間で何分かかったか・何回リスタートしたか等の統計をベースに調整できることに気付きました。
彼らが作り出したHALF-LIFEは、状況に合わせたスクリプトの使用によって、演出重視のFPSという新たな可能性を生み出しました。それまでは物陰に隠れたら無節操に突っ込んできていた敵の兵士が、物陰に隠れたらその場から手榴弾を投げ込み、物陰に隠れてきます。当時としては再び映画の主人公のような体験ができるゲームという評判を呼びました。
Unreal Tournamentの世代では、Botのためにウェイポイントという概念が生まれます。マップ上に配置された、AIが経路探索に使うマーカーのようなものです。この工夫で、まるで人間のようにマップを巡回し、アイテムを取り、陣地を守って戦うBotが生まれました。
日本では、00年代に入ると箱庭タイプのゲームは暫くの間しぼんでしまいます。ファンタシースターオンラインやFF11のような、より仮想現実的なネットゲームも出てはいるのですが……。

他方、FPSの勃興によって少なくとも欧米のハイエンドゲームの世界では、箱庭タイプのゲームと非箱庭タイプのゲーム双方が進化できる時代になります。Deus ExやSystem ShockといったRPG要素をはらんだFPSは、箱庭型の、仮想現実の思想をもったゲームの(当時としての)進化形といえるでしょう。

インターフェースや設計思想は完全にRPG
FPSのメジャー化、Call of Duty 2
とは言っても、FPSはXboxまではずっとマニアックなジャンルという域を脱することはできませんでした。
Call of Dutyは、スクリプトによる演出を最重視し、ある意味でそれまでのPCハイエンドゲームとしてのFPSの進化の真逆を行くような内容でした。当時、Call of DutyがPCゲーマーから「ガンシューティングと何も違わないゲーム性」「ハリボテの建物の後ろに兵士の無限湧きポイントがある」といった、散々なけなされようだったのを思い出します。

しかし、この設計思想は家庭用ゲーム機のプレイヤーには大きく受け入れられ、大ヒットシリーズになりました。彼らが求めていたのは、ヘビーに作り込まれた箱庭ではなく、手軽に楽しめる映画の中にいるような体験だったのかもしれません。
D&Dのコンピュータゲーム化に始まった「最終的には、仮想現実としての箱庭を完璧に作り込めばなんとでもなる」という思想は、常にゲームの潮流のひとつとして存在していました。そこで次に箱庭型の思想をもったデザイナー達が目をつけたのが、物理エンジンでした。
2000年代後半~2010年前半は物理エンジンの性能が一気に伸びた時代です。まるで映画のような市街地での対空兵器とのチェイスシーンや、散乱する物を使った戦いが表現されたHALF-LIFE 2のデモは、限りない未来を感じさせるものでした。しかし蓋を開けてみると、物理エンジンで映画のような興奮が生まれたかどうかは疑問です。予期しない出来事で笑えるシーンは無数にできても、全世界が涙を流すようなロマンスは生まれませんでした(高精度なラグドールやカークラッシュで感動して泣くことはなさそうです)。
かわりに出てきたのが、Trials、QWOPのような物理エンジンの可笑しさや、微細な挙動による高難易度のアクションを楽しむゲーム、あるいはGish、World of Gooのようなインディーズのエクスペリメンタルゲームでした。今や物理エンジンによるゲーム性は当たり前となりましたが、当時はほとんど予期しない方向において衝撃的でした。

幼年期の終わりに
箱庭的な仮想現実を追い求めるのかそうでないのか、という2大思想のせめぎあいは、コンピュータゲームのはじまりの時代に30年続いた宗教戦争のようなものです。
Call of Dutyが全くダメだという意見は、それまでそのジャンルで時間をかけて育まれてきた仮想現実や箱庭への探求のコンテキストからすれば、ある意味で当然です。しかし実際には、そのコンテキストを共有しない巨大なオーディエンスが潜在的に存在していたことから、Call of Dutyは大ヒットシリーズになりました。
あるテーマや物事をデジタルに落とし込んで、あるいはゲームに落とし込んで表現する時、「その世界をどの程度のスケールで再現するのか?」というデザイン上の判断はあらゆる局面において必須です。
これは、究極的には1:1スケールのパリを作って真ん中にエッフェル塔をおいた現実そのものの箱庭世界を作るのか、それともディズニーシーのように世界各国のおいしいところを少しづつ持ってきた、現実より美しく快適な「にせもの」を作るのかという問題でもあります。
ゲームにおいては長い時間をかけて、それがようやくAかBかではなく、繊細なデザイン上の選択の積み重ねであると当たり前に受け入れられるようになりました。
今日のキャラクターAIに欠けているもの
いま、AIの世界ではチャットボットが全盛になっています。ゲームの世界では別の意味で常識になっていたエージェントAIという概念も、MIRI等のアカデミアを経由してシリコンバレーで「再発見」され、新たに注目を浴びることとなりました。
かつてAIがコンピュータサイエンスやアカデミアから見捨てられ、20年ほどゲームやCG業界だけが粛々と取り組んでいた領域だった歴史からすると信じられないことですが、今日のAIの世界はコンピュータサイエンスの人々に再び取って代わられています。
だからかもしれませんが、ゲームの世界が長い時間をかけて和解に至り、乗り越えたスケールの議論を今のAIの世界はもっておらず、メガテックや米中の競争に引っ張られて出来る限り高スペックな(タスク処理能力を持った)人工知能ができれば、あとはなんとかなるという世界観一本になってしまっているようです。ビジネス・エンタープライズ用途に限ったとしても、莫大なコストをかけてすべてをハイエンドにする必要性には疑問がつきまといます。
これはメタバースのような仮想現実にも言えることで、みんな1:1スケールの現実通りの東京や、パリや、ニューヨークや、上海を作りたがります。でも、1:1スケールの世界は目的地にたどり着くだけで大変です。ちょっと楽しいことがしたいユーザーたちは結局、VRChatくらいの小さな世界の集合体がちょうどいいと思うかもしれません。
ゲームには、そのキャラクターによって知能の程度が異なるという概念が卓上RPGの時代から存在してきました。
人間の学者のキャラクターが自分の足を追いかけてぐるぐる回っては困りますが、犬が自分の尻尾を追いかけてぐるぐる回る分には可愛らしくて良いものです。草原で出てくる最弱モンスターが味方の弱点を突いてきては問題ですが、知的なエイリアンのボスキャラが味方の弱点を正確に突いてくれば恐怖とともに興奮する戦闘になるでしょう。
仮想現実の世界に高度なキャラクターAIを住まわせてみたいという考えは、きっと誰しもが持つものです。しかし全てのキャラクターが等しくハイエンドのAIである必要はないのかもしれません。知性にもまた、スケールがあります。
エンタメやゲーム、アートはコンピュータサイエンスと紙一重でありながら、コンピュータサイエンスそのものではないということを忘れないようにすれば、きっと凄いものができるはずです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
