
6インド洋の「仏教国」スリランカ~その受難の近代史|第Ⅰ部 噺家 野口復堂のインド旅行|大アジア思想活劇
光り輝く島
いまや九億もの民がひしめく喧騒のインド亜大陸から東南約三〇キロメートルの海に、前章ではマンゴーと謂いましたがむしろ洋梨か、いや乙女の涙粒のごとき姿をさらした大きな島がある。この島全体がスリランカ民主社会主義共和国であり、六四、四五四平方キロメートルつまり北海道よりひとまわり小さな面積に約千八百万人の人口を抱えている。ご年配にはセイロンという呼び名のほうが通りがよいだろう。スリ・ランカとは「光り輝く島」くらいの意味で。名前に違わずルビー・サファイアなど宝石の産出地として知られ、セイロン・ブランドで有名な紅茶の名産地でもある。欧米人の間ではリゾート地としての人気も高く、『二〇〇一年宇宙の旅』のアーサー・C・クラーク(一九一七〜二〇〇八)が移住したことでも知られる。
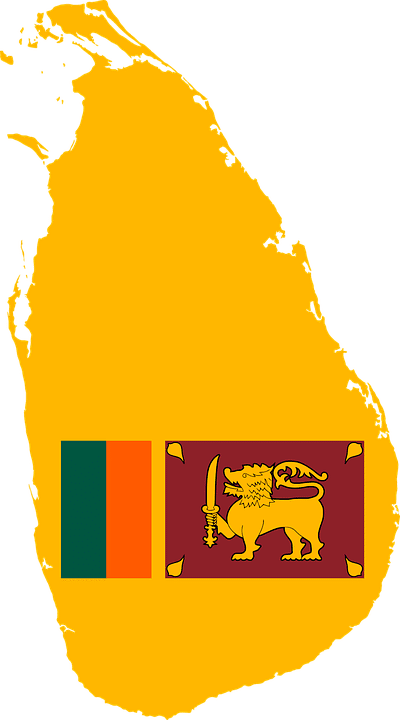
インド文化圏への窓
『千夜一夜物語』やマルコ・ポーロの『東方見聞録』にも登場するスリランカだが、極東の豊葦原之国との縁は薄かった。それこそ比叡山あたりの坊さんが、『法顕伝』(西暦三九九年から四一四年まで中央アジア・インド・スリランカをめぐった中国僧・法顕の求法旅行記)や『楞伽経』(釈迦がスリランカ島に降下して説いたという唯識系の大乗教典)を読んで間接的に知っていた程度であろう。
しかし日本が鎖国の太平から目覚めたあたりから、少しく様子が変わってくる。セイロン島は日本と欧州を結ぶ航路の寄港地にあたり、幕末から明治初期にかけて、欧州に使節や留学生として渡った日本人の多くが、おざなりだがスリランカの見聞録を残してきた。
たとえば明治四年末に欧米文明の視察を目的に派遣された岩倉使節団は、長旅の復路スリランカへ寄港した。その際、久米邦武が『米欧回覧実記』にスリランカ見聞記を残したのはわりと知られている。有名どころでは夏目漱石や徳富蘇峰、後述する森鷗外といった人々も、洋行の往復セイロン島に寄港した。悲しいかな当時スリランカ全島は大英帝国の植民地で、英領セイロンという屈辱的な名称に甘んじていたのだが……。
野口復堂がオルコット大佐を求めて旅立った明治二十一年の頃、インド亜大陸を訪うた日本人はまだまだ少なかった。明治時代にインド洋経由でヨーロッパに向かった知識人たちは、いうならばスリランカという島国を通して、南アジアのインド文化圏に触れたのである。
シンハラ人とタミル人
スリランカはその狭い国土に多民族・多宗教を抱えた国でもある。人口の約七割を占め、テーラワーダ仏教(上座部仏教,上座仏教)を信仰するアーリア系(を自認する)シンハラ人と、人口の二割弱を数えヒンドゥー教を信仰し言語も異なるタミル系住民との間では、タミル人多数地域である北東部の分離独立をめぐって泥沼の内戦が続いている。
ほかにも少数派ながらエリート層に隠然たる勢力を保つキリスト教徒やイスラム教徒と、多数派シンハラ仏教徒との間の緊張も絶えない。スリランカには民族・宗教紛争という冷戦終結後の宿痾を象徴する国というイメージが定着しており、国名が新聞やテレビに登場する機会は、ほとんどテロと内戦のニュースに限られる。ゲリラと政府軍の弾の撃ち合いばかりではない。タミル系テロ組織(LTTE)の命令によって自爆テロを計る若き青年・女性(LTTEによってノウハウを蓄積された自爆テロはその後アルカイーダなど他のテロ組織にも「輸出」されたといわれる)、同じくLTTEによる少年兵の徴兵といった悲劇はあとを絶たない。
スリランカをさいなむ民族の確執は長い歴史を持つとされる。島の中心部を基盤とするシンハラ人は、紀元前より続く仏教信仰を誇り、仏教の守護者たることをシンハラ王権の正統性の証としてきた。西暦四〜五世紀に編纂されたスリランカ最初の歴史書『島王統史(ディーパワンサ)』とその註釈増補版『大王統史(マハーワンサ)』、そして一八一五年のキャンディ王朝滅亡までを記述した『小王統史(チューラワンサ)』は、テーラワーダ仏教の経典語たるパーリ語によって記されており、仏教史書としての性格が濃厚であった。つまりスリランカの歴史観やナショナル・アイデンティティに関わる知識は、他と隔絶した知識人集団でもあった仏教サンガ(僧団)が独占的に伝承してきたのだ(もっとも日本史にしても、中世までは寺社で保管された一次資料なしには、正確な歴史など一行も書けないらしいので、スリランカが特殊だとはいえない)。
これに対し現在、主に島の北部と東部沿岸部に居住するタミル人は、歴史的には仏教の洗礼を受けてきたものの、現在はヒンドゥー教徒・カトリック教徒が圧倒的多数を占める。タミル勢力は北からシンハラ王朝を圧迫する形でじわじわと南下を続け、シンハラ王朝はアヌラーダプラ(大規模な古代仏教遺跡や灌漑遺跡が集中し、シンハラ王朝文化栄光のシンボルとされている)を中心とする北部から追われ、幾度も南への遷都を余儀なくされた。
仏教とナショナリズム
しかし、シンハラ王朝とタミル王朝の間には同盟や姻戚関係が結ばれた歴史もあり、そこに現在の価値観で「数千年にわたる民族紛争」という図式を当てはめるのは無理がある。前述のキャンディ王朝もまた、南インド・マドゥライのタミル系領主と縁戚関係を結んでおり、第九代の王位継承者は南インドから招かれ、キャンディ王朝最後の王もまたタミル系であった。彼らが仏教サンガの保護に尽くしたことはいうまでもない。そもそもスリランカで隆盛を極めたテーラワーダ仏教はかつて南インドでも広く信仰されており、十二世紀後半にスリランカ仏教界を統一する大寺派の教学を大成したブッダゴーサ(五世紀初頭)も南インド出身だったとの説が有力になっている。つまり、現在スリランカにおいてもっぱらシンハラ民族の宗教とされているテーラワーダ仏教の中興の祖は、タミル系インド人だった可能性もあるのだ。
実際に、シンハラ人とタミル人ら他民族との緊張が先鋭化したのは、欧米の植民地支配によって伝統文化の危機があらわになってからのこと。特に一八一五年から一世紀以上にわたって続いたイギリス植民地支配の間、紅茶プランテーション労働者としてインド南部からタミル人(現在、インド・タミル人と呼ばれ、インドとスリランカの緊張関係の狭間で犠牲となっている)が大量に移住させられたことで、伝統的な民族間の均衡は大きく崩された。植民地支配の常套手段である陰湿な「分割統治」もまた、民族対立の炎に確信犯的に油を注いだ*13。そしてランカー島の富をありったけ貪ったイギリス人は、第二次世界大戦によって大英帝国が破産すると、スリランカ人に西欧文明への抜きがたいコンプレックスと相互不信を残したまま、さっさと島を出ていったのである。
のちにこの島を覆う「シンハラ仏教ナショナリズム」は、実は植民地支配のもとで、シンハラ人知識層が伝統的な史書を近代的な文脈で読み直すことで確立された。その際に彼らが重要視したのは、特に仏教色の強い『大王統史』であったという。菩提樹下の大悟した釈迦牟尼ブッダが、神通力でランカー島に飛来し、夜叉族から全島を譲渡されたという聖別の伝承(結局、釈尊は生前三度もランカー島を訪れ、それにより「この島は善人に蔽われ、正法の燈明に光り輝いた」という)から説き始められる『大王統史』は、スリランカの建国そのものを仏教と不可分とする史観の源泉となった。日本では戦前の歴史教育に記紀(古事記・日本書紀)を絶対視する史観が援用されたように、植民地支配にあえぐスリランカ知識層のナショナリズム形成には、仏教護持を王統の中心に据えた「『大王統史』史観」(杉本良男)が大きな役割を果たした。そして仏教を護持すべき主体は、伝統的な「王権」から近代の概念である「民族」へと引き継がれたのである。
だから、今風に穿ったモノイイをするならば、『大王統史』再解釈の過程で、スリランカの多数派である仏教徒は「ブッダに聖別された民族」シンハラ人仏教徒として再編成されたのだ。それは植民地時代に優遇され経済的・政治的優位を誇ってきた宗教・民族の少数派グループ(シンハラ人カトリック教徒やタミル人,沿岸部のイスラム教徒)に対する多数派による失地回復運動の側面が色濃かった。じっさいシンハラ人を支持基盤とするスリランカ政府は、第二次世界大戦後の独立以来ことさらに「シンハラ仏教ナショナリズム」を煽り、民族対立の先鋭化を助長したという批判を浴びせられてきた。その際に、マイノリティ側から問題の元凶として槍玉に挙げられる筆頭人物こそ、アナガーリカ・ダルマパーラというひとりの仏教者なのだ。
「仏教国」の危機
ともかく、二千年を超える繁栄を誇った「仏教国」スリランカも、十六世紀以来、一九四八年に独立を果たすまでの間、ポルトガル・オランダ・イギリスといった西欧列強による圧迫と植民地支配、そしてキリスト教勢力による宗教弾圧にさらされ続けていた。古代インドの英雄アショーカ王のミッションに遡るといわれる島の仏教の歴史は、一八一五年、仏教に庇護を与えてきたキャンディ王朝が滅亡、全島がイギリスの植民地と化したことで存亡の危機に瀕した*14。
本書のもう一人の主人公、アナガーリカ・ダルマパーラが生まれ育ったのもそんな時代だった。彼の伝記から、やや扇情的な一文を引こう。
「前世紀(十九世紀)六〇年代のセイロン仏教の状況はまさに暗黒であった。ポルトガル・オランダ・イギリスの相次ぐ侵略によって、この国の多くの伝統文化は一掃された。宣教師らはこの銅色の島にイナゴの雲の如くやってきた。考えうるかぎりのキリスト教宗派の学校が開かれ、そこで仏教徒の少年・少女たちは聖書の教えをつめこまれ、己自身の宗教・文化・言語・民族・皮膚の色を恥るよう教えられた。
……オランダの占領地域では、仏教徒は強制的にキリスト教徒であると宣言させられた。英国支配に替わった後も、一八八四年にセイロンの仏教徒を代表したオルコット大佐がロンドンの植民地大臣に抗議し、ようやく廃棄されるまで、この法律は七十年間も強制的に施行された。仏教徒の親から生まれた子供たちは、登記のために教会につれて行かれ、そこで聖書にちなんだ名前を授けられた」("Flame in Darkness The Life and Saying of Anagarika Dharmapala" Sangharakshita, Triratna Granthamala, 1995, p17)
香料の 香つたう微風は
セイロンの島 やわらかに包み
よろこばしき よろずのなかに
卑しきは ただ人間のみ
惜しみなき 主の親切もて
振りまかれたる 恩寵も空し
盲いたる異教徒どもは
木や石にひれ伏す
What though the spicy breezes
Blow soft o'er Ceylon's isle,
Though every prospect pleases,
And only man is vile:
In vain with lavish kindness
The gifts of God are strown,
The heathen in his blindness
Rows down to wood and stone!
続いて引いたのはイギリス国教会レジランド・ヒーバー主教(Bishop Regiland Heber)の手による聖歌『セイロン賛歌(From Greenland's Icy Mountains)』である。植民地支配と手を携えたキリスト教宣教師の尊大さがあまりにあからさまで、かえって微苦笑を誘う。しかし当人はマジなのである。そしてスリランカで仏教復興・民族復興の胎動が始まったのは、まさにこの暗黒の時代。十九世紀後半のことであった。次節では、そのあらましを紐解いてみたい。
電書版追記
一九八三年より続いたスリランカ内戦は、本書刊行後の二〇〇九年五月、反政府勢力タミルイーラム解放のトラ(LTTE)の指導者プラバカラン死亡によって終結した。つまりは政府軍の完全勝利であり、多民族多宗教国家スリランカの統一はからくも保たれた。終戦までの経緯は、ジェトロ地域研究センター荒井悦代のレポート「スリランカ—内戦終結から1年」(二〇一〇年六月、ジェトロのホームページで公開)に詳しい。終戦前の記事になるが、筆者も仏教系雑誌『寺門興隆』(興山社、現『月刊住職』)二〇〇八年三月号に「仏教国スリランカ内戦激化の訳」と題して、この戦争の宗教的背景に焦点を当てた記事を寄稿した。拙ブログ「ひじる日々」に転載したので、併せてお読みいただきたい。
註釈
*13 スリランカの伝統的な民族構成と、植民地統治後のシンハラ仏教ナショナリズムの形成過程については『現代スリランカの上座仏教』(前田恵学編 山喜房仏書林 一九八六年)、『スリランカの仏教』リチャード・ゴンブリッチ、ガナナート・オベーセーカラ著 島岩訳 法蔵館 二〇〇二年(Buddhism Transformed: Religious Change in Sri Lanka 1989の邦訳)に詳しい。
*14 キャンディ王領が大英帝国に征服された際、セイロン知事ブラウンリッグ(Sir Robert Brownrigg)とキャンディ王国首長たちの間で結ばれた一八一五年キャンディ協約(Kandy Convention of 1815)第五条には、「ブッダの宗教、その儀礼、聖職者、そして礼拝の場所は維持され、保護されることになる」と明記されていた。しかし植民地や英イギリス本国のキリスト教団体が植民地での仏教保護政策に抗議したことなどから、十九世紀中頃には、キャンディ協約をほごにしたキリスト教優遇と仏教徒に対する改宗政策が取られるようになっていた(「植民地化スリランカにおけるミッションと反キリスト教運動」川島耕司、二〇〇二年参照)。
最後まで読んでくれて感謝です。よろしければ、 ・いいね(スキ) ・twitter等への共有 をお願いします。 記事は全文無料公開していますが、サポートが届くと励みになります。
