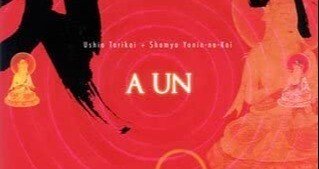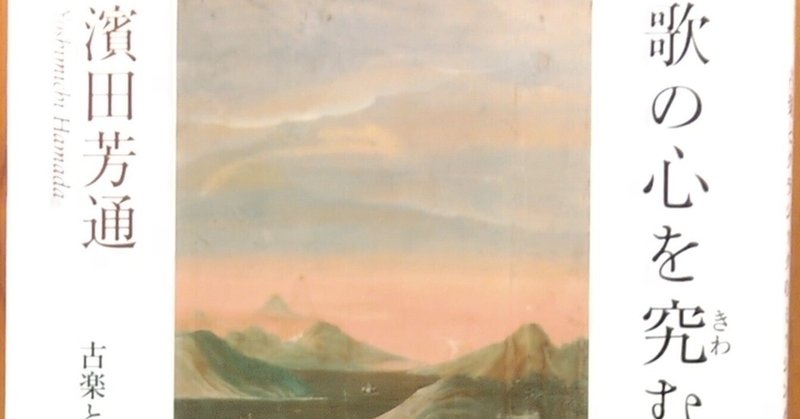2023年11月の記事一覧
きく「Never let me go」「Little boy and girl」marucoporoporo(2018 日本)
秩父前衛派・笹久保伸(ギター)の多様性を楽しんでいたら、彼の隣でピアノを弾く女性。(約一時間の動画あり。)marucoporoporoさん。 その荻窪ライブハウスでの動画をみて、どんな人かと。 2018年デビュー。作詞・作曲・編曲の全てを行なうSSW。 エレクトロニカ・アンビエントと、ワールドミュージックの境界も溶かしながらの、ウイスパーヴォイスによる囁き。 いにしえの日本で和漢の境をまぎらかしてきたように。 個人的には、ポップ・インドネシアの女性SSWが浮かんでくる。 M